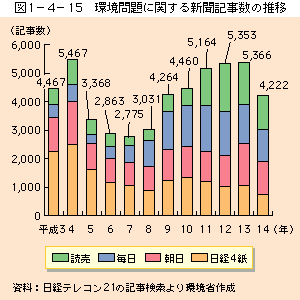
3 その他の主体との関わり
ここまで、本節では企業と行政を取り上げて、一人ひとりとの相互の関わりを見てきましたが、図1-4-1に示したように、一人ひとりが日常生活の中で環境保全の取組を進めていくに当たっては、企業や行政のみならず、NPO、マスメディア、地域等の身の回りの人々等との関わりも見逃せません。
(1)NPO
NPOは公益を実現する担い手として不可欠の存在となりつつあります。環境問題に取り組むNPOの活動は、ごみのリサイクル等の分野で多く見られ、一人ひとりに日常生活と密接に関連した分野での活動の場を提供する役割も担っています。一方、一人ひとりのその様な活動への参加が進むことで、NPO活動の活性化につながり、その結果、地域の環境保全活動の促進が図られることが期待されます(第2章で詳述)。
(2)マスメディア
テレビや新聞、雑誌等は個人が触れる機会の最も多い情報媒体です。環境問題に関する新聞の記事数を見ると、環境に関する情報が日々発信されていることがうかがえます(図1-4-15)。これらのマスメディアから発信される企業の環境広告などを含めた環境情報や社会の動きについての情報は、一人ひとりの環境保全に関する意識の高揚、環境の観点からの企業や製品の選択、日常の行動様式の方向づけを促すことになります。また、一人ひとりの先進的な取組や意見がマスメディアを通じて発信されることにより、他の人やその他の主体の関心や共感を引き起こし、日常生活における環境保全の取組が広がっていくことにつながります。
(3)身の回りの人々
人ひとりは、近隣の人々、知人・友人、家族等身の回りの人々との関係の中で情報交換を行うことを通じ、日常生活における環境保全の取組について、意識を高めたり自分自身の行動へとつなげていくことができます。また、身の回りの人々と一緒に活動を行うことなどにより、日常生活の中での取組の延長として、より積極的に環境保全に取り組んでいくことが可能です(第2章第2節参照)。
このように一人ひとりは、日常生活において、さまざまな主体との間で、さまざまな場や情報媒体などを通じて相互に影響を及ぼしあっています。第3節でも見た一人ひとりの環境保全の取組の広がりは、企業、行政その他の主体の取組を促し、そのことが、直接的に又はマスメディアなどを通じて間接的に一人ひとりの取組をさらに刺激したり、環境に無関心な人や環境に配慮した行動を起こしたことのなかった人に行動へのきっかけを与える等、波及のサイクルを生み出します。こうした一連の動きが、最終的には、一人ひとりのライフスタイルの変革を加速させることにつながるのです。つまり、一人ひとりの取組は、その他の主体の取組との相互影響により、持続可能な社会の構築に向けた社会経済システムの変革の原動力になり得るのです。
コラム 「がんばらない宣言 いわて」
岩手県では、平成12年11月に「環境首都いわて」の実現を目指し、「環境都市創造いわて県民宣言」を採択しました。環境首都を目指す岩手県の姿勢等をアピールしていくため、平成13年1月から3回にわたり、「がんばらない宣言 いわて」と題し、より人間的に生きていけるような取組を進めること、価値観の転換を図り個性ある地域づくりをしていくこと等を新聞広告を使用し発信しています。このように地方公共団体においても、その地域に根ざした環境保全の取組を紹介したり、取組への協力を求めたりするため、地域住民だけでなく日本全国に情報発信する例が見られるようになっています。