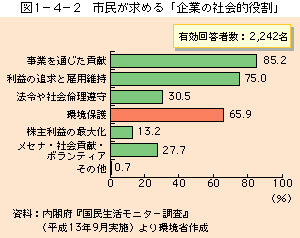
1 一人ひとりと企業との相互関係
(1)企業を取り巻く状況
ア 一人ひとりが求める企業の社会的役割
近年、環境保全意識の高まりも背景として、一人ひとりが求める企業の社会的役割に変化が起こっています。
「国民生活モニター調査」(内閣府、平成13年9月実施)によれば、企業の社会的役割として、3分の2の回答者が「環境保護」を挙げています(図1-4-2)。また、同調査では、今後企業が社会的信用を得るためにさらに力を入れるべきものとして、回答者の7割が「環境保護」を挙げています。一人ひとりの環境に対する関心は、企業に対しても環境問題への対応を求めていることを示しています(図1-4-3)。
イ 企業の環境に関する意識の変化
「平成14年度環境にやさしい企業行動調査」(環境省)によると、半数以上の事業者が地域において環境関連の社会貢献活動を行っています(図1-4-4)。その背景としては、「良き企業市民」として社会参加し、「健全で活力ある社会」に寄与するのみならず、企業が社会に「広いアンテナ」を張り、社会のニーズに敏感になることは、「企業価値」の向上に寄与するとの認識が広まってきていることが考えられます(図1-4-5)。
さらに、同調査によれば、環境に関する取組については、「社会貢献の一つ」から、「企業の業績を左右する重要な要素」又は「企業の最も重要な戦略の一つ」へと、近年、より積極的に企業活動の中に取り込んでいく動きに変わろうとしています(図1-4-6)。また、環境に関する経営方針を制定している企業(上場企業)の割合は、平成10年度調査の56.5%から14年度調査72.0%へ、環境に関する具体的な目標を設定している企業(上場企業)の割合は平成10年度45.3%から14年度69.5%へと、それぞれ増加しています。
ウ 環境ビジネスの成長
環境省が平成14年度に行った推計によれば、平成12年現在、環境ビジネス*の市場規模は29兆9千億円、平成22年には、47兆2千億円、さらに、平成32年には58兆4千億円に達すると見込まれています。この間、雇用規模は76万9千人から、平成22年には、111万9千人、平成32年には、123万6千人に増加するという推計が行われています(表1-4-1)。
また、環境ビジネスについては、経済活性化のため推進すべき産業分野として政府の方針を策定しています。経済財政諮問会議が取りまとめ、平成14年6月に閣議決定された「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2002」の中には、「6つの戦略、30のアクションプログラム」の一つとして、「産業発掘戦略(技術革新が拓く21世紀の新たな需要)」が盛り込まれ、その中で、「環境・エネルギー」分野をはじめとする4分野の技術開発、知的財産・標準化、市場化等を内容とする戦略を策定することとされました。これを受け、平成14年12月に取りまとめられた「環境・エネルギー」産業発掘戦略では、「産業活動のあらゆる局面に環境・エネルギー配慮が組み込まれ、環境・エネルギー問題の解決に資する技術、製品、サービスの創出・発展を通じ、環境の保全を図りつつ経済の活性化が図られる産業社会」など将来の社会像の実現のための戦略目標として、1)「環境・エネルギー技術へのチャレンジを産業競争力の源泉に」(技術のグリーン化)、2)「メイド・イン・ジャパン」の環境ブランド化(産業のグリーン化)、3)「日本市場を世界のエコ市場の登竜門に」(市場のグリーン化)を掲げ、これらを踏まえ環境・エネルギー産業の発掘を推進していくこととしています。
(2)一人ひとりの取組を支える企業の取組
こうした企業を取り巻く状況の変化を背景に、企業は環境の観点を企業経営に取り入れ、積極的に環境保全の取組を進める動きが見られます。
ア 環境配慮型製品の供給
一人ひとりの日常生活に関わるあらゆる分野の製品において、環境配慮が進んでおり、その供給・販売規模が増加傾向にあります。また、環境に配慮していることをセールスポイントに製品をアピールするなど、環境配慮が企業経営の戦略の一つにもなるとともに、環境技術の開発が積極的に行われています。
(ア)エコマーク認定商品
第2節で見たように、日常生活での営みは、製品の消費や使用に伴う直接的な環境負荷のみならず、その製品の製造や輸送に伴う間接的な環境負荷を消費者には見えない形で生じさせています。製品に関するこれらの環境負荷全体を購入者ができる限り考慮できるようにする手法には、購入者が環境負荷の少ない製品やサービスを選択する際の重要な情報源になるものとして、エコマークに代表される環境ラベリングがあります。
平成13年4月から施行された国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法 平成12年法律第100号)では、国等の機関にグリーン購入を義務付けるとともに、地方公共団体や事業者・国民にもグリーン購入に努めることを求めており、こうしたことを背景としたグリーン購入・調達の急速な広がりは、環境配慮型製品の市場への拡大や、エコマーク認定商品数の増加につながっています(図1-4-7)。
また、「第7回グリーン購入アンケート調査結果報告」(グリーン購入ネットワーク、平成14年度)によれば、グリーン購入の主要な対象となっている15の商品分野について、環境配慮型製品の総販売額に占める割合は、全体で35%を占めるまでに至っています(図1-4-8)。
(イ)住宅用太陽光発電
太陽光発電については、政府における研究開発の推進や企業における技術開発の進展の結果、世界最高レベルの発電効率が達成されつつあり、太陽電池の製造コストも大幅に低下しています。また、住宅における太陽光発電の導入に対する補助が行われてきた結果、一般家庭への普及につながり、生産量が増加しています(図1-4-9)。
太陽光発電パネルの生産量は、わが国が世界第一位となっており、世界市場におけるシェアの約44%を日本企業が占めています(図1-4-10)。国内のメーカーでは、需要の伸びに対応するため工場の増設など生産体制の整備・拡充を進めるところもあります。
イ サービスの提供
家電製品や自動車の普及率が示すように、一人ひとりの身の回りには生活に密着した製品が広く行き渡っていますが、製品購入の目的を考えてみると、購入者は、実際には、製品そのものの取得を目的に製品を購入するのではなく、購入した製品によって得られる機能の取得を目的に製品を購入している場合が多いといえます。この点に着目し、近年、製品が持っている機能を提供する「サービサイジング」と呼ばれる概念に基づくビジネスモデルが広がっています。このような、物の重視から機能の提供というサービスの重視への企業の取組の変化は、製品の長寿命化や製品の使用頻度の低減化等を誘発し、ひいては環境負荷の低減にもつながります。
(ア)ペイ・パー・ウォッシュ(Pay per Wash)
スウェーデンでは、1999年(平成11年)11月から、約7,000世帯が在住するゴットランド島において、家電製品の「機能販売―ペイ・パー・ウォッシュプロジェクト」と呼ばれるプロジェクトが家電メーカーにより試験的に開始されています。このプロジェクトは、洗濯機(物)を売るのではなく、衣類を洗濯するという機能(サービス)を売るというもので、消費者はメーカーから洗濯機を無料で借り、洗濯機を利用する毎に約10スウェーデンクローナ(約1米ドル)の費用を支払います。洗濯料金は、家庭内の洗濯機とインターネット接続されたメーカーの中央データベースが管理しており、メーカーと電力会社との連携によって、電力料金と共に請求される仕組みになっています。使わなくなった洗濯機はメーカーが回収し、リサイクル又はリユースされています。
この試験的プロジェクトは、製品の循環システムを形成するだけでなく、洗濯の回数に応じて課金される仕組みから、より無駄の少ない洗濯機の利用を促すことにつながっていると報告されています。
(イ)カーシェアリング
カーシェアリング*は、会員となった人が共同して自動車を利用するシステムで、1980年代の後半、スイスで大気汚染や交通渋滞等の交通環境問題を解決するために考案されました。わが国では、平成14年4月に、横浜市で国内初のカーシェアリング会社が設立され、事業を始めたのを皮切りに、福岡市でも事業化され、その他の地域でも導入が進んでいます(表1-4-2)。
カーシェアリングは、自動車使用の方法を見直すことによる排ガスの削減や交通渋滞の解消といった直接的な環境負荷の低減効果にとどまらず、家計支出の中で大きな部分を占める自動車について、その所有や使用のあり方を見直すことで、日常生活全般にわたる物の購入や使用のあり方の見直しにも目が向けられ、一人ひとりの日常生活全体からの環境負荷の低減のきっかけとなることも期待されます。
ウ 環境情報の提供
企業は、投資家・消費者・従業員等、企業を取り巻いているさまざまなステークホルダー(利害関係者)から評価されており、環境配慮の面からも企業評価が行われるようになってきた今日、企業側でも環境コミュニケーション*の重要性が認識されつつあります。「環境にやさしい企業行動調査」によると、インターネットによる情報発信や、環境報告書*の作成、また、環境会計*に取り組む企業数は増加しています(図1-4-11、図1-4-12)。
このような企業の積極的な動きは、一人ひとりの環境情報の入手経路の変化からも見てとれます。「平成13年度環境にやさしいライフスタイル実態調査」(環境省、平成14年5月)によると、環境情報の入手経路として、「企業の広告、広報誌、パンフレット、環境報告書から」の入手率が、平成9年度調査の15.3%から平成13年度調査の37.5%に増加しています。環境情報を発信する環境報告書などの媒体は、一人ひとりの環境情報入手先として大きな役割を果たすようになってきており、このことは、環境配慮型の製品やサービスの選択等日常生活における環境への取組を促進させるきっかけともなり得ることから、今後とも一層、企業が自らの事業活動に係る環境情報を広く公開していくことが期待されています。
エ 企業による環境教育・環境学習
(ア)従業員へ向けた環境教育・環境学習
第3節で見たとおり、環境教育・環境学習は、一人ひとりが環境保全に能動的に取り組んでいくために重要な役割を果たします。企業自らが行う企業内での従業員等に対する環境教育や環境意識の向上への取組は、一人ひとりのライフスタイルの変革を促し広げていくために、非常に意義が大きいといえます。
例えば、ある電機メーカーでは、製品を提供する企業として、省エネルギー型製品を開発することはもとより、その製品がくらしの中で少しでも環境に負荷を与えないような使い方を率先して行い、社会に広めていく役割を担っているとの認識の下、従業員やその家族に環境家計簿を配布し、その記録を回収・集計し、評価結果を公表するといった取組を進めています。
(イ)消費者へ向けた環境学習・環境啓発
企業活動に伴う環境負荷の状況などの環境情報の提供にとどまらず、地域社会や消費者とのパートナーシップの構築を企業の社会的責任ととらえ、自らが主体となって、消費者を対象とした環境学習会や環境関連のセミナーを開催する動きもみられます。
例えば、「子どもたちが環境についての関心を持つきっかけになれば」と、小学生を対象に、店舗での環境保全活動を実際に見学してもらうなどの環境学習会の開催を続けている大手スーパーマーケットがあります。
また、難しく考えがちな環境問題を「身近な題材で、体験的に楽しく考えよう」と、環境に配慮した食生活を提案し、できることから一人ひとりが取り組むきっかけづくりの講座として、「エコ・クッキング講座」を開催しているエネルギー供給会社もあります。
こうした取組は、消費者団体や地方公共団体、学校等にも受け入れられ、平成13年度における先の環境学習会の開催数は118件、参加者数は3,555人、エコ・クッキング講座の開催数は250回、参加者数は4,700人となり、いずれも増加傾向にあります。
(3)一人ひとりが変える企業活動
本節の冒頭で見たような一人ひとりが企業に求める社会的役割の変化は、一人ひとりが単に企業から提供される製品や発信される情報を受動的に受けとめるだけでなく、消費者、投資家、従業員の立場で企業に積極的に働きかけようとする動きにも現れています。
一人ひとりから企業への能動的な働きかけは、さらに企業の環境保全への取組を促すものとして効果があります。
ア グリーンコンシューマー
一人ひとりが日常生活においてどのような製品を選択するかは、購入した製品の使用段階におけるエネルギー消費やごみの排出量の増減に関わってくることに加え、第2節で見たように、製品の生産、輸送等の段階における環境負荷にも関わってきます。
一人ひとりが、製品のライフサイクルにわたる環境負荷を考えながら、環境に配慮して買い物をすることは、その製品を販売する店や、製品を製造するメーカー、製造方法を選ぶことにもなり、こうした行動の積み重ねにより、小売店やメーカーの行動を変え、最終的には社会経済システムを環境に配慮したものへと変えていくことが可能になります。
このような、日常の買い物で環境への配慮を大切にして商品や店を選び、地球環境を大切にしたくらしを創っていこうとする人々(グリーンコンシューマー)の輪が広がりを見せています。「環境にやさしいライフスタイル実態調査」によると、「今後はもっと行いたいと思う環境保全行動」について、「物を買うときは環境への影響を考えてから選択している」人の割合は平成9年度の65.6%から平成13年度74.8%へと増加するなど、環境に配慮した商品の購入意欲が高まっています(図1-4-13)。
また、環境配慮型の製品やサービス、購入方法等の適切な情報を得たいとする消費者ニーズの高まりに対応し、市場に供給される製品・サービスの中から環境負荷が少ないものを優先的に購入するというグリーン購入の取組を支援するため、消費者・企業・行政が参加するグリーン購入ネットワークによる商品の環境情報や商店の情報提供、グリーンコンシューマー全国ネットワークによる「全国ス−パー・生協・コンビニエコロジー度チェック」等さまざまな取組が展開されています。
イ 環境の観点からの企業評価
環境保全や環境情報の発信に積極的に取り組む企業が増加している中で、企業が行うすぐれた環境保全のための取組の表彰や、企業が作成するすぐれた環境報告書の表彰等、企業を環境の観点から評価し、格付けを行う動きがあります。
例えば、(財)地球・人間環境フォーラム及び(社)全国環境保全推進連合会では、環境情報の開示と環境コミュニケーションを促進し、事業者の自主的な環境保全の取組を促進するため「環境レポート大賞」を実施し、すぐれた環境報告書等を表彰しています。
また、環境配慮型の投資信託であるエコファンド*の登場とあいまって、その銘柄選択の際に活用されるものとして、環境格付が普及し始めています。さらに欧米を中心に、収益性や成長性だけでなく、環境対策を含め法令遵守や雇用など社会的・倫理的側面も考慮して社会貢献度の高い企業に投資する社会的責任投資(SRI:Socially Responsible Investment)が広く普及してきていることに伴い、社会的責任格付が注目されています。
さらに、さまざまな就職情報誌に各企業の環境経営度に関する情報が盛り込まれたり、インターネット上に環境分野の就職情報サービスを専門に掲載するホームページが開設される等、就職活動を行う際、企業を選ぶ観点に環境が考慮されるようになったり、環境関連の仕事や資格が注目されてきています。
このように、環境への関心の高まりを背景とした一人ひとりから企業への働きかけは、企業の行動の変化を促すこととなり、環境配慮型製品の市場への投入などを通じて、環境保全への取組を加速させる動きにつながっています。
コラム 環境広告
環境広告の分野が活性化しています。これまでの「環境にやさしいイメージ」を重視した企業広告や環境問題への取組の姿勢を示す広告から、最近では、環境負荷の低減量を表示することなどにより製品の優位性を訴えるものや自らの製品による環境負荷について情報開示する広告、自社の環境技術を利用した環境問題の解決策を提案する「環境ソリューション広告」、使用後の製品回収への協力を訴えるもののように消費者に協力を求めたり参加を呼びかける広告などが登場しています。このように、環境広告については、環境対策に関する表現の具体化、詳細化や、他の主体への提案や要求を目的とするものがみられるようになるなど広告表現の多様化が進んでいます。