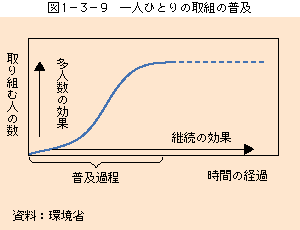
3 一人ひとりの取組の波及が大きな力になる
本節1でも示したように、環境問題に関する国際共同調査の結果では「個人レベルでの取組では環境問題の解決に向けて大した力にはならない」と思っている人が多いという結果になっています。確かに、一人の一時の取組だけを取り上げるとそれは小さな効果しか持たないかもしれません。しかし、以下に見るように、その他の主体との相互影響により一人ひとりの取組が波及していけば、環境問題の解決に向けた大きな力となり得ます。
(1)環境保全の取組の広がりとその要因
一人ひとりの日常生活での取組が波及的に広がり、企業や行政等の他の主体の取組に影響を与え、大きな環境保全の効果をもたらしたものとして、琵琶湖の富栄養化対策に対する住民の取組が挙げられます。この例は、これまでの白書でも取り上げたように、有リン合成洗剤の使用をやめるという一人ひとりの取組が住民の運動となり、滋賀県の「琵琶湖の富栄養化の防止に関する条例」の制定を促し、合成洗剤製造業者による無リン合成洗剤の開発・生産に影響を与えるなど、一人ひとりの取組の広がりが大きな力を持つことを示しています。
以下では、アメリカの社会学者であるエベレット・ロジャースの普及理論(『Diffusion of Innovations』1962年などによる)を基に、環境保全の取組がどのように広がっていくかを明らかにした上で、実際に普及が進みつつある環境配慮型製品を例に、普及の効果を確認していくとともに、普及の要因について見てみます。
ア 取組の広がりとその効果
ロジャースは社会に普及していない新しい技術や製品、行動等(イノベーション)が市場に普及したり社会に取り入れられたりする過程の一般化された理論モデルを提唱しました。その中では、イノベーションは、その購入者や採用者が時間の経過とともに増加することにより普及していくというモデルが示され、普及の速度に影響を与える製品等の要素として、1)「相対的有利性」(イノベーションに利点があるか否か)、2)「両立性」(イノベーションに他の価値基準(経済性、利便性等)が両立するか否か)、3)「複雑性」(イノベーションを理解したり使用することが難しいか否か(難しくないほど普及は早い))、4)「試行可能性」(イノベーションの試行が可能か否か)、5)「可視性」(イノベーションにより得られる成果を容易に見ることができるか否か)の5つが挙げられています。このロジャースの普及モデルは環境配慮型製品の購入といった環境保全の取組にも当てはめることが可能であり、環境配慮型製品の購入といった環境保全に取り組む人の数は、その製品が幾つかの要素を満たしている場合には、図1-3-9に示す普及曲線のように、時間の経過とともに増加していくものと考えられます。その場合、一人の取組が他の人にも広がり普及過程が終了することで多くの人が取り組むことによる効果(多人数の効果)が生み出されることが分かります。さらに、その取組が一時の流行に終わるのではなくその人の標準的な行動様式となり、以後長期間にわたって取り組まれることによる効果(継続の効果)が組み合わされることにより、大きな効果が生み出されることになります。
近年、持続可能な社会の構築に向け、さまざまな取組が始められていますが、その取組が普及曲線で示されるように広まり、さらに長期間にわたって取り組まれることにより全体として大きな力となるよう、それぞれの取組に応じた条件の整備も必要となります。
イ 環境配慮型製品の普及とその要因
最近、広く普及し始めたハイブリッド自動車*と洗剤等の詰替・付替用製品を例に、普及による環境負荷低減効果と普及の要因及び、今後さらに社会全体に広げていくために必要な要素を分析します。
(ア)ハイブリッド自動車
ハイブリッド自動車は、当初大型車から実用化されましたが、平成9年に初めて乗用車タイプが発売され、以降その保有台数は、図1-3-10に示すように増加しています。
初の乗用車タイプのハイブリッド自動車の燃費は、従来のガソリン乗用車の平均的な燃費の2倍以上、二酸化炭素の排出量は2分の1以下となっています。現在までに保有されているハイブリッド自動車が単純に従来のガソリン乗用車から転換されたものと考えればその燃料や二酸化炭素排出量の削減量は年々大きくなっているといえます。
このハイブリッド自動車の普及要因を、その製品の持つ技術面での特徴などに着目し、ロジャースの普及に影響を与える5つの要素の観点から分析すると、1)飛躍的な排出ガス低減、燃費向上、2)従来車と遜色ない機能、デザイン、3)使用段階での不便さを伴わない(操作方法、燃料補給方法に違いはない)、4)従来車と同様に試行使用可能(ディーラーで試乗可能)、5)街路で見かけられることで、静穏性などの特徴が視認可能、といったことが要因として挙げられます。
また、購入に際しての補助制度や、自動車取得税の軽減措置が実施され、行政による制度面からの普及促進策が後押ししたことも、普及の要因に挙げられます。
ハイブリッド自動車をはじめとする低公害車等は、各自動車メーカーの積極的な技術開発や政府における需要促進策等が講じられたことにより普及が進んでいます。平成14年12月には、「究極の低公害車*」と呼ばれる燃料電池自動車について、当初の計画を前倒しし、一部の自動車メーカーから世界で初めて市販されました。政府では、これに対応して、燃料電池自動車の第1号車を含め5台を率先導入したほか、普及の拡大に向けた環境整備を戦略的に進めていくこととしており、今後広く普及していくことが期待されます。
(イ)洗剤等の詰替・付替用製品
石鹸・洗剤業界では、中身が空になった本体容器に洗剤等を詰め替えて使用する「詰替用製品」や、空になった容器のスプレー部分などを新しい容器に付け替えて使用する「付替用製品」の開発が進み、出荷比率を伸ばしています。
詰替用製品等は、平成4年頃から需要が伸び始め、出荷量は図1-3-11に示すように増加しており、平成13年の出荷比率は53%を占めるに至っています。この結果、容器に使用されるプラスチックの削減率は、平成13年には33%となっています。
ハイブリッド自動車の場合と同様に、詰替用製品等の普及要因をその製品の持つ技術面での特徴などに着目し分析すると、1)プラスチック原料の削減、ごみの減量効果、2)従来品と比べ価格が安い場合が多い、3)注ぎ口の開発など機能性も工夫、品揃えも遜色無し、3)使用することが容易(詰め替え、付け替えの行為は簡単)、4)試行する必要はない(試行で確認せずとも使用方法等は容易にわかる)、5)テレビコマーシャルなどで広告、ごみの減量効果が手にとってわかる、といったことが要因として挙げられます。
また、企業において、ごみを減らしたいという消費者の意識の高まりに対応するため、詰替用製品等の開発が進展したこと、さらには、平成7年に制定された容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法 平成7年法律第112号)において、企業に対して、内容物の詰め替え方式を採用すること等により容器包装の減量に積極的に努めるよう求められたことも、普及の要因として挙げることができます。
ここまで見てきた環境配慮型製品については、多くの人に取り入れられるようになってきていますが、その普及率などを見ると最終的な普及への途上にあるといえます。さらに普及を進め、一旦普及した製品がその後も継続的に選択・使用されるためには、企業によるさらなる技術開発など普及の支障となる課題の克服、行政の普及促進策の継続や適時の見直し等が重要であると考えられます。
(2)環境保全の取組を波及的に広げていくためには
一人ひとりの環境保全の取組には、琵琶湖の富栄養化対策や上述のハイブリッド自動車や洗剤等の詰替・付替用製品の普及の例が示すように、その取組を支える企業の環境保全のための新たな技術開発や、環境に配慮した製品設計の実施、行政による一人ひとりの取組を促進する枠組みの構築や制度面の整備等も必要となります。しかし、そのためには、まず一人ひとりが、環境に与えている影響、環境を保全していくことの重要性や有効性等を認識することにより、意識を変え、行動を起こすことが原点となります。つまり、こうした一人ひとりの自主的積極的な行動が、企業や行政等の取組を呼び起こし、そのことでさらに各主体が互いに環境保全の取組を助長しあい環境保全の取組が一層行いやすい社会環境が整えられることにより、結果として、環境保全の取組がわが国全体に波及していき、大きな力を持つことになります。
コラム ロジャースの普及理論
エベレット・ロジャースはニューメキシコ大学コミュニケーション&ジャーナリズム学部教授であり、技術革新、新製品の普及理論の権威として知られ、「イノベーション普及学」等の著書・論文があります。
彼のイノベーション(社会に普及していない新しい商品や行動等)の普及過程の分析理論によると、イノベーションは、革新者、初期採用者、追随者、遅延者の順に採用されることを示しています。革新者は、いわゆる新しいもの好きな人たちで、その革新者の様子を見て、評価した上で、採用するのが、初期採用者です。初期採用者は、新しい情報を常に入手している一方、社会的常識を持っているとされます。初期採用者が採用すると、周りの多くの人々も追随します。そして、保守的で変化を好まないあるいは変化に興味がない遅延者が最後まで残るということになります。一般に、革新者は全体の2〜3%程度、初期採用者は10%強といわれ、追随者は70%弱、遅延者は15%程度だとされています。