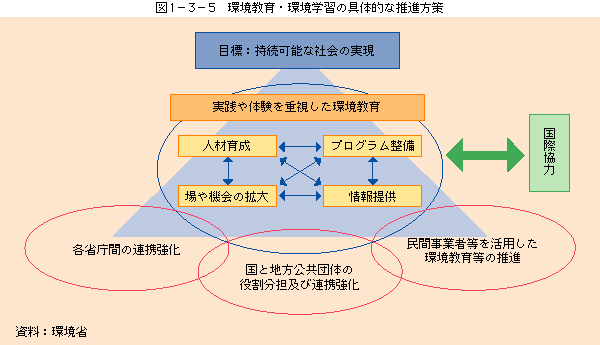
2 行動に至る個人の変化
一人ひとりが環境保全に向けた具体的な行動を行うようになるまでの過程は、大きく3つの段階に分類することができます。まず、現状から環境問題の深刻さに気づき、関心を持つ段階、次に、現実に生じている環境問題と自分たちの生活行動の密接な因果関係を理解する段階、そして、自ら実践することができる様々な対策があることへの認識を高め、問題解決に資する能力を育成する段階があり、これらを通じて具体的な行動へと結びつくようになります。各段階のステップアップには、環境教育・環境学習や環境情報が重要な役割を果たします。以下では、この2つについて現状と今後の方向性を見ていきます。
(1)環境教育・環境学習の推進
ア 環境教育・環境学習の現状
環境教育・環境学習は、社会を構成する各主体の環境に対する共通の理解を深め、意識を向上させ、問題解決能力を育成し、各主体の取組の基礎と動機を形成することにより、各主体の行動への環境配慮の織り込みを促進するものです。このため、これまでも学校における指導の充実、学習拠点の整備、学習機会の提供、人材の育成と確保、教材と手法の提供、広報の充実等が施策として実施されてきました。また、地球温暖化対策、廃棄物・リサイクル対策等の個別の政策分野においても環境教育・環境学習に対して有効な政策手段の一つとして力が注がれています。
環境教育・環境学習をめぐる状況を見ると、学校以外の教育・学習施設の増加などを背景として教育・学習の場が多様化してきているとともに、環境教育・環境学習を行う担い手として、民間団体や事業者等が増加してきています。今後、環境教育・環境学習の場としての学校以外の公的施設や自然のフィールド、担い手としての民間団体や事業者の重要性がさらに増すと考えられます。
また、環境教育・環境学習は、就学年齢層のみならず、青壮年層、高齢者層まで含めて広く国民全体を対象として実施すべきものですが、特に、環境保全のための取組に重要な役割を担う者や次世代を担う年齢層に対する環境教育・環境学習は、必要性が高く効果も大きいと考えられています。
さらに、環境教育・環境学習の内容については、従来、多くの場合は、環境汚染や自然保護の枠にとどまっていますが、今後、持続可能な社会の実現に、より有効なものとするためには、消費、エネルギー、食、住、人口、歴史、文化等の多岐にわたる要素を含めた幅広いものとしていくことが重要と考えられています。また、知識蓄積型ではない、「体験を通じて、自ら考え、調べ、学び、そして行動する」という過程を重視した環境教育・環境学習への拡大が必要とされています。
イ 持続可能な社会を目指した環境教育・環境学習
平成11年12月の中央環境審議会の答申には、環境教育・環境学習の具体的施策の推進方策が8つの項目で示されています(図1-3-5)。
特に、実践や体験を重視した環境教育・環境学習の推進に当たっては、1)推進の原動力として知識・技能を備えた多彩な人材が育つ仕組みを整備する「人材育成」、2)具体的行動に結びつく活動の場、テーマに応じた「プログラム整備」、3)環境教育の基盤となる情報の整備と各主体が有する情報を体系的に整備する「情報提供」、4)実践的体験活動を行うことのできる「場や機会の拡大」の4つの視点からの施策の展開が重要とされています。
4つの視点に対応したそれぞれの関連施策をその目的に応じて「関心の喚起→理解の深化→参加する態度・問題解決能力の育成」の一連の流れの中に位置づけてみると、各段階でさまざまな施策が講じられることにより、「具体的行動」を促すことになることがわかります(図1-3-6)。
社会や環境との関わり方がそれぞれの個人のライフステージに応じて異なっていることを踏まえると、一人ひとりが自分にあった環境教育を受け、環境学習を行えるよう、環境教育・環境学習の主体、対象者、適切な場がうまく組み合わされることが必要とされ、これらを相互に「つなぐ」ことが極めて重要となっています(図1-3-7)。
このように、環境教育・環境学習は持続可能な社会の実現に向け、関心を喚起し、理解し、行動を促すために重要な手段であり、その実効性を確保していくことがますます重要となっています。
(2)環境情報の提供
「環境にやさしいライフスタイル実態調査」によれば、環境情報の情報源の数、充足している環境情報の数が多い人ほど、実施している環境保全行動の数の割合が高くなっており、環境情報は、関心を喚起し、理解し、行動を促すための重要な要素となっています(図1-3-8)。
環境の現状や環境問題に関する正しい情報、消費行動において環境を重視していくことを促す環境ラベリング*やグリーン購入*に関する情報等、環境情報が必要なときに必要な形で入手できるような体制を整えていくことが重要となっています。