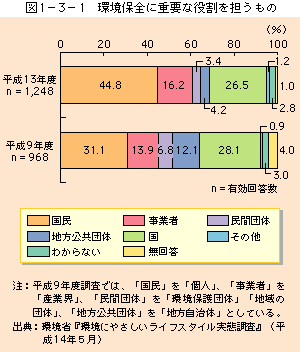
1 環境問題に対する意識と行動の隔たり
「環境にやさしいライフスタイル実態調査」(環境省、平成14年5月)によると、環境保全に重要な役割を担う主体として「国民」を挙げた人が44.8%を占め、前回の調査(平成9年度)に比べ13.7ポイント増となっています(図1-3-1)。また、環境問題を自分自身の問題ととらえている人も増加しており(図1-3-2)、環境問題に対する一人ひとりの意識は高くなっています。
行動の実施状況をみると、「ごみの分別」「ビン、カン、ペットボトル類の分別」「新聞、雑誌の古紙回収」等、ルール化された「リサイクルのための分別収集への協力」に関する環境保全行動や「節電」「冷暖房の省エネ」等、実施することにより個人にも直接の経済的メリットのある環境保全行動は良く行われている一方で、「環境保護団体への寄付」や「地域の緑化活動」、「地域の美化活動」、「環境保護団体の活動」等への参加といった直接、個人が効果を実感できない行動に関しては、相対的に低くなっています(図1-3-3)。また、環境問題についての考え方を見ても、環境保全に積極的に参加したいと答える人が減少するなど、環境問題に対する意識の高まりが能動的な環境保全行動につながらない状況であることがわかります(図1-3-2)。
また、カナダの環境問題専門調査機関Environics Internationalが中心になって行った環境問題に関する国際共同調査「第5回 30カ国環境問題国際共同調査」の結果を見ると、能動的な環境保全行動につながらない要因として、具体的な情報の不足、資金や時間が問題になっているわけではなく、個人レベルの取組では解決に向けて大した力にならないという意識が挙げられます(図1-3-4)。