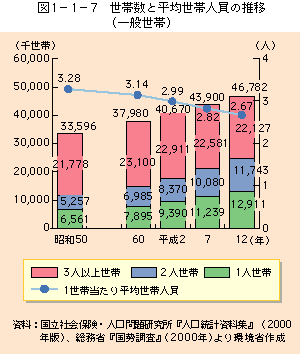
2 近年の社会経済、日常生活と環境との関わり
これまでの社会の変化と環境との関わりに見られたように、社会経済の変化は、さまざまな形で環境に正負両面の影響を与えています。近年の社会経済の動向を踏まえながら、社会、経済の個々の側面における環境との関わりを、もう少し詳しく整理していきます。
(1)少子高齢化と世帯数の増加
わが国の総人口は、平成18年頃を頂点として減少に向かい、少子高齢化が進むと予想されています。少子高齢化は、夫婦のみの世帯や高齢者単独世帯の増加の要因となり、1世帯当たりの人数が一貫して減少にある一方、総世帯数は増加しています(図1-1-7)。世帯数の増加は、一つの世帯が生活の最小単位として個々に保有することが必要とされる住宅やそれに付随する台所、風呂等の設備、洗濯機、冷蔵庫等の耐久消費財をその分だけ増加させることになり、それに伴ってエネルギー消費量や水の使用量も増加させることになります。
(2)産業構造の変化
わが国の産業構造の変化は、先進各国で見られるように、第1次産業から第2次産業、第3次産業へと高度化、サービス化が進んでいます(図1-1-8)。こうした動きは、環境の側面からみれば、相対的に少ない資源やエネルギーにより、「情報」や「サービス」といった付加価値を提供するもので、環境効率性*の改善につながるものと考えられます。
また、環境面でのさまざまな技術革新も進んでおり、製造工程の省エネルギー化や製品における環境配慮、物流の合理化は格段の進歩を遂げています。
(3)情報通信技術の革新
情報通信技術の革新は、通信手段の変化を通じて、従来環境負荷を与えていた活動をより効率化していく可能性を持っています。例えば、テレワーク(Tele Work)、SOHO(Small Office Home Office)と呼ばれる自宅または自宅に近接した小規模な事務所などにおけるITを活用した勤務形態は、交通量の減少、事務所スペースの削減、エネルギー使用の合理化等をもたらし、環境負荷を低減させることが期待されます。
また、インターネットなどの新しい情報伝達手法の導入によって、適切かつ迅速な環境情報の提供・発信が進んでいけば、環境保全の取組への参加やネットワークづくりが促進される可能性もあります。他方で、パソコンや携帯電話といった情報通信機器の増加や必要以上の情報交換はエネルギー消費の増加につながります。
さらに、情報化の進展によって節減された時間や所得の使い方、情報化を支える情報機器の生産、利用、廃棄のあり方次第では、新たな環境負荷が発生することも考えられます。
このように、情報通信技術の革新は、環境に対して正負両面からの影響を与える可能性がありますが、その適切な活用を図れば、環境保全上の大きな寄与が期待できます。
(4)グローバル化の進展
経済活動のグローバル化によって、世界中から様々な製品を輸入することができるようになっています。貿易の拡大は、消費者にとって、世界中の安くて品質のすぐれた製品を居ながらにして購入できるという利点を生みます。しかし、輸入製品の増加は、長距離輸送によるエネルギー消費の増加などにつながっています。
また、グローバル化の進展とともに、環境に関する国際規格であるISO14000シリーズ*といった環境に配慮した規格・制度が身近なところで普及するようになっています。
(5)ライフスタイルの変化
今日の私たちのライフスタイルは、大量生産、大量消費、大量廃棄型の社会経済システムの下、生活水準の上昇と生活の利便性の向上を追求したものとなっており、自動車保有台数の増加、家電製品の世帯当たりの所有台数の増加等に見られるように、エネルギーや資源の消費といった面で環境負荷を増大させています。また、携帯できる情報通信端末の増加(図1-1-9)などに見られるような機器の個人所有化、24時間対応の店舗やサービスの増加(図1-1-10)に見られる生活の24時間化などは、日常生活からの環境負荷を増大させるおそれを有しています。他方で、労働時間の減少、余暇時間の増大を背景として、自然とのふれあいへの志向やボランティア活動への参加志向が強まる傾向も見られ、こうした傾向は、環境保全のための取組への意識を高める可能性を有しています。
ここまで見てきたように、社会経済の変化は、多くの場合そこで営まれている私たちの日常生活を通じて、環境に影響を与えています。今日の環境問題への対応を考えていく上では、問題が産業活動だけでなく、私たちの日常生活も含めた人間活動の量的な拡大や質的な変化に伴って発生し、相互に深く関わり合う一連の問題であることを十分に認識することが必要となっています。