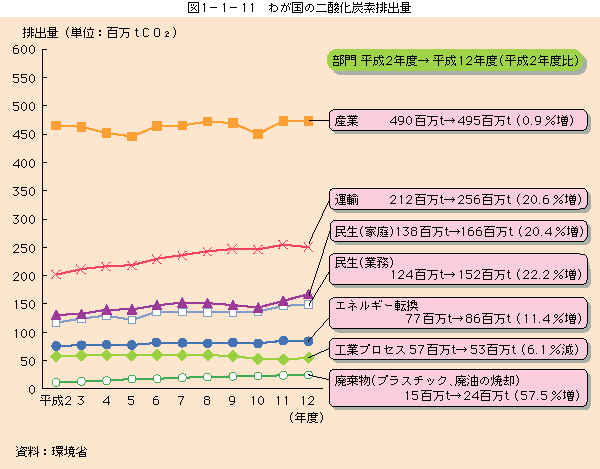
3 日常生活による環境負荷の増大
それでは、主な環境問題について、これまで見てきた社会の変化により、特に日常生活からの環境負荷が増大している現状を見ていきます。
(1)わが国の温室効果ガス排出量
地球温暖化の主要な原因物質である二酸化炭素は、私たちの生産活動や消費活動のあらゆる場面から排出されています。
わが国の2000年度(平成12年度)の二酸化炭素排出量は、12億3,700万トン、一人当たり排出量は、9.75トン/人で、1990年度(平成2年度)と比べ、排出量で10.5%、一人当たり排出量で7.6%増加しています。また、前年度と比べると排出量で0.4%、一人当たり排出量で0.%の増加となっています。これを部門別でみると、民生(家庭)部門からの排出量は2000年度において1990年度比で20.4%の増加となっており、前年度比4.1%の増加となっています(図1-1-11)。
(2)わが国の物質収支
現在のわが国は大量の物質に支えられ成り立っており、廃棄物問題の根本には、大量生産、大量消費、大量廃棄型の事業活動やライフスタイルがあります。図1-1-12は平成12年度におけるわが国の物質収支を示しています。わが国の社会経済活動には約18.4億トンに及ぶ自然界からの資源採取を含め、約21.3億トンの資源が国内外から投入されています(総物質投入量)。そして投入された資源のうち、5割程度がそのまま消費、廃棄に向かっています。一方、廃棄物のうち資源として再利用されているのは約2.2億トンで、総物質投入量の約1割程度にすぎません。
また、一般家庭の日常生活から生じる「家庭ごみ」を含む一般廃棄物について見てみると、1人1日当たりのごみの排出量は昭和60年度以降増加し、近年は高レベルで推移しています(図1-1-13)。
(3)大都市における大気汚染
大都市における大気汚染の原因物質である窒素酸化物は、石油や石炭等の化石燃料の燃焼によって生じ、その主な発生源には工場等の固定発生源と自動車等の移動発生源があります。
東京都における窒素酸化物の発生源別排出量の変化は図1-1-14のとおりです。産業から発生する窒素酸化物は平成2年を最大に近年は減少していますが、暖房器具の使用等により家庭から発生する窒素酸化物は増加しています。
(4)閉鎖性水域における水質汚濁
閉鎖性水域における水質汚濁の原因としては生活排水の占める割合が大きく、特に東京湾においては、COD*で見てみると、生活排水が汚濁負荷の7割近くを占めています(図1-1-15)。さらに、生活排水のBOD*の汚濁負荷量を発生源別にみると台所からの負荷が約4割、し尿が3割、風呂が2割、洗濯が1割を占めています(図1-1-16)。
このように、日常生活からの環境負荷は大きく、さまざまな環境問題の原因となっています。こうした状況を踏まえ、次節では、私たちの日常生活のどのような場面から環境負荷が生じているのか見ていくとともに、日常生活で実践できる環境保全のための取組の可能性を考えていきます。