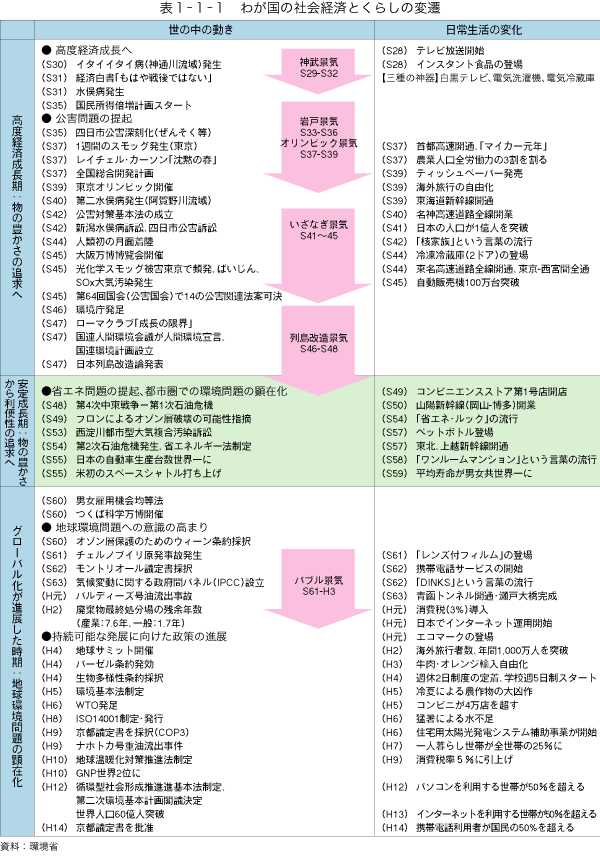
1 日本の戦後における社会経済と環境問題の変遷
私たちは、世の中の大きな社会や経済の営みの中で日常生活を送るとともに、さまざまな形態で環境と関わりをもってきています。このため、社会経済のあり方、生活様式、環境の状況は相互に密接不可分な関わりを有しています。ここではまず、日本の戦後、特に高度経済成長期以降における社会、経済、生活様式の変化と環境問題の変遷を振り返ってみましょう(表1-1-1)。
(1)高度経済成長期:物の豊かさの追求へ
戦後の経済復興を優先した昭和30年〜昭和40年代、生産活動の拡大により、実質経済成長率は、昭和30年代前半には8.9%、昭和30年代後半には9.1%、昭和40年代前半には10.9%と上昇しました。この高度経済成長は、生産額1単位あたりの汚染物質発生量が多い重化学工業によってリードされ、また、汚染物質を除去するための設備投資が優先されなかったため、結果として、汚染物質の環境中への排出量を増大させることになりました。
また、交通面では、昭和30年代半ば以降、モータリゼーション(車社会化)が急速に進み、昭和46年には乗用車保有台数が1千万台に達しました。特に、人口の集中、産業の集積が進んだ都市部における移動量の増大に対応するため、行政は道路整備等により交通容量の拡大を進め、昭和37年にわが国初の高速道路である首都高速1号線の東京・京橋−芝浦間が開通したのを皮切りに、全国各地で高速道路網が整備され始めました。
他方、くらしの変化を見てみると、この時期には、多くの製品が市場に供給されるとともに、所得が増加し、さまざまな製品が日常生活へと普及することになりました。特に、わが国における家電製品の普及はめざましく、電気洗濯機、電気冷蔵庫、白黒テレビの「三種の神器」は昭和40年代にはほぼ100%の普及率を達成しました。さらに、昭和39年の東京オリンピック中継を契機にカラーテレビへの買い換え需要が起こるなど、急速な技術開発から新たな機能を持つ製品が生産されました。しかし一方で、まだ使用可能な製品が大量に廃棄されることとなりました。
こうした社会・経済状況の中、公害問題による被害地域が日本全国に広がり、いわゆる四大公害病(水俣病、新潟水俣病、イタイイタイ病、四日市ぜんそく)の発生を招くなど、大きな社会問題となり、また、モータリゼーションの進展は、排出ガスによる大気汚染、騒音や振動による生活環境の悪化等の問題を引き起こしました。さらに、都市化の進行、別荘、ゴルフ場の造成、観光道路の開発、工業用地等の土地の確保等を背景とした開発の結果、自然破壊も全国的な規模で進行し、都市では身近な緑の喪失や昆虫、野鳥の減少、農山村部ではすぐれた自然や身近な里山の破壊、海岸部では干潟や浅瀬の埋立てが進んでいきました。
(2)安定成長期:物の豊かさから利便性の追求へ(昭和48年〜50年代)
昭和50年代は、昭和48年及び昭和54年の二度にわたる石油危機等を背景に、経済成長が高度成長から安定成長へと移行し、産業においては、省エネルギー化が進む一方で、エネルギー多消費産業から加工型・サービス型産業へと産業構造の変化が起こりました。この時期、昭和40年代の公害経験を踏まえ、さまざまな法制度の整備や工場における対策がなされ、産業型公害は収束を見せつつありました。
他方、くらしの面では、昭和40年代から引き続き大都市圏への人口集中が進む中で、単身世帯の増加による世帯数の増加、女性の社会進出による家事労働の減少を背景に、コンビニエンスストアの利用、外食やレトルト食品を含めた加工食品が増加しました(図1-1-1)。また、所得の増加が進み、大型化、高度化した家電製品や自動車等が、世帯数の増加などとも相まって大量普及していきました。さらに、宅配等の少量物品輸送という新たなサービスも登場しました(図1-1-2)。
こうした社会・経済状況の中、石油危機を契機に省エネルギー化が進んだにもかかわらず民生部門と運輸部門におけるエネルギー使用量が増加したほか(図1-1-3)、容器包装や食品廃棄物の増加、自動車排気ガスによる大気汚染、生活排水等による水質汚濁等、通常の事業活動や日常生活に伴う環境負荷が増大し、都市・生活型公害が顕在化しました。
(3)グローバル化が進展した時期:地球環境問題の顕在化(昭和60年代以降)
この時期は、経済活動のグローバル化が進み、わが国においても国内から、賃金や物価の安い外国へと一部の製品の生産拠点が移るなど、人、物、資金、情報の国境を越えた流れが飛躍的に増大しました(図1-1-4)。国際的な交通も飛躍的に発達し、これにより、日本を出国する海外旅行者の数は、昭和60年から平成13年にかけて約3倍に増加しています(図1-1-5)。
他方、くらしの面では、バブル経済のこの時期、特に耐久消費財やサービスの分野を中心として個人消費が拡大しました。耐久消費財については、物の普及がおおむね一巡した段階に至り、テレビや乗用車では一家に2台目以上の購入が見られるようになり、サービスの分野では、余暇、レジャーの支出が大きな伸びを見せています(図1-1-6)。
こうした状況の中、東京への一極集中が加速し、都市・生活型公害が依然として広がりを見せています。また、大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会経済システムが、わが国のみならず地球規模で拡大を見せたことにより、開発途上国の爆発的な人口増加や貧困問題等を背景とした食料需要の増大と資源利用圧力の強まり等と相まって、地球環境問題が顕在化してきました。
バブル経済の崩壊後、経済成長は鈍化し、個人消費が全体として伸び悩む中で、私たちの働き方や暮らし方は多様化し、撮影機能付き携帯電話や栄養補助食品といった便利さ、快適さ、健康等、個々人の満足度を高めるための製品やサービスが増加しています。一方で、大量生産・大量消費・大量廃棄型の生活を見直し、環境負荷の少ない新たなライフスタイルを実践する動きも見られます。