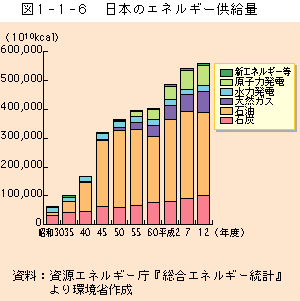
2 日本の環境問題の変遷
ここまでは、社会経済システムと自然環境の関係を現在の状況を中心に地球規模で分析してきましたが、以下、わが国の戦後から現在までの歴史を振り返り、両者の関係を詳しくみてみます。
(1)産業型公害が発生した高度経済成長期(第I期:昭和30年代中頃〜昭和47年)
戦後の経済復興を優先した昭和30年〜昭和40年代の高度成長期において、生産活動の拡大により、実質経済成長率は、昭和30年代前半には8.9%、昭和30年代後半には9.1%、昭和40年代前半には10.9%と上昇しました。経済成長期初期である昭和30年のわが国のエネルギー消費量は小さく、エネルギー供給の大部分を石炭及び水力発電でまかなっていましたが、昭和36年には石油需要が石炭需要を上回り、昭和30年から昭和36年の間にエネルギーの総供給量も約2倍に増加するなど、エネルギー消費量は急増しました(図1-1-6)。この過程でわが国の産業構造の重化学工業化が大きく進みました。重化学工業は、生産額1単位当たりの汚染物質発生量が他の産業より大きく、汚染物質の排出量も経済成長にあわせて増加しました。
こうした経済の急速な発展とそれに伴う汚染物質の環境中への排出は、環境の急速な悪化をもたらしました。
昭和30年から昭和40年頃の大気汚染が最も著しかった時期には、場所によっては、硫黄酸化物やばいじん等による汚染によって視程が30〜50mにまで落ち込むとともに、硫黄酸化物による鼻を刺すような臭いが立ちこめているところもありました。最初の臨海コンビナート型開発を行った四日市地区では、昭和30年頃からコンビナートに隣接している小中学校で、異臭のため夏でも窓を開けられない日が続くようになりました。千葉県の京葉コンビナート、岡山県の水島コンビナートなどにおいても、昭和30年代後半から昭和40年にかけて四日市と同様の道をたどることとなったほか、川崎、尼崎、北九州など戦前からの工業地帯でも深刻な状況でした(図1-1-7)。
こうした深刻な汚染は、人の健康にまで深刻な被害を及ぼし、昭和30年から昭和40年代にかけて、いわゆる四大公害病(水俣病、新潟水俣病、イタイイタイ病、四日市ぜんそく)の発生も招く等、大きな社会問題にまで発展しました。
昭和40年代に入ると高度成長と地域開発の進展に伴い、河川、海域等の公共用水域の水質汚濁が著しくなりました。例えば、昭和40年頃になると瀬戸内海の一部では、赤潮*の発生件数が年間40件を超え、昭和45年には、瀬戸内海のほぼ全域で発生がみられることになり、大量の漁業被害を発生させました。
*赤潮
プランクトンが水面近くで急激に繁殖したため、水の色が変わって見える現象で、しばしば魚介類に被害を与える。
このような全国各地における公害問題の発生に対し、政府においても、昭和33年に公共用水域の水質保全に関する法律*及び工場排水等の規制に関する法律*を制定する等、さまざまな公害防止のための法制度の整備を進めました。昭和42年には、公害対策を総合的かつ計画的に実施していくための公害対策基本法*を制定するとともに、昭和45年のいわゆる「公害国会」においては、規制対象となる地域・施設・物質の拡大、地域の実情に応じた上乗せ規制、直罰制度の導入などを行う14の法律が制定又は改正され、今日の環境行政の基礎が築かれることとなりました。
*公共用水域の水質保全に関する法律
昭和33年法律第181号、昭和46年に水質汚濁防止法が施行されたことに伴い廃止
*工場排水等の規制に関する法律
昭和33年法律第182号、昭和46年に水質汚濁防止法が施行されたことに伴い廃止
*公害対策基本法
昭和42年法律第132号、平成5年に環境基本法が施行されたことに伴い廃止
大気汚染の状況(昭和42年)毎日新聞社 提供
(2)都市生活型公害が顕在化してきた経済の安定成長期(第II期:昭和48年〜昭和50年代)
昭和50年代は、昭和48年及び昭和54年の二度にわたる石油危機等を要因に経済が高度成長から安定成長へと移行した時期です。産業部門においては省エネルギーが進む一方で、エネルギー多消費産業から加工型・サービス型産業への産業構造の変化がおこり、エネルギー消費量は横ばいないし低下しました(図1-1-8)。
石油危機を契機にエネルギー構成は、石油が減少し石炭は横ばいに推移し、大気汚染物質の排出が少ない天然ガスと原子力がシェアを伸ばしました。また、最終エネルギー消費は、石油危機前後の昭和40年と昭和55年を比較すると、産業部門の割合が減少し、民生部門・運輸部門の割合が家電製品の普及・高機能化、自動車輸送の増大等により拡大しました。
産業活動を原因とする公害問題は、法律による規制の効果、企業の努力等によって収束をみせつつあり、例えば、大気汚染に関する硫黄酸化物対策(重油脱硫及び排煙脱硫)は、その効果が顕著に現れた事例であるということができます(図1-1-9、図1-1-10)。
しかし、大都市圏に人口が集中したこと、所得向上によって自動車が普及したこと等により、自動車排気ガスによる大気汚染や生活排水等による水質汚濁など日常生活や通常の事業活動に伴う都市生活型公害が問題となったのもこの時期です。
第I期での大気汚染対策としては、硫黄酸化物の濃度規制に始まり、次いで個別排出源の排出量を抑えるK値規制*に移行し、随時強化がされたことにより汚染は改善傾向にありました。しかしながら、第II期に入っても工場密集地域を中心に環境基準に照らすと依然として深刻な状況にあり、工場、事業場ごとに排出総量を規制する総量規制を昭和49年に導入しました。また、窒素酸化物についても、同様の総量規制を昭和56年に導入しました。
*K値規制
硫黄酸化物の規制方式であり、煙突の高さに応じ、ばい煙発生施設ごとに排出量が定められる。
水質汚濁対策としては、昭和48年に瀬戸内海環境保全臨時措置法*が制定され、昭和54年には、上流域等内陸部からの負荷を効果的に規制するために、瀬戸内海、東京湾、伊勢湾において化学的酸素要求量(COD)に係る総量規制を開始しました。湖沼については、生活系、農畜水産等の水質汚濁に対応するとともに、場合に応じて総量規制の導入を可能とする湖沼水質保全特別措置法*を昭和59年に制定しました。
このように、この時期には、従来の汚染物質の濃度に着目した規制から、総量を規制する方向へと一段の強化が図られました。
*瀬戸内海環境保全臨時措置法
昭和48年10月2日法律第110号
*湖沼水質保全特別措置法
昭和59年7月27日法律第61号
なお、この時期の後半である昭和57・58年度の環境庁調査で、トリクロロエチレン等による地下水の広範な汚染が判明するなど、次の時期に大きな課題となる問題も徐々に現れてきました。
(3)地球環境問題が認識され始めた時期(第III期:昭和60年代以降)
この時期は、経済のボーダーレス化が進み、原材料のみならず、中間原材料、部品等の海外調達や製品の輸入が拡大するとともに、原油価格の下落により、化学、パルプ等のエネルギー多消費型産業の生産が増加したほか、円高の進行により製品の高付加価値化が進みました。一方、国内においては、東京への一極集中が加速するとともに、バブル経済等により個人消費の拡大がもたらされた後、バブル経済の崩壊後は、長期の不況、消費低迷等に直面することとなりました。
前半の急速な経済の拡大期には、すでにさまざまな環境対策の枠組みがあったことから、第I期にみられたような産業型公害の発生が再び繰り返されることはありませんでしたが、第II期の日常生活や通常の事業活動に伴う都市生活型公害が依然として広がりをみせるとともに、大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会経済システムが、わが国のみならず地球規模で拡大をみせたことにより、廃棄物・リサイクル問題や地球環境問題等の新たな環境問題を生じさせることとなりました。また、科学的に未解明な点が多い、内分泌かく乱化学物質(いわゆる環境ホルモン)問題が生じたのもこの時期からです。
政府においては、こうした従来の産業型公害から地球環境問題等の今日の環境問題への環境問題の質の変化に対応するため、平成5年、従来の公害対策基本法を廃止し新たに環境基本法を制定し、翌平成6年には、同法に基づく環境基本計画を定めることにより、こうした新たな課題への基本的な方針を示すとともに、新たな対応を図るための各種対策を急速に整備することとなりました。こうした新たな個別の対策については、総説第2章第3節で紹介することとします。