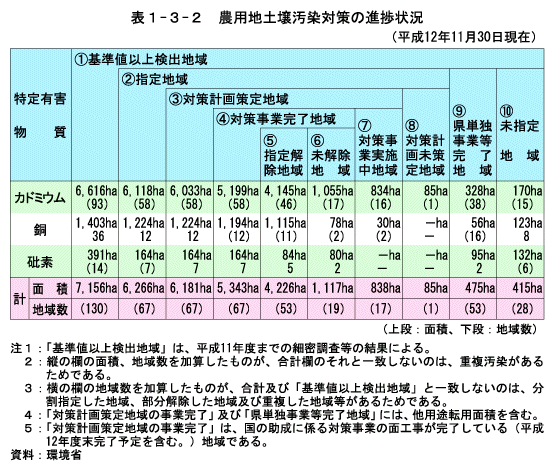
2 土壌環境の安全性の確保
(1)環境基準の設定
平成11年2月、水質汚濁に係る環境基準及び地下水の水質汚濁に係る環境基準に硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素並びにほう素が追加されたことを受け、地下水等における水質保全と密接な関係を有する土壌についても、平成12年12月26日の中央環境審議会の答申を受け、従来のカドミウム等25項目に加え、平成13年3月28日に新たにふっ素及びほう素の2項目が土壌の汚染に係る環境基準に追加されました。
(2)未然防止対策
土壌への有害物質の排出を規制するため、水質汚濁防止法に基づき工場・事業場からの排水規制や有害物質を含む水の地下浸透禁止措置、大気汚染防止法に基づき工場・事業場からのばい煙の排出規制措置、農薬取締法に基づき土壌残留性農薬の規制措置、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき廃棄物の適正処理確保のための規制措置等を講じています。
また、金属鉱業等においては、鉱山保安法に基づき鉱害防止のための措置を講じています。金属鉱業等に係る鉱山の施設には、操業停止後も引き続き鉱害を発生するおそれがあるため、金属鉱業等鉱害対策特別措置法に基づく鉱害防止事業の計画的な実施等に努めています。
さらに、休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金制度により、当該防止工事の促進を図っています。なお、金属鉱業事業団では、使用済特定施設の鉱害防止事業に必要な資金及び土壌改良事業に係る事業者負担金に対する融資・債務保証、鉱害防止事業基金への拠出金に対する融資、鉱害防止積立金及び鉱害防止事業基金の管理・運用、鉱害防止技術の開発のための調査研究、地方公共団体の実施する鉱害防止事業に対する調査指導及び設計等の指導支援の業務を実施しています。また、鉱山における坑廃水処理について、永続的に消費されるエネルギーの削減を図るため、省エネルギー型坑廃水処理技術の開発を行っています。
(3)農用地土壌汚染対策
基準値以上検出地域のうち平成12年11月30日現在までに6,266ha(67地域)が農用地土壌汚染対策地域として指定され、そのうち6,181ha(67地域)において農用地土壌汚染対策計画が策定済みです。公害防除特別土地改良事業等により5,818haで対策事業が完了(平成12年度末完了予定を含む。)しています。対策事業の進捗率は81.3%となっています(表1-3-2)。
なお、カドミウム汚染地域においては、対策事業等が完了するまでの暫定対策として、汚染米の発生防止のための措置が講じられています。
このほか、農用地土壌から農作物へのカドミウム吸収抑制技術等に関する研究が実施されています。
さらに、農用地における土壌中の重金属等の蓄積防止に係る管理基準に基づき、土壌汚染の未然防止に努めています。
(4)市街地等の土壌汚染対策
市街地等の土壌については、環境基準の達成維持に向け、「土壌・地下水汚染に係る調査・対策指針」に基づき、土壌の汚染が明らか又はそのおそれがある場合には、土地改変等の機会をとらえて環境基準の適合状況の調査を実施し、汚染土壌の存在が判明した場合には可及的速やかに環境基準達成のために必要な措置が講じられるよう、事業者等の自主的な取組を促進しています。また、民間事業者による市街地等の土壌汚染対策に対し、日本政策投資銀行が融資を行っています。
また、地方公共団体が実施する環境基準の適合状況の調査、土壌汚染の調査・対策の技術体系をモデル実証する事業に対して助成するとともに、土壌汚染浄化新技術の検討、土壌汚染調査・対策事例等の把握や土壌汚染リスクに関する情報の整備・提供のための調査等を行いました。
さらに、土壌を直接摂取する経路に着目した土壌中の有害物質の含有量によるリスク評価や今後の土壌環境保全対策のために必要な制度のあり方についての検討に着手しました。
(5)ダイオキシン類による土壌汚染対策
社会的に大きな関心を集めているダイオキシン類については、ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、ダイオキシン類に係る土壌環境基準及びダイオキシン類による汚染の除去等をする必要があるダイオキシン類土壌汚染対策地域を指定する要件が定められました。平成12年度からは、地方公共団体による全国のダイオキシン類の常時監視が開始され、土壌については市街地及び発生源周辺を中心に約3,000地点の調査が行われています。
加えて、全国の農用地土壌及び農作物の実態調査を行うとともに、ダイオキシン類汚染土壌を用いた植物栽培試験、またダイオキシン類汚染土壌の浄化技術の実証試験等を実施しました。