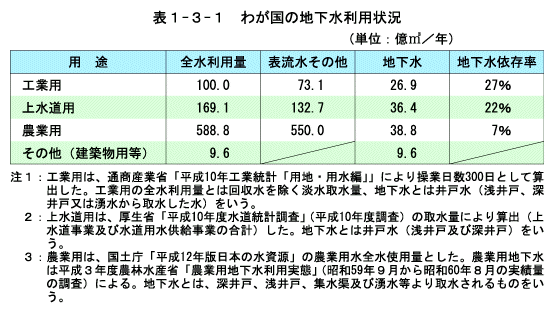
1 土壌環境、地盤環境の現状
土壌は、環境の重要な構成要素であり、人をはじめとする生物の生存の基盤として、また、物質の循環の維持の要として重要な役割を担っており、食料生産機能や水質浄化・地下水かん養機能など、多様な機能を有しています。
土壌汚染の原因となる有害物質は、不適切な取扱いによる原材料の漏出などにより土壌に直接混入する場合のほか、事業活動などによる水質汚濁や大気汚染を通じ二次的に土壌中に負荷される場合があります。また、土壌は、その組成が複雑で有害物質に対する反応も多様であり、一旦汚染されると、有害物質が蓄積され汚染状態が長期にわたるという特徴を持っています。
(1)土壌環境の現状
ア 農用地の土壌汚染
「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律」に基づく特定有害物質による農用地の土壌汚染の実態を把握するため、汚染のおそれのある地域を対象に細密調査が実施されており、平成11年度はカドミウムに係る調査が8地域607haにおいて実施されました。これまでの基準値以上検出面積の累計は130地域7,156haとなっています。
イ 市街地等の土壌汚染
市街地等の土壌汚染問題については、近年、工場跡地や研究機関跡地の再開発等に伴い、有害物質の不適切な取扱い、汚染物質の漏洩等による汚染が判明する事例が増加しています。
平成3年8月に「土壌の汚染に係る環境基準」(以下「土壌環境基準」という。)が設定されて以後、都道府県や水質汚濁防止法に定める政令市が土壌環境基準に適合しない土壌汚染事例を把握しており、平成11年度に判明したものは117件に上っています(序説図2-4-6参照)。
また、事例を汚染物質別にみると、鉛、砒素、六価クロム、総水銀、カドミウム等に加え、金属の脱脂洗浄や溶剤として使われるトリクロロエチレン、テトラクロロエチレンによる事例が多くみられます。
ウ 土壌侵食*
土壌環境への影響は汚染だけでなく侵食があります。
わが国は傾斜地が多く多雨なので侵食を受けやすいため、水田や森林によって表土流出防止が図られています。しかし、水田や森林の保全管理が十分なされない場合には土壌侵食のおそれもあり、留意する必要があります。
*土壌侵食
土壌侵食は水や風の作用によっておこり、侵食量は気候、地形、植生、土壌の種類、人為的要因等により影響される。人為的要因とは過放牧、過度の森林伐採、不適正な農業、大規模開発などをさす。
(2)地盤沈下の現状
地盤沈下は、地下水の過剰な採取により地下水位が低下し、粘土層が収縮するために生じます。いったん沈下した地盤はもとに戻らず、建造物の損壊や洪水時の浸水増大などの被害をもたらします。
地下水の採取は工業用、水道用、農業用、建築物用、水産養殖用、消雪用等多岐にわたっています(表1-3-1)。
代表的な地域における地盤沈下の経年変化は、図1-3-1に示すとおりであり、平成11年度までに、地盤沈下が認められている主な地域は47都道府県のうち37都道府県62地域となっています。
最近におけるわが国の地盤沈下の特徴をあげると次のようになります。
1) 全国の地盤沈下面積の集計を開始した昭和53年度以降、平成9年度に初めて年間4cm以上沈下した地域が認められないという結果となりましたが、平成11年度も引き続き年間4cm以上沈下した地域は認められませんでした。年間2cm以上沈下した地域の数は9地域で、沈下した面積は6平方キロメートルでした(図1-3-2)。
2) かつて著しい地盤沈下を示した東京都区部、大阪市、名古屋市などでは、地下水採取規制等の対策の結果、地盤沈下の進行は鈍化あるいはほとんど停止しています。しかし、千葉県九十九里平野など一部地域では依然として地盤沈下が認められています。
3) 長年継続した地盤沈下により、多くの地域で建造物、治水施設、港湾施設、農地及び農業用施設等に被害が生じており、海抜ゼロメートル地域では洪水、高潮、津波などによる甚大な災害の危険性のある地域も少なくありません。