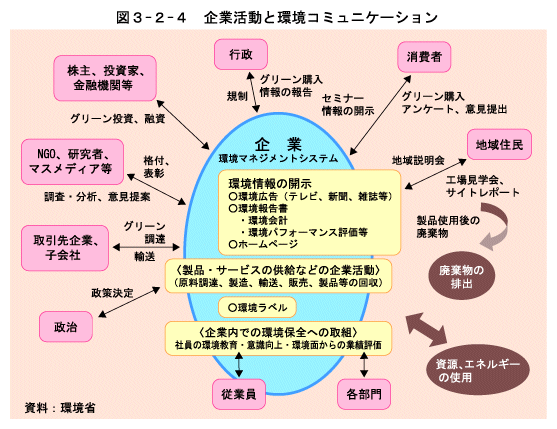
2 企業を中心として見た場合
企業は製品、サービスの市場への供給などの一連の事業活動の中で、資源、エネルギーの使用や廃棄物の排出を通じて環境に負荷を与えています。企業自らが、どのような環境負荷を発生させ、どのように低減していけばよいのかについて的確に把握することがまず重要です。さらに企業が社会の支持を受けながら事業活動を行う上で、それらの現状を環境報告書や環境ラベル、環境広告などを通じて、消費者、投資家、取引先、従業員、金融機関、地域住民といった多様な利害関係者へ開示していく説明責任もあるといえます。環境面からも企業が評価されるようになってきている今日、このような企業による環境コミュニケーションの果たす役割はますます大きくなっており、今後も様々な取組を充実させていくことが重要です。
(1)企業活動と環境コミュニケーション
企業による環境情報の提示は年々増加しており、企業側でも環境コミュニケーションの重要性が認識されつつあります。一方、人々が環境に関する企業イメージを形づくる要因には、製品の開発や設計、製造などにおける具体的な環境対応や、その企業や製品の属する業界や製品のカテゴリー、その企業への信頼性、情報源となる媒体の種類(テレビ、広告等)などが挙げられます。ここでは、様々な利害関係者との関わりを持っている企業を中心とした環境コミュニケーションについて、図を参考にしながらいくつか例をみてみましょう(図3-2-4)。
ア 環境情報の開示件数の増加と意識
環境省が毎年行っている「環境にやさしい企業行動調査」の結果によると、企業による環境情報の開示件数は年々増加してきています(図3-2-3)。また、12年度調査結果によれば、環境情報を公開している企業に対する公開目的についての認識に関する質問では(複数回答可)、約70%の企業が社会的責任、コミュニケーション、PRのため、という回答をしています。なお、約50%の企業が社員等への教育のためと回答しています。
イ 各主体との環境コミュニケーション
(ア)消費者との関係
環境ラベルや環境報告書などの情報による環境コミュニケーションは、消費者のグリーン購入をはじめとする環境保全行動を促進させることができるといえます。国立環境研究所が平成11年度に行った日本の企業調査の結果では、環境情報を提供している企業が、それらの情報への消費者からの反応についての質問(複数回答可)に対して、環境広告に消費者が敏感に反応して売れ行きが伸びた(11%)、環境広告によって環境に配慮しているイメージが定着した(34%)、環境に配慮してほしいという要望が直接寄せられた(12%)という回答をしており、環境情報の提供に対する消費者からの反応をみてとることができます。
さらに、ある通信販売会社では、販売している商品について、「長期使用性」や「再生可能性」などの環境面からの評価をしてわかりやすく伝え、また、「環境保全活動は消費者とともに考える」という趣旨で、消費者を対象にした環境関連のセミナーを開催しています。さらには、製品をどのように使用し、廃棄すれば環境負荷が少ないかという説明や表示を行うことも環境コミュニケーションの一つといえます。また、環境報告書に添付されたアンケートなど、消費者が企業に対して環境対応について意見を提出できる途も増えつつあります。
(イ)株主・投資家、金融機関との関係
企業の環境保全への取組状況や環境負荷量、削減量又は環境リスクなどの現状を投資や融資の際の判断材料とする動きがみられます。例えば、環境負荷低減に積極的な企業の株式に重点的に投資するエコファンドのような金融商品が次々と登場したり、企業の環境保全事業に対して低利融資制度を設ける金融機関が現れたり、保険会社や年金基金が環境という要素に注目しながら運用を行ったりする動きがあり、企業の環境情報は、このような投資、融資のための判断に必要不可欠となっています。
(ウ)行政との関係
水質汚濁防止法やPRTR法のように環境に関する情報の開示が政策手法として位置付けられている法律において、行政も企業からの環境情報の受け手となっています。あるいは、企業の行政に対する意見も十分考慮しながら環境政策が行われることも必要です。さらには、グリーン購入を実施する事業主体としての行政は、環境物品等の調達の推進に関する基本方針に基づき調達方針を定め、財・サービスに関する環境情報の受け手となり、グリーン購入を行います。
(エ)内部組織、従業員との関係
企業とその各部門や社員とその家族もまた環境情報の受け手であり送り手でもあります。社内の環境コミュニケーションは、企業の内部組織や社員への環境教育という効果や、社員やその家族がそろって環境保全活動を行うことの意義が非常に大きいといえます。例えば、ある大手企業では、社員の環境意識を高めるプログラムを進めると同時に、業績評価に環境対策の達成度を組み込む試みを行っています。また、家族も巻き込んだ動きとしては、ある鉄鋼メーカーグループでは、社員と家族に省エネやリサイクルの重要性を認識してもらえるように、独自の環境家計簿を配布し、記録してもらい、その記録を回収・集計した上で評価結果をフィードバックしています。また、グリーン購入ネットワークの第4回グリーン購入アンケート調査によると、グリーン購入ネットワークの会員になっている企業では、非会員の企業よりも社員への環境教育、啓発活動がより盛んに行われているという結果が出ています(図3-2-5)。
(オ)NGO、研究者、マスメディアとの関係
最近では、大学やマスメディアが企業に対して環境意識や環境経営のあり方についての調査を行って発表したり、それをもとに問題提起を行ったりしています。また、ある新聞社やNGOは、企業の発表する環境報告書や環境広告の中で優秀な内容のものに対して表彰を行ったりしています。このように、企業側からただ一方的に情報が発信されるだけではなく、NGOや研究者、マスメディアなどがその情報を解釈、分析するなどして媒介することにより、受け取る側にとっても情報が理解しやすくなります。
(カ)地域社会との関係
事業所、工場や店舗の周辺の住民にとっては、それらの建物や施設でどのような環境負荷が生じ、どのような環境保全対策が講じられているかは非常に身近な問題になります。例えば、ある電子機器メーカーの工場では、地域の住民に対して工場についての説明会を開催し、実際に工場を見学してもらい、あるいは、事業所単位の環境報告書に当たるサイトレポートを作成することにより、住民の無用な不安を解消し、信頼関係を築く努力を行っています。
(キ)取引先、企業同士の関係
環境省が毎年行っている「環境にやさしい企業行動調査」によると、資材や機材の調達を環境への配慮で選別するグリーン購入の動きが本格化していることがわかります。具体的には、多くの電気機器メーカーは、グリーン調達の基準を設け、基準書を作成することにより、グリーン調達を実施しています。また、建設業やガス会社においても、資機材や工法について環境配慮基準を作成し、それを発注の条件としています。
(2)企業を中心とした環境コミュニケーションの深化の背景
企業を中心にした環境コミュニケーションがこのように質、量ともに充実してきている背景としては、環境問題の性質や政策手法、社会の環境問題への意識の変化などに伴い、環境経営がより盛んになり、また、グリーン購入やグリーン投資の増加に伴い、利害関係者による環境面に着目した企業評価の必要性が増大していることなどが挙げられます。
ア 環境問題の質的変化と政策手法の変化
環境問題が、高度経済成長期の産業公害型から、地球温暖化問題や交通問題、廃棄物問題等、環境負荷の発生源が不特定多数の都市・生活型になるなどの質的変化により、それに対応する政策手法も変化しています。従来からの規制的手法に加え、経済的手法の検討や、企業の自主的取組手法、情報的手法の活用を含めた多様な政策手法が取り入れられるようになり、環境問題の解決にも市場原理や競争原理の導入が進められつつあります。また、生産した製品などについて、生産者自らが、製品などが使用されて廃棄物となった後まで一定の責任を負う拡大生産者責任の考え方も重視されつつあります。
イ 環境経営の進展
そうした中で、企業の環境経営への意識の変化も見られます。企業の中でも事業を持続していくためには環境に関する取組が重要であるという認識が高まり、また、エコビジネスは可能性の広がるビジネスチャンスであるという認識が近年増加しています。
そして、企業が経営戦略や事業戦略の中に環境対応を具体化する環境経営を重視する要因としては、従来型のように環境関連の法規制に対する受動的な対応から、近年では環境を重視する取引先や、環境対策が成長力につながると考える消費者や投資家への対応、あるいはトップの経営者の方針や社会的責任の全う、新規市場の開拓、環境汚染による被害の未然防止など、幅広く将来に対する投資として積極的に受けとめられるようにもなっています。
このように、より積極的な対応に潮流が変わりつつある環境経営においては、環境マネジメントシステムの導入や環境配慮型製品やサービスの企画、製造工程のグリーン化、資源や部品のグリーン調達や環境に関する社会貢献活動などの取組が進められています。こうした環境経営を支える上で必要不可欠なものとして、社内組織や消費者、取引先やNGOなど様々な主体と、これまでみてきたような環境コミュニケーションへの取組が積極的に行われるようになっています。
ウ 消費、投資のグリーン化の進展
企業による環境保全への取組が進む一方、環境に配慮した製品を購入したり、無駄なものを買わないようにする消費者も増えてきています。平成4年に発足したグリーン購入ネットワークの会員も年々増加を続けており、企業のグリーン購入への意識も高くなり、取組も盛んになっています。さらに、グリーン購入法も成立し、今後は国や地方公共団体などによるグリーン調達もますます増加することが予想されます。ある大手OA機器メーカーでは、このようなグリーン調達の動きに積極的に対応するため、事務機器全機種の生産、使用、廃棄に係る製品の環境負荷情報を公開しています。
例えば、産業能率大学が行った企業と自治体を対象とした「顧客満足型エコマーケティング実態調査」によると、「グリーン調達・グリーン購入は今後もさらに拡大・定着していくと思うか」という質問に対し、約93%の回答が肯定的であったのに対し、「環境配慮商品に関する情報が充実していると思うか」という質問に対しては、約72%の回答が否定的なものでした。今後グリーン購入が進むにつれ、環境情報がますます重要になることが予想されます。さらに、グリーン購入を実施している企業や自治体は、グリーン購入を実施する際の情報として、現在は環境ラベルを重視していることもわかります。
また、日本でもエコファンドが普及しつつあるのをはじめ、既にUNEP保険業界環境声明*に署名していた損害保険会社に加え、大手証券会社がUNEP金融業界環境声明*に署名する動きがありました。また、東京都教職員互助会により特定金銭信託として自主運用のエコファンドが設定され、さらに、大手都市銀行などにおいても共同して環境リスク評価システムの検討が開始されるなど、金融と環境の密接な関係がさらにこれから進んでいくことが予想されます。
*UNEP保険業界環境声明
1995年に経済と環境の両立や環境リスクの管理における保険業界の役割の重要性に対する認識を基に保険会社によって起草され、署名が呼びかけられたもの
*UNEP金融業界環境声明
地球サミットの前に数十行の銀行とUNEPとが共同して取りまとめた「環境と持続的な発展に関する銀行声明」に、後に資産運用会社や証券会社等が加わってできたもの
エ 市場のグリーン化と環境コミュニケーションの進展
このように消費者や投資家が環境配慮型の製品やサービスをより選好し、グリーン購入やグリーン調達、グリーン投資が拡大することにより市場全体がグリーン化していけば、利害関係者が企業や製品を環境面から評価する必要性が大きくなります。そのような社会的な評価のためには、環境保全への取組状況に関する情報をより充実させていくことが重要であり、それが企業による環境コミュニケーションを一層進展させる動機付けとなります。
これまでみてきたように、環境政策の手法が規制的手法に加えて経済的手法を重視してきていること、同時に企業の環境経営が進んできていること、一方で消費者や投資家も消費や投資をグリーン化しつつあることなどを背景に、企業にとっては「環境」という新しい評価基準が競争条件として出現しつつあるといえます。このいわゆる「環境淘汰」に生き残っていくためにも、企業を中心とした環境コミュニケーションの重要性が高まっていくといえます(図3-2-6)。
(3)環境コミュニケーションの手段の充実
企業の環境コミュニケーションの手段として、企業が市場に供給している製品そのものに関する環境情報を提供する環境ラベルのようなものと、企業活動全体での環境保全への取組についてわかりやすく説明する環境報告書のようなものとが主に考えられます。
ア 環境ラベルなどによる環境情報の提供
消費者が製品・サービスを購入する際、その設計や原材料、生産工程や消費、廃棄の各段階においてどのように環境配慮がなされているのかを判断するために、環境ラベルなどの手段が用いられます。
例えば、国際標準化機構(ISO)による環境ラベル規格の分類では、第三者機関が、独自にラベルの基準設定、認証方法を規定するタイプI、製造者自らが製品、サービスの環境配慮を主張するタイプII、資源消費量の製品の環境負荷などを定量的に表示するタイプIIIに類型化されています。世界エコラベリングネットワーク(GEN)は、世界各国の様々な取組の中からタイプ?の取組を紹介していますが、この中で取り上げられている日本のエコマークについては、専門家による審査委員会により、商品のライフサイクルを通じて様々な環境負荷について総合的な評価・検討を行った上で認定がなされています。また、ある電子機器メーカーでは、独自に環境配慮基準を設け、適用製品に独自のシンボルマークをつけるというタイプ?の取組を行っています。
ただし、環境配慮型の製品であっても、必要以上に使ったり誤った使い方をしては環境負荷が生じかねません。例えば成分が環境配慮型の洗剤であっても適切な分量を考えないで使えば十分な効果は得られません。ハイブリッド車であっても運転の仕方によっては効果が減殺されかねません。また、どんなに長く使用出来る商品であっても、廃棄の仕方によっては環境負荷を生じさせてしまうおそれもあります。それらの製品が正しい用法で使用された上で、適切に廃棄、再資源化されるべく、製造者がわかりやすい情報を説明書や表示などを用いて発信することも環境コミュニケーションの一つだといえます。
このように、消費者が環境配慮型の製品やサービスを使用・消費、廃棄することによってどのように環境負荷の抑制に貢献できるのかという環境情報をラベルや説明書、パッケージなどを活用してわかりやすい形で明示し、環境により良い選択がなされるような仕組みを一層活用していくことが重要です。
イ 環境報告書や環境会計などによる取組
環境ラベルが主に製品そのものの性質に着目した環境面からの評価であるのに対し、環境報告書は、環境マネジメントシステムなどの体制や手続の下で行った事業活動全体の取組に関して、環境会計や環境パフォーマンス評価などの手法で評価し、その結果や過程を公表する手段となっています。それらの手段について順にみてみましょう。
(ア)環境報告書
図3-2-3でもみたように、近年、環境マネジメントシステムを導入し、環境報告書や環境会計を発表している企業は年々増加を続けています。環境報告書は、企業自らの環境保全への取組の方針や計画、実績などを外部に公表し、読み手となる利害関係者による企業評価の判断材料の一つにもなっています。
現在、国際的にも環境報告書のガイドラインが作られており、CERES*、PERI*、UNEP*、WICE*等が発行したものがあります。日本においても、環境省が策定したもの、民間団体が発行したものなどがあります。また、1997年からは、GRI*において、各種ガイドラインを統合し、国際標準を作成する取組がなされ、その成果が2000年6月に「持続可能性報告のガイドライン」として発表されています。今後さらに検討が行われるものの、そこでは、経済的、環境的、社会的パフォーマンスについて報告する上で必要な、記載事項、基本原則や定性的特性、パフォーマンス報告の要素の分類やその指標などについて類型化されています。
また、環境報告書の作り手と読み手による交流も広がっており、環境報告書などによる環境コミュニケーションの発展を図ることを目的として、幅広い企業、NGO、学識経験者などによる「環境報告書ネットワーク(NER)」というネットワーク組織も設立されています。
CERES
Coalition for Environmentally Resposible Economies
PERI
Public Environmental Reporting Initiative
UNEP
United Nations Environment Programme
WICE
World Industry Council for the Environment
GRI
Global Reporting Initiative
コラム参照
(イ)環境会計
環境会計を導入、公表する企業数も年々増加を続けています。環境会計は、企業などが事業活動における環境保全対策のためのコストとそれにより得られた効果を可能な限り定量的に把握、分析し、公表するための仕組みであり、現在その手法等について様々な検討が行われています。環境会計の導入は、作成する企業内部において環境保全コストの把握や環境投資の意思決定に役立てられるというメリットがあるだけでなく、環境会計情報を公開することにより、外部評価を経て社会からの信頼を確保するというメリットもあります。利害関係者は、より体系的で定量的な環境会計情報により、企業を環境面から判断するための材料を得ることができるという意味で、環境会計は環境コミュニケーションの重要な手段の一つだといえます。
なお、環境省によるガイドラインの策定など環境会計の普及に向けた動きのほかに、石油業界やガス業界、建設業界、ゴム業界などでは、環境会計に業種特性を反映していく取組が行われています。
(ウ)環境パフォーマンス指標
企業が事業活動において環境配慮を進めていくためには、自らが発生させている環境への負荷やそれへの対策の成果(環境パフォーマンス)を的確に把握し、自己評価していくことが必要となります。環境パフォーマンス指標とは、この環境パフォーマンスを測るための指標といえます。企業が指標を用いて自己評価するとともに、その結果や過程を広く情報開示していくことにより、その情報の受け手である消費者や投資家などの利害関係者は企業を環境面から判断するための材料を得ることができます。
海外における環境パフォーマンス指標に関する研究状況としては、持続可能な発展のための世界経済人会議*が発表した「環境効率指標と報告」や、GRIが発表した「持続可能性報告のガイドライン」、環境と経済に関するカナダ円卓会議(NRTEE)が発表した「ビジネスにおける環境効率の測定:コア指標の可能性」、世界資源研究所(WRI)が発表した「メジャーリングアップ」などの中でそれぞれ指標の例が挙げられています。
また、ISO(国際標準化機構)がISO14031(環境マネジメントー環境パフォーマンス評価ー指針)を発行し、環境パフォーマンス評価のプロセスを示しています。
なお、環境報告書や環境会計、環境パフォーマンス指標についての行政の取組状況については、第3節で後述します。
*持続可能な発展のための世界経済人会議
WBCSD:1992年の地球サミットに対応して1991年(平成3年)に設置された。世界33カ国から経済界のメンバーが集まり、企業の環境効率性を高めることを目的として主導的な役割を果たしている。
ウ 環境経営への他の主体の参画
(ア)環境コミュニケーションにおける双方向性
企業の環境保全への取組には、環境コミュニケーションを通じて、消費者や取引先などの他の主体からの意見が取り入れられつつあります。この双方向性をもったコミュニケーションによる評価の仕組みは、企業の環境保全への取組のインセンティブとして機能し始め、企業が社会とどのような関わり方をするかが問われてくることになります。これからの環境問題の解決のためには、各主体の持てる能力を最大限に発揮することが重要であるため、それを引き出すための相互評価と透明性、客観性の確保が重要です。
a 媒体としてのインターネットなどの活用
消費や投資を経由する以外にも、企業の環境情報に対して、情報の受け手が直接意見を発信できるような手段で双方向性を確保するものもみられます。
例えば、環境報告書の中にそれを読んだ人が意見や感想を寄せられるようにアンケート用紙や葉書を入れたり、あるいは、ホームページ上で報告書を公開している場合には、情報の受け手がオンライン上で意見を送信することによって、多くのフィードバックがあり、企業にとってもその後の取組の参考やインセンティブにもなります。
b 企業の環境面からの格付け、表彰の動き
企業による環境報告書などの発行数が世界的に増加するにつれ、それらの環境情報をもとに、目的や手法は多様であるものの、NGOや調査機関などの様々な主体によって企業の環境格付けや表彰、監査などが行われるようになっています。これは、企業の発信する環境情報に対する他の主体からの重要な反応の一つだといえます。
3でこれから紹介するNGOによる取組の他にも、調査会社など様々な団体が、環境の状態や、環境を含めた社会的責任について格付けした評価ランキングを消費者や投資家に向けて発表しています。例えば、海外のある調査会社は、金融の専門家が環境要因を組み入れた企業評価モデルを開発し、このモデルを活用した企業の環境格付け情報を大手機関投資家を対象に販売しています。また、ある機関投資家向けの調査情報機関は、社会的責任投資(SRI)指数を作成し、それがアメリカのSRIファンドのベンチマークとして使用されています。このような企業の環境格付けを消費者や投資家を対象に行っている団体は、それぞれに評価のための基準や指標を開発、策定し、それに基づいて格付け結果を公表しています。
優れた環境報告に対しての表彰は、欧米をはじめ多くの国で実施されています。1997年には、イギリスのACCA*の呼びかけにより欧州環境報告賞が創設され、現在、イギリス、デンマーク、オランダ、ベルギー、フランス、ドイツ等の国が参加する制度となっています。日本においても、「環境レポート大賞*」や、「環境報告書賞(グリーン・リポーティング・アウォード)*」が、それぞれ実施されており、優れた環境報告書を社会的に評価しようとする動きが広がってきています。
*ACCA
The Association of chartered Certified Accountants
*環境レポート大賞
(財)地球・人間環境フォーラム及び(社)全国環境保全推進連合会の共催で行われている。
*環境報告書賞
東洋経済新報社及びグリーンリポーティングフォーラム(民間団体)の共催で行われている。
c 第三者意見レビューの動き
環境報告書を環境コミュニケーションの媒体として活用する上で、環境報告書の内容について、中立、独立的な第三者による検証や意見の付記を行うことによって信頼性を高めるという取組も増えています。ただし、検証などに当たっての基準や方法について特にルールが定められておらず、情報の正確性や内容の網羅性、対策内容の適切性、法律等の遵守状況などの観点から審査がそれぞれに行われているのが現状です。また、監査を行う主体としては、環境に関する専門家や監査法人、NGOなどがみられます。このため、環境報告書の信頼性をどのような主体がどのように確保していくかも重要な課題だといえます。 (イ)他の主体とのパートナーシップが生み出す効果
これまで、立場や主張の異なる主体との環境情報の交流を通じた相互理解や信頼関係の深化によって、環境保全への取組が促進される例をみてきました。ここでは、このような環境コミュニケーションを経て、異なる主体同士がさらにそれぞれの持てる能力・資源を有効に組み合せることで、問題解決のための大きな原動力となり得るパートナーシップについてみてみましょう。
a 各主体の得意な分野を活用したノウハウの提供が可能になる
そもそも設立趣旨の異なる企業とNGOが、お互いに持っている人材や情報、アイデアなどを提供し合うことにより、パートナーシップを築きながら環境問題の解決に当たるという動きが見られ、今後このような取組が進むことが期待されます。
具体的には、図3-2-7のように、企業とNGOは寄付やノウハウ、人材の提供などの様々な側面で結びつきを持っています。例えば、アメリカのある大きな環境NGOは、ある大手の食品会社や自動車メーカーなどの環境管理について、計画策定段階からのコンサルティングを実施し成果をあげています。また、環境NGOの安定した組織運営能力を高めるために、企業が経営や人材管理などのノウハウを活かしてNGOに協力する事例などもみられます。
b 他の主体とのコミュニケーションそのものが社会的評価を高める
環境問題に関する政策提言力などで社会から評価されている環境NGOとの間に協力関係を築いていることが、企業の社会的評価を高めることにもなり得ます。例えば、評価される側の企業が、格付け機関やNGOなどの評価を行う主体とどの程度コミュニケーションを行い、信頼関係を築いているかも、評価をする側にとっては重要な点になります。そもそも評価を受ける側に不信感や不安感があっては、適切な環境情報が提供されない可能性もあるからです。このように、様々な利害関係者が企業を評価する際に、その企業が社会と、あるいはNGOやマスメディア、格付け機関などとどのような関係性を有しているかも重要な評価項目となってきています。
(4)企業の環境コミュニケーションの今後のあり方
a 企業による環境情報開示の問題点
様々な企業による環境情報開示が進められていますが、その目的や頻度、内容、手法、情報の送り手と受け手の間の認識のギャップなど、様々な考慮事項があります。
例えば、平成12年度に国立環境研究所が行った、環境報告書を作成している、あるいは作成を検討している企業を対象に行った環境コミュニケーションに関する調査結果によると、企業が環境情報の提供において重視している利害関係者(上位3つまでを回答)として挙げたものは、順に、地域社会、取引先企業、社内(経営者、従業員、労働組合等)、消費者と続き、また、市民としての個人は消費者と異なり「重要視している」という回答が8%にとどまりました。その一方で企業が環境情報を提供した際の利害関係者からの反応についての質問に対しては、最も反応の多かった利害関係者は社内(約85%が「反応がある」(「反応がかなりある」と「反応が少しある」の合計。以下同様。)と回答。)からのものであり、次いで取引先企業(76%)、行政(61%)、マスコミ(58%)、地域社会(48%)と続き、消費者から反応があると答えた企業は40%、NGOについては38%、市民については33%にとどまりました。このように、消費者はコミュニケーションの対象として重視されている反面、他の利害関係者と比べて反応が少なく、また、消費者としてではない一般市民としての個人は対象としてあまり重視されておらず、環境コミュニケーションの対象は誰で、何が目的なのかという点で興味深い結果となっています。
一方、企業が発信する環境情報の信頼性をどのように確保するかも、情報の受け手からはとても重要になります。前述の「環境にやさしい企業行動調査」によれば、環境報告書を作成している企業の信頼性確保の方法としては(複数回答可)、「厳格な内部管理・監査」が約6割、「外部からの意見の受け入れ」が約3割、「特に行っていない」が2割という結果となっており、現段階においては客観性確保のための十分な手段が講じられているとはいえません。
b 環境情報開示の今後の方向性
このように、企業が発信する環境情報は、作り手と読み手の認識の差の問題に加え、そもそも開示をする相手、対象が誰なのか、何をどのように伝えたいのか、何が目的なのかなどによってその開示のあり方も自ずと変わってくるという本質的な問題を含んでいます。
まず、環境情報の受け手は社員から取引先、投資家、一般消費者、報道機関、格付け機関、NGOなど様々なので、読み手がそれぞれの目的に合わせてみられるような情報開示のあり方が望ましいといえます。それには、情報開示の媒体を紙やHP(インターネット・ホームページ)など目的や対象者に合わせて工夫することもでき、例えば情報量を減らして見やすさを優先した小冊子や、さらに詳細情報を必要な人のためには詳しい資料つきのものを、さらにはHPのデータベースでは、受け手が自分に必要な情報を検索して引き出せるようなものを、それぞれ提供キることが可能です。また、どんな媒体のものであっても、受信窓口を常に開いておくことは、企業が社会から意見を聞く上で非常に重要になります。
次に、多くの企業が環境情報を発信するようになり、それらの情報をどのように受け手が比較できるかという問題もあります。受け手にとっては、各情報の間に比較可能性がないと評価が困難となる一方で、画一的になりすぎるとかえって各企業の特徴がみえてきません。ある程度比較可能な大きな枠組みの中でも、それぞれの業種や企業の独自性が活かされるような情報開示が望ましいといえます。また、個々の企業が発信する環境情報について、どのように信頼性を確保するかという問題もあります。これまで、NGOや第三者が環境報告書にコメントを掲載し、また、報告書を作成する段階から各部の人々が参画することも試みられています。
さらに、企業にとって不利な情報をいかに開示していくかも今後の課題といえます。前述の国立環境研究所の調査によれば、環境コミュニケーションにより利害関係者との間に誤解を生じさせたり、苦情を受け厳しい目で見られた企業の方が、そのような経験のない企業に比べて自社に不利な情報の公開について肯定的であることがわかります。これは、経験に基づき、不利な情報でも積極的に公開する方が結果的には企業にとってプラスになるという判断があるためだと考えられます。
また、環境情報の活用という点では、NGOや研究機関などが、企業の発信する様々な環境情報を自ら解釈、分析するなどして仲介することにより、個々の受け手がそれらの情報を理解しやすく、客観性を持つことも強調されるべきでしょう。
いずれにしても、企業が環境情報を開示する手段は多様です。受け手も目的に合わせてそれらの情報を活用することが必要です。自らの要望や意見があれば、受信窓口を通じて積極的に企業にそれらを伝えていくことも今後重要になっていきます。
c 社会経済のあり方への影響
企業が環境コミュニケーションを行っていくことは、とりもなおさず社会とどのような関係を築いていくかという姿勢とつながってきます。企業は、その事業活動自体が社会経済の重要な部分を占めるというだけではなく、生産や販売などの様々な側面で社会経済の他の主体と常に関わり合っているという意味においても非常に大きな影響力をもっています。これらの各側面において、環境コミュニケーションを通じて企業と他の主体との間で環境情報を共有することによって、企業は社会での信頼を得、協力して環境問題に取り組んでいくことが可能となります。そうすることによってコミュニケーションを超えた実質的なパートナーシップへと発展していくことが可能になり、ひいては社会経済のあり方そのものを、持続可能なものへと変えていく力となり得るのです。
コラム GRI(Global Reporting Initiative)について
GRIは、持続可能性報告の国際的なガイドラインを策定する目的で1997年に設立され、2000年6月に「持続可能性報告のガイドライン」を発行しました。
GRIは環境NGOであるセリーズ(CERES)が国連環境計画(UNEP)に呼びかけて設立されたもので、企業、環境保護活動家、会計士、業界団体など、世界中の様々な代表者が参加しています。その活動目的は、持続可能性に関わるすべての側面、すなわち、環境、経済及び社会的側面について報告するための共通の枠組みをつくり、持続可能な発展に関わる情報の質を現在の財務報告書などの一般的な許容範囲まで高めるための土台とすることです。
GRIでは2000年6月「持続可能性報告のガイドライン」の発行後も、継続的にガイドラインを改定し、持続可能性報告書の継続的な改善と普及を目指し、ガイドラインを管理(スチュワードシップ)するために、2002年には独立した常設の国際機関として設立される予定です。
コラム
UNEPとサステナビリティ社は1993年から利害関係者の参加プログラムを継続しており、その一貫としての企業の報告書の比較調査を実施しました。この報告書では、現状の環境報告書の問題点として、「企業自身の活動に付随する最も重大な環境・社会的影響について叙述を避ける傾向が見られる上、ほぼ全企業が途上国に及ぼす影響について触れていない」と指摘しています。