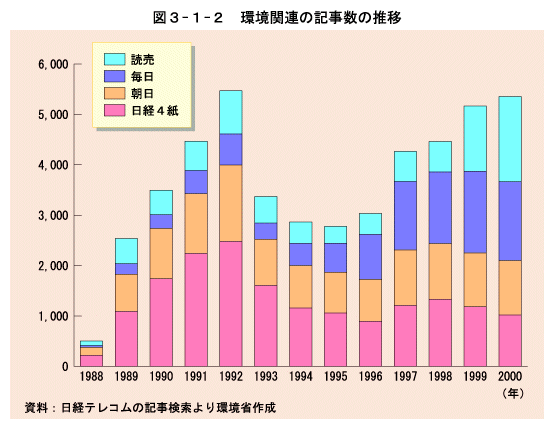
2 環境コミュニケーションの動向
(1)環境コミュニケーションを取り巻く状況の変化
環境コミュニケーションを取り巻く大きな状況の変化の一つは、メディア(情報伝達媒体)の変化だといえるでしょう。これまでの新聞・雑誌のような印刷媒体やラジオ・テレビのような電波媒体に加え、インターネットなどの新しいメディアの登場、普及により、現代のメディアのあり方は大きく変化しています。
具体的には、放送と通信の融合に見られるようなメディア同士の融合や、電子メールの活用などによる双方向性の増大、多主体が受発信を行えるようなネットワーク化などにより、メディアや各主体の関わり方が多様化し、情報の伝達範囲が広がり、伝達スピードも向上しました。環境コミュニケーションについても、個人や企業、NGO、行政などがそれぞれに新しいメディアを活用して環境情報を提供するためのホームページを作成し、お互いのホームページ間でリンクを張ってネットワーク化を図るなどの活発な動きが見られます。
(2)環境コミュニケーションの動向
ア 環境に関連する出来事と環境情報
環境に関連する出来事が社会で起きると、メディアで環境問題が取り上げられる頻度が高くなります。例えば、環境問題に関する記事数の推移を見ると、図3-1-2のように1992年のリオデジャネイロにおける地球サミット*や、1997年の京都における気候変動枠組条約第3回締約国会議といった環境に関する国際会議のような大きな出来事があると、新聞に取り上げられる環境関連の記事数も増えるという関係がみられます。また、1995年(平成7年)以降については、環境経営に関する記事を中心に環境関連記事が増加傾向にあることがわかります。第2節でみるように、個人のレベルでは環境情報の情報源を新聞やテレビに求める人の割合が高いため、メディアによる環境問題の取り上げられ方は、個人の環境意識に大きな影響を与えるといえるでしょう。
イ 環境コミュニケーションの変化とその要因
アでみたように環境情報の量の増加とともに、質的な変化も見られます。例えば、環境広告の例で見ると、これまでの「環境にやさしいイメージ」を重視した企業の宣伝広告から、最近では徐々に環境負荷の軽減量の表示、説明のような環境対策に関する表現の具体化、詳細化や、あるいは宣伝や主張だけではなく、消費者に参加を呼びかける広告なども登場しています。
このような環境コミュニケーションの量的、質的変化の主な要因としては、これから第2節で詳しくみていくように、社会の様々な主体の考え方や行動の変化が取り扱われる環境情報の需要や専門性を高めていることが考えられます。
このように、環境コミュニケーションの態様が変化することにより、各主体はその変化から影響を受け、さらに環境意識を向上させ環境保全へ取り組む動機付けにつながっていくといえるでしょう。
コラム クリックで熱帯林保全
環境情報専門のホームページや、定期的に環境関連のニュースを電子メールで配信するサービスなど、インターネットや電子メールを活用した様々な環境コミュニケーションのあり方が登場しています。
例えば、オンラインショッピングで買い物をしたり、バナー広告*をクリックすることにより、利用者側が追加的な支払なしに、熱帯林保全などの慈善団体に寄付ができるウェブサイトが登場しています。様々なオンラインショッピングができるこのウェブサイトの運営者は、提携先の企業から支払われる売り上げの一部や、バナー広告をクリックすることにより企業から支払われる広告料から、一定割合を慈善団体に自動的に寄付する仕組みになっています。また、利用者は、どの団体に寄付をしたいかをあらかじめ選択することもできます。
*バナー広告
ホームページ上に掲載される、文字、画像などで構成される広告