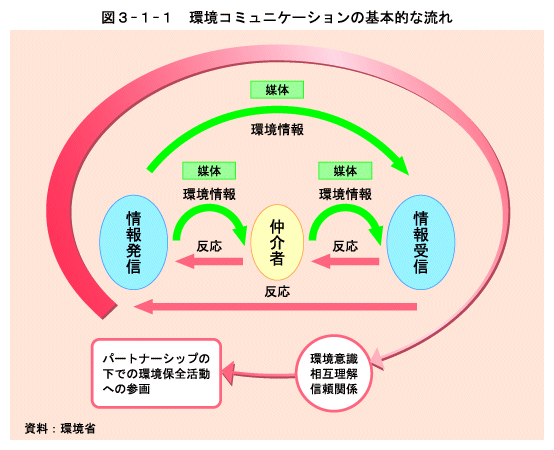
1 社会と環境コミュニケーションの関わり
(1)社会とコミュニケーション
コミュニケーションについては、これまでいろいろな社会学者がその定義を試みています。最近では、ロジャース*による「コミュニケーションとは、参加者が互いに情報を生み出し、それを共有することにより、相互理解に至る過程」という定義に代表されるように、相互作用や双方向性を重視したものが中心となっています。また、社会とコミュニケーションの関係では、社会システムがコミュニケーション活動を基盤にしており、社会のあり方とコミュニケーションのあり方は相互に深く関係し合っているといえます。
(2)環境コミュニケーションとは
「環境コミュニケーション」は比較的新しい言葉ですが、その概念について共通の認識が生まれつつあります。環境基本計画では「持続可能な社会の構築に向けて、個人、行政、企業、民間非営利団体といった各主体間のパートナーシップを確立するために、環境負荷や環境保全活動等に関する情報を一方的に提供するだけでなく、利害関係者の意見を聴き、討議することにより、互いの理解と納得を深めていくこと。」という意味で用いられています。一方、海外の定義の例では、OECDによってまとめられた「Environmental Commu-nication」という文書の中で、「環境コミュニケーションとは、環境面からの持続可能性に向けた、政策立案や市民参加、事業実施を効果的に推進するために、計画的かつ戦略的に用いられるコミュニケーションの手法あるいはメディアの活用」という定義がされています。アメリカのいくつかの大学などでも環境コミュニケーションという分野における研究が進められており、概念として徐々に浸透しつつある段階だといえるでしょう。
(3)環境コミュニケーションの基本的な流れ
ここでは、「環境コミュニケーション」を環境に関わる情報の社会的なやり取りととらえ、その基本的な流れについて簡単にみてみましょう(図3-1-1)。まず、環境情報の発信主体と受信主体があり、その間に仲介者が入る場合もあります。発信されたもとの情報をわかりやすく解釈、分析して公表することにより、環境コミュニケーションをより円滑に進める仲介者には、主にNGOや研究機関、マスメディアなどがなり得ます。また、第2節で詳しく述べるように、情報の送り手や受け手には、個人、企業、NGO、行政などの様々な主体がなり得ます。さらに、環境情報を受け取った者が、3で見るような環境コミュニケーションの効果により、環境意識を高め、相互理解をし、信頼関係を築き、例えばグリーン購入や環境保全活動への参加といった様々な形の行動につなげ、それがさらに他の主体の環境保全への取組を引き出すなど、連鎖反応や相乗効果が生まれます。また、このような環境コミュニケーションが、多主体間で様々な時間や場所で行われることにより、社会全体における環境問題に関する合意やパートナーシップを形成していく土台となり得ます。
コラム ロジャースのコミュニケーション論
1960年代から一般的になったコミュニケーションの定義は、デービッド・K・バーロのS−M−C−R(情報源→メッセージ→チャネル→受け手)モデルに代表されるように、一個人が他者に影響を及ぼすという単一方向のものでした。このような定義は、単一方向のプロパガンダや説得、マスメディアの研究において活用されたものの、人間の間のコミュニケーションで重要となるプロセスや、他に関与する多くの人間を含む全体的なプロセスを軽視していました。ラテン語の語源communisとは、共同参画、共有を意味し、コミュニケーションの概念はその過程における参画者間の情報の交換による共有を意味すべきです。よって、コミュニケーションとは、相互理解のために参画者が互いに情報を作り分かち合う過程であり、個人の集まりによって構成されるコミュニケーションのネットワークは、情報を共有することにより相互理解へと収束する過程だといえます。
*ロジャース
現在ニューメキシコ大学コミュニケーション&ジャーナリズム学部教授。技術革新、新製品の普及理論の権威として知られ、「イノベーション普及学」等の著書・論文がある。