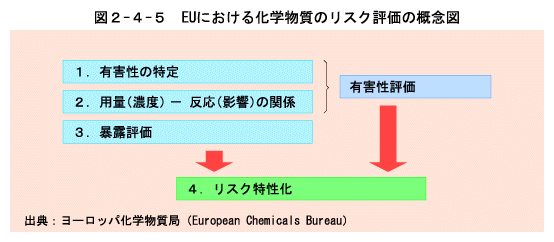
2 化学物質対策の基本的な方向
(1)適正な管理とそのための評価
このような化学物質をめぐる状況を踏まえ、新環境基本計画では、化学物質対策に係る目標として、「…多様な手法による環境リスクの管理の推進を図ることにより、持続可能な社会の構築の観点から許容し得ない環境リスクを回避」することを掲げています。
今後、本目標の達成に向けて様々な施策が講じられることになりますが、化学物質によるリスクのレベルはその種類によって異なることから、適切な管理を行う前提として、まず各々のリスクを評価することが必要となります。化学物質のリスク評価とは、物質そのものの有害性に加え、それが人体や生態系に影響を及ぼす可能性(暴露の頻度・期間や暴露量)を評価することです。このリスク評価は、諸外国及び国際機関においても重要課題として取り組まれています(図2-4-5)。また、リスク評価の結果に基づいて、必要に応じ、化学物質の利用形態や管理方法の見直し等を検討していくことが重要となっています。
さらに、化学物質の利用に際して適正な管理を行うためには、その開発、市場への投入から利用、廃棄に至るまでのライフサイクルの各段階において、情報の整備やリスク低減のための運用管理及び適切な審査を確実に行う仕組みづくりが必要です。
それらの具体的施策としては、例えば、化学物質の構造から有害性などの性状を定量的に予測するQSAR(定量的構造活性相関)、化学物質の環境中における分布や人体への暴露量を予測する暴露予測モデルなどを活用したリスク評価手法、化学物質を用いた製品のライフサイクル・アセスメント(LCA)などの研究開発が挙げられます。環境試料や食材を長期間継続的に保管し、将来の技術進歩や新たな環境問題の顕在化に対応するスペシメン・バンキングの推進などについても検討することとされています。また、化学物質の分析、環境リスクの評価、管理などを行う科学者、技術者の役割が重要となっており、こうした人材の育成などを行うこととされています。
(2)予防的な方策
わが国では、新しい化学物質が市場に出される前に、物質の分解性、蓄積性及び毒性について審査する制度として、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律*」が定められています。
化学物質対策については、平成4年の国連環境開発会議において採択された、環境を保護するために予防的方策を広く適用すべきであるという考え方を踏まえる必要があります。このため、科学的な評価が完全に行われていない段階であっても、国民、産業界、事業者及び行政が化学物質に関する情報を共有しながら、すべての者が必要に応じて、化学物質による環境リスクを低減するよう取り組んでいかねばなりません。
特に、難分解性で生物に蓄積しやすい有害化学物質は環境中に長期間残留することから、こうした予防的方策を講じることに留意することが必要です。
*化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
この法律で定められる第1種特定化学物質は、製造・輸入・使用等が原則禁止されており、第2種特定化学物質は、必要な場合に製造・輸入の制限、指定化学物質については製造・輸入量の届出義務が課せられている。
(3)環境上の「負の遺産」の解消
有害物質による土壌や地下水の汚染、難分解性有害物質の処理問題など、環境上の「負の遺産」のうち化学物質によるものについては、現在世代の責務として、これまでの蓄積も含め、将来世代に環境影響を可能な限り残さないことを目指す必要があります。
こうした環境上の「負の遺産」のうち、例えば、工場跡地等の土壌・地下水汚染問題については、過去の重金属や揮発性有機化合物の漏出が主な原因となっています。特にトリクロロエチレンやテトラクロロエチレンなどの揮発性有機化合物は、工業化学品としての機能性、安全性ともに高いとされ、過去に総合的な管理が行われていなかったため、地下に漏出し、浸透・拡散して、大深度かつ広域の汚染を引き起こす被害が各地で表面化しました。土壌汚染問題は大気・水質汚染と異なり、目に見えない地下の土壌に長期間にわたって汚染が蓄積されることから、実態の把握と対策の推進が求められています。
また、PCB*については、昭和43年のカネミ油症事件発生以来、有害性が取り上げられるようになり、昭和49年には閉鎖系での使用以外のPCBの製造、輸入、使用が禁止されました。PCBは電気製品の変圧器(68%)、熱媒体(16%)、感圧紙(10%)などに用いられてきました。日本で生産された約6万トンのPCBのうち、回収されたのは約7千トンであり、その他は全国の各種施設に散在しています。これらのPCBについては、すでに20年以上経過しているため、施設の老朽化、容器の腐食、地震等の不測の事態による流出が懸念されています。
これまでPCBの処理は技術的な制約から先送りにされてきましたが、近年の技術進歩によって徐々に解決の見通しが立ちつつあります。将来世代の負担を少しでも軽減するためにも、全国に散在するPCBの適正な保管管理と早期回収・処理及びその厳密な監視が必要であり、このため、処理の促進を図る法改正を予定しているところです。
*PCB
1997年の調査では、全国に保管中のトランス、コンデンサは約75万台、使用中が約37万台、保管中の感圧紙が27トン、PCB含有の汚泥等が6300トン、液状のPCBが778キロリットルあることが判明
(4)市民の参画
私たちは多くの化学製品に支えられて生活していますが、一般的に化学物質に対するイメージは、環境汚染や健康への悪影響など、否定的なものが多いのが現状です。また、化学物質に対して十分な知識と情報を持っていると認識する人々は少なく、漠然とした不安感が広がっていることもうかがわれます。
一方、化学物質による環境リスクは私たちの日常生活と深く関わっており、市民の立場でリスク低減のための問題解決に参画することが重要となっています。市民は化学物質に対する適切な知見を身に付け、化学産業、行政、化学品を扱う多くの企業とともにどこまでのリスクが許容でき、どのリスクは低減し、または回避すべきかを考えなければなりません。
現在、各企業の化学物質に関する情報公開は進展をみせはじめています。市民はこうした情報の監視役となって、産業界や行政の取組を促進させるために重要な役割を担っているといえます。
このような、市民とその他の各主体との間での化学物質のリスクコミュニケーション*を推進するため、行政としては、環境リスクに関してわかりやすく説明できる人材や、話し合いを仲介できる人材の養成を進めつつ、PRTR制度*に基づく排出量データなどの情報を正確でわかりやすい形で公表するとともに、広報活動や環境教育・環境学習、意見交換の場の設定などを推進することが重要となっています。
*化学物質のリスクコミュニケーション
化学物質による環境リスクに関する正確な情報を行政、事業者、国民、NGO等のすべての者が共有しつつ、相互に意思疎通を図ること
*PRTR制度
人の健康や生態系に有害なおそれのある化学物質について、事業所からの環境(大気、水、土壌)への排出量及び廃棄物に含まれての事業所外への移動量を、事業者が自ら把握し国に届け出るとともに、国は届出データや推計に基づき、排出量・移動量を集計し、公表する制度