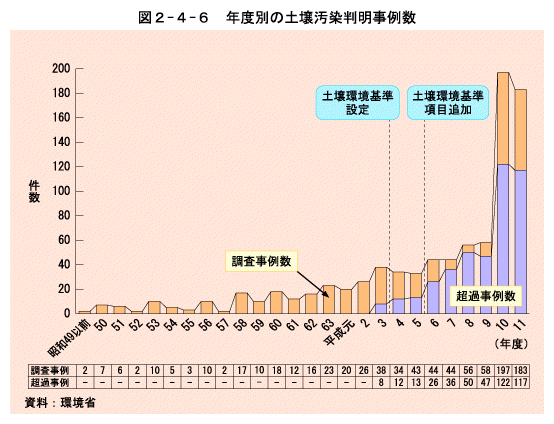
3 環境リスクの低減と環境上の「負の遺産」の解消に向けた取組
(1)国際的動向
化学物質の環境リスクに対する国際的な取組は、アジェンダ21第19章「有害かつ危険な製品の不法な国際取引の防止を含む有害化学物質の環境上適正な管理」に基づいて進められています。アジェンダ21に示された課題は、ア.化学物質リスクの国際的評価の拡充と促進、イ.化学物質の分類と表示の国際調和、ウ.有害化学物質・化学物質リスクに関する情報交換の促進、エ.リスクの計画的削減の推進、オ.各国の化学物質管理能力及び体制の整備、カ.有害化学製品の違法な国際移動の防止の計6プロジェクトです。この課題に取り組むため、1994年にIFCS(化学物質安全政府間フォーラム)を運営する主体として、IPCS(国際化学物質安全計画)が設立されています。また、OECD、UNEP、WHOなど7つの国際機関の調整組織として、IOMC(健全な化学物質管理のための機関間プログラム)が設立され、様々なプロジェクトが推進されています。
ア 国際的な取組の進展
平成12年4月に滋賀県において開催されたG8環境大臣の会合では、人体や生態系への化学物質の環境リスクの低減に取り組むために、すべての国々、産業及びNGOに対し、支援と参加が呼びかけられました。また、同年10月に開かれたIFCSでは、平成17年までに各国は化学物質管理の改善に向けた目標を含む方針を出すべきとの宣言が出されました。
特定の有害化学物質による環境リスクを低減するための条約策定の動きも活発であり、平成12年12月には残留性有機汚染物質(POPs)の製造・使用の廃絶、削減等に関する条約(通称ストックホルム条約)案について政府間交渉会議において合意がなされました。また、有機スズ系船底防汚塗料の全面使用禁止に向けた条約*についても、平成13年中に条約採択のための外交会議が開催される予定です。
さらに、有害化学物質等の違法な国際移動の防止に向けて、国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前かつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約*が採択され、現在は各国の批准に向けた準備が進められています。
*有機スズ系船底防汚塗料の全面使用禁止に向けた条約
船底防汚塗料に使用されている有機スズ化合物(特にTBT)による海洋汚染を防止するための条約
*ロッテルダム条約
使用が禁止又は厳しく規制されている化学物質の貿易時における情報交換の手続及び輸出先国への事前のかつ情報に基づく同意(PIC、Prior Informed Consent)手続を定めた条約。平成13年1月現在で13か国が批准している。
イ 化学物質のリスク評価、情報の整備
アで述べたIFCSの主要な課題の一つに化学物質リスクの国際的評価の拡充と促進があります。具体的な取組としては、既存化学物質の国際的なハザード/リスク評価文書を、2004年までに新たに1000物質について作成するという目標が平成12年のIFCSにおいて設定されました(平成6年目標では平成12年までに新たに500物質の文書作成とされていましたが、目標未達成となったことが今回の会議で指摘されています。)。このため、OECDの高生産量化学物質安全性点検プログラムとIPCSの環境保健クライテリア(EHC)という2つのプログラムにおいて、各国が作成した既存の評価文書を国際的に評価するという取組が行われています。
UNEPでは1976年から国際有害化学物質登録制度(IRPTC)を実施し、各機関から出される化学物質のリスクと便益に係る科学的、技術的、経済的、法的なすべての情報を物質ごとに集めた物質ごとの情報発信を行っています。これまでにもUNEPは様々なデータ索引集を発行しており、今後は国レベルでの情報交換を促進するため、各国の機関がもつ情報システム及びそこで得られる情報の内容を整理し発信することを予定しており、将来的にも化学物質に係る既存情報を検索する上での中心的存在となることが期待されています。現在IRPTCは「UNEP化学(UNEP Chemicals)」と改称され、他の国際機関と連携した活動を行っています。
その連携の代表例が、WHO、ILO、UNEP、OECDが前述のIOMCの示した枠組みに基づき1994年に構築された地球規模化学物質情報ネットワーク(GINC)です。ここでは化学物質の有害性情報、リスク評価の情報、リスク管理や緊急時の対処法など様々な情報の発信をしています。
また、こうしたリスク情報などの整備とともに、PRTR制度を用いた排出データの整備やMSDS制度*を用いた性状及び取扱いに関する情報の提供も重要性を増し、世界各国で法制化が進められています。IFCSでは、化学物質リスクの影響を受けるすべての主体が必要な情報を入手でき、PRTRの仕組みづくりにも参画できるように、各国に働きかけていく方針を明らかにしています。
ウ 予防的取組
平成9年のG8環境大臣会合で採択された宣言では「情報が十分でないときは、子供の健康の保護について予防的な原則又は方策に則ること」が合意されています。また、イギリスが1999年に発表した「化学物質戦略」においても、予防的な取組として、毒性が証明されていない場合でも、難分解性で生物蓄積性のある生産数量の多い化学物質は、優先的に評価の対象となること等が示されています。
このように、化学物質のリスク評価の徹底に向けた動きが加速する一方で、生産量が極めて多い化学物質や、難分解性、生物蓄積性のある化学物質については、科学的情報が完全に整っていない段階でも、予防的に管理すべきであるという考え方が国際的に取り入れられつつあります。
(2)わが国の動向
ア 環境上の「負の遺産」の解消に向けた取組
環境上の「負の遺産」の早期解消に向けて、対策技術の開発・普及と修復への取組が重要性を増しています。
このうち、土壌・地下水汚染については、平成11年に土壌・地下水汚染に係る調査・対策の技術的指針が改訂され、各地方公共団体及び事業者による対応が進められています。また、各事業者や研究機関において浄化のための新技術及び簡易・低コスト技術の開発が進められています。図2-4-6は年度別の土壌汚染判明事例数ですが、平成11年度に土壌の汚染に係る環境基準に適合していないことが判明した事例は117件であり、平成10年度に引き続き高い水準で推移しています。調査件数の伸びの背景には、土地所有者が自ら調査を実施する事例の増加が挙げられ、土壌汚染対策の一層の推進が求められています。このような状況を踏まえ、土壌環境保全対策のために必要な制度のあり方について調査・検討を開始したところです。
一方、PCBの処理促進については、平成13年度に予定される制度改正によって特例措置が講じられることとなるほか、地方公共団体が独自に処理の目標を策定する例も出ています。東京都は平成12年12月にPCB廃棄物の適正処理の促進について、10年以内に都内に保管されているPCB廃棄物の処理を完了する目標を明らかにしました。これに向けた具体的な取組としては、安全性情報の普及啓発など都民の理解を得るための取組、処理施設整備の促進、処理完了の認定制度の創設等による保管者の処理促進を挙げています。
イ 環境リスクの低減に向けた取組
わが国では、制度的対応、科学的知見の充実、対策技術の開発・普及、各種基盤及び体制整備、民間事業者を含めた取組の推進によって化学物質問題への解決策が講じられています。制度的対応としては、PRTR制度及びMSDS制度の平成13年度からの義務化による情報基盤の整備が行われています。また、ダイオキシン類対策特別措置法*等に基づき環境基準の設定、排出規制、汚染土壌対策など具体的な対策が進められています。
内分泌かく乱化学物質(いわゆる環境ホルモン)については、「環境ホルモン戦略計画SPEED'98」に基づき、平成10年度から全国における環境中の検出状況の把握調査が進められるとともに試験研究や技術開発も進められています。さらに、平成12年度からは、ミレニアム・プロジェクトにより3年計画で40物質以上のリスク評価に取り組むこととなっています。
こうした科学的知見の確立に向け、OECDの内分泌かく乱化学物質に関するバリデーション・マネジメント・グループ*や高生産量化学物質の初期リスク評価プロジェクトなど、国際機関の取組への参画を通じ、先進国間での研究協力などの連携の強化を図る必要があります。わが国として重要なプロジェクトを積極的にリードし、国際会議の開催などによりその進展を図ることも必要です。また、化学物質問題に係る条約の批准に向けた国内措置や体制整備が進められています。
事業者の自主的な化学物質の適正管理の取組にも着実な進歩が見られます。特に、日本化学工業協会を中心としたレスポンシブル・ケア活動*については、総合的な管理に加え、地域ごとの説明会開催によって直接対話を進めるなど、社会からの信頼向上に向けた積極的な取組が行われています。また、化学工業界以外の多くの団体においても平成8年の大気汚染防止法改正を受けた自主管理計画が策定されており、指定化学物質の削減目標の達成に向けた取組が行われています(図2-4-7)。
さらに、個別企業においては、製品開発段階における安全性評価の仕組みづくりや、無鉛はんだの拡大など製品及び製造工程における有害物質の使用量の削減、化学物質のデータベースの整備や情報公開、取引先企業との協力によるライフサイクル全体の環境負荷の低減などが進展しつつあります。
化学物質問題をテーマとする環境NGOでは、市民、企業、研究者など様々な立場の人を集め、正確な情報を知るための勉強会や、相互理解のための議論を始めています。また、事業者や業界団体と地域住民とのリスクコミュニケーションも始まっています。地域との共生を重んじるいくつかの企業では、地域住民との日頃からの信頼関係を構築するために、地域向けの環境情報発信や説明会、意見