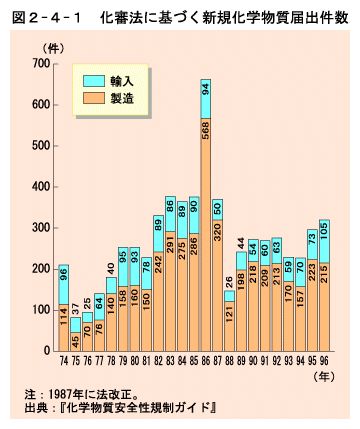
1 化学物質による環境問題の特質
(1)化学物質の種類及び生産量
世界中で開発された化学物質の登録機関である米国のCAS(Chemical Abstracts Service)には、平成12年末時点で約2千8百万種類の化学物質が登録されています。化学物質の種類の増加傾向は、この10年間で特に顕著になっています。このうち、日本において商業的に用いられているものは数万種類といわれ、以下の図に示した新規化学物質届出件数を見ても分かるとおり、化学物質の新たな開発は増加傾向にあります(図2-4-1、図2-4-2)。
また、化学物質については、その種類のみならず、工業製品としての生産量も年々増加しています。国内でも、例えばプラスチック製品の生産量は、平成11年には約6百万トンにのぼり、25年前の約2倍となっています。
(2)化学物質による影響
化学物質の利用は20世紀に入ってから急速に進展し、人類や生態系はその複合的かつ長期的な暴露を受けるという、これまでの歴史上例を見ない状況に直面しています。化学物質は、日常生活のあらゆる場面、モノの製造から廃棄に至る事業活動の各段階において、環境中に放出されたり人体に摂取されたりしています(図2-4-3)。化学物質による環境問題は、産業公害問題が主な関心事であった頃には特定の地域や条件の下で問題とされていました。しかし、現代では、こうした問題が国民の日常生活や通常の事業活動に起因し、不特定多数の者が原因者になっているという状況や、原因者が同時にその影響を受ける者にもなっていることが一般化しています。また、影響の発現までに長期間を要する問題やその影響が長期間にわたる問題、また、発生の仕組みや影響の科学的解明が十分でない問題が増えています。
こうした中、化学物質の安全性を評価し十分な情報を整えることが重要となっていますが、現在流通している化学物質の中には未だ安全性の評価が行われず、人体や環境への影響の大きさが分かっていないものが多く残されています。例えば、OECDが登録している高生産量化学物質*は2000年時点で5,235種類ですが、そのうち有害性をスクリーニングするための十分なデータセット*が揃っているものは約5%に過ぎません。当初は有害性の認識は無くても、数十年の使用期間を経て有害性が判明するという問題が今後増加する可能性もあります。そうした意味で、このような化学物質を私たちが利用するに当たっては、常に慎重であることが求められます。
化学物質は一般に安全か危険かというように単純に区分できるものではなく、物質自体の有害性の有無やその程度と影響の可能性、範囲などは物質ごとに異なるため、リスクの概念を用いて評価されることが一般的です。
様々な化学物質による環境リスクについて、影響を及ぼす範囲と有害性との関係を整理すると、大まかに図2-4-4のように表すことができます。
このリスクの考え方には、様々なとらえ方があります。少しのリスクも許容できない、つまりリスクゼロの状態を求めるという人もいますが、これは不可能ですから、多様な手法による環境リスクの管理の推進を図ることにより、持続可能な社会の構築の観点から許容し得ない環境リスクを回避することが必要です。そのためには、各段階で一定量以上のリスクを排除するように評価と管理を行ったり、リスク削減に伴う経費の増大や便益の減少との兼ね合いで目標を明確にしてリスク削減を図ることが必要です。私たちは、日常生活の中で化学物質とどのように付き合っていくのか、さらに今後の化学物質対策はどうあるべきかについて真剣に考えなければならないのです。
*高生産量化学物質
OECDの定義では、少なくとも1つの先進国における年間生産量が1000トン以上のもの
*データセット
例えば、OECDが開発しているスクリーニング情報データセット(SIDS)では、少なくとも環境中での分解性や拡散経路、生態毒性データ、哺乳動物毒性データなどを揃えることが定められている。