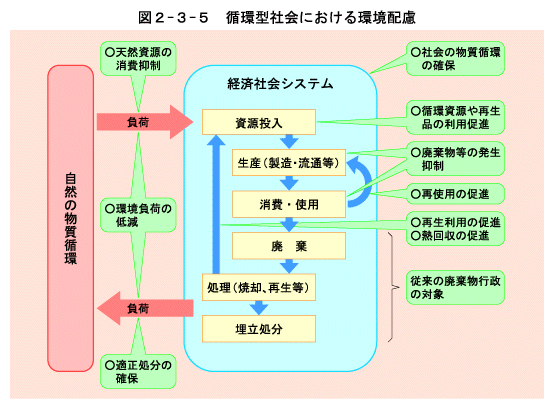
2 循環型社会形成に向けた道筋と法的枠組みづくり
(1)廃棄物の適正処理から健全な物質循環の構築へ
わが国における廃棄物処理制度は、家庭ごみの衛生的な処理を図ることから出発し、従来の廃棄物行政の主な目的は生活環境の保全を図る観点からの廃棄物の適正処理の推進でした。現在では、廃棄物の大量発生等が社会問題となっていることを踏まえ、廃棄物の発生抑制、循環的な利用及び適正処理まで、物質の流れ全体を見据えた施策を推進し、環境負荷が低減された循環型社会の構築が重要となっています。循環型社会の構築に当たっては、物質循環そのものの構築を目的とした政策の強化はもちろん、資源投入から製造、流通・販売、消費、回収、再生製造段階への再投入までの各段階において環境保全上の隙間をなくし、物質循環がより健全なものとなるよう、適切な施策を講じることが必要となります。
(2)循環型社会形成推進基本法の基本的考え方と個別法の位置付け
こうした廃棄物・リサイクル行政に対する社会的要請に応えるため、平成12年6月、循環型社会形成推進基本法と各個別法が制定されました。
循環型社会形成推進基本法は、社会における物質循環の形成を通じた、製品などの使用・廃棄に伴う天然資源の消費抑制と環境負荷の低減を目的としており、循環型社会の形成に向けた基本原則、施策の基本事項など対策の枠組みが示されています。また、ここでは廃棄物処理の優先順位が、1)排出抑制、2)製品・部品としての再使用、3)原材料としての再生利用、4)熱回収、5)適正処理であることが初めて法定化されました。これにより、廃棄物・リサイクル対策が、廃棄物の発生抑制から、循環的な利用、適正処理まで、廃棄物になる前と廃棄物になった後の両方のものの流れ全体を見据えた施策へと転換し、循環型社会の構築への原動力となることが期待されています。
循環型社会形成推進基本法では、事業者に対して拡大生産者責任を課している点も大きな特徴です。これは、製品の製造者などが物理的又は経済的に、製品の使用後の段階においても一定の責任を果たすという考え方です。これによって生産者は生産段階から廃棄物の発生抑制や再使用、再生利用時における環境配慮を進めることになり、社会内の物質循環を十分に活用した、より環境負荷の少ない廃棄物処理が自律的に進んでいくことが期待できます。
循環型社会形成推進基本法の個別法として、改正廃棄物処理法、資源有効利用促進法、食品リサイクル法、建設リサイクル法、グリーン購入法*が制定されました。先だって制定されていた容器包装リサイクル法と家電リサイクル法を含めたこれらリサイクル関連法の概要は表2-3-1のとおりです。
個別のリサイクル法は、再生利用の促進を主な役割としていますが、再生利用に関する規制を設けることで、間接的に廃棄物等の発生抑制や再使用を促進することも視野に入れています。グリーン購入法は、これまでの廃棄物・リサイクル行政には欠けていたリサイクル商品の普及促進の役割を持っています。これによって、リサイクル製品の需要を生み出し、物質循環を促すという重要な役割を果たします。
各個別法は、循環型社会形成推進基本法が示した方針の下で、社会内の物質循環におけるそれぞれの役割を果たし、適正な社会内の物質循環を構築していくのです(図2-3-6)。
循環型社会の構築に向けた法的枠組みは、このように着々とできあがりつつあるといえます。しかし、物質循環の構築は持続可能な社会への第一歩でしかありません。資源の循環に伴う環境負荷や経済性を考慮して、排出抑制・再使用・再生利用・熱回収を適切に組み合わせていくことが重要です。また、他の手法との比較を行いながら、ごみ処理手数料、税、課徴金、デポジット制度などの経済的手法も幅広く活用する一方、再生利用認定制度の対象範囲の拡充や、企業に対する技術的支援の推進などの政策展開により、廃棄物問題の解決と資源利用効率の向上に向けた取組をより実効性の高いものにすることも重要です。
*グリーン購入法
→講じた施策第3章第2節2参照