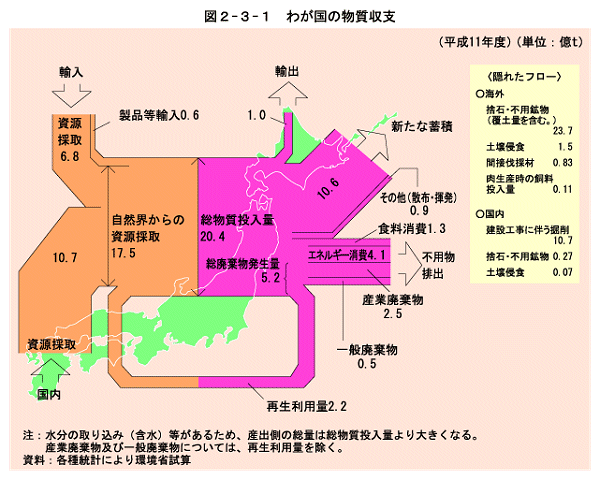
1 物質収支から見た廃棄物・リサイクル問題
(1)大量の物質に支えられたわが国の社会経済活動
図2-3-1は平成11年度におけるわが国の物質収支を示しています。わが国の社会経済活動には17.5億トンに及ぶ自然界からの資源採取(水及び大気を除く。)を含め、20.4億トンの資源が国内外から投入されています(総物質投入量)。そして投入された資源のうち、5割程度がそのまま消費、廃棄に向かっています。また、投入された資源の約1.8倍の「隠れたフロー*」が生じています。一方、廃棄物のうち資源として再利用されているのは2.2億トンで、総物質投入量の約1割程度にすぎません。このように、わが国の物質収支をみると、資源採取から消費、廃棄へ向かう一方通行が主流となっており、「循環型社会」と呼ぶにはほど遠い状況です。
昭和45年の資源採取量、総物質投入量はそれぞれ14.4億トン、17.5億トンであったと推計されており、30年間でどちらも1.2倍程度増加しました。これまでの社会経済活動の拡大は資源・エネルギー利用量の増大を伴っており、現在の社会経済活動を維持するためにも、環境からの多くの物質投入を必要としています。社会全体における資源利用の効率性の向上を通じて、自然界からの資源採取量を削減させていかねばなりません。
*隠れたフロー
わが国の経済活動に直接投入される物質(総物質投入量)が、国内外において生産、採掘される際に発生する副産物、廃棄物を「隠れたフロー」といいます。「隠れたフロー」には、建設工事による掘削、鉱滓、畑地等の土壌侵食などがあります。
(2)わが国の廃棄物問題の現状
平成9年にわが国で排出された廃棄物の量は、一般廃棄物が5,120万トン、産業廃棄物が4億1,500万トンでした。昭和40年代以降、排出量は急激に増大しましたが、近年はほぼ横ばいで推移しています(図2-3-2、図2-3-3)。これらの廃棄物は、焼却を中心とした中間処理を経た後、最終処分場に処分されています。
現在、中間・最終処分場からの有害物質の排出、漏出などの懸念から、廃棄物処分場建設反対運動や高度処理への要請が高まっています。これによって廃棄物処分に係る費用は高騰し、自治体や事業者への負担増、不法投棄の増大といった問題を引き起こしています。また、最終処分場の残余年数はすでに一般廃棄物で11.2年(平成9年)、産業廃棄物で1.6年(平成11年)と後がなく、早急な対策が必要となっています。
図2-3-3
(3)環境負荷を低減する社会の静脈としての廃棄物・リサイクル対策
廃棄物問題は、社会経済における過大な物質の流れが引き起こす歪みの一つといえます。従来のように焼却処分、最終処分に大きく依存する方法は、すでに社会的に行き詰まりを見せており、社会全体での廃棄物排出量の低減に向けた根本的な対策が必要となっています。
廃棄物削減対策における主要なメニューとして、排出抑制(リデュース)、製品・部品としての再使用(リユース)、原材料としての再生利用(リサイクル)・熱回収(サーマルリサイクル)が挙げられます。まず、排出抑制を伴わない大量の再生利用は、その過程でエネルギーをはじめとする大量の資源が必要となり、環境負荷がゼロになるわけでもありません。環境負荷をできる限り低減させるためには、最優先でその限界まで、長寿命製品の開発や簡易包装の選択などによって排出抑制に取り組むことが重要となります。次に、再使用と再生利用は、社会内に物質循環を構築することで、廃棄物の削減と同時に自然からの資源採取を低減する効果があり、物質の流れの適正化において重要な役割を果たします。再使用や再生利用は経済的な条件から対象が限定されることが多く、図2-3-4に示すように近年は産業廃棄物で40%程度、一般廃棄物で10%程度にとどまっていますが、廃棄物の回収システムや費用負担に関する制度を整備することで、一層の拡大を見込むことができます。このように社会内に静脈機能を組み込んで物質循環を構築することにより、自然界からの資源採取と廃棄物を同時に削減することが期待できます。