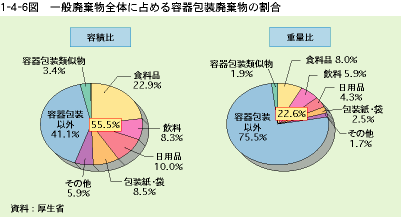
2 適正なリサイクルの推進
(1)使用済製品の再使用の推進
容器包装の再使用を促進するため、平成7年度から調査検討を開始した。その結果を踏まえ、リターナブルびんの普及を図るため、その普及に向けた課題やその課題の解決に必要な対策について整理を行った。
(2)回収・再生利用の推進
環境への負荷の低減のため、廃棄物の再生利用、再生資源の回収・利用を促進する必要がある。
事業活動における再生資源の利用を促進するため平成3年10月に施行された「再生資源の利用の促進に関する法律」に基づき、再生資源の利用を総合的かつ計画的に推進した。
平成9年に改正された廃棄物処理法に基づき、一定の廃棄物の再生利用について、その内容が生活環境の保全上支障がない等の一定の基準に適合していることを国で認定し、認定を受けた者については業及び施設設置の許可を不要とする規制緩和措置が講じられ、これまでに廃ゴムタイヤ、建設汚泥及び廃プラスチック類がこの再生利用認定制度の対象となり、4事業者が認定を受けている。
また、「エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法」に基づく、リサイクルを推進するための設備の導入、技術開発に関して、金融・税制上の特例を実施した。
さらに、毎年10月の「リサイクル推進月間」において、リサイクルに関する国民の理解と協力を得るため、広範な普及啓発活動を実施することとしており、平成11年度も、各種シンポジウムの開催、リサイクル推進功労者の表彰等を行った。
リサイクルに関する各種の調査研究や普及啓発の推進、民間団体によるリサイクル活動に対する地球環境基金を通じた支援を行った。
また、産業構造審議会報告書「循環型経済社会の構築に向けて(循環経済ビジョン)」(平成11年7月)における従来のリサイクル対策の抜本的強化とリデュース・リユース対策の本格的導入が必要との提言を受け、廃棄物の処理・リサイクルの推進のために、同審議会において毎年策定されている品目別・業種別廃棄物処理・リサイクルガイドラインにリサイクル対策の抜本的強化とリデュース・リユース対策を取り入れ、さらに新たな品目・業種を追加する大幅な改定及びフォローアップを行った(現在の対象分野は28品目、18業種)。また、廃棄物発電技術、ケミカルリサイクル技術等の広範な技術開発を行うとともに、各種の調査研究や普及啓発を推進したほか、廃棄物の再資源化を促進するため、(財)クリーンジャパンセンターの実証プラント設置、再資源化推進大会・再資源化貢献企業等表彰の実施等の各種の再資源化事業に対する補助を行った。さらに、「古紙リサイクル促進のための行動計画」(平成9年9月策定)の周知徹底・フォローアップを行うとともに、「使用済み自動車リサイクル・イニシャティブ」(平成9年5月策定)における使用済み自動車マニフェストの導入等を行った。
各都道府県に設置されている省資源・省エネルギー国民運動地方推進会議を通じ、リサイクル活動団体への支援を行った。
地方公共団体における体制整備を推進するため、ごみの再資源化経路の構築や組織づくり等に関する事業に対して補助を行うとともに、5月30日から6月5日までの「ごみ減量化・リサイクル推進週間」を中心に、廃棄物の減量化や再生利用を促進するための各種啓発活動を行った。
建設廃棄物等のリサイクル推進については、平成9年10月に策定された「建設リサイクル推進計画’97」に基づき、各施策を進めている。第一に、公共工事の発注者の責務の徹底を図るために行うべき事項についてとりまとめた「建設リサイクルガイドライン」の徹底、研究・技術開発の推進、公共工事発注者間の連携を強化するための情報交換体制の強化、平成10年12月に策定した建設副産物適正処理推進要綱の周知・徹底等を図った。また、公共事業等におけるリサイクルの推進を図るため、建設発生土の再生利用を促進するための情報交換システムを平成11年4月より運用を開始するとともに、建設汚泥のリサイクルを推進するため、平成11年10月に「建設汚泥リサイクル指針」をとりまとめた。さらに、建設工事以外から発生する他産業の再生資材を公共工事に受け入れる場合の試験評価方法について、平成11年9月に「公共事業における試験施工のための他産業再生資材試験評価マニュアル案」をとりまとめた。
また、特にリサイクルの取組の遅れが指摘されている建築解体廃棄物について、平成11年10月に「建設解体廃棄物リサイクルプログラム」を策定し、建築解体廃棄物の分別及びリサイクルの推進等について対策をとりまとめた。
このプログラムを踏まえて、建築物に係る分別解体等及び再資源化等の義務づけや解体工事業者の登録制度を創設することを内容とする「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律案」を第147回国会に提出した。
下水道事業において発生する汚泥(発生汚泥等)については、コンポスト化、建設資材化による再生利用等を推進するとともに、再生利用推進のための各種調査研究等を行った。
農業集落排水事業の実施においては、発生汚泥を有機質肥料等とするリサイクルなどを推進した。
また、リサイクルの一層の促進を図るため、リサイクルに関連する経済的手法のあり方についての検討がそれぞれ進められた。
(3)容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の施行
一般廃棄物の大部分を占め(1-4-6図)かつ再生資源としての利用が技術的に可能な容器包装廃棄物について、市町村による分別収集及び事業者による再商品化等を促進する「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(通称:容器包装リサイクル法)に基づき、ガラスびん及びペットボトルについて分別収集及び再商品化を実施した。平成10年度においては、無色ガラス303,240t、茶色ガラス256,227t、その他ガラス123,227t、ペットボトル45,192tが再商品化された。
また、平成11年6月には、ペットボトル以外のプラスチック製容器包装及び飲料用紙パック及び段ボール以外の紙製容器包装に関する分別基準の設定、同7月には、平成12〜16年度についての再商品化計画の策定及び基本方針の改正、同12月には、特定事業者の再商品化義務量算定方式等に係る主務省令・告示の改正を行った。
さらに、分別収集及び再商品化が円滑に進められるよう、市町村による分別収集計画の策定の支援、再商品化技術の開発、再商品化によって得られた物の需要の拡大、必要な調査研究説明会等により、容器包装リサイクル法の普及・啓発を行った。また、キャラクターマーク「分け兵衛」の活用、容器包装リサイクル法に関するパンフレットの作成、事業者等に対する地域毎の説明会の開催などにより普及啓発を行うとともに、(財)日本容器包装リサイクル協会等の関係機関における効果的な普及啓発事業を促進した。また、平成12年4月の同法の完全施行に向け、産業構造審議会において、新たに分別収集及び再商品化の対象に加わる紙製容器包装及びプラスチック製容器包装について、識別表示等のあり方を検討し、平成11年12月に表示義務づけの方向性を打ち出した。
(4)特定家庭用機器再商品化法について
家庭から排出される廃家電製品等は、現在、その多くは破砕処理の後に鉄などの回収のみにとどまったリサイクルしか行われておらず、一部はそのまま埋め立てられている。我が国の廃棄物最終処分場の残余容量は一般廃棄物、産業廃棄物ともに逼迫しており、廃棄物の減量化は急務の課題となっている。
このような状況を踏まえ、廃棄物の減量と再生資源の十分な利用等を通じて、廃棄物の適正な処理と資源の有効な利用を確保するため、市町村における廃棄物処理に関する技術及び設備に照らし高度な再商品化等(リサイクル)が困難なもの等の要件を満たすものを特定家庭用機器として指定し、これらの機器が廃棄物となったもの(特定家庭用機器廃棄物)について、小売業者による収集及び運搬、製造業者等による再商品化等を義務づけることにより、廃家電等の適切なリサイクル・処理を確保するため、平成10年6月、特定家庭用機器再商品化法が公布された(1-4-7図)。同年12月には施行令が公布され、特定家庭用機器としてエアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機が指定された。さらに、平成11年5月には同施行令が改正され、いわゆる再商品化率等が策定された。また、同年6月には本制度にかかる基本方針が策定された。
(5)リサイクル関連施設整備の推進
一般廃棄物について、廃棄物循環型のごみゼロ社会を目指し、21世紀初頭を目途に、廃棄物のほとんどすべてを、「単に燃やして埋める処理」から、極力リサイクルを推進し、焼却処理を行う場合においても熱エネルギーを活用するものへ転換を図ることとしている。このため、廃棄物の排出抑制・リサイクルに努めた後に、なお排出される可燃性のものについては焼却処理等を行うとともに、積極的に余熱利用を行う「廃棄物循環型処理」を促進するための施設整備を推進した。
リサイクル関連施設については、ペットボトル等の容器包装廃棄物の再商品化、廃プラスチックの油化、焼却灰の溶融固化、余熱利用、廃棄物発電、ごみ固形燃料化等の普及・技術開発等を推進するとともに、「民間事業者の能力の活用による特定設備の整備の促進に関する臨時措置法」等により、リサイクル関連施設の整備を支援した。また、家畜排せつ物等の有効利用を促進するため、堆肥化施設や脱臭施設等の環境対策施設の整備を推進した。
(6)リサイクルにおける環境配慮
電気製品や自動車などの有害物質を含む使用済製品について、有害物質を含む部品の回収による有害物質のリサイクルの促進方策について調査検討を行った。また、廃棄物の減量化及び環境への負荷の低減を図るため、リサイクルの促進に関する各種普及啓発事業及び調査研究を行うとともに、廃棄物のリサイクルについては、現在環境保全面からの適切な基準が設定されていないことから、廃棄物のリサイクルに係る環境保全上のガイドラインを策定するための調査を行った。また、リサイクルの環境に与える影響を把握し、リサイクルされた原材料を使用した製品等に含まれる可能性のある有害物質等に関する情報の把握を行い、必要な施策を検討した。
(7)ゼロ・エミッション構想の推進
地域における資源循環型経済社会構築の実現に向けて、ゼロ・エミッション構想推進のため「エコタウン事業」を実施しており、平成9年度の4地域(川崎市、長野県飯田市、岐阜県、北九州市)、平成10年度の3地域(福岡県大牟田市、札幌市、千葉県)に加えて、平成11年度は秋田県、宮城県鶯沢町の推進計画を承認し、それぞれの計画に基づくリサイクル関連施設整備事業等に対するハード面の支援、及び環境関連情報提供事業等に関するソフト面での支援を実施した。
環境事業団では、循環と共生を基調とする地域づくりの実現に向けて、平成10年度に「ゼロ・エミッション団地」建設構想を具体化するための調査及び基本計画の作成を行い、これに基づき平成11年度は、神奈川県川崎市において異業種中小企業の連携・集団化等を通じて廃棄物再生・余剰エネルギーの有効利用、CO2排出削減等を総合的に推進する企業団地の建設譲渡事業を実施した。また、平成10年度に引き続き2地域を対象として、循環型・低環境負荷型システム構築のための調査研究、基本計画の作成を実施した。