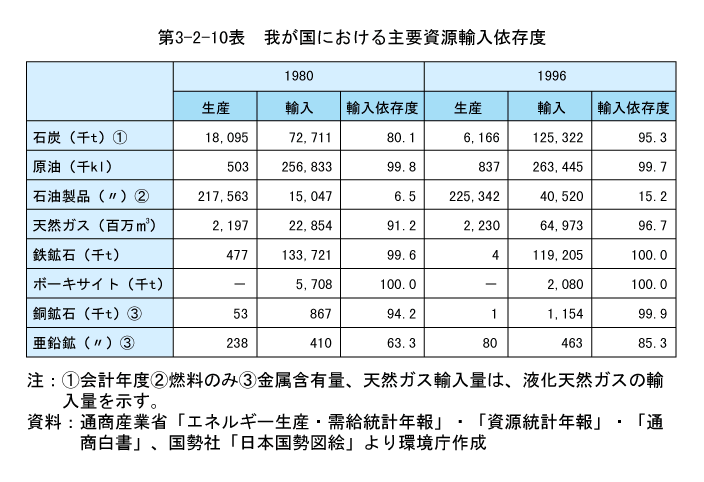
3 日本とアジア地域の関わり
(1) 先進国としての日本の構図
現在、我が国では、大量生産、大量消費、大量廃棄型の経済社会活動が営まれている。我が国は、この活動の基盤を海外からの資源・エネルギー等の輸入に依存しており、最近は中間財、部品の輸入国としてもアジア諸国と関わっている。その貿易量は、第3-2-10表に示すとおりである。また、輸出入構造を地域別に見てみると、我が国は特に輸出において東南アジア、アメリカを中心としている(第3-2-11表)。平成7年版の環境白書で、環境と貿易について論じているとおり、貿易自体が環境問題の本質的な原因ではないが、現象面をみると、貿易は需要と供給を国際的に結びつけるという機能を通じて、直接的又は間接的に、環境に対してプラスの影響もマイナスの影響も及ぼすことがある。
経済活動に伴い生じる環境への負荷としては、資源の採取に伴う環境負荷と、不用物の排出に伴う環境負荷に大別することができる。資源の採取に伴う環境負荷としては、鉱物資源等の枯渇性資源の採取に伴うものと、森林資源等の再生可能な資源の採取に伴うものとの二つに大きく分けられる。
(2) 資源の採取に伴う環境負荷
再生可能性との関係に着目して資源の採取に伴う環境負荷について整理してみると次のとおりである。
ア 枯渇性資源の採取に伴う環境負荷
我が国は、原油、鉄鉱石等の多くを海外に依存しており、これら枯渇性資源を産出する海外地域において、その採取に伴う環境への様々な負荷が生じていることが考えられる。
鉱物資源の採掘に伴う環境負荷の主なものは、?地表の直接的な破壊、?資源採取や精錬作業に伴う水質汚濁、大気汚染、土壌汚染、?大量の捨て石・不用鉱物の発生と不適切な処理等が挙げられるが、我が国に関わるこれらの活動がどの程度環境に負荷を与えているかを定量的に把握することはできていない。
イ 再生可能な資源の採取に伴う環境負荷
再生可能な資源の採取に伴う環境負荷の例としては、森林の伐採や食料生産によるものが挙げられよう。
日本の木材供給の推移を見てみると、第3-2-11図に示すとおり、自給率は年々下がり、現在では約8割を外材に依存しており、これが海外地域において環境負荷を生じさせていると考えられる。
森林の伐採に伴う環境負荷は、地域レベルにとどまらず地球規模に至る影響を生じさせる。まず、一地域の木材資源への過重な依存は、持続可能な配慮、例えば生態系に配慮した森林計画に基づく造成や植林などの適切な配慮がなされない場合には、地域的な環境悪化を招き、土壌の侵食などを誘発する可能性が高まる。一旦破壊した植生を回復させるには、多大な時間がかかったり、修復が不可能になる場合も考えられる。また、木材・薪炭材の資源の不足は、地域社会の安定的な発展を阻害すると考えられる。次に、地球規模での影響については、生物種の宝庫である森林の減少による生物多様性への影響が考えられる。また、森林は、二酸化炭素の吸収・固定化に役立つことから、その減少による温室効果ガス排出の増加や地球規模の気候調節機能の減少が懸念されている。
また、食料生産に伴う環境負荷についても同様に考えられる。我が国の食料自給率(供給熱量自給率)は先進諸国の中でも最も低いレベルである。しかも長期的な低下傾向が続いており、昭和35年度(1960年度)に79%だった食料自給率は平成9年度(1997年度)には41%にまで下がっている。平成9年における我が国の食料品の輸入額は5兆 5,769億円に上り、肉類 202.0万t、魚介類 280.1万t等をアメリカやアジアを中心とする広範囲の国々から輸入している(第3-2-12表)。また、エビを例にとって我が国の需給動向を見てみると、第3-2-12図のとおり海外からの輸入が9割近くを占める。
他方、途上国側の視点で見てみると日本との関わりはどうであろうか。マレイシアの丸太の対日輸出量は、全体の44.6%(量ベース)を占め、同様にインドネシアの合板の対日輸出も39.5%を占めるなど非常に関わりが深い。また、エビについてみると、インドネシアにとっては、日本が59.4%(1997年)を占める最大の輸出相手国であるが、近年のエルニーニョ現象による異常乾燥が、当該地域の水中の塩分濃度を上昇させエビが育たない事態が発生している。さらに、タイでは、第3-2-13図の示すとおり対日輸出量は減少傾向にあるが、近隣諸国の追い上げに加え、長年の連作障害により養殖池に白斑病などの病気が発生したとも原因として指摘されている。
このように、我々の生活は海外との貿易によって支えられている。途上国では、農林水産製品の製造、販売、輸出が、経済発展の中で大きな役割を果たしている場合が多い。
我が国が輸入している食料生産に伴う環境への影響は、輸出用のエビの養殖のためのマングローブ林の開墾による海岸生態系の破壊や、プランテーションによる農薬の影響等の事例が挙げられる。熱帯・亜熱帯の河口などの淡水と海水の混ざり合う汽水域や潮の干満の影響を受ける潮間帯などに成立する生態系をマングローブ生態系と言うが、このマングローブ生態系を構成する植物は90〜100種、あるいはそれ以上と言われている。これにはオヒルギ、メヒルギ、ヤエヤマヒルギなどの名前で知られるヒルギ科の植物だけでなく、シダ植物やヤシ科の植物も含まれる。我が国にも沖縄にマングローブ林が存在する。マングローブ林には、多様な用途や機能がある。例えば木材は燃料材、木炭材、船材、建築用材、実や種子は薬用や食用、樹皮は染料などに利用されている。また、その葉はヤギ、ラクダ、水牛などの飼料としても利用される。住宅や農地を高潮や強風から護ったり、風や波による海岸侵食を防止する等の防災機能、野生動物の生息場所を提供し、そこに生息する動物やそこに生育する植物の遺伝子を確保したり、沿岸の生態系を広域的に保全するなど、地球環境保全に役割を果たしている。マングローブ林は陸上の生態系ばかりでなく、海洋生態系にも重要な役割を果たしており、魚類、貝類、エビやカニといった甲殻類などの「最適な生息地」あるいはその「揺りカゴ」として餌場、産卵場所、生息場所を提供するなど、海洋生態系と切っても切れない関係にある。したがって、マングローブ生態系の保全は、陸上生態系と同時に、海洋生態系を保全することにもなる。マングローブ林の破壊で最も被害を被るのは地元の住民である。地元の人を直撃する被害としては、生活資源としての木材の不足、次いで生態系の破壊、そして沿岸保護機能が破壊されることである。このように我が国がエビを大量に消費することで、これを生産する途上国地域の人々の生活や生態系そのものへの影響を及ぼす場合がある。
ウ その他の側面
先進国と途上国の経済的な関わりが深まるにつれて、途上国の一部等から先進国によるいわゆる公害輸出を懸念する声が起きた。
具体的には、?危険物・有害物の輸出、?公害発生源となる工場、製造工程の輸出、?資源開発による環境の破壊などが指摘された。ASEAN諸国では、日本、欧米、NIESの企業進出の誘致を急ぐ余り、産業廃棄物処理が後回しになり、重金属の垂れ流しなどが生じている例もあったと指摘されている。
諸般の事情から国内における立地が困難になり、海外へと活路を見いだして立地を行う場合があるものと考えられるが、我が国からの進出企業がこうした批判にさらされることのないよう十分に環境保全に配慮していくことが重要である。
囲み3-2-1 地球温暖化対策と炭素リーケージ
地球温暖化防止京都会議で先進国(移行経済国を含む。以下同様)における温室効果ガスの排出削減目標の数値目標が設定された。この達成に向けて先進国が対策を講じた場合、先進国において相当量の排出削減効果が生じると同時に、途上国の二酸化炭素排出量が増加するという影響(以下、「炭素リーケージ」という。)が生じることが指摘されている。IPCCの報告書においては、炭素リーケージは、?エネルギー集約的な製品の生産拠点の対策を講じていない地域への移転?対策を講じた地域におけるエネルギー需要の減少に呼応した化石燃料の低下によって引き起こされる非抑制地域におけるエネルギー消費量の増大などを含むエネルギー市場効果、?交易条件の変化によって引き起こされる各地域の所得、エネルギー需要の変化などを含む多くの経路を通じて生じうるとされている。
炭素リーケージは、先進国の二酸化炭素削減目標が厳しい程、大きいと予想されるが、排出量取引によって軽減される可能性がある。京都議定書の目標達成の場合、排出量取引が導入されないケースでは、2010年の炭素リーケージの量は先進国の二酸化炭素削減総量の10%以下に見積もる予測もある。
いずれにせよ、グローバル化した現在の経済社会において環境対策を講じていくに当たっては、その国際的な波及効果を十分考慮した対応が求められている。