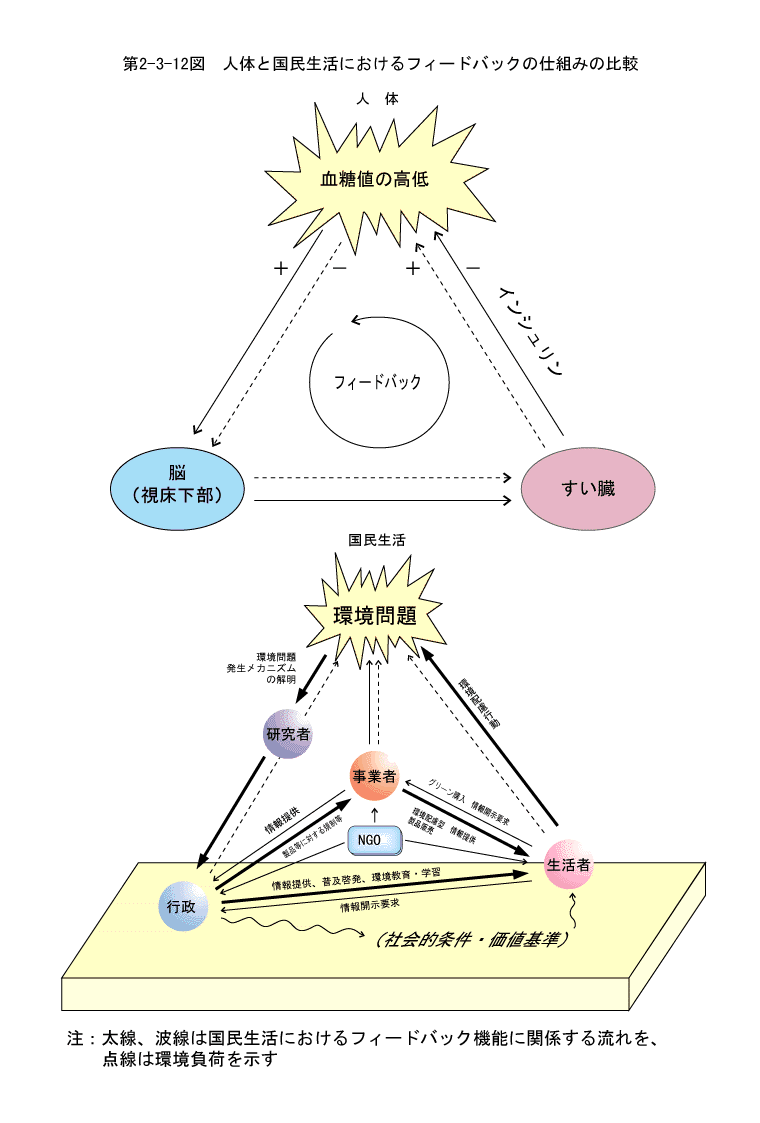
4 環境に配慮した生活行動に向けて
これまで、環境に配慮した生活行動を3類型に分け、それぞれについて、生活行動を阻害する要因に対し行政を始めとする各主体はいかなる対策を講じるべきかについて論じてきた。これまでの議論をまとめるに当たって、人体における「フィードバック機能」を国民生活にあてはめて考えてみると理解しやすい(第2-3-12図)。
人体には、ホルモンの合成と分泌を調整することで、人体を一定の安定した状態に維持するフィードバック機能が存在する。例えば、血糖値の高低に関する情報を受けた視床下部は、下垂体前葉でのホルモン合成と分泌の調整を通じ、内分泌腺(すい臓)から分泌されるホルモン(インシュリン)の作用を調整する。そして、仮にホルモンのレベルが上昇しすぎると、その情報を受けた視床下部が同じような調整過程をとることにより、安定した血糖値を保つのである。
こうしたフィードバック機能は、経済活動においては、市場における価格調整という形で存在する。しかし、価格の存在しない、市場から外部化された「環境」は、このフィードバック機能が有効に働かず(「市場の失敗」)、これまで、問題が顕在化し被害が生じた後に、追随的に対策を講じることがしばしばであった。さらに、数多くの被害者が発生するとともに、対策コストも被害が発生する前に対策を講ずる場合よりも過大となる例もあった。
このような過去の教訓に加え、地球温暖化問題等の生活行動に起因する環境問題が重大性を増す中で、生活行動にも何らかのフィードバック機能が必要ではないだろうか。
より具体的に説明してみよう。生活者の中には、これまで述べてきたように、環境保全意識はないが身の回りのリスクを回避しようとする人、自らの便益を損なわない程度の環境保全行動をとる人、環境保全意識が高く環境NGOへの寄附や活動に参加する等積極的に環境保全行動を実践する人など、様々な生活者が存在する。このように、生活者は、所与の社会的条件の下、自らの意思に従い自由に行動することができるし、その権利を誰も侵すことはできない。
こうした事実を前提とすれば、行政としては、まず環境保全に関する情報の収集・提供、普及啓発活動、環境教育・環境学習等を行うことで、生活者全体に環境保全意識を普及させ、生活者それぞれに「環境合理性」という行動規準を根付かせることにより、環境に配慮したより高次元の生活行動への進展を促していく。また併せて、グリーンGDPのような環境保全を重視した指標を使い経済活動を分析することで新たな価値観を創造するよう努める。しかし、仮にこれでも環境保全効果が低ければ、社会的条件を生活者が環境に配慮しやすいものに変更することが必要なのである。このように、生活行動におけるフィードバック機能を高く維持し、活用するに当たって、行政の大きな役割は、生活行動に起因する環境問題を把握するとともに、それに見合ったレベルの対策が講じられているのか常にチェックしつつ改善を施すことであろう。そして、各主体との連携の下、こうしたフィードバック機能が生活行動の中にうまく機能した時、言い換えれば環境保全という観点が生活者の行動目標の中に組み込まれた時、経済社会全体が環境負荷の少ない持続可能なものへ移行することになるだろう。