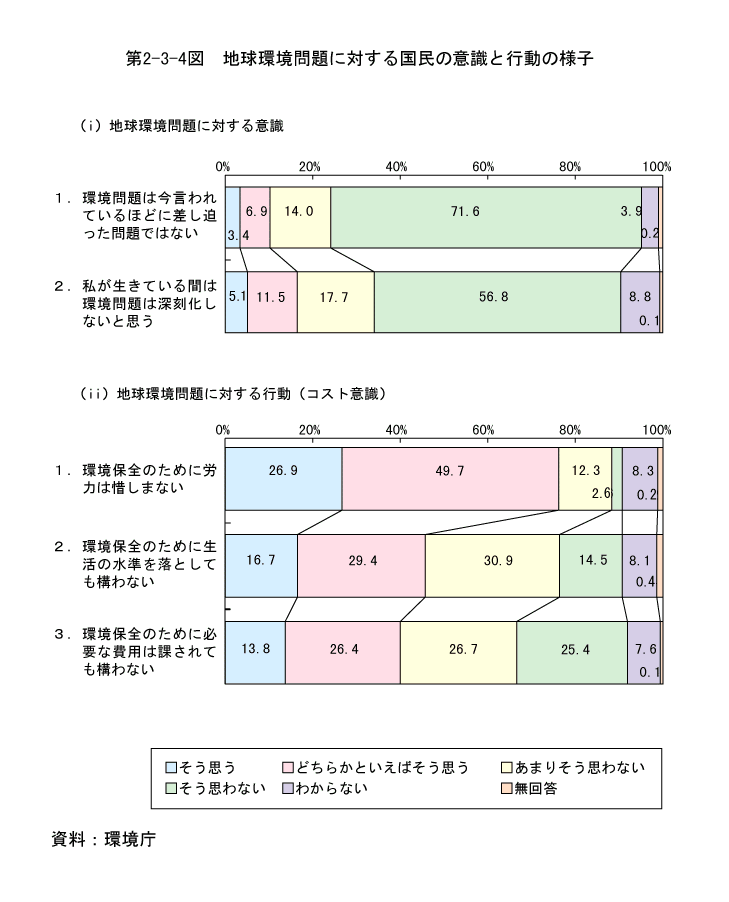
3 環境保全における意識と行動のギャップの解決
(1) 環境保全行動とは
日常生活からは、あらゆる場面において環境負荷が多少なりとも発生している。このため、生活者が自らと環境との関わりについて理解を深め、日常生活に起因する環境負荷の低減や身近な環境をよりよいものにしていくため、様々な環境保全行動を自主的、積極的に進めることが期待される。
(2) 環境意識と行動のギャップ
このように、環境問題の深刻さと自らの行動の必要性について自覚すれば、さらに生活者が身近で行うことのできる取組がたくさんあることが分かる。しかしながら、このような取組を率先的に行う必要性は認識しているものの、実際には、自らの生活の利便性や快適性を優先し、具体的な行動をとることができないのが常である。
このことは、国立環境研究所が平成7年9月に行った「地球環境問題をめぐる消費者の意識と行動が企業戦略に及ぼす影響調査《消費者編》」を見れば顕著である。
これによると、「環境問題は今言われているほどに差し迫った問題ではない」、「私たちが生きている間は環境問題は深刻化しないと思う」という2つの考え方に対して否定した人(「あまりそう思わない」、「そう思わない」と答えた人の合計)は、それぞれ85.6%、74.5%であった(第2-3-4図)。
その一方で、地球環境問題に対する生活者の行動に関する意識について聞いたところ、「環境保全のために労力は惜しまない」という考え方に対して賛成した人(「そう思う」、「どちらかといえばそう思う」と答えた人の合計)は、76.6%と高かった。しかし、「環境保全のために生活の水準を落としても構わない」、「環境保全のために必要な費用は課されても構わない」という考え方に賛成した人は、それぞれ46.1%、40.2%にとどまった。
囲み2-3-3 環境保全行動による環境負荷削減効果
環境保全行動とそれによる環境保全上の効果について代表的な事例を示すと、以下のとおりである。
? 駐停車時のアイドリングストップ、急発進・空ぶかしの抑制、タイヤの空気圧の適正化を始めとする点検・整備の励行等を実施する
→我が国全体で年間約100万kl(原油換算、以下同じ)のエネルギー節約
? 冷房温度は28度以上に設定する
→家庭全体で年間約38万klのエネルギー節約
? 暖房温度を20度以下に設定する
→家庭全体で年間約74万klのエネルギー節約
? 電気製品の主電源をこまめに切る
→家庭全体で年間約44万klのエネルギー節約
? シャワーのお湯の流しっ放しを1日1分間止める
→家庭全体で年間約27万klのエネルギー節約
? 再生紙100%のトイレットペーパーを使用する
→年間77千tのトイレットペーパー原紙(一人当たりトイレットペーパー5個)の節約
? スーパー、商店街などでの買い物には買い物袋を持参し、ポリ袋をもらわない
→年間18千tのポリ袋(横に広げると山手線に囲まれた地域の約3.5倍に相当)の節約
出典:「夏季の省エネルギーについて」「冬季の省エネルギーについて」(省エネルギー・省資源対策推進会議省庁連絡会議申し合わせ)「何から始める? リサイクル実践講座」(通商産業省編)
以上から、生活者の多くが、地球環境問題は遠い未来の問題ではなく、自分自身の生活にも影響を与える問題であるという危機意識を持っているものの、その一方でそのために不自由な思いをするのは困るという考えを持っているため、具体的な行動としては、不利益を及ぼさないものに限られることが見て取れる。こうした生活行動パターンは、「コモンズ(共有地)の悲劇」と呼ばれる寓話からも説明できるように、生活者が自らの便益のみを追求するあまり、将来的には社会全体更には生活者自身の便益を失わせることとなるのである。
囲み2-3-4 コモンズ(共有地)の悲劇
コモンズ(共有地)の悲劇は、生物学者のG.ハーディンによる同名論文(1968年)をきっかけに盛んに議論されるようになった。その内容は、次のとおりである。
「一定の広さの牧草地を共有しながら、羊を飼育する牧夫の集団がいるとする。放牧された家畜の総数が、その土地の環境容量の範囲内であれば、継続的に彼らは共有地を使用し、利益を得ることができる。ある個人が羊を増大させることは、一方でその個人には頭数の増加による利益をもたらすが、他方で、過放牧によって、一頭当たりの肥育状況を悪化させる。だが、後者の形での損失は、全員に分散されるので、この個人にとっては、頭数の増加による利益と比較して小さい。こうして、自分の直接的利益を最大化するという合理的行動をとるとき、各人は自分の羊の頭数を増加させようとするのである。しかし、こうした行動が重なると過放牧による共有地の荒廃が起こり、共倒れとなってしまう。」
これが「コモンズの悲劇」が描くシナリオであるが、同じことは、環境問題にもいえる。例えば、大気はコモンズであり、排出規制がない場合、企業や人々は無制限に大気を汚染物質の捨て場所として利用するため、大気は汚染され人々の健康が損なわれる可能性が生じるのである。
(3) 環境保全行動の実践を促す社会の実現
コモンズの悲劇は、「生活者が、認識している社会的条件の下で、自らの価値観や行動規準に従い自らの便益を最大化する」結果生じるものである。この時、コモンズの悲劇を解決するには、一人一人の努力に期待するだけでは不十分であり、生活行動の基盤となり制約条件ともなっている社会システムを変えることにより、生活者に環境に配慮した生活行動を実践しようとするインセンティブを与えることが必要不可欠であることがわかる。具体的には、第一に、生活者が置かれている「社会的条件」そのものを変えていくこと、第二に、社会的条件に対する生活者の「認識」を深めていくこと、第三に、生活者に環境重視の「価値観」や「行動規準」を確立させるよう促すこと、が考えられる。
ア 解決方策その1〜生活者が置かれている「社会的条件」の変更
生活者が置かれている社会的条件として、法律、税制等の社会制度、社会に長年定着してきた生活様式、社会資本など様々なものが考えられるが、以下では、主に地球温暖化対策、特に生活者との関わりの深い二酸化炭素排出抑制対策の観点からこれらを考察する。
(ア) 国内における地球温暖化対策の枠組みの構築
コモンズの持つ浄化能力、再生能力の範囲内で、生活行動から生み出される環境負荷を確実に抑制するためには、大きく2つの措置を通じて環境コストを内部化することが必要となる。つまり、その一つが自らが直接生み出す環境負荷を抑えようとするインセンティブを生活者に与える方法であり、もう一つが生活者が購入する財・サービスの性能を改善することを通じて間接的に生活者による環境負荷を抑制する方法であるが、これらの措置は状況に応じて適切に組み合わされることが望ましい。
このことを二酸化炭素排出抑制対策の点から具体的に考察してみよう。
平成8年度の二酸化炭素の部門別排出量の推移を見ると、民生(家庭)部門の二酸化炭素総排出量に占める割合は12.8%、自家用車利用による排出量を加えてもおよそ2割であり、産業部門等と比較すると小さい。しかし、平成2年度と比較した伸び率で見ると、産業部門がほぼ横ばいであるのに対して、家庭部門は14.8%、運輸部門(自家用車利用も含む)は19.2%の伸びを示しており、京都議定書で我が国に課せられた温室効果ガスの6%削減目標を達成するためには、家計部門(民生(家庭)部門+運輸(自家用)部門)の対策が急務と言える(第4章第4-1-2図参照)。
では、生活行動に関係する部分の二酸化炭素の排出削減については、具体的にいかなる対策がとられているのであろうか。
現在法律としては、「地球温暖化対策の推進に関する法律(地球温暖化対策推進法)」と「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」の大きく2つが存在する。
地球温暖化対策推進法では、「国民の責務」として、「温室効果ガスの排出の抑制等のための措置を講ずるよう努める」とともに、「国及び地方公共団体が実施する温室効果ガスの排出の抑制等のための施策に協力しなければならない」と定めている。同法に基づき、平成11年4月に閣議決定された「地球温暖化対策に関する基本方針」では、大量消費、大量廃棄型の生活様式を見直し、温室効果ガスの排出の少ない製品・設備やサービスの選択、節電に努めるなどの具体的な国民の措置が定められている。また、直接国民に対しては、「地球温暖化防止活動推進員」や各地に設置される「地球温暖化防止活動推進センター」を通じ、様々な情報提供を行い、生活者が日常生活において排出抑制行動をとることを促すこととしている(第2-3-5図)。
一方、平成10年に改正された省エネ法は、自動車や家電・OA機器等の省エネルギー基準について、現在商品化されている製品のうちエネルギー消費効率が最も優れている機器の性能を勘案し目標値とする、いわゆるトップランナー方式の考え方を導入した。こうした機器のエネルギー消費効率の飛躍的な改善を通して生活者の二酸化炭素排出削減を図ろうとしている。
また、6%削減目標達成のための当面の対策として、平成10年6月に地球温暖化対策推進本部(本部長:内閣総理大臣)において、地球温暖化対策推進大綱が決定され、エネルギー需給両面の対策、ライフスタイルの見直し等幅広い分野の対策を推進することとなった(第2-3-6図)。
以上のように、生活行動から排出される二酸化炭素を削減する方法として、地球温暖化対策推進法に基づく基本方針等にのっとり生活行動から直接排出される二酸化炭素を削減するインセンティブを与えていく方法と、省エネ法に基づき機器のエネルギー消費効率の改善を推進することにより間接的に二酸化炭素の排出量を削減する方法が存在する。そして、これらが適切に組み合わされることにより、総合的な地球温暖化対策の枠組みが構築されることが期待される。また、こうした枠組みの中でより円滑かつ効果的に抑制効果を確保するためには、規制的措置のみならず、技術開発や排出抑制を誘導するような経済的措置を重視することが必要である。
(イ) サマータイム(夏時間)制度の導入
a サマータイム制度と我が国における経緯
サマータイム制度とは、日の出時刻が早まる時期(例えば4月〜10月)には、時計の針を1時間進め、夕方の明るい時間を増やし、日の出から1日の活動開始まで太陽光を有効活用できない時間を減らす制度のことである(第2-3-7図)。海外ではデイライト・セイビング・タイム(DaylightSaving Time)とも呼ばれ、現在70か国以上で導入され、そのうちOECD加盟29か国の中では、日本、韓国、アイスランド(白夜になるためサマータイムを導入する必要がない)以外のすべての国において実施されている(第2-3-8図)。
我が国においても、戦後の石炭事情の悪化、電力不足の深刻化を背景として、GHQの指示に基づき、昭和23年よりサマータイム制度が導入されたが、国民の半数以上の者から反対され不評である旨の世論調査結果や電力事情の改善等により、昭和27年に同制度は廃止された。
しかし、オイルショック以後、エネルギー利用の効率化の必要性が高まるとともに、特に近年は、地球温暖化問題が深刻化し、再びサマータイム制度の導入について議論がなされるようになった。さらに、平成9年12月の気候変動枠組条約第3回締約国会議で採択された京都議定書における6%削減目標を達成するためには、生活者の生活様式の変更も含めた抜本的な対策が必要となっている。平成10年6月には、地球温暖化対策推進本部が地球温暖化対策推進大綱を決定し、その中に「夏時間(サマータイム)の導入と地球環境にやさしい生活の在り方について国民的議論を行う」ことが盛り込まれた。これを受けて、平成10年9月に「地球環境と夏時間を考える国民会議」(事務局幹事:経済企画庁、環境庁、通商産業省)が発足し、多面的な議論が展開されている。以下では、この国民会議の内容及び世論調査結果を基に、サマータイム制度の効果について考察する。
b サマータイム制度の効果
サマータイム制度を導入すれば家庭における朝の照明用と夕方の冷房用の電気消費量が増加する一方で、夕方の家庭用・業務用の照明用電力消費量などが節約できる。ただし、余暇需要拡大に伴うエネルギー消費等への影響を考慮すると、サマータイム制度導入に伴う全体的な省エネルギー効果は約50万kl、二酸化炭素削減効果は約44万tと推計される(1997年実績ベース)。これは、我が国の一次エネルギー供給の約0.1%程度であり、省エネ・温室効果ガス削減施策としての意義が少ないのではないかという意見がある。しかし、サマータイム制度については、地球温暖化対策推進大綱にも述べられているとおり、同制度がきっかけとなって、地球環境にやさしいライフスタイルへの転換が図られることがねらいとされている。例えば、年2回時計を調整する際に、国民一人一人がどうしてこのような制度が導入されたのかを心に留めることを通じて、地球環境にやさしいライフスタイルを実現するための意識改革に寄与するという効果があると考えられる。そこで、サマータイム制度が生活者の意識改革に果たす役割について見てみよう。
平成10年11月に行われた「地球環境とライフスタイルに関する世論調査」によると、サマータイム制度導入に賛成すると答えた人の割合が54.0%となり、前回の調査(平成8年2月)と比較してみると、賛成と答えた人の割合が上昇(46.7%→54.0%)している。さらに、賛成と答えた人にその理由を聞いたところ、「エネルギーの節約になるから」と答えた人の割合が37.1%と最も高く、以下、「余暇時間の拡大になるから」(17.2%)、「太陽(日光)を活用する習慣をつけることはよいことだから」(13.6%)などの順になっている。このことから、サマータイム制度がエネルギーの節約、余暇時間の拡大といったライフスタイルへの転換につながるとの認識が増してきており、実際サマータイム制度を導入した際には、その効果は大きいと考えられる。
(ウ) 自動車交通需要を調整するための施策の実施
我が国においては、戦後一貫して大都市圏への人口の集中、産業の集積が続いてきた。特に、近年は、首都圏、関西圏、名古屋圏の三大都市圏だけでなく地方中核都市においても程度の差はあれ、人口の集中、産業の集積が進んだ。こうした都市における経済活動や生活の発展から発生する交通需要の増大に対して、従来は、道路を整備し、交通サービスの供給を拡大するという需要追随型の対策が中心であった。
しかし、最近では、土地利用の側面、そして自動車の排気ガス中に含まれる二酸化炭素や窒素酸化物といった環境面から見て、交通容量の大幅な拡大が困難な状況になり、自動車交通需要を調整するための施策の必要性が論じられるようになった。具体的には、環境負荷の少ない公共交通機関を整備し、その利便性を向上させることにより、公共交通機関へ需要を誘導することが必要となった。このため、鉄道、バス交通システムを整備するとともに、バス・自転車・自動車等との結節の強化による乗り継ぎの抵抗の軽減、利用効率の向上のための環境定期券を販売すること等による公共交通機関への誘導を図っている。
囲み2-3-5 公共交通機関の利用による環境対策と高齢者対策との融合
急速な人口の高齢化に対応し、かつ都市部における交通渋滞の緩和や排気ガスによる大気汚染の防止に資するものとして、近年公共交通機関の活用が注目されている。
警察庁、運輸省及び建設省は、平成9年度より「オムニバスタウン構想」を推進している。これは、都市部での自動車事故の防止、交通渋滞の緩和、排気ガスによる大気汚染の防止を目的に、公共交通機関であるバスの利用促進を市町村が自主的かつ一体的に取り組むものである。高齢者への配慮として、例えば平成9年12月に初めてオムニバスタウンの指定を受けた浜松市においては、ノンステップバスを導入している。
また、近年、欧米の各都市において、新しいタイプの路面電車システムであるライト・レール・トランジット(LRT)が導入されている。LRTは、都市内の交通渋滞緩和やこれに伴う大気汚染の解消を図る上で有効な公共交通機関である。現在、我が国においては、熊本市においてLRTの車両であるLRV(超低床電車)が導入されているが、プラットホームからの乗降時の移動には、ほぼ水平移動となり、高齢者の移動手段としても非常に有用と言える。
また、円滑な自動車走行確保のため、交通需要マネジメント(TDM)施策や高度道路交通システム(ITS)等を推進している。特に、ITSのうち、ナビゲーションシステムの高度化に関しては、全国の高速道路や三大都市圏等の9都府県の一般道路において運用中の道路交通情報通信システム(VICS)の全都道府県の一般道路への拡大を推進するとともに、ノンストップ自動料金収受システム(ETC)に関しては、整備効果の高い路線の料金所から逐次導入を図ることとしている。
このような交通対策に加え、適切な運転の励行、低公害車や低燃費車の普及を進めることにより、自動車単体当たりの窒素酸化物、二酸化炭素の排出量の削減を図っている。
囲み2-3-6 低公害車の普及に向けた取組
平成10年12月末現在、国内における低公害車の保有台数は約24,000台程度である。低公害車は、自動車交通に起因する大都市地域を中心とした窒素酸化物等による大気汚染や地球温暖化等の環境問題の解決に有効であり、その普及に向けて、?低公害車の導入コストの低減、?燃料インフラの整備促進、?低公害車の車両としての性能向上、?低公害車への理解の促進、の4つの方向を軸に様々な施策が推進されている。
イ 解決方策その2〜社会的条件に対する生活者の「認識」の深化
(ア) 環境教育・環境学習の推進
a 環境教育・環境学習の現状
大量消費・大量廃棄型社会の定着によるごみの排出量の増大や、生活排水の流入による河川の水質汚濁等の身近な都市・生活型公害、あるいは温室効果ガス排出量の増大による地球温暖化問題といったように、日常生活と環境問題は多様な因果関係を持っている。したがって、環境教育・環境学習を通じて、こうした因果関係について幅広く理解し、実際の行動に活かしていくことが必要である。
環境基本計画にも示されているとおり、今日の環境教育・環境学習は、「環境に関心を持ち、環境に対する人間の責任と役割を理解し、環境保全活動に参加する態度及び環境問題解決に資する能力が育成されること」を通じて、各主体を「具体的行動」に導き、持続可能な生活様式や経済社会システムの実現に寄与するものと位置付けられている。
環境庁では、環境基本計画に定められた方針にのっとり、平成7年6月から、全国の小中学生を対象として「こどもエコクラブ」への参加を呼びかけ、地方公共団体との連携の下、子どもたちが楽しみながら地域で環境に関する学習や活動を行えるよう支援している。本事業は、子どもを対象に継続的な学習・活動機会を提供するものであるが、事業開始から4年を経て、地域住民、民間団体、企業等と連携した取組も増え、多様な活動が展開されるようになってきている。平成10年度には約4000クラブ、7万人の小中学生が参加した。さらに、生活の場で環境に配慮した行動の実現・定着を図るため、環境庁では、二酸化炭素の排出を減らす環境家計簿運動やエコライフ実践活動等を展開するとともに、自然についての学習や自然とのふれあいを目指し「自然大好きクラブ」を支援するなどして、多くの参加者を得てきたところである。
しかしながら、先に見てきたとおり、社会全体については環境保全に向けた具体的行動が広く生活者に根付いているとはいまだ言い難い。「環境基本計画の進捗状況の第3回点検結果」(平成10年8月)においても、生活様式の変革という観点からの環境教育の政策的な方向付けがほとんど行われてこなかったことが指摘されている。
b 環境教育・環境学習についての今後の方向性
平成10年9月に、中央環境審議会環境教育小委員会が中間取りまとめを公表したが、その中で、今後の環境教育・環境学習の推進方策の基本的な考え方として、知識・理解を行動に結びつけるために、継続的な実践的体験を環境教育・環境学習の中心に位置付けることや、体系的かつ総合的な環境教育・環境学習が可能となるような機能的、効果的な仕組みを構築すること等が指摘されている。さらに、早急に取り組むべき課題として、プログラム等の体系化、人材の育成、情報提供体制の整備、拠点の整備及び拠点間のネットワークの構築等が提示されている。
この取りまとめを受け、環境庁では、環境学習を体験を通じて深められるよう学習現場の整備をまず進めることとして、平成10年度に「総合環境学習ゾーン・モデル事業」を実施した。
囲み2-3-7 総合環境学習ゾーン・モデル事業
環境にやさしいライフスタイル、ビジネススタイルを普及させ、21世紀の新しい経済社会づくりの担い手を作ることを目的に、平成10年度に「総合環境学習ゾーン・モデル事業」を実施した。この事業により、全国4つのモデルのゾーン(?日本海東北部、?東海、?京滋・阪神、?瀬戸内海中央)それぞれにおいて、地球温暖化、ごみ問題等の多様な環境問題についての体験的な学習を行える現場が整備されるよう、資機材の充実が図られたことに加え、優れた学習機会が幅広く提供されるよう、学習現場相互のネットワークの整備も行われた。
学校教育においては、平成10年12月の学習指導要領の改訂(高等学校については平成11年3月)に際して、各教科等における環境に関わる内容の一層の充実を図るとともに、環境等の横断的・総合的な課題などについて学校の実態に応じた学習活動を展開する「総合的な学習の時間」を新たに設けたところである。
今後、学校、地域、家庭、職場、野外活動の場等多様な場において、幅広い関係者の緊密な連携により、体験的な学習・活動を重視しつつ環境教育・環境学習が総合的に推進され、環境負荷の少ない行動様式が現実のものとなり、持続可能な経済社会の実現に生活者が目に見える役割を果たすようになることが期待される。
(イ) 環境保全型製品の普及促進
a 環境ラベルの活用
環境ラベルとは、製品等が環境に与える影響に関する属性情報をラベルの形で表示することにより、製品の差別化を図るものである。このような環境ラベルは、
? 製品の「環境への負荷」についての情報を消費者に伝達することにより、環境保全型製品の選択を促し、消費者がより環境保全に配慮した行動をとることを可能にする
? 事業者に対し、環境保全型製品の開発の動機を与える
といったことを通じ、経済社会が環境保全をより内在化したものになることに貢献するものとして捉えることができる。
我が国における環境ラベルとしては、例えば、平成元年2月より(財)日本環境協会が実施しているエコマーク事業がある。平成10年12月31日現在、70商品類型について認定基準が定められており、事業者の申請に応じて、この認定基準に適合する2,711商品にエコマークがつけられている。エコマーク事業は、平成8年3月に実施要領が改正され、認定基準の制定に当たっては、これまでの特定の環境負荷の低減だけを考慮した基準の設定から、製品の製造、流通、消費、廃棄等のライフサイクル全体での環境負荷を考慮することとした。
諸外国においても、ドイツの「ブルーエンジェル」、アメリカの「グリーンシール」等20以上の環境ラベリングが実施されている。また、こうした環境ラベリングが不必要な貿易障壁とならないよう、基準の統一化や相互認証等について、WTO、OECD等の場で議論がなされている。こうした中、環境ラベリングを実施している各国の機関により、1994年(平成6年)世界エコラベリングネットワーク(GEN)が設立され、我が国からは(財)日本環境協会が理事として参加している。環境庁は、国際貢献の一環として東京に設置しているGENの総務事務局を支援している。
b グリーン購入ネットワーク
第1章で既に触れたように、「グリーン購入ネットワーク」は、我が国におけるグリーン購入(環境負荷の少ない商品やサービスを優先して購入すること)の取組を促進するために、平成8年2月に設立された企業・行政・消費者による緩やかなネットワークである。本ネットワークは、グリーン購入に関する普及啓発や必要な情報の収集・発信を行うことにより、環境負荷の少ない商品やサービスの市場の成長を促し、環境保全が内在化された経済社会の実現に寄与することが望まれる。
ウ 解決方策その3〜環境重視の「価値観」や「行動規準」の生活者への定着
(ア) 新たな価値観の創造と「環境合理性」の提案
戦後、我が国はGDPの伸びに見られるように飛躍的な経済成長を遂げた。物質的にはこれまでにない「豊かさ」を実現してきたわけだが、その根底には企業中心的な大量生産指向型経済成長を追求する姿勢がうかがわれる。つまり、人々は、公害等による健康被害、会社での長時間労働、うさぎ小屋と言われる住宅事情や超満員電車での遠距離通勤などと引き換えにして、歴史上かつてない規模の生産力を達成してきたのである。
しかし、このような企業中心的な大量生産指向型経済成長は大きな壁にぶつかりつつある。1980年代後半のバブル経済を経た後、1990年代に入ってからの不況ないし低成長時代は、20世紀型の成長パターンが行き詰まりつつあることを予告しているのではないだろうか。これからは、従来の大量生産指向型経済成長から脱却する、具体的には企業を中心とした「生産量」重視の経済社会から生活者(勤労者)を中心とした「生活の質」を重視した経済社会へ転換することが必要である。環境面から見れば、生活者が自らの健康やそれを支える環境に対する価値に重きを置く、つまり、環境価値を重視した行動規準(「環境合理性」)に従い、生活者が行動することが求められる。様々な意味で転換期を迎えている今こそ、「環境に配慮した生活行動」を生活者の手で創造することができる好機と言えるかもしれない。
この時、行政は、環境重視の価値観や「環境合理性」に基づく生活行動を生み出すバックグラウンドを整備することが必要である。すなわち、既に述べたとおり、未知の部分も多い環境に関する知見の収集や必要な情報提供、環境保全行動に資する各種ツールの整備など、行政の果たすべき役割は大きい。以下では、その一つである「生活の質」の豊かさを表す指標について、これまでの行政の取組と今後の方向性を考察する。
(イ) 「生活の質」の豊かさを表す指標の構築
a GDPの矛盾
経済発展の指標として現在でも広く使われているGDPは、国内市場において取引された財・サービスのみを計上するため、市場を経由しない環境価値の喪失・改善等による国民生活の質の問題を適切に反映していない。例えば、自然の浜辺が埋め立てられレジャー施設ができたとすると、以前はただで海水浴ができたためGDPとして全く評価されなかったものが、レジャー施設の建設により建設費と使用料が生まれてGDPが押し上げられ、その一方で環境破壊が生じるのである。このように、GDPが上昇することによりあたかも生活が豊かになったかに見えるが、実際は自然破壊、公害等が進展し生活に豊かさを感じないことが起こりうるのである。
b グリーンGDPの開発
人間活動と環境との関係を統一的な基準で把握しようとする取組として、環境勘定の開発が経済企画庁や環境庁で行われている。
国連による平成5年(1993年)の国民経済計算体系(SNA)の改訂に際してサテライト勘定の一つとして環境・経済統合勘定(SEEA)の導入が勧告されたことを受け、経済企画庁において研究が進められ、平成10年7月に試算値が公表された。これは、?SNAのフロー、ストックに含まれる既存計数から環境保護関係の計数を分割して明示するとともに、?経済活動に伴う環境に関する外部不経済を貨幣評価し(帰属環境費用の算出)、?国内純生産から帰属環境費用を差し引いた環境調整済国内純生産(EDP)、いわゆるグリーンGDPを示したものである。経済企画庁の試算によると、平成2年の帰属環境費用は4.2兆円、対GDP比で1.0%であった(第2-3-9図)。この費用の中には二酸化炭素による地球温暖化については試算が行われていないなど、今後検討が必要な部分も多いが、国連の提示した枠組みに基づく先駆的な取組の例として意義のあるもので、引き続き改良が進められている。
また、環境庁においては、平成9年度に物量ベースの包括的環境勘定体系(CASE)を開発した。これは、業種毎に環境に負荷を与える人間活動、環境負荷、環境の状況、環境負荷による人間活動等への影響、そして各段階での対策といった個別の環境問題における一連の流れを把握するとともに、業種間における資源利用量や資源の流れとそれに伴う環境負荷を体系的に整理したものである。このCASEは、SEEAと密接に関係するものの、その主たる目的が基礎的な統計情報整備であり、国民にとってわかりやすいものとするには、CASE上のデータを基に指標化することが必要である。
c その他の指標の開発
これら以外にも、様々な指標の開発が進んでいる。
例えば、イギリスの地球の友は、人類の進歩とは何かを再定義し、GDPに代わる生活の質を重視した指標として、「持続可能な経済厚生指標(ISEW)」を開発した。また、UNDP(国連開発計画)においても、GDP等の経済指標が必ずしも国民の豊かさを反映していないとして、富が生活、健康、教育にどれだけ有効に使われているかを示す指標「人間開発指標(HDI)」を開発し、1990年(平成2年)以降毎年、国別HDIを公表している。
また、こうした「生活の質」の豊かさを表す指標と同様に、これまでの量的な豊かさの弊害を示すものとして、我々の消費活動がどれだけ地球環境に対し負荷を与えているのかを示す指標が有効であると考えられる。例えば、平成10年10月、スイスに本部を置くWWF(世界自然保護基金)は「生きている地球レポート1998」を出版し、地球の生態系がどこまで悪化しているかを示す「生きている地球指標:LPI」を公表した。この指標は、時間的に見た森林や淡水、海洋生態系の平均的変化のデータに基づいて得られた、地球規模の生態系と生物多様性の健全度を示す指標である。これによれば、LPIは1970年から95年の間に30%以上減少し、特に1990年から95年の間で劣化のスピードが増しており、平均減少率が毎年約3%であるとされている(第2-3-10図)。また、この報告書では、LPIに加え、6つの主要な消費項目(穀物、海洋魚、木材の消費、淡水の利用、化石燃料の消費に近似するものとしての二酸化炭素排出量、土地の使用に近似するものとしてのセメント消費量)について、各国の総消費量(=資源生産量+輸入量-輸出量)を人口で割って、一人当たり消費量を求め、世界人口一人当たりの消費量と比較することにより、各国の消費に係る環境負荷の大きさを考察している(第2-3-11図)。
また、カナダのブリティッシュ・コロンビア大学は、「エコロジカル・フットプリント」と呼ばれる指標を開発した。エコロジカル・フットプリントとは、直訳すれば「経済活動による生態系の踏みつけ面積」であり、ある特定地域の経済活動、又はそこに住む人々の生活を持続的に支えていくためにどれだけの生産可能な土地(水域)が必要かを算出し、面積を単位として表した指標である。つまり、食糧、木材を得るための農地や森林、二酸化炭素を吸収するための森林、漁業資源を得るための海洋等の面積を合計し、地球上に存在する生産可能な土地水域面積と比較することにより、経済活動が水土の再生供給能力とバランスがとれているかを判断するという概念である。第2-3-1表は、日本人全体と一人当たりの消費に係るエコロジカル・フットプリントを示したものである。
その他には、オランダの地球の友が、将来の世代の資源使用の権利を犯さない限りでどの程度のエネルギー、水、その他資源の利用や消費活動、そして環境汚染が許されるのかを世界中の人々が公平に持ち得る一人当たりの利用の許容限度を「エコスペース(環境容量)」として算定している。