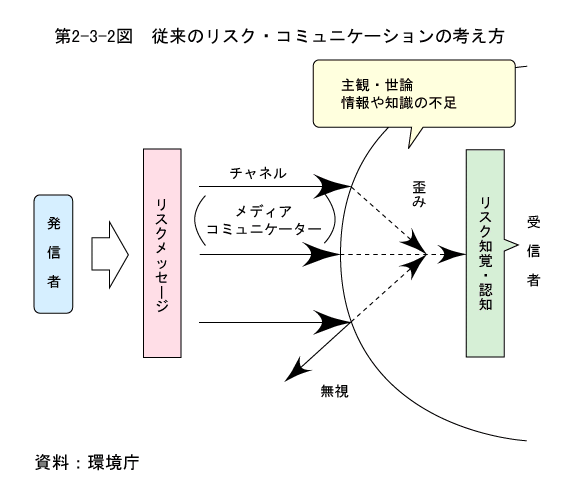
2 リスク・コミュニケーションを通じた回避行動の必要性
(1) 環境リスクについて
ここで、まず「環境リスク」について整理したい。
「リスク」(risk)とは、人間の活動に伴う望ましくない結果とその起こる確率を示す概念である。人間にとって好ましくない出来事について、「影響の大きさ」に「発生の不確かさ」を掛け合わせて評価するのがリスクの基本的な考え方である。例えば、懸念される影響が相当大きなものであっても、その発生する確率が非常に小さければ、リスクは小さいと評価される。
また、「環境リスク」とは、環境基本計画においては、生産、使用、廃棄等の仕方によっては人の健康や生態系に有害な影響を及ぼすおそれのある化学物質が、環境の保全上の支障を生じさせるおそれを示す概念である。
今日の化学物質による環境問題は、人間や生態系が複雑な経路を通じて長期間にわたり微量の物質に曝露されることから生じるものであるが、この物質を検出し、その原因を特定するには困難が伴う。こういった不確実性を孕んだ問題に対処するには、環境リスクの考え方に沿って問題を整理し、判断の基礎とすることが必要である。
つまり、環境リスクの考え方を取り入れる意義は、
? 不確実性を伴う環境問題について科学的知見に基づき様々な影響を予測、評価し、判断の根拠を示しうること
? 環境リスクの比較により、多数の要因に対する政策と取組の優先順位を客観的に示しうること
? 環境リスクの考え方を応用すれば、大気、水等にまたがる複数の媒体(クロスメディア)の汚染や、各分野の対策を横断して、より効果的、整合的に環境リスクを削減しうること
と考えられる。
(2) 環境リスクの評価の必要性
環境リスクへの対応を図るに当たっては、科学的な知見に基づきリスクを客観的に評価するリスク評価(リスク・アセスメント)を実施し、リスク評価の結果に基づき、排出抑制等によるリスクの低減やリスクを正しく伝達して相互理解を促進するリスク・コミュニケーションなどから成るリスク管理(リスク・マネジメント)を行うことが重要である。
囲み2-3-1 人の健康への影響の発生確率の推定例
大気中の濃度が1μg/m
3
の化学物質に一生涯曝露されたときの発がんの確率が3×10
-6
(=百万人のうち3人)である場合、我が国の全人口(1億2千万=1.2×10
8
人とする)が当該化学物質に曝露しておりその生涯曝露レベルが2μg/m
3
であったとすると、全人口の生涯における発がんリスクの推定は、
3×10
-6
×2×1.2×10
8
=720
となり、平均寿命を80歳とすると、当該化学物質による1年間の過剰発がんリスクは、720÷80=9、即ち9人となる。
囲み2-3-2 環境リスクの管理における原則について
一般的に、環境リスクの管理に当たっては、次の3つの原則が考えられる。
(ア) ゼロリスクの原則
環境リスクをゼロにする事を目指す原則である。しかし、あるリスクをゼロにしようとすると、他に大きなリスクが生じる場合がある等の矛盾を抱え、実際に用いるのは困難である。
(イ) リスク一定の原則
すべてのリスクの大きさを一定のレベル以下に抑える原則であり、非常に小さな一定以下の環境リスクを実質的に安全と見なそうという考え方を基礎にしている。例として、我が国のベンゼンの大気環境基準の設定の考え方として、10万分の1(10
-6
)の確率をリスク制御の目安としている。この方法は今後も使われるであろう。しかし、その場合も便益(ベネフィット)に対するリスクの値(リスク/ベネフィットの値)の小さな物質や活動に対しては、リスクの値そのものは大きくとも認めるという例外を作らざるを得ない。
(ウ) リスク・ベネフィットの原則
環境リスクと引き替えに得られる便益(ベネフィット)と環境リスクの大きさを比較し、その結果によって許容される環境リスクを求めたり、対策の優先順位を決めたりする考え方である。金銭的な尺度で表現される場合、一種の費用便益分析(コスト・ベネフィット分析)となり、リスク削減のための対策によって生じる費用(リスク削減によって失われる便益を含む)と、リスク削減によって得られる便益が比較衡量される。
リスク・ベネフィットの考え方は、広範多岐にわたる環境リスク対策を限られた人的・経済的資源の中で進めていくための有効な手段となることが期待される。
リスク評価は一般に次の4つの手順に従って行われる。
(ア) 有害性の確認
ある化学物質等が持つ有害性の情報について、定性的に明らかにする。人については、一般環境における影響の知見は少ないので、主に、労働環境における曝露の知見などから一般環境における影響が推定される。
(イ) 量−反応評価
動物実験の結果などから、化学物質の曝露量とそれにより生ずる健康や生態系の影響の関係について定量的に明らかにする。
(ウ) 曝露評価
呼吸や食事などを通じて、化学物質を取り込む量(曝露量)を定量的に明らかにする。
(エ) リスクの判定
上記の(ア)(イ)(ウ)の結果から、人や生態系に対する影響の種類、程度を明らかにするとともに、必要に応じて健康影響の発生確率を推定する。
環境リスクへの対応を適切に進める上で、化学物質の特性、環境中での動態、環境中濃度、人や生態系への曝露量など環境リスクに関する知見の充実、情報の適切な提供を行い、環境リスク評価を実施していくことが重要である。
(3) 適切なリスク・コミュニケーションの必要性
ア リスク・コミュニケーションとは
これまで見てきたように、加害者と被害者が明確に分かれて存在した従来の産業公害と違って、現在の環境リスクは、日常生活を含めた経済社会活動全般から生じている側面が強い。したがって、このような環境リスクの低減を円滑かつ効率的に進めるためには、行政のみならず、事業者、生活者、専門家、NGO等の関係者がリスクに関する正しい知識とお互いの意見を理解した上で、一体となって取り組む必要がある。このためには、各主体相互の情報交換を通じて、リスクに関する情報や認識を共有し、冷静な行動を促すというリスク・コミュニケーションが重要であり、リスクの大きさが社会的に正しく認知されることが、新たな対策を実施するための合意形成の前提となる。
リスクに関する情報が適切に伝えられることは、事業者や生活者が環境リスクを自主的、積極的に削減していくのを促す上で重要である。直ちに規制を行うには至らない環境リスクであっても、その要因と大きさが明示されることで、生活者は自らの判断で冷静に行動することが可能となる。
ここで注意すべきことは、リスク・コミュニケーションとは、「生活者の理解を進める」ことを目的としているが、これと「生活者の合意を形成する」こととは別であるという点である。
つまり、従来のリスク・コミュニケーションは、行政や事業者から、生活者やNGO等に一方的にメッセージを伝達し、情報発信者の見解を受信者に受け入れさせること(合意形成)を目的としていた(第2-3-2図)。しかし、最近では、リスク・コミュニケーションは、行政、生活者、事業者やNGO等の関係者全体が、情報と意見の相互交換を通じて問題や行為に対しての理解レベルを上げることを目的とするようになっている(第2-3-3図)。言い換えれば、受信者に対し発信者の意図した行動をとらせることではなく、受信者に利用可能な知識の範囲内で十分に情報が伝えられたと納得させることができれば、リスク・コミュニケーションが成功したと言える。
リスク・コミュニケーションの推進に当たっては、確率で表されるリスク概念自体の理解の促進に努めるとともに、リスク評価・管理の過程で随時情報が提供され、かつ、受信者からの情報がフィードバックされる双方向的な在り方が重要である。
イ 適切なリスク・コミュニケーションの実現のための各主体の役割
次に、適切なリスク・コミュニケーションを実現するための各主体の役割について考察する。
リスク情報発信者になることの多い事業者は、生活者を合意させるためではなく、生活者のリスクに対する理解を深めながら、リスクを削減する努力を行う役割を持つ。
リスク・コミュニケーションの基盤を支える行政は、情報源情報の整備や、リスクの概念、リスク・コミュニケーションの本質等の基礎的情報を整備、普及させる役割を持つ。
受信者である生活者は、これまでの公害問題であったような、企業対住民といった対立の図式から脱却し、環境リスクの正しい理解に努めるとともに、他の主体との対話を通じ、総体的なリスク管理に参加する役割を持つ。
マスメディア、NGO等は、行政、事業者と生活者をつなぐ第三者機関としての重要な役割を持つ。リスク情報の受信者である生活者は、多様な価値観、情報に対するニーズ等を持っており、行政、事業者から生活者に情報を直接伝えることにより、生活者のニーズをすべて満たすことは困難である。そこで、事業者等のリスク情報をわかりやすく翻訳して生活者に伝える伝達者(コミュニケーター)の役割をこれらの第三者機関が担うことが期待される。
その際、リスクメッセージは、
? 明確かつ簡明な言葉で表現すること
? 科学的不確実さがあれば、そのことを明記すること
? 受信者とその関心事を尊重すること、ただし、公正で均衡のとれた表現であること
が求められる。