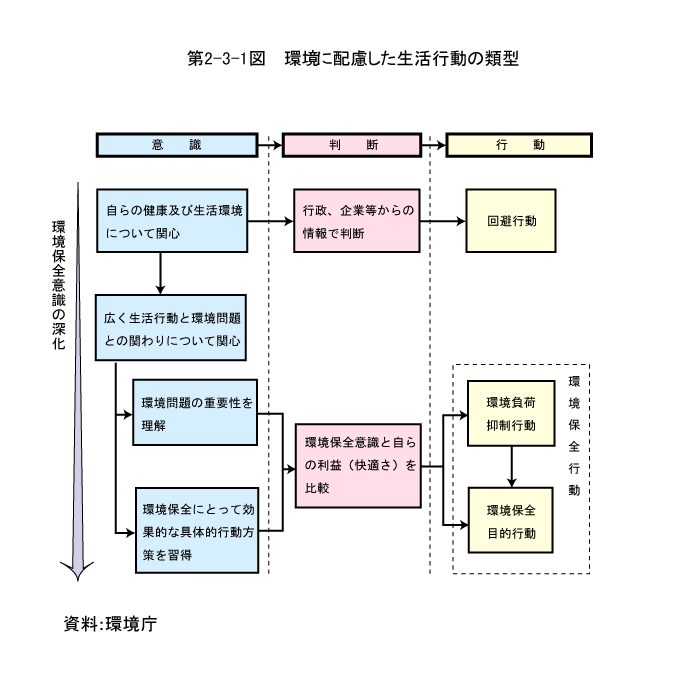
1 生活行動における環境配慮の分類
生活者は、自らの健康や生活環境について関心を持っており、環境を通じ人体や生活環境に有害な影響を及ぼすおそれ(環境リスク)があれば、それを避けるべく行動する(以下、「回避行動」と言う)。具体的には、公害を発生させるおそれのある工場の建設に対する住民の反対運動や、環境リスクの高い製品等の購入を避けること等が挙げられる。
また、生活排水の流入による河川の水質汚濁等の身近な都市・生活型公害、エネルギー消費に伴う二酸化炭素の排出量の増大等による地球温暖化問題などに見られるとおり、生活行動と環境問題には密接な因果関係があり、生活者は自ら行うことのできる様々な対策があることを認識すると、環境保全意識と、物質的な豊かさや生活の利便性・快適性とを比較衡量して、環境に配慮した様々な行動をとる(以下、環境保全意識の強い順に「環境保全目的行動」「環境負荷抑制行動」と言う。また、この2つの行動を合わせて「環境保全行動」と言う)。
このように、生活者の誰もが自らの生命や健康を守ろうとするいわば「自己防衛」意識により、即座に回避行動を起こすことはもとより、自らが生み出す環境への負荷に対する反省や地域又は地球レベルでの環境配慮意識が高まることで、これが環境保全行動として反映される(第2-3-1図)。
しかし、生活者は、得られる情報が限られていることなどにより冷静に行動できないこともある。また、環境への負荷に伴い社会に生じる費用が市場メカニズムの中に適切に織り込まれていないなど、生活者に対して、環境への負荷を削減しようとするインセンティブを欠き、具体的な行動につながらない場合もある。行政の役割は、こうした環境に配慮した生活行動への様々な阻害要因を排除し、社会システムを環境保全に適したものにしていくことであろう。
次に、上に挙げた生活行動ごとに、その性質や阻害要因、行政等が行いうる対策について具体的に考察したい。