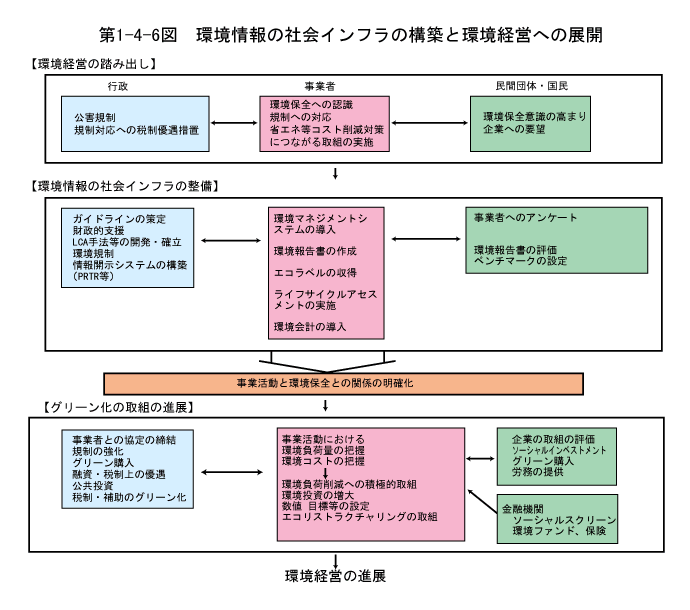
2 環境保全の内在化を進めるために
1で提示した環境保全型の経済社会の将来像を目指し、経済活動の中に環境保全の視点を着実に組み込んでいくためにどのような取組が必要か、ここではその方向性について考察したい。
(1) 環境効率性を高める企業行動の推進
事業者の環境経営は、第2節で述べたとおり行政による公害規制の対応や、省エネ・省資源等生産コストの削減対策につながる取組から始められることが多い。これらの取組の背景には、地域住民による環境保全意識の高まりに伴う地域への配慮もあろう。
これを一歩進めて環境保全を内在化していくためには、それぞれの企業が事業活動によって生じる環境負荷を把握するとともに、企業経営の中に環境配慮を確実に織り込み、環境効率性を高める必要がある。
以下で説明する「ライフサイクルアセスメント」「環境マネジメントシステム」「環境報告書」「環境会計」「環境ラベル」等の取組は、事業活動と環境保全との関係を明らかにするための「環境情報の社会インフラ」を整備するものと言える。このほかにも、第2章で述べる環境リスクを管理するためのPRTR制度などが含まれる。
すなわち、これらの取組により事業活動における環境保全の内在化が進むだけでなく、一方で国民にとっては、製品やサービスを購入する時や、企業に対して投資を行ったりする際の環境に係る基礎情報を提供するものになりうる。他方で行政にとっては、事業者との協定締結を始め、グリーン化促進のための技術支援や融資、補助金等の財政上の支援措置等の導入の適否の判断、グリーン購入などの際の基礎的な情報を提供するものともなる。さらに、金融機関にとっても、適切な融資、投資を行う際に必要な企業情報としても用いることができよう。
ア ライフサイクルアセスメント
ライフサイクルアセスメント(LCA)とは、その製品に関わる原料の採取から製造、輸送、使用、廃棄、などすべての段階を通して、投入資源や排出環境負荷やそれらによる地球や生態系への環境影響を定量的、客観的に評価する手法である。
このLCAは、企業においては、リサイクル設計、プロセス改善や環境への負荷の少ない製品の開発、また消費活動においては、より環境への負荷の少ない製品の選択が可能となるなど多様な用途に適用することができる。また、環境ラベルの実践や環境家計簿の評価基準などとして、LCAの考え方を適用する方向でも検討が進められている。
現在、LCA実施に必要なデータベースの整備やデータ収集が簡易なLCA手法の検討、環境影響項目間の統合的評価手法の確立、などの検討が進められている。
イ 環境マネジメントシステム
事業者が、環境に関する方針などを自ら設定し、これらの達成に向けて取り組んでいくことを環境マネジメントといい、このための工場や事業所内の体制、手続きなどを環境マネジメントシステムという。環境マネジメントシステムの構築に取り組むことで、環境負荷排出量の削減をはじめ、従業員の環境保全に対する意識が高まり、積極的な環境保全活動が推進されるなど、様々なメリットがもたらされる。
我が国ではISO14001に関する適合性評価制度として、審査登録制度が確立されており平成11年3月現在、我が国でISO14001規格を審査登録している事業所等は1,960件となっており、その数は年々増加している。
ウ 環境報告書
環境報告書とは、事業者が事業活動に伴って発生させる環境に対する影響の程度やその影響を削減するための自主的な取組をまとめて公表するものである。記載内容としては、環境に関する経営方針、組織体制など環境マネジメントシステムに関わる内容や二酸化炭素や有害化学物質等の環境負荷物質の排出状況や環境負荷の低減に向けた取組の内容などがある。
囲み1-4-1 環境保全コストの把握及び公表に関するガイドライン
1) このガイドライン案は環境報告書による公表を想定したもの。
2) 「環境保全コスト」とは、環境保全のための投資額と当期費用。
3) 環境規制遵守又は環境負荷低減のためにのみに支出されたコスト全額、その他のコストは通常コストとの差額集計等が原則。
4) 環境保全コストに対応する取組内容、改善効果、環境負荷データ等が環境報告書に記載されることが理想。
5) 環境保全コストの分類は以下のとおり。
? 環境負荷低減に直接的に要したコスト(公害防止施設等)
? 環境負荷低減に間接的に要したコスト(環境マネジメント等)
? 生産、販売した製品等の使用・廃棄に伴う環境負荷低減のためのコスト(リサイクル、回収、再商品化等)
? 環境負荷低減のための研究開発コスト(環境R&Dコスト)
? 環境負荷低減のための社会的取組に関するコスト(事業所及び周辺の環境改善対策等)
? その他環境保全に関連したコスト
6) 環境保全コストの上記分類に該当する具体的なコストの当てはめ方について詳しく記載し、環境報告書における記載方法についても留意点を付記。
7) また、事業者の実状に即した利用ができるよう、段階的取組や勘定料の取捨選択、追加を容認しているのが特徴。
8) 環境報告書による公表を前提とした、モデル集計表を2種類添付。
エ 環境会計
企業が環境保全活動を行う上で、その費用がどのくらいかかるのかを把握することは非常に重要である。費用の適切な把握により、効率的な環境保全活動を行うことが可能となる。環境会計は環境管理における目標実行に伴う支出額の管理などに利用されており、自主的な環境保全活動を行うための内部管理ツールとして大きな役割を果たすと考えられる。
また、環境報告書の中で環境保全活動の費用についての記述が行われているようになってきており、環境会計には、外部の利害関係者に対する情報提供の役割もある。
また、環境報告書の中で環境保全活動の費用についての記述が行われているようになってきており、環境会計には、外部の利害関係者に対する情報提供といういわば財務会的な役割もある。
環境庁においては、企業が環境報告書等を用いて環境保全コストの公表を行うに当たり、集計すべき項目、集計に当たっての方法等を中間的にとりまとめた「環境保全コストの把握及び公表に関するガイドライン(中間とりまとめ)」を平成11年3月に公表したところである。
オ 環境ラベル
多くの製品の中で何が環境への負荷が少ないのか、具体的にどのような環境負荷があるのかといった情報を提供する手段として環境ラベルがある。これについては第2章で詳しく述べることとする。
カ 企業の取組を進めるための行政の役割
以上のような企業の取組を進めるための行政の役割は、手法の開発、ガイドラインの作成、統一規格の設定、環境情報の開示システム等を整備することに加え、その活用普及を助長する仕組みを構築すること、すなわち、環境情報の社会インフラの整備と適切な支援を行っていくことと言えよう。また、国民や民間団体では、事業活動における環境配慮の状況について、情報開示を求めるとともに、それを基にグリーン購入を進めていくこと等が重要である。最近は、民間団体により環境報告書のベンチマーク(環境報告書に盛り込むことがふさわしい事項)を設定したり、環境報告書の評価を行ったりすることにより、環境情報の社会インフラが一層機能するための活動もなされている。
このように、「環境情報の社会インフラ」を行政、事業者、国民のパートナーシップの下に構築することにより、事業活動と環境保全との関係を明確化し、企業の事業活動における環境配慮が相乗的に進むことが望ましい。すなわち、環境情報の社会インフラの整備により、行政による技術的・財政的支援やグリーン購入が進むとともに(2)に述べるような国民の経済行動が進むことにより、グリーン化が進展していき、企業経営と環境保全とが融合した「環境経営」へと発展していくことが期待される。こうした展開シナリオの1つを、モデル的に整理すると第1-4-6図のようになろう。
(2) 環境合理性に基づく経済行動の推進
経済主体としての国民は、産業活動によって提供される製品・サービスを購入する消費者として、また産業活動への資金を提供する投資家として、さらに産業活動への労働力を提供する労働者として、持続可能な産業活動を支えるために重要な役割を担っている。それぞれの立場において、第2章でも述べるとおり、環境合理性(環境価値を重視した行動規準)に基づいた経済行動が実践されることにより、経済社会自体が環境保全を内在化したものに徐々に変わっていこう。
ア 環境に配慮した消費者として
製品・サービスの需要者である国民の選択が生産活動に大きな影響を与える。製品・サービスを購入する際に必要性をよく考え、価格や品質だけでなく、環境負荷ができるだけ少ないものを優先的に購入することをグリーン購入と呼んでおり、そのような行動を通じて産業活動における環境保全の取組を支援する消費者の役割が期待されよう。
グリーン購入を支える消費者を増やすための活動はNGOを中心に進んでおり、平成9年に全国レベルのグリーン購入のネットワークが形成され、「環境にやさしい買い物ガイド」等の作成や環境報告書を作成している事業者に事業活動における環境配慮の有無を問うアンケートの実施等が行われている。グリーン購入の考え方も時代の流れにより変わってきており、製品の環境負荷という観点から事業活動全体における環境配慮にまで視野が当てられるようになってきている。
また、近年の健康ブームによる有機農産物の人気の向上は、健康への配慮と環境保全とを同時に満たすものとして、農業のグリーン化を促進するものとなっている。近年の多種多様な食品を求めるグルメ志向や消費者の農産物の見栄えを重視する姿勢等が、生産者側にビニールハウスでの生産や農薬の多用等を間接的に助長している状況にあると言える。こうした流れを変え、環境保全型農業を促進する食のグリーン購入を支える消費者が増加することが求められている。
イ 環境に配慮した投資家として
金融は経済活動の中で重要な役割を果たしており、企業への資金調達等を通じて環境に大きな影響を及ぼし得ることは、第2節で述べたとおりである。このため、国民による株や債権の購入や金融機関への預貯金は、間接的に事業者活動への影響力を持っていると言え、金融機関の融資先への関心や環境保全型の金融商品に積極的な関心を持つ人々が増加することも、資金の流れのグリーン化を促すために重要である。事業者の環境配慮を進めることを株主行動として促すという取組も海外では行われている。経済同友会が平成10年に実施した企業経営者に対するアンケートにおいては、株主や投資家が企業を選ぶ際、企業の環境対応を評価基準にすることについて75.4%の経営者が10年後には一般的になると回答しているのが注目される。
ウ 環境に配慮した労働者として
国民の労働者としての役割は、消費者としての役割と同様に非常に重要なものである。すなわち、職業を選択する際に、当該職業の遂行と環境保全との関係を配慮する労働者の存在も持続可能な産業活動を促すという意味で重要である。事業活動を進めるに当たっては、当該事業者の活動を支える労働力が必要不可欠であるが、当該事業者における環境配慮を事業者選択の基準の1つとすることにより、間接的に事業活動の環境配慮を促すことができよう。
例えば、職業選択の際に環境保全のことを考える学生等は近年増加している。大学の環境保全に関わるサークル活動のネットワーク組織であるエコリーグでは、行政、事業者、農業、NGO等で環境保全を考えながら働いている社会人をカウンセラーとして招き、環境保全に関心のある大学生の就職相談を行う「環境に配慮した就職相談会」を毎年2回程度、東京と大阪で開催している。学生の関心の高まりに伴い、年々開催回数と場所を増加させているという。
囲み1-4-2 自給自足のライフスタイルを実現する自然農
近年、援農や市民農園等様々な形で農に親しむ人々が増えてきている。その中で、自給自足のライフスタイルを目指して自然農を始める人も出てきている。
自然農は自然生態系を最大限活かして、人間の介入を最小限に抑えて行われる農である。これは土を耕さないこと、田畑の中で一体の営みをしているすべての生命を田畑の中で生死にめぐらすこと等により農地における豊かな自然生態系を回復維持させながら、農作物を生産するものである。つまり、「不耕起」を基本として無農薬、無肥料で行われ、また草や虫を敵とせず無除草で行われる場合もある。
これは、人間の労働を自然循環の営みの中に組み込んでいくことにより、自然環境との共生を図った永続可能で自立したライフスタイルを実現するものとして注目できよう。
エ 環境NGO等における取組
産業活動における環境保全の取組の推進のためには、事業活動をモニタリングし、環境保全的な取組を促していく環境NGO等の取組も重要な役割を果たしている。こうした取組を評価し、環境NGO等からの合理的な改善要望については、真摯に対応することが企業経営のために重要だと考える事業者サイドの動きも見られる。
環境NGO等の活動としては、環境に深刻な影響を与える製品の不買運動や環境保全型の製品を積極的に購入する消費者としての活動の推進に加え、企業の環境情報の開示の要求、環境報告書の評価、解釈等により事業者の環境に係る情報をわかりやすい形で投資家や国民に伝える等の活動が行われている。さらに、アメリカのセリーズのように事業活動における環境配慮に係る協定を締結したり、スウェーデンのナチュラル・ステップのように企業の経営者層への環境教育を行っている団体もある。我が国においても、企業関係者も交えたネットワークをつくり、ISOの取得や環境報告書の作成を促すための研究会を開催している団体もあり、こうした方向での環境NGO等による取組の進展が期待されている。
(3) 地域主導による環境保全と地域経済の融合
環境保全に関する活動の大半は地域レベルで行われており、経済社会に環境保全を内在化していく基礎は地域社会に置かれ、その取組は地域主導で行われることが望ましい。これまでの公害防止における地方公共団体や地元企業、地域住民の取組経験、そこに存する多様な自然環境との共存の歴史などにより、有用な人材、技術、ノウハウが地域には相当に蓄積されていると言える。こうした財産を活かしつつ、地域経済の振興を図ると同時に着実に環境配慮を織り込んでいくため、資源や産業基盤など地域の特性に適合した取組が重要であり、地域主導により画一的でない個性豊かなものが生まれる可能性を秘めている。地方分権の進展に伴い、環境保全と融合し、バランスのとれた地域経済を実現するためには、それを計画的にリードする地方公共団体、特に市町村の役割が重要になってこよう。一方で国は、地方行政との連携を強めながら、そうした取組に活用できる多様な支援方策を用意していく役割が求められよう。
第3節で述べてきたとおり、例えば、自然との共生や持続可能な地域づくりに関する多様で自由な発想を活かし、情報発信や人的交流による経済波及効果も期待できる地域発の事業活動とか、健全な生態系の維持という観点から自然環境や地域資源をその自浄能力や再生能力の範囲内で有効活用を図る、地域特産のエコ資源を活用する事業活動とか、より環境効率的な物質循環を進めるという観点から一定の地域というまとまりの中で環境負荷の少ない物質循環を促す事業活動など新しい取組が生まれ、環境保全の融合した地域経済の実現につながることが期待される。
(4) 環境投資の積極的な推進
先行的な環境投資は、環境保全の推進の動きに弾みをつけ、経済社会の活性化につながりうるものとして重要である。
ア 環境保全型の経済社会に関するビジョンの提示
今日の環境問題は通常の事業活動や人々の日常生活に起因しているものが多く、その根本的な解決には、源に立ち返った対応が必要である。このため、事業者を始め各主体が明確な目的意識をもって環境保全への取組できるよう、政策主体が経済社会の目指すべき方向を明らかにしていかなければならない。
こうした意味で、環境基本法に基づき総合的かつ計画的な環境政策の推進のため、平成6年12月に閣議決定された環境基本計画が果たすべき役割はますます重要である。同計画では、長期的な4つの目標として「環境への負荷の少ない循環を基調とした経済社会」「人間と自然との共生」「公平な役割分担の下ですべての主体の参加による環境保全の具体的取組を展開すること」「国際的取組を積極的に推進すること」が掲げられているが、今後は事業活動を念頭に置いてこれらを一層具体化した社会経済の全体像(ビジョン)を提示することが必要である。
これに関連する産業政策のビジョンとしては、1の(3)で触れた経済構造の変革と創造のための行動計画や産業再生計画、平成6年7月の産業構造審議会による産業環境ビジョンなどが挙げられる。
イ 環境関連分野への民間投資の誘導
(1)で述べた産業活動のグリーン化の推進に加え、来たるべき環境保全型の経済社会にふさわしい方向で、産業構造が変化していくことが必要であり、環境関連分野への積極的な民間投資に期待するところが大きい。このため、将来を見据えた環境保全上の重点分野において、ベンチャービジネスによる創業の動きや、意欲のある既存企業が、自らの持つ経営資源を活用して事業部門を強化していく動きを積極的に支援していくことが必要である。
エコビジネスの推進やグリーン化の推進に当たっては、民間事業者の創造力や活力を最大限に引き出すことを原則として、行政は適時適度の関与にとどめ、自立的な発展が可能となった段階では過度の介入は慎むべきである。こうした観点から、事業主体の生い立ちや、揺籃期、市場形成期、成熟期という発展段階に応じ、適時適切な形で新規事業創出、技術開発、設備投資等に係る融資、債務保証等の措置を講じていくことが必要である。さらに、行政機関によるグリーン購入や緑化事業等の環境保全型公共事業や公共事業実施の際の企業の環境配慮の条件付け等行政機関の事業活動のグリーン化を行っていくことも産業活動における環境保全の内在化を進めていく上で、非常に有効である。
こうした民間事業者の活動を支える公的主体による社会資本投資は、環境保全上の支障を防止し、民間による環境投資とあいまって環境保全の推進に資する基盤整備の役割を担うべきであろう。
また、第2節で述べた民間の金融機関による環境投資も非常に重要な役割を果たしうる。
ウ 創造的な環境研究・技術の振興
環境保全に関する調査研究や技術開発は、経済社会に対し科学的知見や技術的基盤を提供するものであり、民間の事業活動に変革を促すものとして期待される。また、我が国が環境分野で国際的貢献をしていくためには、これまでの公害経験や得意分野を活かした創造的、先導的な環境研究・技術の成果を世界に向けて発信することが求められる。
環境保全に関わる調査研究や技術開発が必要とされる分野は、極めて多岐にわたる。例えば、将来的に枯渇することが予想される地下資源やエネルギーの利用の効率化を図るための「資源・省エネルギー技術」、資源生産性の向上と有害化学物質の排出抑制を図るための「環境低負荷型生産技術」、物質循環の円滑化と資源利用の効率化を図る「廃棄物処理・リサイクル技術」に加え、持続可能な経済社会を構築していた時代の伝統的な技術の現代的応用や自然のメカニズムを最大限に活かした技術等環境保全上有効な技術の一層の開発・普及を図る必要がある。これらの技術の振興に当たっては、事業活動への適合や経済的な波及効果を考慮すれば、できるだけ民間の技術開発能力の活用も図る方向で進められることが望ましい。
環境技術の振興に際しては、化学企業、化学工学会、工業技術院等との連携のもと行われている化学産業における革新的な省エネルギー・省資源化を図るための技術開発(次世代化学プロセス技術開発)のような産学官の連携を通じた研究開発プロジェクトや事業化に直結した技術開発等を推進するための支援措置を講ずるとともに、国立試験研究機関等を活用した基礎的・基盤的研究を推進していく必要がある。また、経済社会への円滑な適合を考慮し、機器、装置等のハードの技術のみならず、その効果的な使用方法等のソフトの技術も開発するよう心がけることが重要である。また、新しい環境技術等を適用した場合の環境保全上の効果、寄与等について適切な評価を行い、事業活動に活用する必要がある。
さらに、環境技術の振興を促す人材の育成も重要である。つまり環境保全のために必要な技術分野(ニーズ)と既存の技術の応用(シーズ)を結びつけ、より効果的な研究・開発を実行するための環境技術のコーディネーターの育成が急務であろう。例えば、未利用特許の活用を促す特許アドバイザーや知的所有権のコンサルタントのような異業種企業間の連携の触媒としての機能を果たす人材の育成を支援していくことが望ましい。
(5) 経済社会全般に及ぶグリーン化の推進
企業が環境効率性を向上させるための(1)で述べた環境情報のインフラ整備により、個々に環境効率性を向上させるために取り組むことに加え、経済社会のあらゆる部門に影響を及ぼしつつ、各主体の取組を包括的に助長するための効果的な政策手法を導入するなど、経済社会が自律的に環境保全の視点を組み込んでいく仕組みを重層的かつ多角的に構築・強化していく必要がある。ここでは、事業活動と環境政策との関係を中心に、行政の取組のあり方を欧米諸国の政策実例を踏まえながら考察したい。
ア 欧米諸国にみる政府の取組
オランダで検討されている環境効率を実現するための環境政策としては、規制政策、協定政策、誘導政策、自由政策の4形態の環境政策を提示している。(第1-4-7図)
さらに、OECDの環境政策委員会で承認された「Eco-efficiency」の報告書においては、環境効率を経済全般において推進する際の政府の役割として、次のような施策の方向性を示している。
○ 汚染の除去や資源の効率的利用を支援する補助金や税を改革することにより経済的インセンティブを首尾一貫させること
○ 環境被害の費用を価格、規制によって内部化すること
○ 環境効率性を高めることに資する土地利用計画、教育、技術革新等の政策を開発すること
○ 持続可能な開発の指標の一部として環境効率の指標を確立すること
○ 環境負荷物質の排出と資源利用を経済成長から切り離すための研究を進めること
○ 環境効率の向上を支援する政策についての情報交換を行うこと
○ 環境効率を向上するための政策やプログラムの環境と経済への影 響についての研究を進めること
また、アメリカでは、持続可能な発展に関する大統領諮問委員会では、以下の5つの政策原理を採用している。
○ 結果責任を伴う柔軟性の高い規制の導入
○ 製品責任の拡大
○ 市場原理の活用
○ 政府機関とのパートナーシップ
○ 環境技術の導入・促進
このように、環境政策を推進する政府の役割としては、自国の経済社会の状況や風土等を踏まえつつ、問題の特質に応じた手法を組み合わせながら総合的に施策を講じていくとともに、それを裏付ける政策原理の確立も重要であることが分かる。
イ 事業活動を念頭に置いた環境政策の展開
環境保全という視点を社会経済システムの中に内在化させていくためには、関係する多様な主体に効果的に働き掛ける様々な政策手法を重層的・多角的に組み合わせていくことが重要である。以下、環境政策を構成する政策手法の在り方について考察したい。
(ア) 規制的手法
環境汚染物質について排出基準を設定し、全ての事業者に遵守を求めるといった直接規制は、序章で述べたとおり従来から行政が用いてきた規制的手法であり、我が国において公害の防止に大きな貢献をしてきた歴史がある。また、環境に係る法規制の導入が間接的に環境保全に関わる新たな事業分野を創造したり、技術革新の契機となることもある。
一方で、従来型の事業活動を前提とした法律その他の制度が今後期待されるエコビジネス等の新規事業の成長を妨げている面がないか十分点検し、適切な制度改善を検討することも、規制的手法における課題である。
また法的な規制を補完するものとして「協定」という手段がある。例えばアメリカにおいては、環境保護庁(EPA)が複雑な環境規制を補完する観点から、コモン・センス・イニシアティブ(CSI)等の協定政策を進めている。コモン・センス・イニシアティブは現在のところ自動車製造業等の6つのパイロット産業が環境保全の取組に参加しており、複数の法律による重複した行政への報告義務の削除や、許可交付の過程の効率化、環境に係る意思決定における地域の関与の改善等を目指している。
我が国においては、公害防止に関し、地方公共団体と個別企業が公害防止協定を締結し、公害防止の観点から大きな貢献をした歴史がある。現在は、環境保全協定という形で、締結される事例が増加している。
環境保全上有効な技術や排出物に関する情報は事業者が把握している場合が多い。このような手段は、政府がそうした情報を集めたり、法制化したり、効果を監視したりするコストを省くことができ、事業者にとっても、手段の選択肢が広がる一方、裁量の余地が大きく、ルールに基づかないものとして問題が生じる場合がある。従って、事業者の取組がうまく作用し、信頼できるものとするために、事業者と行政が十分協議し、双方の期待と要求を枠組みとして明確にすることが欠かせない。
(イ) 経済的手法
経済的手法とは、環境汚染による外部費用を内部化するために市場メカニズムを活用し、各経済主体が環境保全に適合した行動をとるよう促す政策手法である。具体的には、税、課徴金、排出権取引、預託金払戻制度(デポジット・リファンド・システム)、補助金、政策融資等がある。
税について、諸外国の例をみると、フランスでは1999年(平成11年)税制改正により、環境負荷の高い石油製品に係る税の増税や、汚染活動一般税の創設などが行われている。また環境に係る税を拡大する一方で他税目ないし社会保険料の引下げを行った例として、所得税減税及び社会保険料の引下げと同時に行われた1996年のオランダにおける小口エネルギー消費者(一般家庭、小規模事業施設等)課税の導入例が挙げられる。その他ドイツでは、社会民主党と90年連合/緑の党が1998年(平成10年)に連立政府樹立にあたって連立協定を締結し、これを踏まえ本年4月よりガソリン、ガス、軽油にかかる鉱油税の引き上げと電気税の新設が行われ、さらに雇用者、被雇用者の社会保障負担分の軽減が行われている。
税制に関して、OECDは、1997年5月の理事会において「ENVIRONMENTALTAXES AND GREEN TAX REFORM」と題する報告書を採択している。この報告書は、?税制のグリーン化、?税収の使途、?雇用の「二重配当」、?インフレーション、?分配効果、?貿易と競争力について考察を行っており、「各国は各々特定の経済、財政、環境状況に従って税制のグリーン化の機会と可能性について検討すべきである」としている。ここで税制のグリーン化とは、税制の設計に当たって環境上の配慮を行うことを意味しており、具体的には
・ 環境に悪影響を与えるような税制上の措置を取り除くか、又は環境保護により適したものに再構築すること
・ 環境汚染物質等に対する環境に係る税を導入すること
により達成できるとされている。
またこの報告書では、「環境に係る税を含む経済的手法は、規制的手法よりも低いコストで環境政策の目標を達成する方法を提示し得るほか、汚染減少や技術革新に対する継続的なインセンティブを与え得る。」としている。
また、預託金払戻制度(デポジット・リファンド・システム)とは、製品取引又は販売時にデポジット金(預り金)を賦課し、製品が消費されて不要となった際にその使用済製品と引き替えにデポジット金を消費者に返却する仕組みをいう。我が国では、自主的にビール瓶や一升瓶でデポジットが行われているが、アメリカでは飲料容器(瓶、缶、ペットボトル)のデポジット制度が、スウェーデンでは廃自動車のデポジット制度が導入されている。
農業政策と環境政策が統合した補助制度の例として、EUの1992年(平成4年)5月の共同農業政策改革についての決定が注目される。ここでは、農業従事者に対する自然保護措置助成の可能性を含む「補助的措置」が認められた。これに基づき、EUの全加盟国が環境に適した生産方法のための助成計画を農業従事者に提供するよう義務づけた「環境に適し自然の生活圏を保護する農業生産方式促進のための指令EEC2078/92」が出された。この指令により農業従事者は、環境保全上の効果のある農業活動について助成を受けることになった。国内においても、持続的な生産方式を導入する農業者に対して、資金的な援助を進める法律案が現国会に提出されたり、高い環境保全機能を有する中山間地域における農業生産の直接所得保障制度の検討がなされている。
(ウ) 自主的取組を支える基盤整備
事業者における環境配慮の自主的取組を行政が最大限尊重するという政策は、環境政策の始まりであると同時に終わりでもある。こうした政策においては、(1)に述べた自主的な取組のためのツールの提供に加え、国内国外の事業者についての環境保全の取組の実施状況等を含め調査研究により得られた環境に関わる行政情報の提供・公開等の仕組みづくり、環境アセスメント(環境影響評価)の手法の普及などの基盤整備が重要であろう。
(6) 環境と経済の統合に向けて
第1章では、産業活動のグリーン化の方向性を論じることを通して環境と経済との統合の在り方の一つの形を論じた。また、経済のグローバル化とそれを補完する自立した地域経済の在り方や環境保全型の経済社会についての将来像について考察した。さらにこのような方向性に進んでいくための各主体の在り方とそれらの取組を推進すべき環境政策の役割について論じた。持続可能な経済社会を構築するためには、既存の経済社会システムや経済の考え方を延長したりするだけでなく、持続可能性を模索する世の中の動きも視野に入れ、今後の経済社会の在り方を大胆に考えていく視点、そして望ましい経済社会を能動的に作っていくために各主体が今何をなすべきか考えていく視点がむしろ重要であろう。