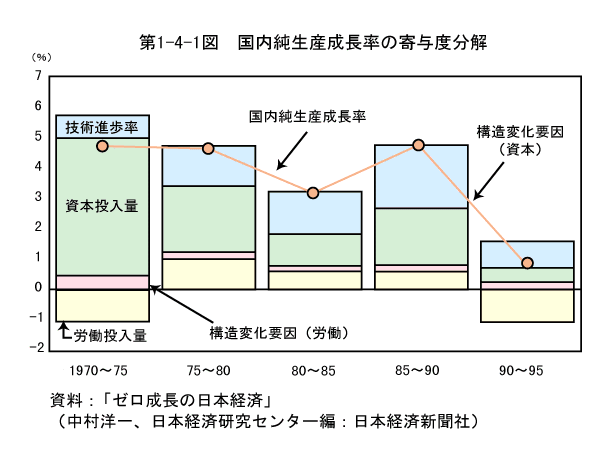
1 環境保全型の経済社会についての将来像
前節までに議論を今一度整理して、環境保全を内在化した経済社会はどのようなものであるべきか、以下では、その将来像を展望することとしたい。
(1) ストック活用型の経済社会への転換
戦後の日本は、GDP等の一定期間に新たに作り出される付加価値、すなわちフローを重視した大量生産、大量消費型の経済社会を構築してきた。この延長線上では資源の枯渇や環境負荷の増大が懸念されており、この現状を打破する今後の方向として、財貨の存在量を重視し、それを最大限活用して効用を得るストック活用型の経済社会へと移行していくことが重要である。新たな経済社会においては、量的な成長のためのフロー増大政策はとらず、大量生産からストックの修復、更新等を中心としたストック活用と最適生産による使用価値の創造へと移行することになろう。
国内の純生産成長率の寄与度の経年変化を見ると、成長率の寄与度に占める資本投入量が減少しており、一方で技術進歩率の寄与が大きくなってきている(第1-4-1図)。
また、産業資本ストックの資本生産性は低下の一途にあったが、日本経済研究センターの研究によれば、2005年(平成17年)以降向上し、ストックを有効活用する構造に変化していくことが予測されている(第1-4-2図)。このことから、日本経済がストック活用型の経済へと転換を図りつつあること、ストックの修復、更新による需要を中心に、新たな事業分野の進展やサービスの需要が加わり、全体としては安定した成長が維持できる可能性があることが分かる。
また、一人当たりの国民総生産と一人当たりのエネルギー消費量との関係を、時系列変化を国際比較してみよう(第1-4-3図)。カナダを除きいずれの国も右へシフトし、ドルベースでみても一定の経済成長をしている。日本の場合には、グラフの傾きが若干緩くなっていることから、エネルギー効率の向上が伺えるが、欧州主要国についても同様の傾向が見られ、特にドイツ、オランダ、イギリス等は、右下がり又は横ばいのグラフとなっている。このことから環境保全の内在化と経済成長は両立し得るものであることが分かる。
20世紀後半の日本は、モノの豊かさを存分に享受した経済社会であったが、来世紀においては、モノそのものによる豊かさにこだわるのではなく、モノが提供する機能やサービスの向上、知識、情報、人的交流等による豊かさを追究する経済社会への転換が求められるであろう。こうした経済社会においては、「モノ」の生産・流通も規模と範囲において最適化が図られることにより環境効率性を高めることが望まれる。
これまでの議論を踏まえると、ストック活用型の経済社会は、ある意味では資源・エネルギーの消費量と経済発展とを分離するところから始まるといえ、その基本的な要素は、以下のように整理できよう。
○ 資源生産性を大幅に高め、総投入物質量を削減すること
○ 経済活動において資源生産性をより重視していくこと
○ モノを所有することより、モノが提供する機能と、サービス等を重視すること
これら環境効率性を高める供給者サイドの取組により、環境負荷を削減し、地上資源を有効利用し、新たな地下資源の利用削減を図っていくことと同時に、需要者サイドの取組としては、2や第2章で述べるとおり生活の豊かさの価値基準をモノの所有そのものからサービス、機能の享受へと転換を図っていくことが重要であろう。
ストック活用型の経済社会における各経済主体の行動目標は、環境負荷をできるだけ抑制しながら、同時に生活の質を向上させることであり、具体的には以下のように整理できよう。
○ 消費する資源・エネルギーの量を削減しながら、同時に生活の質を維持又は向上させること
○ 製品の機能を高め、製品を上手く使い、モノの使用価値を重視すること(長寿命化、メンテナンス、機能拡張等)
○ 軽薄短小化、省エネを進め、資源やエネルギーの生産性を上げること
○ 物質収支における物質投入量と排出量の収支を最小化すること
○ 製品をサービスで置き換え脱物質化を図ること
(2) 相互にバランスと連携のとれた循環促進型の産業構造への移行
経済社会システムが環境保全を内在化するに伴い、産業構造自体も環境への負荷の少ない持続的発展が可能なものへと質的変化が求められる。ここでは、従来の第一次から第三次までの産業が、それぞれ持続可能性を高めていくとともに、相互にバランスをとりつつ連携を強め、全体として循環促進型の産業構造を形成していく方向を模索したい。
ア 第一次産業〜環境保全機能の維持・増進〜エコ資源の供給
農林水産業は、生産力の基礎を自然の物質循環の中に置いており、森林の適正な整備を通じて環境を維持・形成するなど環境を積極的に管理し、その適切な活動を通じて環境保全機能の維持増進を図る必要があろう。
また、農林水産業を通じた物質循環は、原理的には自然の力(太陽光と微生物の力)の範囲で、閉鎖系の循環を維持することができるため環境効率性が高いものとなっている。
林産物、農産物の有機系資源は、自然の力と人間の活動さえあれば持続的生産が可能で環境負荷の少ない資源(以下、「エコ資源」という)であり、再生産能力の範囲内で製造業の原材料への有効活用が期待される。これらのエコ資源にふさわしい利用用途の開発を進め、第二次産業で利用されている鉱物・金属等枯渇性資源の代替品としての可能性を追求すべきである。このように、第一次産業は食糧供給源としての主要な役割に加え、第二次産業に対してエコ資源を供給する産業として発展すると同時に、それを利用する側の第二次産業におけるグリーン化の促進にもつながることが期待される。
イ 第二次産業〜環境効率性の追求〜リサイクルの循環回路
第二次産業は日本の産業の基幹的部分であり、多くは鉱物系資源を加工し、付加価値を付け、製品を製造することを中心的な役割として担ってきていた。今後は、環境効率性を高める観点から次のような新たな役割を果たすことにより、環境負荷の低減や資源効率性の向上に積極的に貢献することが求められよう。
第1に、家電業界にその動きが見られるような、自社や業界の使用済み製品の回収ルートを確保し、再使用やリサイクルをしたり、リサイクル・マイン・パーク構想の考え方に見られるような、既存の鉱業技術を活用して製品に使われている金属資源を再資源化するなどの役割も期待される。ここでは、製品の回収ルートの確保などの面において、第三次産業との連携が図られていく必要がある。
第2に、前述のエコ資源を原材料として適切な活用を図るという、第一次産業からの供給資源の受け手としての役割がある。鉱物資源の乏しい我が国において第二次産業の原材料は、外国からの輸入にほとんど頼っている。枯渇性資源から持続的な再生可能資源へと利用の転換を図っていくことは、輸入相手国の環境保全の観点だけでなく、国内の第一次産業の活性化のためにも非常に重要である。
ウ 第三次産業〜ストック活用の媒体〜非物質系循環の推進
第三次産業の主な役割の1つとして、第二次産業において製造された製品を消費者に販売することがあった。環境制約の下では、個々人が同じものを所有する発想から、複数の人が同じものを共有することで、必要な人が必要な時だけ利用する共有の発想が重要である。その導入の際には、製品の利用マナー、円滑なメンテナンスの実施、管理責任の所在の明確化など解決すべき課題は多い。これは、製品の「所有権」の販売・購入の形態から、利用者サイドからは必要な時だけ利用する「使用権」の獲得、事業者サイドからは「資産管理」へと社会システムを移行することが重要であることを示すと同時に、これを支える当事者の意識改革や契約体系の整備などストック活用型の経済社会の枠組みづくりが進むことが期待される。
地域を基礎に持続的発展が可能な経済社会が形成されるためには、健全な物質循環の輪をつなげることを、さらにそれを支える「マネー」「情報」等の循環が非常に重要となってくる。そこで、モノの移動やマネーや情報の循環を担う第三次産業は、健全な物質循環を支え、新たな付加価値を生み出すものとして、環境保全型の経済社会への移行を推進する機能が期待される。(第1-4-4図)
(3) エコビジネス(環境関連産業)発展への期待
近年、リサイクル装置・技術や低公害車、多様な環境配慮型製品などを提供するエコビジネス(環境関連産業)がにわかに注目を浴びている。エコビジネスは、環境保全への取組の積極性や事業内容からみて産業活動の変革の推進力となり、あるいは市場メカニズムを通し人々の消費活動の変化に影響を及ぼすことにより、環境への負荷の少ない持続可能な経済社会を形成するために大きく寄与しうる存在である。エコビジネスは、環境基本計画においても位置づけられているとおり、環境政策の上からもその発展が期待されている。すなわち、我々は地球規模において様々な環境制約に直面しているが、これを契機に量的拡大を追求してきた大量生産・大量消費・大量廃業型の経済構造から脱却を図り、積極的に環境と経済の統合を成し遂げることで、エコビジネスの発展という新たな可能性が生まれると言えよう。「経済構造の変革と創造のための行動計画」(平成9年5月閣僚決定)においては、環境関連分野が今後成長が期待される15分野のうちの1つと位置づけられ、日本経済の発展や変革の大きな原動力となりうると期待されている。同行動計画の第2回フォローアップでは、今後の発展に向けた課題の解決のため、行政としての役割としては、以下の具体的な施策により基盤整備を行うことが重要であるとしている。
? 地球温暖化への対応
? リサイクル施設・廃棄物処理施設等の整備や廃棄物の広域処理の促進といった循環型経済社会システムの整備
? 環境への負荷の低減に資する環境関連技術の開発・普及の促進
? 事業者・消費者の環境マインドの醸成やこれをリードする人材の育成
? 事業者の環境配慮を促す制度等の構築改善
? 環境関連産業の創業利益水準を確保するに足る市場の創造
? 途上国への環境協力の促進
また、「産業再生計画」(平成11年1月閣僚決定)においても、環境関連分野に関する施策を含む「新規産業創出環境整備プログラム」を加速的に推進することが必要であるとしている。
エコビジネスの原動力を産業活動全体へ波及させることにより、環境配慮型への産業構造の変革や企業活動における環境配慮の高度化、すなわちグリーン化を推進していくことが必要である。また、環境配慮がグローバルスタンダード化しつつある中、それが我が国の産業の国際競争力の強化につながることが期待できる。今後、環境制約に挑戦するエコビジネスの活躍する領域が飛躍的に拡大することが予想される。(第1-4-5図)
(4) 新たな経済主体としての「協」的セクターへの期待
現在の経済社会を構成する主体として、市場メカニズム(自由・競争)を基礎にした「私」的経済セクター(民間事業者)と計画メカニズム(統制・管理)を基礎にした「公」的経済セクター(行政)に加え、協同的メカニズム(自治・参加)を基にした「協」的経済セクターが存在していると考えられる。「協」的経済セクターとしては、2節の4で紹介した協同組合、市民事業に加え、NGO、ボランティア等が挙げられる。
欧米では、上記の「協」的経済セクターが影響力を持つようになっており、非営利経済部門の活動が盛んになってきている。「協」的経済セクターの一般的な活動原則としては、利潤追求でなく、組合員又はその集団へのサービスを究極目標とし、管理の独立と民主的な決定手続き、利益配分においては資本に対して労働を優先すること等が挙げられる。つまり、生活者・市民が自らの問題解決のための活動を個人の持つ資源(マネー、知恵、労働力、時間)を総動員する参加型システムにより生みだそうとするものである。
「協」的経済セクターを代表する協同組合活動は、共通の目的を持つ人々が、自発的に集まり、事業を手段として、構成員によって目的追求のために運営される事業であり、貧困、失業、環境問題等の産業社会の矛盾の解決を目指して、19世紀半ばから発展してきたといえる。1972年(昭和47年)の国連人間環境会議や1987年(昭和62年)の環境と開発に関する世界委員会を始めとする国際会議等では、人間と共同体が自然に対し責任を持つことの必要性が議論されてきた。このような人間と共同体が自然に対し責任を持つ経済主体として今後の働きが注目されるのが、家族、地域共同体、協同組合、NGO、ボランティア等の「協」的セクターといえよう。
(5) 環境保全と両立しうる「経済性」からの新たなアプローチ
産業活動においては、経済性の追求が必要不可欠であり、高度成長期から現在に至るまで「規模の経済性」の飽くなき追求によりめざましい経済発展が達成されてきたが、これと並んで環境保全と両立しうる「経済性」からの新たなアプローチが注目されている。
ア 範囲の経済性
近年の多品種少量生産を求める消費動向に呼応しつつ、企業内・組織内の資源である共通生産要素(生産設備、販売ルート、投資、ノウハウ)を統合活用してコストを引き下げ、利益を上げることを目指す「範囲の経済性」を求める取組も広がってきている。
イ 連結の経済性
互いの得意分野を強化したり、不十分な点を補完したりすることにより、相乗効果を生み、利益を上げることを目指す「連結の経済性」も最近注目されている。ゼロエミッションやインバース・マニュファクチュアリングの取組や第2節で紹介した地域内資源循環の取組は、この連結の経済性を追求するものとも言えよう。
ウ 合意の経済性
共通した概念や当事者間の合意に基づいて行われる取引から利益を上げる「合意と関係の経済性」を追求する取組も始まっている。例えば、第1節で紹介した食のグリーン化における顔と顔の見える関係を重視する産直宅配、第2節で紹介した相互扶助の精神を掲げる協同組合やNGO等による市民事業等があげられよう。
新しいこれらのアプローチは、大量生産から脱却した最適生産のシステムの転換を図っていくという観点から今後の応用が望まれよう。また、これらはそれぞれ独立に追求されるものではなく、相互補完的なアプローチとして用いることができよう。例えば、有機農産物の流通は合意の経済性から始まり、市場規模が大きくなるに従って、範囲や連結の経済性を活用するようになってきていると言えよう。
今までの議論を踏まえ、20世紀の経済社会と環境保全型の経済社会像との違いを経済社会の特徴を示すキーワードをもとに以下のように整理できよう。(第1-4-1表)