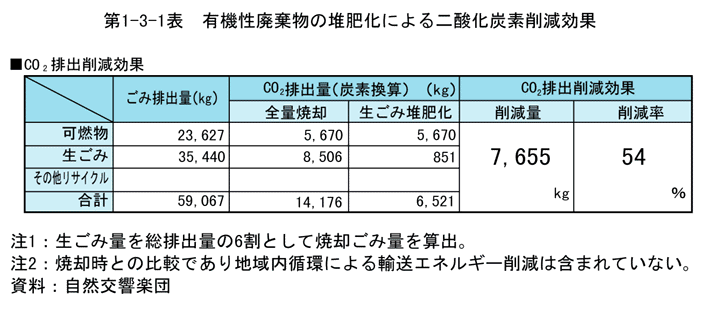
2 地域経済を形成する産業活動の在り方〜地域内資源活用の取組
ここでは、1で触れた状況を踏まえ、地域固有の環境問題へ対応しながら地域経済の活性化を図っていく、産業活動の在り方について論じたい。
市町村の周辺地域に産業廃棄物処理施設が様々な経緯で林立し、ダイオキシンによる環境汚染問題を引き起こし、地元の農産物への影響が懸念された事例があった。これは地域経済の中に適切な形で位置付けられていない産業活動が、環境保全上の問題で地場産業と軋轢を生んだ悪例と見ることもできる。言い換えれば、地域経済と環境保全の融合を目指していく上で、地域経済を形成する産業活動の在り方を論ずることが重要であることを物語っていると言えよう。
以下では、地域内資源活用を基調とする具体的な事例を紹介することを通じて、地域経済の安定性、地域住民の社会参加、地域振興における効果に加え、環境保全上の意義に注目しつつ考察することとする。
(1) 有機系資源循環を目指す取組 〜自然交響楽団の事例〜
茨城県の筑波地方において、地域のスーパー等で生じた有機性廃棄物を農家に使いやすい形で堆肥化し、地域の有機農業で生産された野菜等を地域内で流通、販売する「地産地消」により地域内資源循環を目指す取組が平成10年から開始された。これは、農家、農協、流通、運輸、プラントメーカー等による共同出資の事業体である自然交響楽団が行っているものである。これは、輸送エネルギーの削減、未利用資源の有効活用と有機農業の推進という点で環境効率性の高い取組であるとともに、地場の新鮮で安全な食品を提供することにより豊かな食生活を実現しうるものとして今後の発展が期待される。有機性廃棄物の堆肥化による環境保全効果は第1-3-1表のとおりとなっている。さらに有機性廃棄物の排出者や堆肥を購入する農家にとって、コスト削減につながるものとなっている(第1-3-1図)。この取組の成功のポイントは、農家を中心とした様々な主体の連携、地域内資源循環へのこだわり、農家にとって利用しやすい肥料の開発と関係者のコスト上のメリット等が挙げられよう。
(2) 地場産材を活かした地域づくりへの取組〜熊本県小国町の例〜
小国町は、阿蘇山の北山麓に広がる森林の町で、「小国スギ」で有名な林業の町である。昭和60年から豊富な森林資源を町の産業と地域の活性化や環境保全とを結びつけることを目指して「小国未来21・悠木の里づくり」をスタートさせた。小国スギの評価を高め地域内で活用することにより森林資源の維持保全を行うことを目的として、新鋭の建築デザインを開発し、大屋根建築物の「小国ドーム」、学習と交流の拠点「学び舎の里・木魂館」等により、小国町は一躍注目を集めるようになった。外部の情報と技術と人の誘致により、住民の意識を高め、地域資源を活用した産品の開発や農産物の地域内循環等を進め、「コミュニティプラン」作りと「草の根自治」等の住民主体の地域づくりが実践されている(第1-3-2図)。
(3) 地域における資源循環型システムの構築を目指すエコタウン事業
地域における資源循環型システムの構築に当たっては、その主要な担い手となるリサイクル産業を始めとした環境関連産業の創出が鍵となるが、そのためには地域住民・地方公共団体と事業者との密接な連携による地域ぐるみでの取組が有効である。このような、個々の地域におけるこれまでの産業集積を活かした環境産業の創出による地域振興とリサイクル及び廃棄物の適正処理の推進による地域におけるゼロエミッションの実現に向けた取組をソフト・ハード両面で支援するエコタウン事業が通商産業省と厚生省との連携により実施されている。
現在福岡県北九州市、札幌市等7地域の推進計画が承認され、これらの地域でそれぞれの地域特性を踏まえつつ一般廃棄物の収集・処理との連携や産業集積の活用を図りながら、ペットボトルリサイクル施設や廃プラスティックリサイクル施設、廃自動車リサイクル施設、エコセメント製造施設などの整備が進展しており、地域における新たなリサイクル産業が芽吹きつつある。
(4) 地上資源の循環を目指すリサイクル・マイン・パーク構想
日本の非鉄金属自給率は年々減少しており、平成5年度の自給率は0.3%になっている。このような海外鉱石への大きな依存と調達力の脆弱性、や廃棄物処分場の逼迫状況をみると、地上資源のリサイクル等による有効利用が持続可能な経済活動のために必要不可欠である。平成5年に提唱されたリサイクル・マイン・パーク構想(RMP)は鉱山や精錬所が有する施設、技術、ノウハウの積極的な活用を図り、廃棄物の徹底した再資源化、無害化、減量化等のリサイクル事業を推進すると同時に、回収エネルギーを地域に供給しようとするものである。これにより地域コミュニティとの調和を図りつつ、金属資源の循環利用と環境保全に資する構想であり、平成7年から具体的な調査検討が行われている。鉛亜鉛鉱山により栄えてきた町である宮城県の鶯沢町では、鉱山閉山後衰退、過疎化の一途にあったが、鉱山の町として蓄積された技術や歴史的資産を活かし、観光坑道の開発事業に取り組んでおり、平成2年には「細倉マインパーク」を開設し観光の町への転換を図っている。鶯沢町では、地域産業の活性化の拠点として、また再資源化施設を一般に公開することによる新たな観光資源としてRMP事業を展開することを検討している。
(5) 地域連携による取組〜天竜川の流域ネットワーク
天竜川流域においては、循環型社会の構築を目指す「伊那リサイクルシステム研究会」による、経営と環境を同一の視点で捕らえた活動が10年余にわたり進められている。この研究会は、動脈・静脈産業を含む異業種企業で構成されており、ノウハウの交換や小冊子の発行、また、地域企業への廃棄物処理に関するアンケート調査や、これに基づく廃プラスチックの共同回収などのシステムづくり、生産リードタイム短縮・在庫削減が資源の有効活用や廃棄物削減等につながることから、生産ラインの短縮、分業システム(単能工)から統合システム(多能工)へ、見込み生産から受注生産への転換など環境効率性の高い生産システムの構築が進められている。また、天竜川水系を地域連携のキーワードにし、河川のゴミ拾いや天竜川及び支川の24時間連続水質調査を、諏訪湖近隣市町村の住民(住民、旅館、学者)を中心とした環境保全の取組を実践している「諏訪環境まちづくり懇談会」と共同で企画し、浜松地域の企業・団体の協力を得て実施するなど、地域ぐるみの環境保全活動を展開、さらに最近では、天竜川河口でウミガメ等の自然保護活動を行っているサンクチュアリ・ジャパンとの交流活動も行うなどその輪を広げている。
一方、天竜川流域の村である阿智村では管理型処分場の建設が計画されており、住民等による自主的な活動として「社会環境アセスメント」が行われている。この中で住民の勉強会の一つとして研究会参加企業の廃棄物に対する取組の視察等も実施している。
諏訪環境まちづくり懇談会、伊那リサイクルシステム研究会、阿智村での社会環境アセスメント委員会、サンクチュアリ・ジャパンはそれぞれ全く別の組織であるが、これらの活動は、個々に目指すシステムを有機的に結合させ、天竜川流域の循環経済・環境システムの構築を目指すものとして今後の取組が期待される。
(6) 森のゼロエミッション構想
兵庫県では、農山村地域における持続可能な循環型社会形成のための「森を基軸とした」地域版のゼロエミッションである「森のゼロエミッション構想」を平成11年3月に発表した。これは林業経営の低迷や農地生態系機能の喪失等の中山間地域等が抱える課題を発展的に解決し、自然の豊かさを倍に、資源消費を半分にする循環型の地域づくりを目指した構想である。
森のゼロエミッション化の基本的取組としては、第1-3-3図のような戦略を検討している。本構想に基づき、平成11年度より宍粟郡一宮町で構想の具体化を検討し、他の市町村に普及していくことを目指している。これは地域の再生可能資源を地域の中で積極的に活用し、還元することにより、林業ひいては日本の森林を守ると同時に、21世紀の新たなライフスタイルを提案するものであり、具体化の行方が注目される。
ここで、以上の取組における共通的な特徴とグローバル経済との関係を考察してみよう(第1-3-2表)。まず、再生可能な地域資源や地上資源の地域内での利用が資源供給・活用側双方における産業振興や新規産業の立ち上げ等が進むことにより地域経済を活性化させるとともに雇用の場を創出させている。同時にその産業活動が、地域内での資源の効率的な循環(以下、「モノ」の循環という。)を促進させる形で行われていることが分かる。
また、この「モノ」の循環の成功の要因としては、地域の共通な課題を解決するための産業間の相互連携や様々な主体のパートナーシップによる活動が、人々や情報の交流を活発化させ、地域一帯となった活動や地域の固有の生活文化を形成につながったことが考えられる。さらに、自然交響楽団や小国町の取組に見られるように、中小事業者を中心とした地域資源活用型の事業活動が、地域における信頼と輸送コストの削減等を競争力にしながら発展していることも分かる。
一方、安価な外材やヴァージン資源との競合にさらされているのも事実である。また、地域内に循環の輪をつなぐ産業が十分立地していない、地域市場の小ささ等地域内の課題もある。そこで、以下ではこのような課題の解決のために必要だと考えられる、人々や情報の交流などの「モノ」の循環の円滑化に資する取組手法について考察したい。