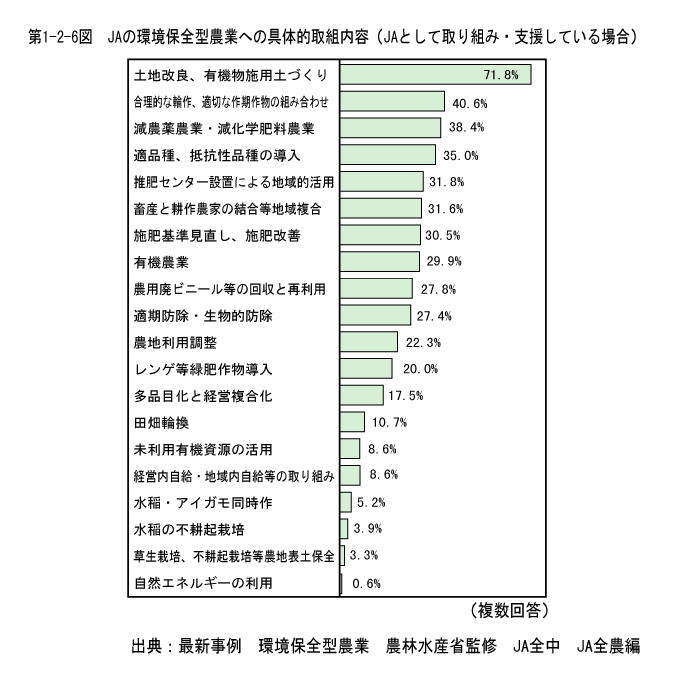
3 「食」を支える産業における取組
以上「モノ」づくりを中心とした第二次、第三次産業に係るグリーン化の方向性について論じた。ここでは、第一次産業におけるグリーン化に目を向けたい。
第一次産業は、太陽と豊かな自然環境の恵みを基盤として行われる産業であり、自然環境の維持・保全と密接な関係を持ちながら生産活動を行っている産業である。また、第一次産業は、自然環境の改変や実施手法如何によっては環境負荷を引き起こす可能性を持っているが、その産業の振興自体が自然環境の維持・保全や資源の持続可能な利用を可能にするという点で他の産業とは違ったアプローチで考える必要がある。
「食」は我々の命の源であるとともに、健康を保ち生活を豊かにするために必要不可欠なものである。近年有機農産物の人気が高まっている等「食と健康と環境」という観点から事業者や消費者の様々な取組が見られる。そこで、ここでは、「食」を支える農業を中心に関連の産業も含めた形でグリーン化の方向性を論じることとする。
(1) 農業と環境保全
農業は基本的には、自然の営みと人間活動との共生を図りつつ営むことのできる産業である。農地においては、水田を主体とした健全な農業生産活動を通じ、国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全、良好な景観の形成、文化の伝承等の多面にわたる機能を持っている。また、化学肥料、農薬の節減等により営まれる環境保全型農業は、家畜排せつ物の有機性資源を堆肥として還元するという有機系の物質循環を支えるものである。また、山の自然と人里の営みの接点に位置する棚田は、野生動物や鳥、昆虫たちの餌場となり、それ自体が自然環境の一部を成しているといっても過言ではない。
一方、農業によって生じる環境負荷も少なくない。化学肥料や農薬の不適切な使用や家畜排せつ物の不適正処理等による硝酸性窒素等の地下水汚染や河川の水質汚濁、農業機械や施設での化石燃料の使用等による二酸化炭素の排出、水田や家畜の反すう等からのメタン、亜酸化窒素の排出、オゾン層破壊物質である臭化メチルの土壌病害虫防除等への使用等による環境負荷も懸念されている。
(2) 環境保全型農業の実践とその要因構造
農業生産は既に述べたように基本的には、自然生態系との共生、物質の循環再生等環境保全に寄与してきた産業である。しかし、近年の集約的農業はエネルギーや農薬、化学肥料などの生産資材を多用し、生産性の向上を実現させた反面、環境保全への配慮を欠き、連作障害の発生など農業の持続可能性に問題が生じている。そこで、農林水産省は、平成6年に環境保全型農業の推進本部を設置し、環境保全型農業の推進に力を入れるようになった。
環境保全型農業は、資源循環を基礎とする地域の伝統的な農法の再評価と環境負荷の軽減を可能とする新たな技術との組合せが出発点となっており、環境保全と生産力を両立させるため、たい肥等の利用による土づくりの実践、合理的な輪作体系の導入、耕作と畜産との連携等による有機性資源の循環などにより持続性の高い農業生産の確立を目指したものである。
また、環境と調和をめざす農業は、大量生産、大量消費型の生活様式を見直し、量より質を尊重し、さらに農業者や消費する人間の健康と福祉と自然環境の豊かな地域を守ることを目指すものといえよう。
そこでまず、現在の環境保全型農業の実践事例を整理したい。
ア 水質汚濁等の環境問題を改善することで取組が始まった事例
水質汚濁等の環境負荷が深刻化してから、環境保全型農業が始められている事例がいくつかある。
この場合の対策は、一般的に行政主導の啓発活動、規制強化が行われることになるが、農家個々の経営目的は必ずしも環境保全にあるわけではないので、なかなか協力が得られないことが多い。このような中、長年琵琶湖の水質保全を目指す「クリーン・アンド・リサイクリング農業(現在の環境保全型農業)」を展開している滋賀県の湖東町地域は、地域ぐるみの取組で成功している。用排水分離、川の堤防のコンクリート化に伴う自然浄化作用の減少等がこの地域を流れる河川の水質汚濁の原因の一つであったことを認識した農家が水質保全のための取組を始めたことが契機であった。現在は地域ぐるみで土づくり、側条施肥、緩効性肥料の使用、濁水の反復利用、転作田での濁水浄化等の用排水の水管理や作業体系の改善等の農業排水対策が積極的に行われている。これらの取組は、環境保全だけでなく生産過程における効率性の向上にもつながったという。このように農業経営上のメリットや地域振興と結びつけた形で取組まれることが重要であろう。滋賀県では、平成9年度よりこのような地域の抱える課題を少しずつ解消しつつ、住民主体の環境保全が進められるよう、「水・物質循環」「自然との共生」「住民参加」を3本柱に農村地域の水質と生態系の保全を目的とした「みずすまし構想」を進めている。
また、肥料の過度の施用による水質汚濁を防ぐため、地方公共団体における施肥基準の見直し等の取組も進みつつある。
イ 農業生産をより安定的に発展させる観点からの取組
有数の野菜生産地である北海道七飯町、神奈川県三浦市、長野県朝日村などでは、単一な作物の連作、化学肥料の過剰施用を進めた結果、土壌の悪化や連作障害、病害虫被害などが深刻化したが、生産者全員が参加する講習会や堆肥センターの設置等地域ぐるみの改善対策などにより自然と環境保全型農業を目指す取組が行われるようになった。また、水田地帯でも健康問題や防除労働の軽減の観点から減農薬栽培に取り組まれている。これらの多くは、生産者全員が参加する講習会や土壌診断による適正な施肥管理等農協が中心となった地域ぐるみの活動として行われているものが多い。
ウ 有機農業の導入等により安全な農産物の生産を目指す実践
地域農業の過疎化や担い手の減少、高齢化などを克服し、消費者の求める安全な農産物生産を重視する方向で、有機栽培に組織的に取り組んでいる事例として、秋田県仁賀保町の「自給農産物分け合い運動」、島根県石見町の「地球にやさしい農業の町」等がある。これらの取組では、効率性のみを求めてきた従来の農業生産に疑問を投げかけ、伝統的な手法も含めた環境と調和した農法の活用、消費者との産直や契約栽培、また栽培基準の設定、ガイドラインの整備などを行っている。
エ 環境保全と地域農業振興の結合
環境保全と地域農業振興を統合して、産直、加工などに組織を挙げて取り組んでいる事例がある。これらは複合汚染などを背景に生協などとの産直を始め、消費者との交流の中で安全な農産物を求める消費者のニーズを知り、その要望実現に対応したものである。「自然生態系の農業推進に関する条例」を定めた宮崎県綾町、「総合産直」を目指した茨城県八郷町等で取組が見られている。
また、地域ぐるみでの徹底した環境保全型農業が地域への新規就農者を増加させている埼玉県小川町の取組は注目に値する。ここは、長年有機農業を実践してきた人物の下で学んだ人々が、小川町で独立し、消費者と提携しながら有畜複合の自給・循環型農業を営んでいる。具体的には、有機農法米や多種類にわたる野菜の栽培のほか、雑穀栽培等地域で伝統的に栽培されてきた作物への取組や地元産の酒ヌカ、クズ米やクズ麦、野菜クズを主体とした飼料での平飼自然卵養鶏も行われている。エネルギー効率の面でも、野菜栽培に重油や電気を利用しない伝統的な踏み込み温床(粗材のわかる落葉、稲ワラ、家畜ふん、米ヌカ等で作る野菜苗を自給した上での季節栽培)、また自然エネルギー自給の試みとしてディーゼルエンジンのトラクターやトラックの燃料も廃食油から作られた軽油代替燃料の活用、家畜排泄物や生ごみ等を活用して台所のガスの自給や太陽発電等身近にあるエネルギーを存分に活用し、化石燃料を極力利用しない取組も一部で行なわれている。
以上のような事例を踏まえれば、環境保全型農業の推進パターンは次のように整理できる。
? 水質汚濁等の環境問題に対応した取組
? 農業生産をより安定的に発展させる観点からの取組
? 有機農業の導入により安全な農産物の生産を目指す実践
? 環境保全と地域農業振興の結合
このことから、環境保全型農業の追求は、農業生産を安定的に行い、より安全で安定した価格の農産物を供給し、さらには地域の活性化に資することがわかる。一方、有機質肥料は化学肥料より高価であり、兼業化、高齢化が進む農家において新たな手間をかけることになるため、消費者との連携などにより環境保全型農業を農業経営と調和する形での取組をいかに強化するかが課題となっている。
また、農協における環境保全型農業の具体的な取組内容は、第1-2-6図のようになっている。これらの取組事例を踏まえ、環境保全型農業の概念について整理してみたい。(第1-2-7表)これはあくまで1つの枠組みであり、地域の実状、自然的特性に応じて相違があるものであろう。
(3) 農業のグリーン化における課題と今後期待される取組
以上、農業のグリーン化の方向性等について論じたが、環境保全型推進上の課題としては、除草や堆肥づくり等の労働力の負担や経費の増加、販売確保と価格問題、技術の未確立等の問題点が挙げられている。
従って、環境保全型農業を推進するためには、たい肥の安定供給、作業の省力化、化学肥料、農薬等の低減を可能とする技術の確立、有機農産物等の流通システムの整備等や農業就業者の高齢化や減少による労働力不足への対応等が必要である。これらの課題を解決するために、肥効調節型肥料や、自然生態系の営みを活かした天敵・フェロモン、あいがも農法等の利用がなされている。また、住民参加型の農業、有機農産物の認証制度によるラベリングや農協等による技術の提供や産直等の消費者と連携した取組が始まっている。
また、日本の農業は産業としてだけでなく、持続可能な地域づくりを支え、発展させるために必要不可欠なものであると考えられる。
例えば埼玉県で行われている県産の農作物を主原料とした食品に対して認証を行う「ふるさと認証食品認証事業」や農作物を6時間以内に流通することを目指す「新鮮さいたま6時間流通促進事業」のように、特定の農産物の大量生産、広域流通が一般化している状況に対し、地域の農産物を地域内で流通させる取組が始まっている。また、このように農産物や飼料を地域の中で消費する地産地消をすすめ、さらにその生ごみ等を堆肥化し、農地に還元するという地域内資源循環を進める試みも始まっている。これは他地域の資源に依存しない地域自立型の農業を実現するものともなり、持続可能な地域づくりへとつながるものであろう。(第1-2-7図)
さらにこのような取組を発展させ環境保全型農業を地域ぐるみで取組む地域住民参加型農業(CommunitySupported Agriculture)の試みも始まっている。これは、地域の住民が農家の生産についての決定と労働に直接参加し、農業、農家、消費者間の結びつきを回復させ、有機農業を通じて地域社会を形成することを目指すもので85年(昭和60年)以降多くのCSAの取組がアメリカで行われている。このような取組の背景には、農業と環境の問題は、農家だけでなく地域全体に関わるものだという認識がある。我が国においても都市住民による援農、東京の練馬区等で行われている体験農園等(農家が経営する市民農園)もこの種の取組として今後の発展が期待される。
囲み1-2-4 身土不二
気象条件や土壌条件は地域によって大きく異なるものであり、なるべく住んでいる場所から近くの安全で健康な土から生み出された旬のものを食べるのが人間の健康のために最も良いとする「身土不二」という考え方がある。つまり、体を冷やす働きを持っている食物は温暖な地域で夏に、体を温める働きを持っている食物は冷涼な地域で秋から冬に採れることものが多く、食物と気候の調和が自然と図られているのである。
「食料・農業・農村基本問題調査会」の最終答申は、栄養バランスのとれた健康的で豊かな日本型食生活等の普及や啓発の必要性、さらに食生活の在り方を見つめ直す国民的な運動を展開すべきである旨を指摘しており、伝統的な日本の食生活の在り方を再評価すべき時期にきているといえよう。
このような地域における取組が試みられている一方、国際化が進展し、農産物の輸入が増加している状況にあり、国内の農業生産、ひいては適切な農業生産活動が行なわれることにより生ずる農業のもつ国土・環境保全機能の発揮が困難となる可能性があることにも留意することも必要であろう。
また、第一・二・三次産業を「食」を介して有機的につなげることにより環境保全型の農業を振興する取組も今後必要であろう。食品産業における国内の有機農産物の利用や有機農産物の宅配、さらには農業者による販売を行うファーマーズマーケット、農業者による加工、販売を行ういわゆる第六次産業の取組等が有効であろう。また近年取組が始まったゼロエミッションにおいては、有機物の循環を担う農業サイドの関与が非常に重要である。
さらに、再生可能な資源の供給源としての農業の役割にも注目できよう。滋賀県愛東町では、休耕田や耕作放棄地に市民参加型でなたねを栽培し、なたねから絞った油を地域のトラック等のガソリンとして用いる試みが始まっている。なたね油は地域の資源を活用した再生可能な資源であるとともに、なたね畑は地域の観光資源ともなるという。これは地域の農業と工業との連携により、地域の活性化を図り持続可能な地域づくりを行っていくものとして今後の展開が期待される。また、福井県今立町では、森林保全とエネルギー供給を行うため木炭を燃料源とする木炭自動車等の木質バイオマスの利用を進めている。これらは地域の農林業と工業との連携により、地域の活性化を図り持続可能な地域づくりを行っていくものとして今後の展開が期待される。
このように工業と農業の連携を図る取組はヨーロッパで積極的に行われており、ドイツは、総耕地面積の4%の農地が、工業やエネルギー原材料の生産のために用いられている。一年草の亜麻のような植物には化学肥料や農薬の使用をほとんど使用しなくてもすむため、輪作体系におけるこのような作物の栽培が土壌環境の改善効果を持つという。