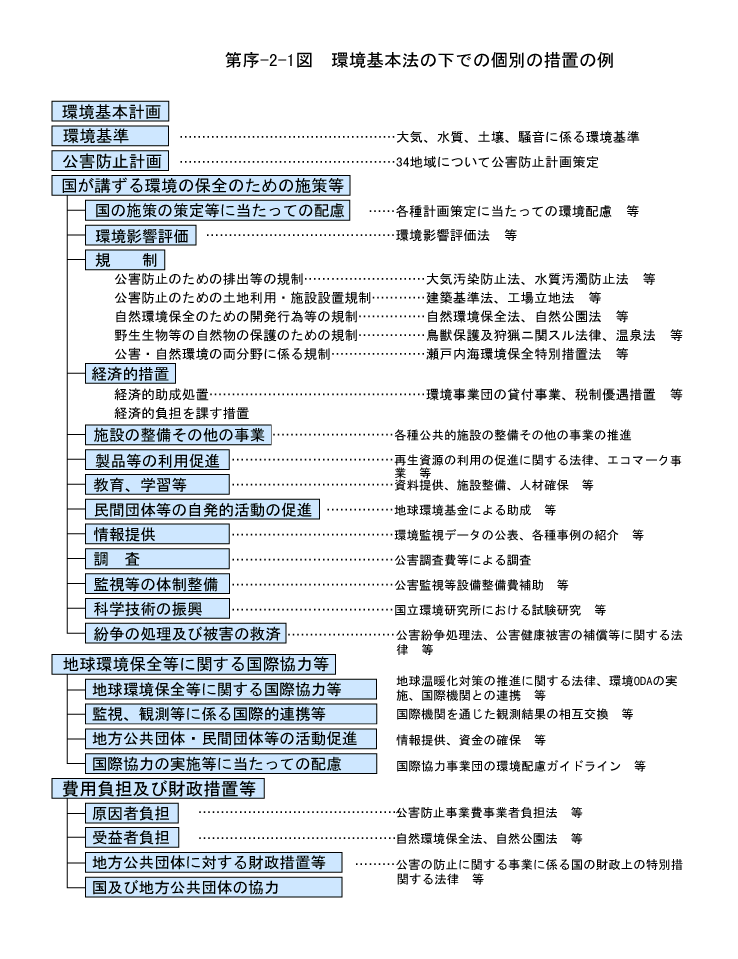
6 新たな環境政策の枠組み
(1) 「環境基本法」、「環境基本計画」の制定
第1節において戦前まで遡って我が国の環境行政の発展を振り返って来たが、昭和60年代に至り、環境の保全は次々と生起する問題に後追い的、対症療法的に取り組むことでは到底十全には果たされないことが認識され、ここに環境行政の大きなパラダイムシフトが起きることとなった。
ア 環境基本法
我が国の環境行政は、昭和42年に制定された公害対策基本法、47年に制定された自然環境保全法を基本として推進され、これまで、公害防止、自然環境保全のため一定の役割を果たしてきた。しかしながら、今日の環境政策の対象領域の広がりに対処し、特に大都市における窒素酸化物による大気汚染、生活排水による閉鎖性水域等における水質汚濁などの都市・生活型公害問題、増え続ける廃棄物の問題、地球温暖化、オゾン層の破壊などの地球環境問題等に対し適切な対策を講じていくためには、規制的手法を中心とする公害対策基本法や自然環境保全法の枠組みでは不十分となっていた。すなわち、国、地方公共団体はもとより、事業者、国民の自主的取組などすべての主体による対応が必要であり、多様な手法を適切に活用することにより、経済社会システムの在り方や行動様式を見直していくことが必要となっていたのである。
政府においては、このような観点に立って、平成4年10月20日の中央公害対策審議会・自然環境保全審議会の答申「環境基本法制のあり方について」を踏まえ、地球環境時代に対応した新たな環境政策を総合的に展開していく上での大きな礎となる「環境基本法案」を、平成5年3月12日に閣議決定し、第126回国会に提出した。その後、修正や再提出を経た第128回国会において、11月12日、政府案が参議院本会議で全会一致で可決されて成立した。これにより、「環境基本法」が11月19日、公布、施行された。
環境基本法は、第1に、環境の保全についての基本理念として、環境の恵沢の享受と継承等、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築等、国際的協調による地球環境保全の積極的推進という3つの理念を定めるとともに、国や地方公共団体、事業者、国民の環境の保全に係る責務を明らかにしている。
第2に、環境の保全に関する施策に関し、まず、施策の策定及び実施に係る指針を明示し、また、環境基本計画を定めて施策の大綱を国民の前に示すものとするとともに、環境基準、公害防止計画、国等の施策における環境配慮、環境影響評価の推進、環境の保全上の支障を防止するための規制の措置、環境の保全上の支障を防止するための経済的な助成又は負担の措置、環境の保全に関する施設の整備その他の事業の推進、環境への負荷の低減に資する製品等の利用の促進、環境教育、民間の自発的な活動の促進、科学技術の振興、地球環境保全等に関する国際協力、費用負担及び財政措置など基本的な施策について規定している。
第3に、環境庁及び都道府県に環境審議会を設置すること等について規定している。(第序-2-1図)
イ 環境基本計画
環境基本計画は、平成5年11月に制定された環境基本法第15条に基づき、内閣総理大臣が中央環境審議会の意見を聴いて案を作成し、閣議により決定されるもので、環境の保全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱等を定めるものであり、6年12月に閣議決定された。この計画は我が国初の閣議決定された国レベルの包括的な環境計画であり、行政のすべての分野にわたって環境保全の考え方を織り込むことによって、トータルな視点で持続的発展が可能な社会を構築するための枠組みとなるものである。また、同計画の内容も新たな視点と構成を持ったものとなっており、環境対策の効果の高い推進という観点からの意義を有するものになっている。
環境基本計画の全体の構成は、計画策定の背景と意義、環境政策の基本方針、施策の展開、計画の効果的実施の4部に分かれている。
第1部は計画策定の意義を扱っている。21世紀半ばまでを展望し、環境政策の長期的な目標を定めた上、21世紀初頭までの国の施策を体系的に定め、地方公共団体、事業者、国民などに期待される取組を明らかにしたものである、との本計画の策定の趣旨を述べている。第2部は、環境政策の基本方針であり、環境政策の基本的な考え方や、これを受けての4つの長期的な目標を定めている。第3部は、施策を定めている箇所であり、同計画の約3分の2の分量を占める部分である。ここでは、4つの長期的な目標に沿って施策を掲げるほか、これらの目標の達成に共通して役立つ施策について一括して定めている。第4部は、計画の実施の仕組みを定めており、具体的には、財政措置や国の各種の計画との関係、計画の進捗状況の点検と計画の見直しなどについて定めている。
計画策定の背景と経緯について定める第1部では、これまでの環境問題の推移を踏まえた上で、今後の経済社会の見通しを踏まえた環境問題の今後の動向についての認識を示し、今後対応すべき環境問題の特質等を整理している。それは第1に、環境問題が、人の健康、生活環境、自然環境といった分野別に捉えるのではなく、環境そのものを総合的に捉える必要があるということである。第2には、今日の環境問題の多くは、通常の事業活動や日常の生活行動による環境負荷の増大に起因する部分が多く、その解決のためには、経済社会システムの在り方や生活様式を見直していくことが必要であり、そのために、広範な主体の参加による自主的、積極的な環境保全が必要だということである。その第3は、今日の環境問題が、地球規模の空間的広がりと将来世代にもわたる時間的広がりを持ち、人類の共通の課題となっており、このため国際的連携を強化するとともに長期的視野に立った予防的措置が必要であるということである。
このような特質を持った現代の環境問題に対応するためには、従来からの規制を中心とした環境政策の進め方だけでは不十分であり、日常的な事業活動や生活からの環境負荷が社会全体として小さくなるような多様な取組を、環境全体としてみて改善がなされるように有機的かつ整合的に進め、社会全体を環境への負荷の少ない持続可能なものにしていく必要がある。このような総合的、体系的取組を進めるためには、その全体を見渡した一覧的かつ総合的な指針が定められることが非常に効果的な方法であり、またそれが行政の全分野の責任者の合意として定められることはその実施を効果的に進める上で必要なことである。このような意味で、環境基本計画の策定は新たな時代の環境政策を効果的に進める枠組みとなるものである。
(2) 「環境影響評価法」の制定
我が国の環境アセスメント制度は、昭和47年の「各種公共事業に係る環境保全対策について」の閣議了解に始まった。そして、59年の「環境影響評価の実施について」の閣議決定により統一的な制度が構築され、この閣議アセス制度を運用することにより、一定の成果を上げてきた。他方、既に見たとおり、一定の限界があることも事実であった。こうしたことから閣議アセスの定着も踏まえつつ、環境基本法、環境基本計画の制定過程においては、制度の見直しの必要性が指摘され、また、行政手続法の制定により行政運営における公正の確保と透明性の向上が求められたこと等から、平成9年6月に「環境影響評価法」が制定されるに至っている。
環境影響評価法制定の意義としては、法制化自体の意義、制度内容の充実の2点が挙げられる。特に後者については、対象事業の拡大、アセスメントの方法について意見を求める仕組み(スコーピング)の導入、住民等の意見提出機会の拡大、環境庁長官の意見提出機会の拡大、評価書の記載事項の充実、できる限り環境影響を低減したかどうかという新たな評価の視点の導入、などを閣議アセスの内容や考え方に比べた場合の大きな変更点として挙げることができる。
とりわけ、スコーピング手続と新たな評価視点の導入が重要である。従来の制度には、事業の詳細が事実上決まってから手続が行われるため事業内容を見直す余地が小さい、地域特性・事業特性に関係なく画一的な方法によりアセスメントを行っている、固定的な環境保全目標への適合関係のみを判定するという許認可的な運用がなされている、等の問題点があった。このため、早い段階での情報交流、柔軟なアセスメント方法の決定、複数案の比較検討等を行いつつ環境負荷の少ない事業計画を模索すること、などを目指して制度改正を行ったものである。
このような制度の見直しの視点は、環境アセスメント以外にも今後一層必要となる、意思決定に環境保全の観点を組み込む仕組みや住民参加の仕組みを考えるに当たって、一定の示唆を与えていると言える。
このように、法の制定により環境アセスメント制度は大いに進展した。しかし、個別事業の実施の段階での環境アセスメントには、より上位の政策や計画の段階で事実上事業の実施が決定されている場合がある、複数の事業の累積的な影響の評価が難しい、という構造的な問題が指摘されている。
こうしたことから、世界的にも政策・計画について環境アセスメントの手法を適用する戦略的環境アセスメントの制度を導入する機運が高まっており、一部の国では既に制度化され、EUでは共通制度導入への検討が進められている。我が国としても、環境影響評価法の国会審議における附帯決議の趣旨を踏まえ、国際的動向などを参考にして、戦略的環境アセスメントの導入に向けた検討が必要となっている。
(3) 地球温暖化防止京都会議と京都議定書
人間の活動によって発生する二酸化炭素等によって地球が温暖化することは既に19世紀から指摘されていた。しかし、多くの国際会議において地球温暖化防止が国際的に重要な政策課題として議論されるようになったのは、1980年代末からである。1989年(平成元年)11月の「大気汚染および気候変動に関する閣僚会議」において、遅くとも1992年(平成4年)の地球サミットまでに地球温暖化防止の枠組みとなる条約を採択すべきであること等が盛り込まれた宣言が取りまとめられた。
その後、1990年(平成2年)8月に取りまとめられたIPCCの第1次評価報告書等をもとに、1991年2月から条約作成のための政府間交渉会議が開催され、1992年5月に、先進国が西暦2000年までに温室効果ガスの人為的な排出量を1990年レベルに戻すとの目的を持って政策・措置を講じ、その実施状況を報告することを約束すること等を内容とする「気候変動に関する国際連合枠組条約(気候変動枠組条約)」が採択され、同条約は、1994年3月に発効した。
さらに1995年(平成7年)にベルリンで開催された同条約の第1回締約国会議(COP1)においては、先進国における2000年以降の取組に関する条約の規定が不十分なものであることが認められ、2000年以降における人間活動に伴う温室効果ガスの排出を抑制又は削減するため、先進国の温室効果ガスの排出量について数量化された目的を設定し、その達成のために先進国が取るべき政策、措置を規定する等、地球温暖化防止のための新たな国際的取組について定める議定書又はその他の法的文書を、1997年に開催される第3回締約国会議(COP3)において採択することが決定された(いわゆるベルリン・マンデート)。
ベルリン・マンデートを受け、約2年間の外交交渉を積み重ねた上、COP3が京都において、12月1日から11日に開催された。交渉当初から各国の主張は大きなばらつきを見せたが、主要な論点としては、? 先進国における温室効果ガスの排出削減のための数値目標、? 政策・措置、? 途上国の取組強化が挙げられる。困難な交渉の末、全会一致で京都議定書が採択された(第4章参照)。
(4) 地球温暖化対策推進大綱の策定
平成9年12月に、内閣に設置された地球温暖化対策推進本部(本部長:内閣総理大臣、本部員:関係閣僚)は、2010年に向けて緊急に推進すべき地球温暖化対策として10年6月19日、地球温暖化対策推進大綱を策定した。政府としては、同大綱に従って、地球温暖化対策の総合的推進、エネルギー需給両面の対策を中心としたCO2排出削減対策の推進、その他の温室効果ガスの排出抑制対策の推進、植林等のCO2吸収源対策の推進、革新的な環境・エネルギー技術の研究開発の強化、地球観測体制等の強化、国際協力の推進等を進めていくこととしている。
(5) 「地球温暖化対策の推進に関する法律」の制定
京都議定書には、排出量取引のルールなど今後の国際的な交渉に委ねられている部分があるため、京都議定書の実施を担保する法律をすぐに策定することはできないが、我が国の温室効果ガスの排出量が1990年のレベルを相当に超過し、今後には厳しい対策努力が必要であることを踏まえると実施可能な対策を現段階から講じていかなければならない。
このため、京都会議直後の平成9年12月16日に、環境庁長官から中央環境審議会に「今後の地球温暖化防止対策の在り方について」の諮問がなされた。中央環境審議会においては、特に今日の段階で取り組むべき対策に重点をおいて審議を行い、平成10年3月、「今後の地球温暖化防止対策の在り方について(中間答申)」を取りまとめた。中間答申で、将来の京都議定書の締結に備え、一層の対策の検討を行うことと併せて、今日の段階において、地球温暖化防止を目的とする法的なルールを定めることが効果的なものについては、早急に法制度化を図ることが必要であると指摘した。政府では、中間答申を踏まえ、法律案の作成を進め、平成10年4月28日に「地球温暖化対策の推進に関する法律案」を閣議決定し、同日第142回通常国会に提出した。法案は、温室効果ガスの排出の抑制等にはあらゆる主体が参加した幅広い取組が不可欠であることから、今日の段階からの取組として、国や地方公共団体、事業者、国民それぞれの責務を明らかにするとともに、自主的な計画の策定やその実施状況の公表など各主体の取組を促進する枠組みを整備することを目的としたものであり、通常国会で継続審議となった後、第143回臨時国会において審議が再開され、一部条文修正の上、平成10年10月2日に参議院本会議で全会一致で採択され、10月9日に公布された。なお、同法は京都議定書の実施を担保する法律とは位置づけられていない。