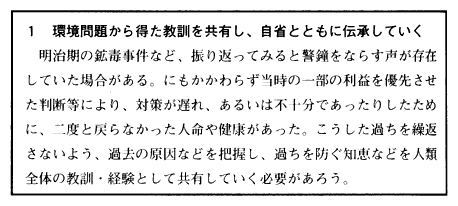
環境の世紀となると目される21世紀に向け、これまでに得た教訓が果たして十分なものかは不明である。しかし、教訓を十全に踏まえた慎重で賢明な行動が必要なことは間違いないところである。本節では、前節までの考察を踏まえ、20世紀に人類が直面した様々な環境問題とその対応を通じて我々が学んできたことを整理してみたい。
過去の公害などの事例から学べることは、行政としても鳴らされた警鐘に謙虚に耳を傾けていく姿勢が必要であるということである。環境の変化やそれに伴う損失には不可逆なものがあった。失われた命や健康は、何にも代え難いものである。健康影響等の発生メカニズムの解明や、環境モニタリングをできる限り速やかに行い、科学的知見に基づいて対策を講じることが原則であるが、科学的知見が若干不十分な点があっても、まずは被害拡大の防止のための対策を講じ、逐次的に対策を修正していくなど人命や健康を十分に尊重した判断が極力速やかになされるべきである。過去の例では、必要な情報が必ずしも体系的に把握されず、行政としての対応が後手後手に回りがちであった。また、政府だけでなく地元に密着したNGO等にも一定の役割が期待される。例えば独自に科学的な検証を行っていくシンク・タンク的な役割と地域の活動を盛り上げていく運動体としての役割が考えられる。我が国のNGOはこうした点で欧米のNGOに比して改善・発展の余地があると指摘されており、政府を補完するNGOの建設的な役割の伸張が望まれる。
人類は、過ちを繰り返すことがある。第3章で見るように、アマゾンの一部では、毛髪水銀値が高く、有機水銀中毒になる可能性のある者の存在が報告されている。不幸にも過ちが起きた場合、それを、その場限りのものとせずに深く自省し、過ちの原因や過ちを防ぐ知恵や仕組みなどを将来世代のための貴重でかけがえのない経験・教訓として人類全体で共有していくことが必要である。特に我が国は公害等の痛ましい経験をしてきた。この経験から学んだ教訓を世界に向けて積極的に伝えていく必要がある。とりわけ、社会的インフラ・ストラクチャーの整備が不十分なまま急速に経済発展を遂げているような途上国において、激甚な公害が繰り返されることのないよう、あるいは少しでも環境負荷の少ない経済社会の在り方を提示できるよう、我が国として積極的にODAによる支援や注意喚起・情報提供を行っていく必要があろう。例えば、環境庁地球環境経済研究会では、日本の公害経験に関する反省を率直に収めた報告書をまとめ、これを公表したところ、アジア地域の途上国等で高い評価を受けた。こうした努力が継続して続けられる必要があろう。また、環境問題に関する人類の失敗を風化させないように、NGO等には語り部としての役割も期待される。
囲み序-3-1 四日市ぜん息障害賠償事件に関する47年7月の津地方裁判所判決(2)
同判決は、「人間の生命、身体に危険のあることを知りうる汚染物質の排出については、企業は経済性を度外視して、世界最高の技術・知識を動員して防止措置をすべき」とした。司法判断においても人命尊重の基本姿勢が高らかに打ち出されたものと言えよう。
琵琶湖においては、特に52年以来毎年大規模な淡水赤潮が発生した。これは、一般に湖沼が、閉鎖性水域であるため汚濁物質が蓄積しやすく、富栄養化の進行しやすい性格を有していることによる。湖沼で水質の汚濁によるアオコの発生や悪臭、水道水の異臭味などが問題となる場合があったが、水質汚濁の要因が生活系、農畜水産系など多岐にわたっているため、従来の水質汚濁防止法による対策が及ばなかった。水質汚濁の原因に占める生活排水の割合が高い場合、住民の日常生活が原因となっているが故に、住民と連携しながら対策を進めなければその効果が上がらない。湖沼対策は公害対策がこのような難しい領域に踏み込んだ典型例と言える。
政策の発想という観点からも旧態依然としたままでは解決策はすぐには出てこない。環境問題の複雑な構造に合わせた根元的な対策を複合的に講ずることが必要になってくる。平成9年版の環境白書が指摘したように人類が直面している現在の環境問題は、特効薬のない慢性病に例えられ、1日1日の生活そのものを変えていく、その積み重ねにより、人と人との関係も変えていくという、言い換えれば根治療法が何よりも重要で不可欠であることを学んだ。
環境問題の性質に応じて、環境影響評価、規制的措置、経済的措置、社会資本整備、環境教育・環境学習、事業者・国民の積極的な支援、科学技術の振興等の多様な施策手法を適切に組み合わせて息永く計画的に強化していくことが重要である。こうした認識も踏まえて、平成6年に環境基本計画が策定されたところである。
我が国は先進国として、大規模な経済活動を営む過程で、地球規模で大きな環境負荷を与えている。こうした我が国は、地球全体として環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会を構築するとの観点からも自らの取組を積極的に進めていく必要がある。また、諸外国から寄せられる期待も大きいと言える。我々は、環境外交においても我が国が国際的にふさわしい役割を果たし望ましい国際秩序の形成に力を尽くしていくことの重要性を学んだ。その意味で、我が国がイニシアティブを取って行われた地球温暖化防止京都会議等では、第2節で述べた通り、京都議定書という成果を得たが、その成果だけでなく、その準備・調整過程についても学ぶところが大きかった。
大きな地球の利益の実現のためには、責任ある決断やイニシアチブが必要なことを学んだ。地球環境問題に対しては、「共通だが差異のある責任」を各国が確実に果たしていけるように、場合によっては対策のオプションを提示するなどそれぞれの国情に対して十分配慮することが必要である。我が国が、前述のような環境外交を展開していくためには、環境保全効果が高く実現可能である様々な施策を提示できるよう、各国の事情に通じていくことも重要となろう。そのためには、言葉の壁を越え、世界に通用するような人材を育成することも有益であろう。
さらに、第3章でも述べるとおり環境協力の在り方についても学ぶところがあった。我が国からの環境協力においては、国、地方公共団体、事業者、NGO等の担い手がそれぞれの特徴を活かしつつ相手国との間に複線的なパートナーシップを構築することが必要である。こうしたパートナーシップが相乗効果を伴い途上国自身の取組を力強く支援することが環境協力の実効性を高めることになろう。
囲み序-3-2 国際的に高い価値があると認められる環境の保全
環境基本法では、第32条(地球環境保全等に関する国際協力等)において、国際的に高い価値があると認められている環境の保全について規定している。こうしたものの例には、南極や世界遺産がある。ユネスコの世界遺産の考え方を見てみよう。世界遺産とは、過去から引き継がれてきた人類の宝物であり、今日我々が共に生き、未来の世代に引き継いでいくものとされる。世界遺産の概念を特別なものにしているのは、遺産が「顕著な普遍的価値」を有しているためである。この根底には、世界遺産に登録された場所は国境とは関係なく世界のすべての人々に属しているという考えがある。例えば、エクアドルのガラパゴス諸島はエクアドルの人々だけでなく、日本人にも他の国の人にも同じく顕著な価値が認められるということである。現在、世界遺産のいくつかは、他国の援助なしには保存するための資金が不足し、崩壊の危機に瀕しているものもある。このため、国際社会全体が責任を持ってこうした遺産の保護のために協力していこうとするものである。
地球環境問題は、地球の宇宙船地球号的性格が強まったという意味で究極的な環境問題であるが、その対策を巡って、南北間あるいは世代間の公平をどう図るべきかが最大の問題である。地球全体を見たときに、地球の有する良好な環境が普遍的な価値を有していることに異を唱える者はなかろう。こうした地球的な利益を担う地域に対しては、特に国際社会全体が、グローバル・コモンズの考えの下、適正に責任を分担し合いながら保全していくことについて検討を深めることが有益であろう。
従来の自然環境保全行政は、希少性や学術性の観点から価値の高いものを規制的手段で守るということが中心であった。このような保護地域・貴重種という視点では、自然公園や世界遺産などのすぐれた自然地域や絶滅のおそれのある生物を守ることは可能でも、普遍的な種を中心とする身近な自然が減少することを防ぐことができない。その結果、日常的な生活のレベルで重要な役割を持つ身近な自然が急速に失われ、以前は普通に見られたメダカのような種までが絶滅の危機にさらされている。
今後は、生物の進化の観点も含め、地域固有の自然環境に応じて、様々な生物種が存在すること、同じ種でも遺伝子レベルでの様々な多様性があること、さらに、生物の相互関係の複合体としての生態系が多様であること、という、各レベルでの多様性を全体として表現する「生物の多様性」という考え方で自然環境保全の問題を捉えるべきであること、それを保全するためには、各レベルでの多様性の保全に向けた取組が重要であることを学んだ。
また、原生的な自然のみならず農林業等人間の営みの中で形成されてきた自然の重要性、及び農林業等が自然の循環機能を活用して行われており、環境保全機能を有することも認識する必要がある。
生物の生態、生態系の機構、生物間の相互作用等は極めて複雑で、全容を明らかにすることは不可能に近い。我々が有している生物や生態系に関する情報は極めて少なく、往々にして手遅れになってから解明されることもある。自然環境への影響を評価する際には、我々が生物や生態系に関し、むしろ知っていることはわずかであるということを認識する謙虚さが求められている。
また、知見が少なくとも、その時々の最新の知見を基に、人間活動が自然に与える影響を事前に予測・評価し、その結果を踏まえて負荷を軽減するための対策を講じる必要がある。このため、自然環境に関する知見を常に最新のものとするよう調査を充実し、事前の予測・評価のためにその結果が広く活用されるような形で蓄積・提供することが重要である。
自然とのふれあいは人間性の回復や子供たちの情操を培うのに必要不可欠であり、自然に対する理解を深め、自然を大切にする気持ちを育むなど、高い環境教育・学習的効果があること、その効果を発揮させるためには、自然とふれあう機会とそれに関する情報を提供することや、プログラムの作成、人材の育成というソフト面の対策が重要であることを学んだ。
一方、ふれあい活動が特定の地域に集中していわゆる過剰利用となったり、大規模なスキー場等の開発が適切な配慮無く進められば、自然環境に過度の負荷を与えてしまう例は多く、保全・修復のための対策に多くの時間と費用を要する結果となっている。本来自然環境の賢明な利用であるべき自然とのふれあいが、自然の価値を損なうことなく継続されるためには、すぐれた自然環境の地域では、他の場所では得ることのできない利用形態を優先するなど、それぞれの環境の許容量を踏まえた配慮が必要である。
自然は人類の生存の基盤であり、持続可能な形での賢明な利用を進めることが、我々の社会を持続させるための大切な前提である。
第1節から始まり、これまで産業経済の興隆からバブル、そしてその崩壊による不況までを見てきたが、経済にはこの100年の間、栄枯盛衰があり、それに応じて環境問題の態様も変わってきた。経済社会の持続可能な発展ととともに環境の枠の中で人類と他の生き物が永続的な営みを続けられるようにするためには、この経済の在り方にまで遡って取り組む必要がある。
「環境への負荷の少ない循環を基調とする経済社会システム」を構築していかなければならないのである。第1章で見るように最近では、同じ資源でより大きい効用を得ることや同程度の効用を得るためにより少ない資源消費でこれを達成する、というファクター10等の考えが示されるようになっている。環境保全上の観点から今後の産業活動のグリーン化の目標は、?経済活動へ投入される物質量や一次エネルギーの供給量の削減、?投入物質やエネルギー供給源の質の転換、?自然界への物質の排出量の削減、無害化や最終エネルギー消費量の削減となろう。また、これまでのフロー重視から「ストック活用型」の経済へ転換し、最適生産・最適消費・最少廃棄型の経済へ移行していくことも必要になろう。エコビジネス(環境関連産業)の推進とともに、それとあいまった産業全体のグリーン化を支援するための積極的な施策を講じていくことが必要である。
また、第2章で見るように、消費者は、徒に目先の利便性を求めるのではなく、一歩立ち止まって正確な情報を基に、環境を重視した合理的な価値判断に基づく行動をとることが重要となろう。現世代に属する個人のレベルの多少の利便性の自制と引き換えに保たれる価値が世代を越えた地球的な意義を持つことをはっきりと認識する必要がある。例えば、現在社会の有する利便性はその多くを多種多様な化学物質に支えられており、いわば化学物質に依存する社会と言うこともできるが、その多様かつ大量の使用による内分泌かく乱等のおそれが、大きな社会問題となっている。また、使い捨て商品の利便性に過度に依存することが、廃棄物量の増大に寄与したことも否めない。さらに、壊れた物は修理して使うという商品に対する愛着を持つことが重要であることも学んだ。最近では、第1章で見るように、超長寿命商品や成長する製品とのコンセプトで販売される商品が出てきた。このような商品は長期的に見れば消費者利益、生産者利益をもたらすものである。製造者はLCAの考えを取り入れて製品を作っていくことが必要であろう。
近年、廃棄物の排出量の増大や質の多様化、最終処分場の残余容量の逼迫、不法投棄や不適正処理の増加などの問題が生じている。これらの問題に対応するため、平成3年に廃棄物処理法の改正が行われた。この改正により、それまで排出された廃棄物の処理に重点を置いてきた対策から、廃棄物の排出抑制と減量化の積極的な推進を含めた総合的な対策への方向転換が図られた。また、併せて資源の有効利用の確保を図ること等を目的とした「再生資源の利用の促進に関する法律」(再生資源利用促進法)が平成3年に制定され、リサイクルの推進への取組が本格化された。
環境基本計画では、「大気環境、水環境、土壌環境等への負荷が自然の物質循環を損なうことによる環境の悪化を防止するため、生産、流通、消費、廃棄等の社会経済活動の全段階を通じて、資源やエネルギーの面でより一層の循環・効率化を進め、不用物の発生抑制や適正な処理等を図るなど、経済社会システムにおける物質循環をできる限り確保することによって、環境への負荷をできる限り少なくし、循環を基調とする経済社会システムを実現する。」ことを長期目標の1つとして掲げた。経済社会のシステムの見直しは、今後、環境の観点からも求められているのである。
現代の人類の活動は、自然の自浄能力、再生能力を上回って環境に負荷を与えている。黙っていても、環境問題は改善・解決しない。複合型の環境問題への取組という舞台においては、皆が主役であることを学んだ。また、対策の効果を高めるために、適切な役割分担をし、対策の実施に際して連携・協力を行っていくことやこうした努力が報われ、評価されるような社会を構築していくことが必要となる。
第2章で見るように環境保全の意識と行動の間にはギャップが存在する。各種の調査で明らかなように、一昔前に比べ、環境への意識は高まり、入手できる情報も飛躍的に増えてきたとはいえ、環境保全意識が高くても、自分一人が行動を起こしても効果がない、という考えから改善行動をとろうとしないケースがあるように、環境保全意識の高まりが必ずしも環境保全に資する行動につながっていないということを学んできた。個と全体の利益の間に相克があるとも言える。一人一人が自覚と責任を持ち、自らの健康やそれを支える環境に対する価値を重視した合理的な判断に基づいて行動すること、いわば、「環境合理性」を重要な行動規準の1つとして尊重していくことが重要である。第2章で見るように、具体的な行動を起こす枠組み・機会・きっかけ作りに行政・マスコミ等が積極的に取り組んでいくことが必要であろう。また、行政が正確でわかりやすい科学的知見に基づいた情報を不断に提供していったり、環境教育を進めていくこと、特に実践的な学習活動を進めていくことも忘れてはならないであろう。
また、一般に事業活動において環境対策にかける費用は、直接的で明確な利益を産み出さない等として、理解・協力が得られにくい。OECDでは、汚染者負担の原則を策定したものの、その適用は、国により温度差が見られる。我が国の公害防止支出の国内総生産(GDP)に占める割合は、昭和50年には3%に達したが、これは先進諸外国における公害防止支出割合をはるかに凌駕する水準であった。当時、多額の公害防止投資を行うことと経済発展との関係を疑問視する向きがあった。また、自動車排出ガス規制(昭和53年規制)の際に産業界からは、公害防止投資によるコスト増が景気浮揚に悪影響をもたらし、日本経済の国際競争力の低下をもたらすおそれがあるとの懸念が示され、不況の中で、環境保全と経済成長との調和を求める声が復活してきた。一方、環境庁においては、計量経済モデルを開発し、公害規制が国民経済に与える影響を定量的に検討し、排出ガス規制等の厳しい公害対策のマクロ経済に与える影響はそれほど大きなものではないと予測した。結果としては、公害防止施設の生産増加などのため成長率などに大きな影響は生じなかったものと見られる。環境対策は、長期的には報われる結果を生むと考えられる。
また、第1章で見るように、環境報告書、あるいは環境会計に係る情報を公表することで、企業の環境問題への取組が定性的・定量的に明らかになっていく。さらに外部環境監査を受けることで、事業活動に伴う環境負荷の把握が透明性・客観性を増す。このように企業活動に伴う環境への負荷を明確化・透明化するとともに、環境保全に関する取組を進めている企業に対しては、社会全体としてそのような取組が評価されるようにし、支援をしていくことが必要である。
囲み序-3-3 環境報告書の提出義務付け−オランダの例−
オランダでは、1999年以降、対象企業(一次精練金属業、化学工業、貯蔵運搬分野、廃棄物焼却及び空港)に対して環境マネジメント法が適用され、環境報告書の提出が義務付けられる。具体的には対象となった業種に属する330社に対して、政府提出用と一般公表用の2つの報告書の提出が義務付けられることとなる。
国の環境行政の責任体制が明確になっていくにつれ、国と地方の環境行政の間の関係を整理し、地方公共団体がそれまで果たしてきた積極的な役割を損なうことなく、その活力を一層発揮させていくことが大きな課題となった。このため、昭和45年の公害国会においては、大気汚染防止法等が改正され、規制対象地域を国が指定する制度が廃止され、地方公共団体の条例に基づく排出規制などの法的位置付けが明らかにされた。新設の環境庁では、この枠組みの下で、地方の力を活用する形で国と地方との連携した取組が強められていった。最近の地方分権の動きの中で、更に地方公共団体の役割が高まっている。
環境基本計画においては、「あらゆる主体が、人間と環境の関わりについて理解し、汚染者負担の原則等を踏まえ、環境へ与える負荷、環境から得る恵み及び環境保全に寄与しうる能力等それぞれの立場に応じた公平な役割分担の下に、相互に協力・連携しながら、環境への負荷の低減や環境の特性に応じた賢明な利用等に自主的積極的に取り組み、環境保全に関する行動に参加する社会を実現する」ことを、長期的な目標の1つとして示している。
対策強化に係る明確な政策主体の意思表示が技術の革新を呼び、当初予想されていた困難を乗り越える場合がある。具体的には、ガソリン乗用車の排出ガスの昭和53年度規制に関する対応の例が挙げられる。この過程を振り返ってみると、科学的な技術評価に基づく明確な政策決定があったことが自動車メーカーによる技術開発競争を促進し、その結果、極めて困難な技術開発目標が達成され、ガソリン乗用車の排出ガスの大幅な削減が可能となったものと言えよう。
囲み序-3-4 53年規制の周辺
53年度規制に関しては、OECD(経済協力開発機構)が52年に日本の環境政策をレビューした報告の中で、当初に規制値の達成可能性について詳細な「検討が行われていたならば、基準は多分より緩やかなもの」になったであろうし、この経験は「技術が政策選択を制約するのではなく、政策選択が技術を制約するという考え方を支持するものである」と好意的に評している。
ただし、53年度規制の経験の理解に当たっては、“不可能と思われる目標でも、それを決めてから技術者を督促すればいつでも目標は達せられる”との誤解があってはならない。53年度規制は技術的に極めて困難な目標ではあったが、決して不可能な目標ではなかった。当時、実験室段階では目標を達成したシステムはいくつか存在しており、問題はその耐久性・信頼性等を向上させて実用化するための技術開発の時間にあったのである。科学的な技術評価に基づく明確な政策決定に基づき、自動車メーカーが総力を挙げて技術開発に集中したからこそ、早期の技術の実用化が可能になったと言えよう。
なお、53年規制に関し、輸入車の取扱いについてEC代表団との協議が開催された。EC側は、EC内の自動車メーカーの53年度規制に対する技術上の困難性などを説明し、適用期日についての格別の配慮を強く要請した。EC側が、日本におけるものと同様な研究開発を進めることが極めて困難な状況であることなどを勘案し、53年4月から3年間の猶予期間を置き、56年4月からの適用が決定された。我が国における規制制度がECにおける技術開発を促した側面があったことも記憶されるべきであろう。
環境問題の解決までに見られるタイム・ラグ(遅延)としては、以下の3点が考えられる。まず環境問題の認識に係るタイム・ラグである。環境の現状を正確かつ迅速に把握する行政の体制が整っていない場合、あるいは環境問題に対する関心が一般に低い場合など、当該環境問題が認識されるまでに時間がかかることが考えられる。このような場合、先に見たように速やかなデータ収集・解析を行い得る体勢の整備、積極的な普及・啓発策を通じた国民レベルでの環境問題に対する関心の向上などが重要となってくる。次に政策の決定までに要するタイム・ラグである。科学的知見の充実度や排出抑制技術に対する認識が一致しない場合等には、関係者の調整に時間がかかり、政策の意思決定までに相当程度の時間がかかることが考えられる。また、最近極めて短期間の内に世界的な問題となるものが増えていることから、環境保全に当たる組織は、こうした問題への対処能力を予め含んだものとして柔軟な組織を作ることが考えられる。そして3点目は、政策が実際に講じられてから、政策の効果が現れるまでのタイム・ラグである。地球規模での環境問題の場合、先に述べたように国際的に足並みの揃った対策を講じていくことが、このタイム・ラグを少なくしていく上で極めて重要である。
人類の経済活動が、予想もしていなかった環境問題を引き起こしてきた例は枚挙にいとまがない。また、これらの環境問題の中には急激に深化するものや、対策に極めて長い時間を要するものなどがある。現在、資源の適正な循環が行われなくなることで、環境への負荷が様々な場で生じており、循環全体を視野に入れた各種の対策を講じていくことが必要であることを学んだ。我々が直面している環境問題の多くは、人生80年時代の今日の我が国にあっては、ほぼ一世代で発生してしまった問題と言える。環境問題に関する予測の困難性や不確実性から、日頃より研究や監視に係る体制を充実させ、環境情報データ等の政策判断の基礎となる情報の収集・整備を地道に進めておくことが第一義的に重要となろう。環境政策の基本的な考え方としては、過去の経験に照らし、未然防止という観点を一層重視していく必要がある。また第2章において考察するようにリスク管理の考えを踏まえる必要があるものと考えられる。かつての公害問題などは五感によって認識できるものが比較的多かったが、今日の環境問題は、例えば地球温暖化問題など五感によってではなかなか認識が容易でないものになってきている。また、多数の化学物質の暴露による健康や生態系への影響については、種の存続に関わる生殖メカニズムへの作用が懸念されている。しかし完全に科学的な知見の充実を待っていては手遅れになる。地球温暖化の問題では、わからないことがあっても行動に迫られる場合があることも学んだ。IPCCにより世界の知見を集積し、コンセンサスを形成していく方法が採られたが、これは、後の温暖化対策に係る検討の場で高く評価されている。従って、未然防止や早期の対策のために、国民的な合意や国際的な合意の形成が重要である。環境問題の発生や影響に関する予測が困難であるからこそ、そのことを踏まえた考え方や仕組みの下で人々が知恵を絞り、将来を視野に入れて、現在から対策に取り組んでいくことが重要であろう。
我が国が激甚な公害を経験していた頃、各省に分散して行われていた環境行政を調整し、統一的に実施していくことの必要性が認識された。このため、「公害対策連絡会議」、「公害対策本部」などの組織面での試行を踏まえ、環境庁が創設され、環境行政の一元的な推進の組織的な基盤が整えられた。
今日の環境保全に関する施策の手法は、従来からの主たる行政手法である排出規制などの規制措置のみならず、環境影響評価、経済的措置、社会資本整備、環境教育・環境学習、事業者・国民の積極的な支援、科学技術の振興等広範多岐にわたっている。環境保全施策を効果的に推進するためには、こうした多種多様な施策を有機的連携を保ちながら進めていく必要がある。また、地球環境問題のように、長期間にわたる環境の変化が問題となり、対策の効果が現れるのに長期間を要するなど、長期的な視点で対策を考える必要がある。さらに、今日の環境問題の多くは、国民生活一般や事業活動一般に起因する部分が多く、こうした各主体の取組を総合的な視点で調節し、組み合わせ全体として効果が高まる形で促進することが必要である。
以上の認識から、国の環境政策はもとより、地方公共団体、事業者、国民に期待される取組をも含めて、環境の保全に関する施策を有機的連携を保ちつつ、すべての主体の公平な役割分担の下、長期的な観点から総合的、計画的に推進するため、平成6年、環境基本計画が策定された。
また、環境政策の効果的な推進を図るという観点からは、政策の責任主体において皆の取組の目標となる定量的な目標を設定することが有効である。定性的な目標を設定しても、その達成度合や政策の評価は困難を伴うことが多いものと考えられる。工場などの集積によって汚染物質の絶対量が増加しても、環境上の目標が欠如していると個々の発生源に対する規制強化が行いにくく、結果として、環境汚染が加速度的に進行して、かつ全国的に広がりつつある状況に対応しえなかったという事態がある。こうした事態を反省して、深刻化する公害を防止するため、諸施策の目標として、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音の4つの公害について環境基準が設定されることになった。これにより、政策の効果を把握することが容易になり、また客観的な外部からのチェックといった透明性を確保することができるものと考えられる。利害関係者との調整が困難を極めたような場合、成案を得たそのことで満足しがちであり、我が国では、決めさえすれば実行されるとの過信も見られるが、決めたことにこそ検証と改善が必要である。平成6年に策定された環境基本計画に基づく率先実行計画においては、数値目標とその進捗状況がチェックされ、現在見直しの作業が進んでいる。
さらに、専ら環境保全を目的とした施策以外にあっても政府で講じられる各種の政策には環境の観点が十分に盛り込まれていることが必要である。所管の省庁における積極的的な取組が期待されるほか、全体的な視点からその不足等がある場合は、これを補う仕組みを持つことが有効である。例えば、環境庁長官は、関係行政機関の長に対して、環境の保全に関する重要事項について勧告することができるが、これまでに3度実施された勧告では、緊急に対応を要する環境問題に関し、対策の目標に係る指針や指針達成のための方策まで踏み込んだ意見が示された。勧告を受けた関係行政機関はこれに基づき各種の対策を講じている。
囲み序-3-5 OECD環境保全成果審査
OECD(経済協力開発機構)においては、加盟国間で、お互いの環境政策の成果を審査する方法が進められている。これは、環境保全成果審査(EnvironmentalPerformance Review)と呼ばれるもので、1993年より行われており、我が国はパイロット被審査国として他国に先駆けて既に審査済みである。同審査では、加盟国における環境政策を主として公害関係、自然保護、経済(産業)との関わり、国際的な環境問題への取組、という分野毎に審査をしている。同審査では、当該分野において進展の見られた政策、さらに進展が必要な政策、そして必要な政策の勧告(recommendation)を行っている。2000年にすべてのOECD加盟国(現在29カ国)の環境保全成果の審査を終え、2000年より第二サイクルの審査が全加盟国に対して行われる。
新たな世紀まで1年と半年を残すところとなった。
20世紀の学習を経て人類の価値観と経済社会の在り方は、ひたすらに利便性を追求していたものから持続性の確保へと変わりつつある。別の言い方をすれば、環境的な合理性という、新たな時代の行動原理が、次第に輝きを増しつつある時期を我々は迎えているとも言えよう。それぞれの主体が、経済社会活動を持続的に行えるよう資源効率を高め環境負荷を最少限にとどめるなど、環境が人類にもたらす価値を重視した合理的な判断に基づいて行動すること、いわば、「環境合理性」を重要な行動規準の1つとして尊重していくことが、新たな世紀を迎えようとしている我々に求められている。こうした環境的な合理性を経済社会の各人の考え方に着実に根付かせ、経済社会の各部門における環境効率性が高まること、すなわち経済社会に環境保全の内在化が進むことにより、我が国において、ひいては世界において、環境と経済が真に統合され、持続的に発展をすることが可能な、新たな時代を迎えることができよう。
この白書は、以上のような20世紀の環境対策の教訓も踏まえつつ、「持続的発展が可能な経済社会は環境保全を社会の目的の1つとして組み込み、内在化させることで実現するのではないか」という基本的な考え方に立って21世紀に向けた政府の取組を紹介している。こうした基本認識から産業部門、国民生活そして国際社会へと視点を変え、それぞれの分野で注目すべき環境政策上の課題に焦点を当てて論じていくこととする。
まず第1章においては、経済活動、特に産業活動に焦点を当てる。近年の産業のグリーン化の実態と方向性を先進的な取組も交え整理してみたい。次いで地域の活性化と環境保全との両立を図ることのできる地域経済の形について考察する。さらに環境保全型の経済社会について将来像に関する考察を加え、最後に環境保全の内在化を進めるための事業者、国民、そして国の取組についてまとめてみた。第2章では、国民の生活行動に着目し、これまでの利便性追求の結果、ややもするとその環境へ十分な配慮がなされず、知らぬ内に驚くほどの環境負荷を発生させてきたことなどを改めて認識してみたい。さらに、昨今関心の高い内分泌かく乱化学物質等を含む化学物質について、これまで論じられている学説なども踏まえ、現状の概観を試みる。同章では、最後に国民が、環境に配慮した生活行動を行うに当たってそれを支える行政を始めとする各主体の役割を考察することで、社会全体から見た「環境保全上望ましい生活行動」像について考えたい。第3章では、開発途上国の環境の現状等を見る。アジア地域等の一部で伝えられている経済の危機的状況の陰で、ともすれば看過されがちな環境保全の問題はどうなっているのだろうか。また、これから積極的な環境外交が期待される我が国は、開発途上国に対してどのような環境保全面での協力ができるかといった点から考察してみたい。第4章では、環境問題を把握する上で基礎となる環境の現状を各種の調査結果から得られたデータを元に概観していく。