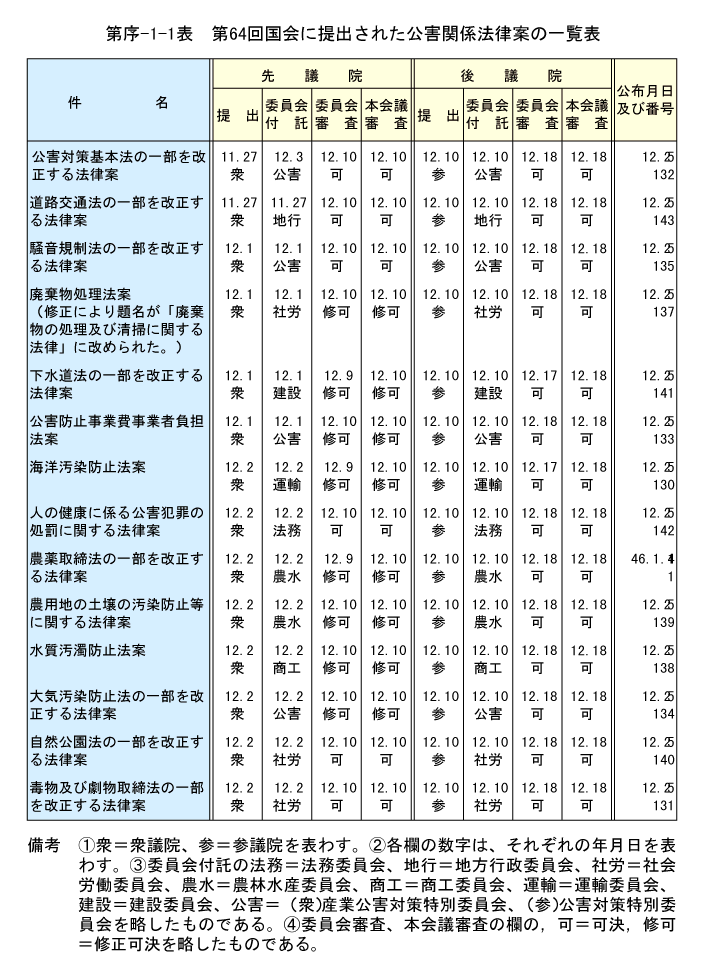
3 環境行政の体系化
(1) 地方公共団体における環境問題への先駆的取組
地方の問題として環境問題に直面し、住民の批判、運動の矢面に立たされた地方公共団体では、国における施策の実施に先立ち、自らの力でこれらの地域的課題に対処していかなければならなかった。昭和24年の「(東京都)工場公害防止条例」の制定をはじめとして、多くの地方公共団体において公害防止条例が制定された。しかし、その大部分は、定量的な基準によって排出規制を行うものではなかったため、実質的に環境汚染の進行を許すこととなった。
一方、公害防止協定の締結などの創意工夫を凝らして公害対策を進める地方公共団体も見られた。このような公害防止協定、要綱等は、公害対策上、法律、条例による規制を補完する働きをし、その数は30年代後半から40年代前半にかけて急増した。
一方、自然保護に関しては、この時期、条例による県立自然公園などの指定が盛んに行われるとともに、45年の北海道の「自然保護条例」の制定を皮切りに、各地で自然保護に総合的に取り組んでいくための条例が制定されるようになった。
以上のように、我が国の環境保全施策は一般的に、地方公共団体による先駆的な取組により開始されやがて国の施策を定着させることにつながっていった。
囲み序-1-1 最も古い公害防止協定
一般に我が国で最も古いとされる公害防止協定は、昭和27年3月の島根県が山陽パルプ(株)江津工場及び大和紡績(株)益田工場とそれぞれ結んだ「覚書」である。これは、工場の進出に際し、県等の技術指導により排水処理施設を設け、所期の水質を得るまでは本操業をしないこと、廃水による漁業損害が発生した時には、補償額の認定等につき県等の委員会の結論に従って補償をすること等を定めている。
(2) 国における公害対策と自然保護対策
国における公害対策の取組として厚生省では、30年8月「公害防止に関する法律案要綱」を関係省庁に示した。一方、通商産業省は、公害の発生源に対する規制として「産業の実施に伴う公害の防止等に関する法律案(仮称)要綱」を9月に提示した。厚生省では、公害の防止に関する法律案の検討をさらに進め、同年12月「生活環境汚染防止基準法案要綱」を作成公表したが、関係官庁等と調整がつかず国会提出は不可能となった。さらに厚生省は32年12月に再び同法律案の一部修正案を提示したが、結局この法案も日の目をみなかった。このように、公害対策の体系化については議論が分かれ、国としての統一的な対応は困難であった。
40年の48回国会においては、衆参両院に産業公害対策特別委員会が設置され、国会で初めて本格的に公害問題が議論される場が設けられ、早速同年、社会党と民社党はそれぞれの立案になる「公害対策基本法案」を提出するなど活発な審議が行われ始めた。
(3) 基本法の制定に向けた動きの高まりと「公害対策基本法」の制定
昭和30年代の国における公害対策は、「ばい煙の排出の規制等に関する法律」や「公共用水域の水質の保全に関する法律」等により、個々の発生源をそれぞれの観点から規制する方法によっていた。
しかし、これら問題の後追い型の対策は、必ずしも十分な対策とはなりえなかった。このため、公害発生源の直接の規制にとどまらず、計画的総合的な行政によって公害問題の根本的な解決を図ることが要請されるようになり、政府においては、39年3月の閣議決定により「公害対策連絡会議」が設けられ、基本法についての検討が進められた。地方公共団体や産業界をはじめ各方面からも、それぞれの立場からの提言がなされ、公害対策基本法の制定を望む声は支配的な世論となった。
公害対策の基本方針に関しては、公害対策と産業発展との関連について、「経済の健全な発展との調和」という考え方を公害対策全般に通ずる一般的配慮事項として規定すべきだとの主張がなされる一方で、健康の保持という面での公害対策においては、経済との調和という考え方は不適切という強い主張があった。最終的には、生活環境の保全に限って「経済の健全な発展との調和を図る」という考え方がとられるようになった。
環境基準の性格については、厚生省原案における「人の健康を保護し、生活環境を保全するために維持すべき基準」という考え方に対し、「維持すべき」という表現では、拘束性が強すぎるという意見が強く、結局環境基準は行政上の目標であることを明らかにすることとなった。
行政組織については、各省庁がそれぞれの権限に基づき個々の施策を推進すると同時に、政府全体としての公害対策の一貫性を保ち、総合的な調整推進を図っていくため、内閣総理大臣の主宰による閣僚レベルの会議を設置する方向で検討することになった。また、総合的な対策を具体化するものとして公害防止計画の規定を置く方向となった。このほか、無過失責任の問題、国と地方の役割分担、被害救済制度で多面的な議論が行われた。
42年2月、公害対策連絡会議は試案要綱を策定した。同試案要綱に沿って法案作成作業が進められ、5月「公害対策基本法案」が第55回国会に提出された。国会では、特に「経済の健全な発展との調和」についての議論が活発になされ、審議の結果、「経済の健全な発展との調和」の規定は、法案の目的から分離され、法案の目的規定の第2項に留意事項的に規定することとするとの修正がなされた。同法案は42年7月に可決成立し、同年8月3日に公布、即日施行された。
「公害対策基本法」の制定により、同法の規定、趣旨を受けて続々と法制等の整備が図られた。43年6月には、規制対象地域の拡大、自動車排出ガスの規制を目的に「大気汚染防止法」が制定され、「ばい煙の排出の規制等に関する法律」が廃止されるとともに、「公共用水域の水質の保全に関する法律」が改正され、規制対象の拡大などが図られた。また、新たに「騒音規制法」が制定された。更に、44年12月には、「公害紛争処理法」が制定された。
公害の防止を直接の目的とはしない関係法律においても、例えば、新「都市計画法」では、「都市計画は、公害防止計画に適合したものでなければならない」との規定を置くなどの整備がなされた。「公害対策基本法」の制定とそれに引き続くこれらの法制の整備により、ようやく公害法は体系的に整備され始めたのである。
(4) 環境庁の設置
ア 公害対策本部の設置と公害国会
「公害対策基本法」制定以後も、公害問題は、各種対策の効果を上回って激化した。45年7月31日には、閣議決定により「公害対策本部」が内閣に設けられることとなった。さらに、政府は公害対策本部の設置に引き続き45年8月、少数の関係閣僚からなる「公害対策閣僚会議」を発足させ「公害対策基本法」の全般的再検討の是非など公害対策の基本的な問題について検討を行った。また、公害対策本部の設置に伴い、同年8月、公害対策の実施は地方公共団体に深く関係することに鑑み、当面の緊急措置として地方公害対策本部の設置が地方公共団体に対し要請されることとなった。
45年11月末に開かれた第64回国会(臨時会)は、召集の主目的を公害関係法制の抜本的整備を図ることに置き、公害問題に関する集中的な討議を行ったことから「公害国会」と呼ばれた。その推進力となったのが公害対策本部である。同国会においては政府提出の公害関係14法案がすべて可決・成立した(第序-1-1表 )。その主な内容は以下のとおりである。
第1は、公害の防止に対する国の基本的な姿勢の明確化である。「公害対策基本法」をはじめとする公害対策の関係法から「調和条項」を削除し、経済優先ではないかという国民の疑念を払拭した。
第2は公害の範囲の拡大である。典型公害に土壌の汚染が追加されるとともに、水質の汚濁に「水質以外の水の状態、また、水底の底質の悪化」が明定された。
第3は、規制の強化である。例えば大気汚染、水質汚濁については、従来の指定地域制を改め、未汚染地域を含め全国を規制対象地域とするとともに、規制対象物質項目の範囲が拡大されるなどした。
第4は、自然環境保護の強化である。公害対策基本法において、公害の防止に資する自然環境の保護に関する政府の責務が明定された。
第5は、事業者責任の明確化である。「公害防止事業費事業者負担法」の規定により、公害防止事業についての事業者の費用負担義務が具体化されることとなった。
第6は、地方公共団体の権限の強化である。特に「大気汚染防止法」、「水質汚濁防止法」では、国の設定する全国一律の規制基準に加え、地方公共団体に上乗せの一層厳しい規制を行う権限があることを明定し、また基準遵守のための強制権限をほぼ全面的に都道府県知事に委嘱した。
こうして、公害関係14法の制定、改正が行われたことにより、法律の規定は抜本的に強化・拡充され、今日の公害規制の骨格が形成された。
公害対策本部は、短期間のうちに、当時危機的な状況にあった公害についてその対策の基本的枠組みをまとめることに一応の成果をあげた。しかし、公害対策本部は臨時的な機関であり、公害規制の立案権限、実施権限も各省庁に分散したままであったことから、公害対策を強力に推進していくための常設の行政機関を設置する必要があるとの認識が広まっていった。
自然保護行政の分野についても、自然破壊が現に進行していくことから、公害対策と併せて強力に対策を推進していくことの認識が高まっていた。
イ 環境庁の設置
環境庁の設置は、昭和45年末、 46年度予算編成の過程において、佐藤内閣総理大臣の裁断により決定され、翌46年1月8日の閣議で閣議了解された。この結果、環境庁は、環境の保全に関する行政を総合的に推進すべき任務を果たすため、その権限の面では、公害の防止に関し根幹となる事務については、その企画から実施までを含む一切の権限を一元化して所掌すること及び自然保護に関する事業の一部を実施する点において実施官庁であると同時に総合調整官庁としての性格を有するユニークな役所が誕生することになったのである。このようにしてまとめられた「環境庁設置法案」の大綱は46年1月26日の閣議で了承され、同法案は、閣議決定の上2月16日国会に提出され、同年5月31日可決成立し、7月1日環境庁が発足した。
環境問題の発生の原因又は現象機構の解明、防止技術の開発等の調査・研究は環境行政の不可欠な基礎をなすものであり、国が中核となってこれを推進する必要がある。このため、公害問題に関する総合的な研究機関として国立公害研究所が設置されることとなった。また環境行政担当職員等の資質向上が不可欠であることから、これらの職員等を養成するため環境庁の設置に際して公害研修所が設置(48年3月発足)された。
(5) 環境政策の進展
ア 大気汚染対策
37年には大気汚染防止に関する最初の法律である「ばい煙の排出の規制等に関する法律」が制定され、国としての対策が始った。さらに、42年の公害対策基本法の趣旨に基づき、硫黄酸化物に関する煙突毎の排出量規制(K値規制)や自動車排出ガスの許容限度の規定を導入するなどのため、大気汚染防止法が制定され、ばい煙規制法が廃止された。
45年の公害国会では、さらに、大気汚染防止法を改正し、指定地域制度の廃止、規制対象物質の拡大、地方の事情に応じた上乗せ規制の法的位置づけ、直罰制度の導入など、大幅な規制強化がなされた。
環境庁設置前夜になると、汚染被害の加害者が過失の有無にかかわらず損害賠償の責任を果たすべきであることを法律上明定する必要があるとの声が一般的になっていった。こうした期待を背に、環境庁は、無過失責任法の政府案をとりまとめ、同法案は昭和47年「大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律」として公布された。同法により、工場又は事業場における事業活動に伴って大気や水中に排出される有害物質が人の生命又は身体を害した場合には、事業者に過失がない場合であっても、事業者はその損害を賠償するという制度(無過失賠償責任制度)が確立した。この他、規制対象物質、規制対象施設の逐次の追加、規制基準の累次の強化、総量規制制度の導入などの規制の強化が積極的に進められた。
イ 水質汚濁対策
水質保護に関する法規制の我が国最初の動きは、昭和3年4月の水質汚濁防止協議会による水質保護法案にさかのぼることができるが、同案文は議会提出に至らなかった。戦後は、33年の「公共用水域の水質の保全に関する法律」及び「工場排水等の規制に関する法律」(この2法を併せて旧水質二法と呼ぶ。)の下、経済企画庁及び多数の事業所管省庁によって水質保全対策が行われていた。
昭和45年の第64回国会、いわゆる公害国会では、旧水質二法が廃止され、新たに「水質汚濁防止法」が制定された。これにより、全国で排出規制が行われることとなるとともに、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる恐れがある物質を排出する施設を政令で指定することにより、それらの施設を有する工場、事業場について規制の対象とし得ることとなった。また、環境庁の発足により、規制基準の設定権限が環境庁に一元化された。環境庁では、規制対象の拡大や排出基準の強化、新たな設定等に順次取り組んでいった。
このような努力により、有害物質による汚濁は顕著に改善した。しかし、有機物質による汚濁に関しては、高度成長の下での人口の都市集中、生活の高度化などにより改善効果ははかばかしくなかった。
ウ 土壌汚染、農薬対策
土壌汚染対策は、45年に制定された「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律」(以下「農用地土壌汚染防止法」と略称)により行われており、「農用地土壌汚染防止法」の施行を受けて、カドミウム及びその化合物が特定有害物質として指定され、客土事業などが行われていたが、環境庁発足後、特定有害物質として銅及びその化合物並びに砒素及びその化合物が追加され、対策が拡充された。
また、農薬汚染対策については、23年に制定された「農薬取締法」により行われており、46年の改正により、酸性砒酸鉛等が作物残留性農薬等に指定された。環境庁発足後には権限が一部環境庁に移管され、「農薬の作物残留に係る登録保留基準」を48年にキノメネチオート等3農薬について定めたことを皮切りに精力的に基準値の追加設定などが行われていった。
エ 騒音対策
公害に関する苦情件数のうちで最も多いのが、騒音に関する苦情であり、騒音は、国民に深い関わりを持つ公害である。騒音公害については、「工場法」(明治44年)や「市街地建築物法」(大正8年)によって部分的に規制が行われてきたが、戦後は、多くの地方公共団体において条例が制定され、これに基づき各種の対策が講じられてきた。しかし、急速な都市化、工業化の進展により騒音問題は全国的な問題へと発展し、昭和43年6月、工場騒音の規制と建設作業騒音の規制を柱とした「騒音規制法」が制定された。
自動車騒音については、45年の公害国会において、「騒音規制法」と「道路交通法」が改正され規制の対象とされたが、翌46年の環境庁設置により、環境庁長官が自動車1台ごとの騒音の大きさの許容限度を定め、運輸大臣が保安基準によりこれを確保することとなった。環境庁の下で、その後逐次許容限度の強化が行われていった。
航空機騒音については、46年に環境庁長官から運輸大臣に対し、環境庁設置法第5条に基づく初の勧告を行い、深夜の静穏の維持、騒音の大きさが一定限度を超える地域での緊急の対策を求めた。運輸省は、これに対応し、ダイヤ調整等を行うこととなった。さらに、環境庁は、48年に航空機騒音に係る環境基準を設定した。
新幹線騒音については、47年に環境庁長官から「環境保全上緊急を要する新幹線鉄道騒音対策について」運輸大臣に勧告を行ったほか、50年には新幹線鉄道騒音に係る環境基準を設定した。
以上のほか、飲食店営業等に係る深夜騒音、拡声機騒音については、「騒音規制法」において、営業時間等に関する規制措置を条例により講ずるものとしてしており、この規定に基づき条例化が進められている。
オ 振動対策
振動公害についても、古くは「工場法」、「市街地建築物法」等によって部分的に規制が行われてきたが、戦後は、多くの地方公共団体において条例が制定され、これに基づいて地域別に各種対策が講じられた。
振動問題は、都市における住居と工場の混在に加え、機械設備の大型化等に伴って全国的な問題となったが、測定方法等の技術的な問題があったため、「振動規制法」の制定は51年6月と典型7公害の中では最も遅かった。同法は、工場・事業場振動、建設作業振動および道路交通振動に対する規制を柱としており、騒音規制法と同様、都道府県知事等による地域指定制をとり、規制基準については、環境庁長官が定める範囲の中で、都道府県知事等が具体的な基準を設定する仕組みを設けた。
また、鉄道振動は、本法の対象とはされていないが、特に問題となっている新幹線鉄道振動対策については、51年、環境庁長官が、運輸大臣に対して「環境保全上緊急を要する新幹線鉄道振動対策について」の勧告を行い、これに基づき事業者において対策が講じられることとなった。
囲み序-1-2 環境庁長官による勧告
環境庁長官による最初の勧告は46年12月、運輸大臣に対して行われた。当時、ジェット機を中心とした航空運輸の増加に伴い、東京国際空港、大阪国際空港周辺では航空機騒音による被害が深刻な状況にあった。このため、環境庁長官は「環境保全上緊急を要する航空機騒音対策について」の勧告を行い、運輸省では、この勧告に基づいた深夜離発着の原則禁止、民家の防音工事及び移転補償の促進等の緊急対策を実施することとなった。翌年には、運輸大臣に対して「環境保全上緊急を要する新幹線鉄道騒音対策について」の勧告が行われた。39年の東京・新大阪間の開通以来、利用客が増大し、整備拡充が進められていた新幹線鉄道の列車の走行に伴って発生する騒音により沿線の一部で看過しがたい被害が生じている状況に対処することを狙ったものである。また、51年には、新幹線鉄道の列車の走行により発生する振動により沿線の一部で看過しがたい被害が生じている状況に対処すべく、「環境保全上緊急を要する新幹線鉄道振動対策について」運輸大臣に対して勧告がなされた。
なお、このほか、勧告には至らなかったものの騒音等の道路交通公害が各地で大きな問題となっている状況を踏まえ、52年12月、建設大臣に対して、「環境保全上当面講ずべき道路交通騒音対策に係る措置について」要請が行われた。
カ 悪臭対策
悪臭については、「へい獣処理場等に関する法律」(23年)や「清掃法」(29年)により、限られた発生源について間接的に規制されることがあったものの直接的な規制がなされていなかった。このため46年6月「悪臭防止法」を制定し、都道府県知事等による規制地域内の工場・事業場を総理府令で定める大枠の中で都道府県知事等が定める具体的な規制基準によって規制する仕組みが設けられた。なお、平成7年には悪臭防止法が改正され、以後規制地域毎に、政令で定める22の特定悪臭物質濃度か、人間の嗅覚を用いて測定した臭気指数のいずれかにより規制を行うことになっている。
キ 地盤沈下対策
地盤沈下については、31年制定の「工業用水法」と37年制定の「建築物用地下水の採取の規制に関する法律」の2法により地下水採取が規制され、地盤沈下の鈍化に一定の成果を上げた。さらに、56年には、地盤沈下防止等対策関係閣僚会議を設置し、地域の実状に応じた総合的な地盤沈下対策がとられることになった。同会議決定に基づき、地盤沈下を防止し、地域の実情に応じた総合的な対策を推進するため、60年には濃尾平野、筑後・佐賀平野について、平成3年には関東平野北部地域について、地盤沈下防止等対策要綱が策定された。
ク 廃棄物対策
廃棄物の処理は、腐敗しやすい生ごみを市街地に放置しておくと伝染病まん延の原因となるため、公衆衛生上の観点からの行政による処理として始まっている。昭和29年には公衆衛生保持の観点から、汚物の衛生的処理を市町村の固有事務とした「清掃法」が制定された。その後、昭和45年には、公衆衛生保持のみでなく、生活環境保全の観点から廃棄物の適正な処理を確保するため、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)が制定された。廃棄物処理法では、廃棄物を一般廃棄物と産業廃棄物に区分し、一般廃棄物の処理は市町村の固有事務、産業廃棄物の処理は排出事業者に義務付けるといった新たな廃棄物処理の体系がつくりあげられた。
ケ 公害健康被害補償予防対策
公害健康被害者の迅速かつ公正な保護を図るため、「公害健康被害補償法」が昭和49年9月1日から施行され、健康被害者の保護に大きな役割を果たしてきた。本制度は、民事責任を踏まえ、汚染原因者の費用負担により、健康被害者に対する補償給付等を行うものである。制度の対象となる疾病は、気管支ぜん息等のような原因物質と疾病との間に特異的な関係のない疾病(大気汚染が著しく、その影響による気管支ぜん息等の疾病が多発している地域を第一種地域として指定する。)並びに水俣病、イタイイタイ病及び慢性砒素中毒症のような原因物質と疾病との間に特異的な関係がある疾病(環境汚染が著しく、その影響による特異的疾患が多発している地域を第二種地域として指定する。)の2種類がある。
コ 自然保護行政
(ア) 自然公園行政
自然公園行政は、昭和6年の国立公園法の制定に始まり、我が国の自然公園制度は、土地所有関係にかかわらず民有地についても公園区域として指定し、風致景観を保護する観点から一定の行為について規制を行うといった他国にほとんど類を見ない「地域制」といわれる方式がとられた。32年には、国立公園法を改めて自然公園法が制定され、国立公園、国定公園、都道府県立自然公園の3種類の自然公園からなる総合的な自然公園制度が確立された。しかし、高度経済成長の流れの中で次第に目立ち始めた地域開発や観光開発による施設建設の進展に伴い、自然公園の過剰利用などの問題が生じ、自然公園行政には一層厳しい対応が迫られるようになった。
自然公園の健全な利用に関しては、22年から施設整備が開始され、順次、国立公園内、国定公園内で都道府県の行う公共施設設備に対する補助制度がそれぞれ創設された。また、30年代から40年代にかけて到来したレジャーブームの時期、公共の保養施設の整備も進められた。
自然保護教育については、早くから取組がみられた。20年代から自然研究路等の施設を活用した「自然観察会」などの野外活動が行われてきた。30年代には、国立・国定公園内においてビジターセンターが設備され、利用者へ自然解説などを行うボランティアとしての自然公園指導員制度も導入された。40年代には「長距離自然歩道」や「野鳥の森」の整備も始められた。
環境庁発足に伴い、自然保護行政の強化と組織の一元化、公害行政との緊密な連携を図る観点から、厚生省国立公園部が所管していた自然公園行政が環境庁自然保護局へ移管された。47年6月に国土全般にわたる自然環境の保全の基本方向を明らかにすることなどを内容とする「自然環境保全法」が制定された。同法に基づき、国は、自然環境保全基本方針を決定し、環境庁においては、自然環境保全基礎調査の実施、自然環境保全地域等の指定を行った。
(イ) 国民公園行政
皇居外苑、新宿御苑及び京都御苑については、昭和22年の閣議決定に基づき、平和的文化国家の象徴としてこれを永久に保存することと広く国民の利用に供することを目的として皇室苑地から国民公園へと移管された。これらの国民公園の由緒ある沿革を尊重し、努めて現状の維持保存を図るとともに、無名戦士の墓苑として国が設置した千鳥ヶ淵戦没者墓苑と併せて、それぞれの特性を生かした整備運営を行うことを内容として国民公園行政が開始された。環境庁の発足とともに国民公園は同庁に移管され、これらの公園は、引き続き厳しく維持管理が行われ、都市化の著しい進行により自然が失われつつあった都市部において、貴重な緑のスペースとして広く親しまれている。
(ウ) 温泉行政
我が国の温泉は、経験的に病気に効くということで古くから療養を目的とした湯治場として利用され、保養地としても広く親しまれてきた。昭和23年には、温泉源の保護と適正な温泉利用の推進を目的とする温泉法が制定され、同法に基づき、乱掘による温泉の湧出量の減退等を防止するための掘削規制、温泉の浴用、飲用等の衛生的利用の適正の確保等が図られることとなった。また、同法の環境庁への移管後には、温泉の公共的利用増進のため、温泉利用施設の整備及び環境の改善に必要な地域として指定する温泉地を「国民保養温泉地」という名称に統一し、温泉地及び施設の整備が進められている。
(エ) 鳥獣行政
鳥獣保護の面では、行政の重点は狩猟の安全対策から鳥獣の保護中心へと移行し、昭和25年に鳥獣保護区制度を創設、さらに「狩猟法」(明治28年)の名称を、昭和38年に「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律」に改め、目的として鳥獣の保護繁殖を明記し、禁猟区制度を廃止して鳥獣保護区制度に統合し、鳥獣保護区特別保護地区や休猟区の制度を設ける等の改正を行った。
(オ) 国際協力による野生生物保護の萌芽
日本の野生生物に係る国際協力の原点は、渡り鳥の保護を対象とした二国間条約に求められる。昭和47年(1972年)の3月に署名された日米渡り鳥等保護条約は、渡り鳥の保護について規定しているほか、いずれか一方の締約国が絶滅のおそれのある鳥類を決定し、その捕獲を禁止し、その決定を通報した時は、相手方の締約国が当該鳥類又はその加工品の輸出入を規制することによって両国の対象鳥類の保護を図ろうとするものである。その後、48年(1973年)に日ソ間で渡り鳥等保護条約が、49年には日豪間で渡り鳥等保護協定が、56年(1981年)に日中間で渡り鳥等保護協定が署名された。
サ 環境教育の胎動
46年の環境庁発足あたりから、環境保全一般に関する国民の理解と意識の啓発の必要性が認識されはじめ、48年には前年に開催された国連人間環境会議を記念して、6月5日を初日とする「環境週間」が設定された。これは、「環境月間」へと発展し、環境保全の認識向上等に資する環境月間行事が官民様々な主体により開催されている。
48年には、自然環境保全法に基づく自然環境保全基本方針が閣議決定されたが、この中で「学校や地域社会において環境教育を積極的に推進し、自然のメカニズムや人間と自然との正しい関係について国民の理解を深め、自然に対する愛情とモラルの育成に努める」との方向が示されている。また、翌49年には、自然環境の保全を求める国民運動の成果として自然保護の重要性を訴えた自然保護憲章が制定された。
また、学校教育においても昭和52年の学習指導要領の改訂に際して、理科、社会科などの教科において、環境教育の重要性に配慮されるなど、いわゆる公害教育に加え、広く環境教育へと内容の充実が図られた。