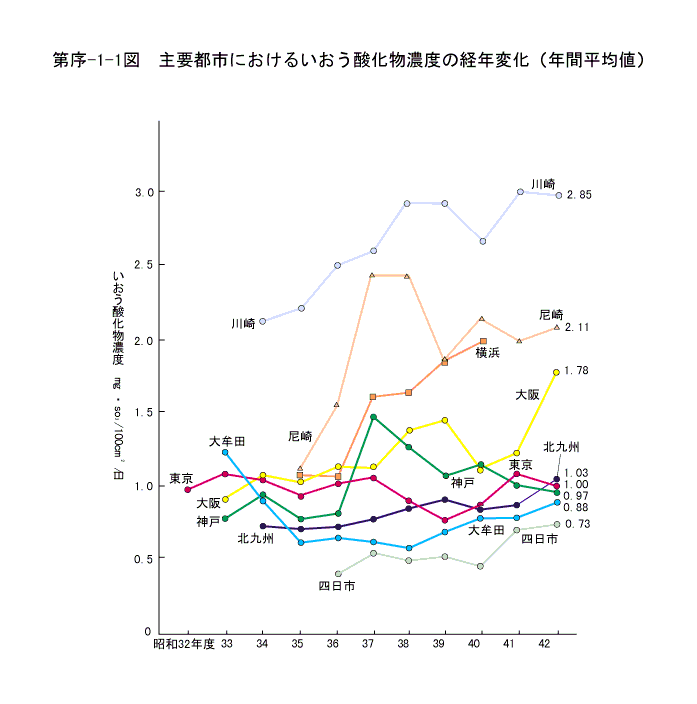
2 高度成長期の環境問題の変遷と対策の系譜
(1) 高度経済成長政策の環境上の帰結
何物をも戦争遂行につぎ込んだ挙げ句、日本の都市は焼土となり、多くの山は木を失って、ようやく終戦を迎えた。ところが、長い間の軍国主義の重圧から解放されたとはいえ、経済運営に当たっての環境上の配慮はやはり乏しかった。戦前の深刻な公害経験が反省として生かされず、公害行政の成果も引き継がれなかった。経済の復興がまず最優先されたからである。
その後、日本経済は、成長の歩みをますます早めた。30年代前半に8.8%だった実質経済成長率は、同年後半9.3%、40年代後半が12.4%としり上がりに上昇した。我が国経済の成長経路は、輸出と産業を高度化させるための設備投資とによって導かれたものであった。このため、生産設備などの中間財や輸出製品を製造する重化学工業のシェアが高まった。それに伴って、GNP1単位あたりの汚染負荷量も高くなり、汚染物質の発生量は経済成長率以上のスピードで増えていったと考えられる。
経済の重化学工業化に伴う汚染負荷の増大に加え、当時の政策も、結果としてみれば、環境への重圧となった。
高度成長対策は、経済活動の隘路となる様々の障害を取り除き、成長力を遺憾なく発揮させることを狙いとしていた。例えば、限られた予算に依存している政府資本形成は道路などの産業基盤整備に振り向けられ、下水道、廃棄物処理、都市公園などの生活環境整備には乏しい予算配分しかなされなかった。例えば、高度成長の末期の45年度の公共事業費のうち、約半分が産業関連事業で、生活環境関係事業は公共事業費の約5%程度にしか過ぎなかった。これが公害の拡大を防ぎ得なかった一つの原因となった。
さらに、地域間の経済発展の不均衡も問題となった。このため、37年には、全国総合開発計画が策定され、工場の地方分散、拠点における集中的な地域開発が方針とされた。この政策に沿って、いくつかの地方では、最新鋭のコンビナートなどが立地した。工場を誘致するための経済的な優遇策なども用意されたがそれらがもたらす公害問題に対する対応が十分になされなかったため、公害は、地方の工業都市にも広がり、産業規模の増大と共に深刻の度を加えていった。
(2) 高度経済成長下における環境破壊の進行
ア 水俣病、イタイイタイ病の発生
今日、我が国の公害問題の原点と言われる水俣病は、熊本県水俣市の風光明媚な不知火海に面した漁村で発生した。チッソ株式会社の前身である日本窒素肥料(株)が明治41年に水俣工場を建設して以後、水質汚濁が始まった。昭和20年代後半には、水俣湾の魚が海面に浮きだし、カラスや水鳥が空から落ち、ネコが狂死し始めたと言われている。このような中で、31年5月、水俣保健所に脳症状を主とする原因不明の患者の入院が報告され、この時点が水俣病の公式発見と呼ばれている。水俣病は、工場排水によって汚染された海域に生息する魚介類を食用に供することによって魚介類に蓄積された有機水銀が人体に取り込まれ、その結果起こる中枢神経系の疾患であり、当時の状況のおそるべき悲惨さゆえに世界に知られることとなった。水俣病は、40年頃、昭和電工株式会社鹿瀬工場の排水を原因として、新潟県阿賀野川流域でも生じた。(新潟水俣病)
一方、富山県神通川流域においては、大正時代からカドミウム、鉛、亜鉛等の金属類が神通川の水とともに水田に流れ込み、農業被害が発生していた。イタイイタイ病は、長年にわたり原因不明の特異な地方病として同川流域の富山県婦負郡婦中町及びその周辺に発生していたものの、学会に報告されたのは昭和30年が初めてである。イタイイタイ病の症状は、その名からも察せられるように、身体各部に耐え難い痛みが起こり、正常な歩行が妨げられ、病勢が進むとつまずいただけでも骨折を起こした。
イ 大気汚染の深刻化
30年代の飛躍的な経済成長により、我が国のエネルギー消費量は10年間で約3倍になり、また、エネルギー源も石炭から石油へ転化していった。このため、大気汚染も粉じんを中心としたものから硫黄酸化物を中心とした汚染に形態を変化させつつ広域化していった。とりわけ、30年代以降各地で進められた石油コンビナートの形成は、硫黄酸化物による広域的な大気の汚染や悪臭、水質汚濁などの問題を引き起こした。
かくて、わずか37万平方キロメートルの国土の各地に重化学工業地帯を擁することとなった我が国は、工業国として知られる一方、「公害列島」の汚名でも知られることとなった。
30年頃から我が国最初の石油コンビナート型開発が進められた三重県四日市市では、30年代半ばに煙突から排出されるばい煙により、住民の間では涙をこぼしたり吐き気を催したりする被害が続出したほか、いわゆる四日市ぜんそくや悪臭魚問題などが社会問題化していった。千葉県の京葉コンビナート、岡山県の水島コンビナートなどの新設工業地帯においても30年代後半から40年代にかけて四日市と同様の道をたどることとなったほか、川崎、尼崎、北九州など戦前からの工業地帯では事態はさらに深刻であった(第序-1-1図 、第序-1-2図 )。一方、45年頃から毎年夏になると光化学スモッグが発生し、目や喉の痛み、頭痛、しびれ、吐き気などを届け出る被害者が多数出た。この年、被害届は約1万8000件にのぼった。
ウ 水質汚濁、地盤沈下等の深刻化
昭和40年代に入ると、以前は局地的な事件にとどまっていた公害事象が、その要因や被害の態様においても、また、地域の広がりにおいても比較にならないほど広範なものへと変化していった。河川、湖沼、沿岸海域等の公共用水域についても、当時の高度成長、地域開発の進展に伴い、水質の汚濁が著しくなっていった。
例えば、瀬戸内海における赤潮の発生状況の推移を見ると、年を追うごとに地域的な広がりを見せている。瀬戸内海における赤潮は、25年から30年頃までは、大阪湾の北部、広島湾奥の一部など、いずれも局地的なものであった。ところが、40年頃になると広域化の傾向が急速に進むとともに、発生件数も年間40件を超え、45年においては、伊予灘ほかごく一部を除き瀬戸内海のほぼ全域に発生がみられるまでになった。かつて白砂青松と謳われ国立公園に指定され、水産資源の宝庫と言われた瀬戸内海も、大量の漁業被害を発生させるに至った。
このほか、地盤沈下については、戦前よりその発生が認められていた。戦災を受けた20年代前後には一時停止していたが、25年頃から水需要の急激な増加に対し、水資源開発等が遅れ、地下水の使用量が急増したため地盤沈下は再び激しくなり、その地域も拡大していった。30年代以降になると、以前から沈下の進んでいた関東平野南部、大阪平野に加え、関東平野北部、濃尾平野、新潟平野、筑後・佐賀平野などの全国各地で地盤沈下が認められ、東京都江東区では明治期に始まる観測開始以来の累積沈下量が4.5メートルを記録するに至った(第序-1-3図 )。
さらに、新たな汚染物質が複雑な汚染経路を経て、これまで経験したことのない環境汚染をもたらした例として、PCB問題をあげることができる(第2章)。
(3) 公害反対の世論の高まりと住民運動
経済の高度成長の過程における環境問題の多発に伴い、一般市民を含めたいわゆる「市民パワー」が現れた。33年の江戸川の製紙工場排水による漁業被害をめぐる漁民と工場との乱闘事件は、水質汚濁対策が促進される契機となった。このほか、38年から39年にかけて三島・沼津地域で起こったコンビナート建設反対運動は、これまでの農漁民対企業という従来の公害紛争の型を超え、広く一般市民の関心を集めた。高度経済成長政策の主要な柱である臨海コンビナートの立地が計画段階で公害問題を理由に中止されたことは、国や産業界、地方公共団体に大きな衝撃となった。
一方、自然破壊に反対する人々の動きも次第に活発化していった。30年代に入って国民生活が安定してくるにつれ、都市住民の間にすぐれた自然とのふれあいを求める気持ちが高まる一方、急激に過疎化が進行した農山村地域では、観光開発が進められた。しかし、道路建設などのこれらの観光開発は、自然保護に対する配慮の不十分さ、施工技術の遅れ等により自然破壊をもたらすとともに、自動車の排出ガス等による2次的な自然破壊を引き起こすことにより、結果的には自然の利用者に深い失望を与えることとなった。富士スバルラインや石鎚山スカイライン等は批判の対象となった例であり、こうした批判を背景に尾瀬道路主要地方道沼田田島線等は工事の中止や路線の変更に至った。
昭和45年は「公害メーデー」などの全国規模の公害反対運動がおこり、「公害国会」が開催されるなど公害に明け、公害に暮れた一年であった。 この年から世論は経済成長に対する評価を一段と厳しくし、公害反対の旗色を鮮明にした。この年のNHKの世論調査では、「公害や物価上昇をもたらし、国民生活が一部の企業や産業の犠牲になってきた」として、経済成長を否定的に捉える人が初めて55%と過半数を超えた。また、国民の批判は、行政にも向けられていた。公害国会が開催されるなど、政府の公害に対する取組が徐々に本格化してきたにもかかわらず、56%の人が政府の公害対策への取組を積極的でないと受け取っており、政府は「何もしていない」と決めつける人も17%を数えた。
46年の総理府の世論調査では、工場全部の排出物を厳しく規制するという考え方に対して90%の人が賛成したことにも見られるように、公害対策の強化は、国民の一致した世論となるに至った。