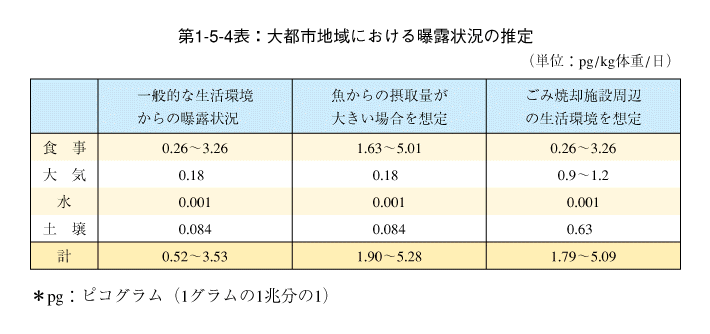
3 化学物質の環境リスク評価の推進
(1) 化学物質の環境リスク評価
現在、我が国で約5万種以上流通していると言われる化学物質の中には、発がん性、生殖毒性等多様な毒性を持つものが多数存在し、これらが、大気・水等様々な媒体を経由して人や生態系に影響を与えている恐れがある。
こうした影響を未然に防止するためには、多くの化学物質を対象に、それらが環境中を通じて人や生態系に有害な影響を及ぼすおそれ(環境リスク)の評価を行い、その結果に基づき適切な環境リスク対策を講じていく必要がある。これまで、我が国の環境リスク評価は体系的に行われてきていないが、国際的には環境リスク評価の推進が急務とされ、国際協調のもと、早期に評価を実施していくことが求められるなど、環境リスク評価体制の整備が不可欠となっている。
このため、環境庁は、平成9年4月、環境リスク評価室を設置し、適切な環境リスク評価の推進を図ることとした。
(2) ダイオキシン類のリスク評価の概要
平成9年5月、環境庁が設置したダイオキシンリスク評価検討会は、ダイオキシンのリスク評価について、報告書を取りまとめた。
この報告書では、動物実験におけるダイオキシンに係る一般毒性、発がん性、生殖毒性、催奇形性等のデータ、人に対する影響についての疫学調査の結果、発がん性に関する国際がん研究機関(IARC)の評価等の情報をもとに有害性を評価した結果、環境保全対策を講ずるに当たっての目安として、健康リスク評価指針値5pg/kg/日を設定した。この値は、人の健康を維持するための許容限度としてではなく、より積極的に維持されることが望ましい水準として人の暴露量を評価するために用いる値である。
また、我が国におけるダイオキシン類に係る暴露の推定量は、健康リスク評価指針値と同程度以上となることがあり得るため、今後、健康リスクを小さくする観点から、ダイオキシン類の環境中の低減を図る必要があるとされた。(第1-5-4表)
なお、厚生省厚生科学研究班においては、平成8年6月に、人が一生涯にわたり継続して摂取しても健康上、問題がないとされる耐用一日摂取量(TDI)として10pg/kg/日が提案され、この数値に基づき各種の健康上の施策が講じられたところである。