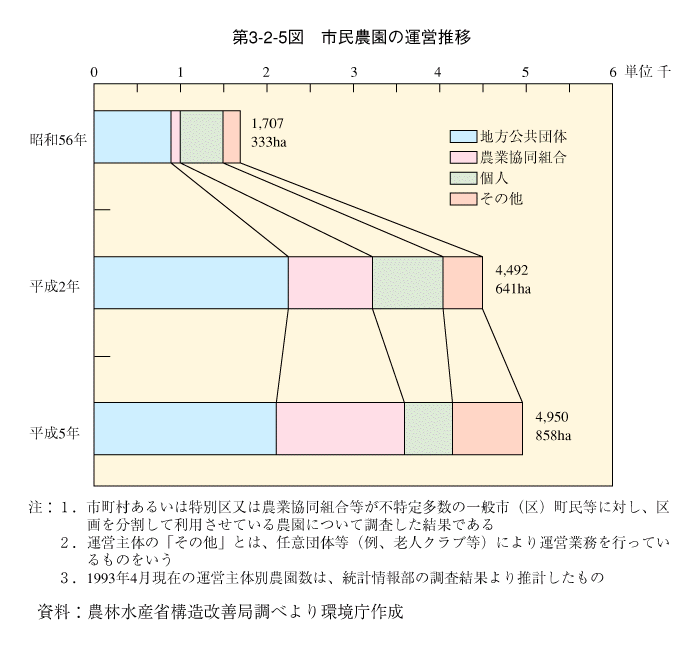
2 自然とのふれあいを生活に取り込む意識
近年、余暇時間の増大や環境に対する国民意識の向上などにより、自然とのふれあいの欲求が高まっている。
(1) 余暇での自然とのふれあい
平成8年11月に総理府が行った「自然の保護と利用に関する世論調査」によれば、「今よりもっと自然とふれあう機会を増やしたいと思うか」という質問に対し、「大いに増やしたいと思う」、「もう少し増やしたいと思う」と答えた人が6割を超えた(第3-1-1図参照)。また、「自然とふれあう機会を増やす方法」については、「自宅や勤務先などの周辺に、身近な自然を残したり、増やしたりする」、「身近な自然の中で気軽に利用できる歩道を整備する」、「公園や緑地の整備を推進する」、「地方に残る自然を国立公園などにして保護する」、「自然とふれあうための行事や企画を増やす」、等の各項目について、20%台から30%台の回答となっており、自分たちの生活の周りにある身近な自然から国立公園などのすぐれた自然まで、それぞれの段階でのふれあいの機会を望んでいることが推察される。こうした意識を裏付ける現象が起こっている。近年のRV(レクリエーショナルビークル)の好調な売れ行きに代表されるアウトドアブームや、中高年者層の登山、ウォーキングブーム、小中学生を中心にした釣りブームが挙げられる。また、近年都市住民を中心に市民農園が人気を集めている。農林水産省構造改善局の調べでは、市民農園の運営推移を見ると、昭和56年から平成5年の間に農園数は約2.9倍、面積は約2.6倍に増えている(第3-2-5図)。
これらの現象は単なる一過性の流行ではなく、自然とふれあいたいという人々の意識が余暇活動に現れたものではなかろうか。現代においては、余暇活動の中で積極的に自然とふれあう機会を得ようとしている。
囲み3-2-1 「レジャー白書」にみる余暇の自然志向
(財)余暇開発センターの発行する「レジャー白書」(平成9年版)では、20〜30代のオートキャンプや中高年層の登山、園芸など、自然に親しみふれあう形態のレジャーを望む声が多く見られる。
(2) 高まる身近な自然環境への関心
総理府が行った世論調査では、身近な自然に対する関心の高さも現れた。「自分が住んでいる周辺は、自然に恵まれていると思うか」との問に対し、8割近くが「恵まれている」と答えている。その地域差は大きく、大都市部においては約5割であるのに対し、小都市部や町村部では8割を超える。
次に「自然に恵まれていると思う理由」についての質問には、「四季の変化を感じさせる田畑がある」という回答が7割近くに上っている。以下、「魚釣りや水遊びのできる池、小川、海浜などがある」、「子供が遊んだり、虫取りができる原っぱなどがある」などと続く。
「住まいの周辺にもっと自然があった方がよいと思うことがあるか」という問に対しては、8割の人が「もっと自然があった方がよいと思うことがある」と答えており、あった方がよいと思う自然については、「子供が遊んだり、虫取りができる原っぱ」と答えた人が3割近くいた。
また、「自然保護に最も力を入れるべき地域」については、「メダカやホタルなどの昆虫・小動物が生息している地域」を挙げる人が3割を超えており、特に地方都市部や町村部でその傾向が強い。次いで「都市内の自然が残っている地域」を挙げる人が2割以上おり、これは大都市圏で3割を超えている。つまり、大都市部の住民も町村部の住民も、自分たちの生活圏内にある身近な自然を保護していく必要性を感じていることが推察される。
囲み3-2-2 谷戸の自然が保育園〜神奈川県鎌倉市「なかよし会」〜
「谷戸(やと)」とは、「やつ」【谷、谷津、矢津】と同じく、低湿地を表す地形用語である。神奈川県鎌倉市周辺はこの谷戸地形に恵まれ、古くから水田(谷戸田)などの農耕地として利用されてきた。市内には現在も「扇が谷」等、「谷」の付く地名が存在している。そのうちの一つ、通称「山崎の谷戸」の自然を丸ごと利用して自主保育を行うグループが「なかよし会」である。
「なかよし会」の保育は昭和60年に始まり、現在では、週3回、1・2歳児の組と3歳児の組に分かれ、保育者や当番の親による保育を行っている。自分たちの身近にある自然の中で遊ぶことにより、豊かな感性とたくましい精神力を育んで欲しい、という考えから、既存の公園や道具はなるべく使わない。子どもたちは藪の中を歩き、土の斜面をよじ登り、泥だらけになりながら友だちと遊ぶ。四季の変化を五感で体験し、時には生き物の死に直面する−こういったことを日常的に経験することにより自然との、人とのふれあい方を身につけていく。親たちもまた、保育を通じてこの谷戸の豊かな自然を再認識することとなった。「山崎の谷戸を愛する会」を発足させ、稲作農家の手伝いや炭焼き、わら細工などの作業に取り組むようになったのである。
かつての谷戸は、田畑や雑木林という生産の場として利用され、また、身近な生物の宝庫としての機能を果たしていたが、高度経済成長期以降、谷戸における農業は経済的に成り立たなくなり、多くは宅地開発された。しかし、身近な自然が見直されている今日では、山崎の谷戸は貴重な存在となっている。