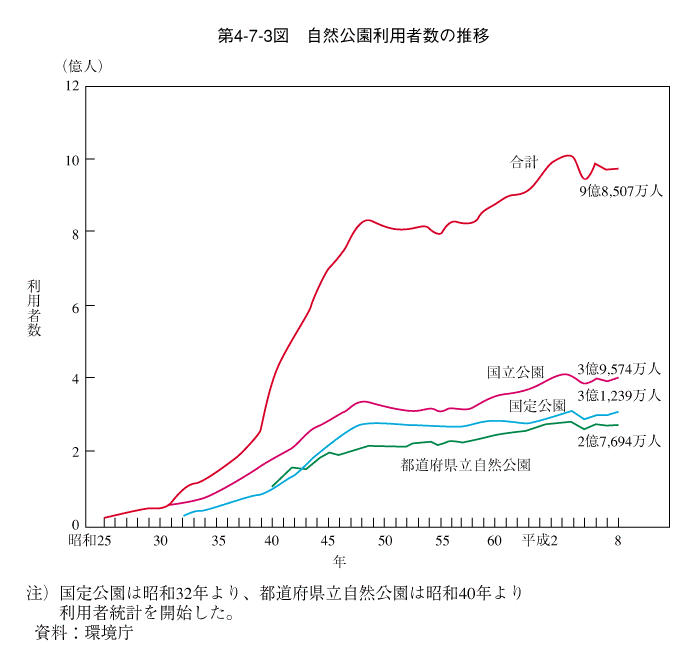
3 自然とのふれあいを生活の中へ
余暇活動における自然とのふれあいは、人間性の回復、自然に対する豊かな感性の醸成など、今日の都会化された日常生活を送る多くの国民に必要なものである。また、身近な自然に触れることは、精神的に豊かな生活を送るための要素として重要である。
さらにそれらの体験を通じて、自然に対する豊かな感性を育て、環境と人間活動について考察し、環境問題を自分自身の問題として捉え、その解決を図りうる人材を育てるような機会としても重要である。
また、自然とのふれあいの機会は、身近な自然から自然公園まで、多様な場所で得られ、全国の各地域の自然環境と人間の関わり方それぞれの特長に応じたふれあいの推進が必要である。
(1) 自然公園を利用したふれあいの推進
すぐれた自然を有している我が国の自然公園をふれあいの場、あるいは環境学習の場として利用することは、自然のメカニズムや自然と人間との関係についての理解を深めるのに役立ち、積極的に推進する必要がある。
ア 自然公園の役割
自然公園利用の特徴としては、?より原生に近い、人の意思で制御できない自然の世界にふれることにより人間性の回復を図る、?自然公園でしか体験できない原生自然、野生動物との出会いなど、代替性がない体験が可能なことである。ここでは、自然の持つ「美しさ」、「偉大さ」、「荘厳さ」、「野生」等をそのまま直接的に体験し、感動や喜びを得る利用が最優先されよう。
また、利用の場が原生自然を含む、微妙なバランスの上になり立っている地域であることを考える必要がある。良好な自然を保護することが大前提であり、環境容量を考慮に入れた持続可能な利用の仕方が必要となってくる。一方でアウトドア活動の利用についても、適地適利用の考えにより、野放しでも完全排除でもなく、地域を限定しつつ棲み分けさせることが必要ではないだろうか。環境教育・環境学習の手段としても積極的に活用していくことが望まれる。
イ 自然公園の利用状況
我が国の自然公園の利用者数は増加傾向で推移している(第4-7-3図参照)。特に昭和60年代以降、「リゾートブーム」の影響により自然公園を訪れる人は増加した。過疎や第一次産業の不振にあえぐ地方にとっては地域活性化の手段として、全国各地で大規模リゾート施設の整備計画が次々に打ち出され(第3-2-6図)、リゾートマンションやホテル、ゴルフ場、マリーナ等の施設建設が位置付けられた。開発計画地と自然公園が重なる地域においては特に自然環境への影響が懸念された。
しかし、バブル経済の沈静化以降、大規模開発は一応の落ち着きを見せ、最近ではその地域の自然環境や文化・生活といった既存のものを生かすような、いわば「身の丈にあった」開発へと移行する傾向が見られる(第2章第4節参照)。また、その地域の自然環境を損なうことなく、地域の自然や文化を学び、ふれあう旅行の形態(エコツーリズム)といった、その地域の自然環境や文化を様々な活動を通じて学ぶこともできる形の余暇活動・旅行形態が注目されている。
ウ ふれあいの機会づくり
(ア) 環境庁の施策
環境庁では、従来からビジターセンターの整備事業等、自然とのふれあい推進の事業を行ってきた。平成7年7月に出された自然環境保全審議会の「自然公園における自然とのふれあいの確保の方策について」の答申を受けて、平成7年度から「自然公園核心地域総合整備事業(緑のダイヤモンド計画)」を実施している。また、子どもたちが自然にふれあい、学ぶことのできる「エコミュージアム整備事業」を進めている。
平成9年度からは「ふれあい自然塾整備事業」及び「ふれあい自然塾活動推進事業」という、国立・国定公園の中で、自然の中での暮らし、学び、冒険などを体験する施設の整備と、併せて参加型自然体験学習プログラムの策定を進めている(第3-2-7図)。また、自然塾の友の会ともいえる、「自然大好きクラブ」が平成9年8月に設立された。現在、自然ふれあい活動などの情報が入手できる体制を整備中である。
(イ) (財)国民休暇村協会の活動
(財)国民休暇村協会では、各休暇村施設を環境教育・環境学習の拠点として活用させる構想を進めている。国民休暇村は平成10年3月末現在、全国で35カ所が低廉な料金で快適な宿泊施設を中心にレクリエーション施設等を提供している。そのいずれもが国立・国定公園内の自然環境に恵まれた場所に立地していることを積極的に活かして、施設周辺における自然体験行事等の実施や修学旅行での多彩な自然とのふれあい等を組み込んだ環境学習を進めていくためのプログラムの開発などを行っている。
エ 自然とのふれあいを担う人材
(ア) 自然利用に関わる人材
我が国の自然公園において自然解説(インタープリテーション)を行う指導員など、自然の利用に関わる人材は、第3-2-1表のとおりである。国立公園管理官(レンジャー)は環境庁職員であり、11の国立公園・野生生物事務所に44の管理事務所があり、167人が勤務している。
また、パークボランティア(管理事務所長委嘱、約1,700人)や、自然公園指導員(環境庁自然保護局長委嘱、3,000人)といった人材を育成し、国立・国定公園での利用者指導、自然解説活動を行っている。
民間団体においても、(財)日本自然保護協会認定の自然観察指導員制度や(財)日本野鳥の会のサンクチュアリボランティア、(財)国立公園協会派遣のサブレンジャー(尾瀬、箱根、立山、大山などで活動)などがあり、それぞれ指導者の養成と全国規模での自然解説、観察活動に活躍している。
現在、我が国においても自然解説指導者の役割が重要視されてきており、その活動の場も拡がってきている。しかし現状ではその数は充分とは言えず、今後は国、民間団体、ボランティアそれぞれにおいての人材育成が必要である。
(イ) 利用者の意識向上
アウトドア活動を行うために自然公園を利用する人々への指導・解説も重要である。アウトドア活動は、ともすればその行為自体が大きな自然破壊につながる恐れがある。最近の余暇活動のアウトドア志向の中で、自然公園内での環境汚染の問題が多く取り上げられるようになった。アウトドア活動とは本来、自然の中に入り、人間の力の及ばない自然の力、風、波、雨などの気象条件や、越えがたい岩陵、闇、静寂といった、いわば「自然の摂理、自然の時間」の中で、自然の偉大さ、すばらしさ、あるいは恐ろしさを体感し、自然とつきあう知恵を修得するものであろう。そこに「人間の都合、人間の時間」を無思慮に持ち込めば、微妙な生態系に影響を与えてしまう。
このような利用者のマナー向上対策には、国などの行政機関だけでなく、愛好者団体等の自主的・積極的活動が重要である。最近のアウトドア雑誌では、自然に負荷のかからない形での活動を特集するなど、愛好者自身の取組姿勢が見られるようになった。また、南アルプス国立公園では、「南アルプス倶楽部」というNGOが、南アルプス北部周辺の自然保護活動や登山者指導を行っている。この一帯は「種の保存法」によって貴重種に指定されたキタダケソウを始め貴重な高山植物が自生しており、盗掘や登山道を外れた場所での踏みつけ被害など、登山者のマナー如何で自然環境が破壊される恐れがある場所である。同会では環境庁と地元の芦安村の委託により、平成6年度から高山植物の生態調査を行っている。また、夏の登山シーズンには登山道沿いの沢水が登山者の排泄物により汚染されていることが同会による平成8年度の調査で判明した。そこで平成9年度に、南アルプス国立公園周辺の登山者を対象に、山で排泄したものをパックに入れて持ちかえる「山のトイレ改善運動持ち帰りキャンペーン」を実施するなど、登山者に対する普及啓発活動を積極的に行い、南アルプス国立公園内での健全な自然とのふれあいの推進に貢献している。
(2) 身近な自然とのふれあい
余暇活動以外においても、日常生活の中で身近な自然を感じ、ふれあうことのできる機会を確保することが重要である。
また、近年は都会の公園などでも自然観察会を開催する公園が多く、NGOや行政主催の身近な自然の観察会も活発に行われている。このような機会を利用して自分が住んでいる地域の自然を足元から見直すことで、地域に対する愛着も増し、また地域の課題も見えてくるのではなかろうか。
ア 身近な自然を保全する手だて
身近な自然が残る場所は多くが民有地であり、自然環境保全法や自然公園法の対象外である。また、我々のライフスタイルが変化した現在では、こういう場所を改変した方が経済的に成り立つ状況があり、地主だけでの管理は不可能な状況になっている。そこで最近では、行政や地域住民、民間団体等、様々な主体が関わる形で身近な自然を管理し、そこに新しい価値をつける動きが起きている。
(ア) 都市緑地保全法の改正
第2章でも述べたように、平成6年に都市緑地保全法が改正され、市町村が「緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画(緑の基本計画)」を策定し、緑地保全を主体的に推進できることとなった。建設省の調べでは、平成9年3月現在、鎌倉市など72市町村がこの緑の基本計画の策定を完了しており、さらに今後策定予定の市町村は約1,200余りと、市町村の積極的な対応が見られる。
囲み3-2-3 民家の雑木林を区民に開放〜(財)せたがやトラスト協会による市民緑地の設置・管理〜
本文中でも紹介した都市緑地保全法には、「市民緑地」という制度がある。
これは、地方公共団体もしくは緑地管理機構として都道府県知事に指定された法人が、土地所有者との契約(市民緑地契約)を通じて、樹林地や草地等の緑地の管理を行い、住民に開放するものである。
その緑地管理機構として(財)せたがやトラスト協会が東京都知事より全国初の指定を受け、上記の業務を行えることとなった。今回、その第1号地として、世田谷区内の民有緑地1,229平方メートル(約370坪)について、市民緑地契約を結び、区民に開放している。現地は多摩川の支流である野川によって形成された国分寺崖線の一部であり、武蔵野の面影を残す場所である。
この取組をNGOが進めることにより、市民主体の身近な自然の保全活動が活発化されることが期待されており、同財団では今後も積極的に市民緑地契約を行っていくこととしている。
(イ) 「ふるさと自然ネットワーク」事業
環境庁では、国立公園・国定公園以外での、身近な自然環境を保全活用し、いきものとのふれあい、自然の中で憩うことのできる場づくりを進めており、地域の特徴に応じて、「環境と文化の森」、「ふるさといきものふれあいの里」、「ふるさと自然のみち」、「自然観察の森」などを整備している。
(ウ) 住民、民間団体の取組と行政との連携
身近な自然を保全していくためには、その地域の住民や民間団体の取組、行政との連携が重要である。
横浜市では、市立舞岡公園において、地元のNGOとの連携により、横浜市周辺の自然を、市民の農作業を通じたふれあいの機会を設けることにより保全している。さらに市内に「市民の森」を整備し、身近な自然の観察や憩いの場を市民に提供している。
また、大阪市西淀川地区では、公害により疲弊した地域環境の再生を図るため、身近な自然の掘り起こしを行っている。この地区は工場と自動車公害によるぜん息被害が生じ、西淀川公害訴訟の舞台となった場所である。平成8年には裁判の和解金を基金とした(財)公害地域再生センター(愛称「あおぞら財団」)を設立し、様々な活動を進めている。
その一つとして、この地域の公害が深刻化する以前の地域の子どもの遊びや「原風景」「原体験」の聞き取り調査や、身近な自然等を探す「まちづくりたんけん隊」を地域住民や学生、こどもエコクラブの参加により組織し、活動を行っている。これらの成果をまとめて、「まち歩きマップ」を作成するとともに、公害被害の経験の伝承と併せて、楽しみ、学びながら地域の将来を考える「フィールドミュージアム活動」として展開している。
イ 自然とのふれあいから学ぶ
科学技術の発達した現在の文明社会においては、人間の社会経済活動が地球規模に拡大する一方で、個々の人間の働きが専門化・細分化され、自然と人間の関係を見渡すことが難しくなっている。また、都市化された生活スタイルにより、自然体験に基づいた「知恵」を修得する機会も減少している。
しかし、生活の中において自然とのふれあいを通じ、自然と人間の関わり、人間と人間の関わりを感じることは、環境配慮行動の実践にとって重要であり、自然と人間の共生する社会の形成を考えるきっかけとして不可欠な要素である。
平成7年に出された環境庁水環境懇談会の報告書は、「かつて存在した人と水の密接で多面的な関わりが失われるとともに、身の回りに存在する水路や河川、湧水等の水環境を大切に保存していこうとする心も失われてしまったように感じられる。」と指摘し、水環境の保全には、地域住民の水環境への関心が重要であると述べている。
囲み3-2-4 市民の農作業を通じた身近な自然の保全 〜横浜市舞岡公園〜
神奈川県横浜市の舞岡公園では、市民グループと行政との連携により身近な自然を保全する活動が行われている。
同公園は、横浜市戸塚区と港南区(横浜市南西部)にまたがる市営の広域公園であり、面積は30.6ha、谷戸地形や雑木林のある、典型的な里山景観を残した公園である。この景観はかつて横浜市周辺では特に珍しいものではなかった。
しかし高度経済成長期以降、大規模宅地開発などにより市内の緑地が減少してきたため、市では昭和45年の都市計画の線引きにより舞岡地区周辺を市街化調整区域として保全を図るようになった。昭和48年の「横浜市総合計画1985」では、農地、森林、公園の3つの手法を組み合わせることで保全することが検討され、昭和59年には公園基本計画が立案された。その中で同公園は、「周辺農地や森林と一体化した特性を生かし、市民が生産の喜びを体験でき、田園風景にひたれるような、失われた少し前の時代の横浜の郷土文化を残す公園」と位置付けられ、平成5年に開園した。
公園計画立案1年前の昭和58年、横浜市から使用許可を得て、公園予定地の一部を利用し水田耕作・雑木林育成作業を行い、谷戸の再生を図るための市民グループ「まいおか水と緑の会」が活動を開始した。また同時に、地元の農家、農協、「舞岡ふるさと村推進協議会」等に、会としての積極的な関与・提言を行い続けることで、地域社会における信頼を得ていった。
このような活動を通じ、市民活動のノウハウや、市民参加の公園管理のあり方など、舞岡公園の運営案を市に提案し、平成5年には、公園の「田園体験区域」の管理運営を行う「舞岡公園を育む会」が発足、横浜市の委託を受け様々な事業を行うようになった。この「田園体験区域」にある水田を利用しての稲作作業や、雑木林の手入れ、植林事業、季節の行事、農芸作業、自然観察会などを、市民参加のイベント方式で行い、専門的な人材を育成するだけでなく、様々な市民の要望に応じた行事を設けたところに特徴がある。
少数のプロ(農業従事者等)により守られてきた都市周辺の身近な自然が危機に瀕している今日、舞岡公園では、一般市民の日々の暮らしの中に「農」を取り込み、体験的にふれあう機会を設け、身近な自然を保全する取組を行っている。
これは水に限ったことではなく、自然環境全般に言えることであろう。体験的に自然とふれあうことは、自然への豊かな感受性が育てられ、環境保全意識が芽生える重要なきっかけとなりうるのである。
大量生産、大量消費、大量廃棄ということが、一見当たり前に感じられる現在の生活も、高々この半世紀のことである。この社会を持続可能なものに変え、21世紀に生きる我々と我々の子孫が豊かな自然と共生していくために、我々の先祖が営々と積み重ねてきた自然との関わりの歴史、自然への畏怖、尊敬の念を日々の生活において身近に感じ取ることができる機会が必要である。
またそれは苦痛を伴う義務的なものではなく、精神的ゆとりを持った豊かな生活のことを指す、ということを、本書で掲載した多くの事例が示しているはずである。