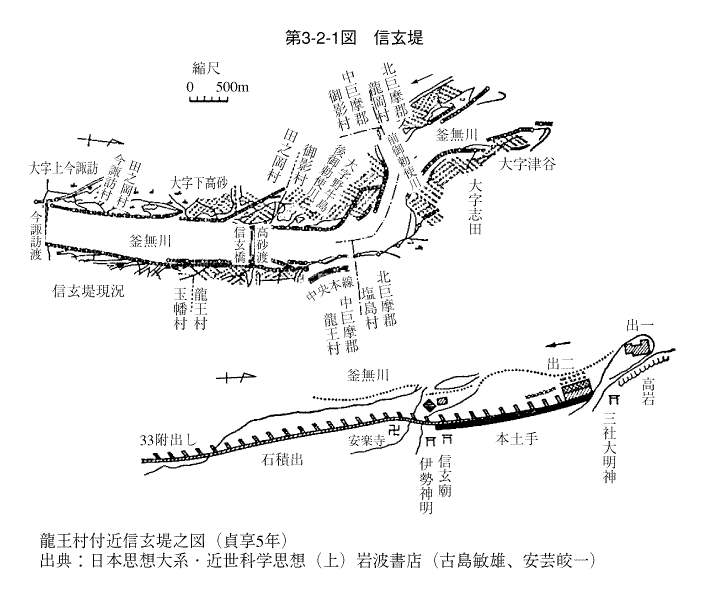
1 変化した人間と自然との関係
(1) 歴史に見る自然と人間活動との関わり
第2章第1節において概観した恵まれた自然環境の中で、我が国においては太古から、各地の環境特性に応じた人々の営みが続けられてきた。
弥生時代には中国大陸から稲作技術が伝わり、主に西南日本から東日本において栽培された。また、沖縄の人々、東北地方のマタギの人々や北海道のアイヌの人々の暮らしなど、多種多様な生活様式があった。その中で共通していたのは、自然の脅威を感じながらも、常に自然の摂理を研究し、自然に無理に逆らうことなく生きる態度であった。
例えば稲作を行う人々は一年間の気象サイクルを考慮し作業日程を決め、水の得やすい河川の後背湿地に自然地形に従った水田を開き、自らの集落は自然堤防等の微高地上に築いた。また、人間活動の領域が拡大した中世以降でも、例えば武田信玄の築いた「信玄堤」のように、川の流れる力そのものを上手く利用した治水事業が行われていた(第3-2-1図)。また、日々の暮らしや収穫祭・地鎮祭などの祭り、郷土芸能なども地域の自然環境と密接に結びついており、和歌や俳句、茶道、華道など、文学や芸術分野においても自然を題材にしたものが多かった。
(2) 自然との関係の希薄化
ア 戦後の社会経済と我々の生活
戦後の高度経済成長期以降、我々国民の多くは自然の直接の恩恵を特段意識しない生活スタイルを続けてきた。より豊かな生活を目指して国民一丸となって進めてきた経済成長は、物質的豊かさの享受という点では見事に成功したが、自然と人間との関係を我々の意識から遠ざけていった。
戦後の我が国の産業別就業者割合の推移を見てみると、昭和25年から平成7年の45年の間に劇的な変化が生じている(第3-2-2図)。
戦後間もなくの頃には我が国の就業者の約半数は第1次産業に就いていたが、高度経済成長期に入り、第1次産業就業者の割合は急速に減少し、昭和40年代初めには製造業従事者に抜かれ、現在は、約6%に至っている。
従業上の地位別就業者構成比の変化を見てみると、昭和35年には自営業主と家族従業者を合わせた割合は全体の約4割であったが、平成7年には2割を下回った。雇用者については、平成7年には8割以上となっており、戦後の就業者は急速にサラリーマン化したと言える。これは、経済活動の拡大に伴い、業務が細分化・専門化した結果であろう。また経済成長とともに、三大都市圏への人口集中が起こり、総面積の10%に満たない地域に全人口の40%以上が居住している。
また、自然に働きかけ、自然の脅威を克服する努力が、安全な生活や経済発展をを可能にした一方で、自然に対する意識を希薄なものにしてしまったという指摘もされている。平成9年版建設白書においては、「河川整備が進み水害が減少すればするほど、人々がかつて抱いていた川に対する畏敬や恐怖心は薄れつつあり、また地域の人々が受け継いできた水害に対処する貴重な教訓や生活の知恵等が忘れ去られようとしている。このように、近年において、人々の意識から河川の存在が遠いものとなり、地域と河川の関係は希薄化してしまった。」と述べている。
イ 遠くなった身近な自然
また、平成8年版環境白書総説でも取り上げたように、子どもの自然体験が減少していることも指摘されている。
神奈川県立橋本高等学校の第1期生と第15期生を対象に、昆虫及びオタマジャクシ、カエルについての体験と昆虫への認識について行ったアンケート調査(昭和53年と平成4年に実施。田口正男教諭による)では、虫取り体験について第15期生の体験率が第1期生に比べて軒並み低下していることが分かった。男女差では特に女子生徒の体験率が大きく減少している。また、ホタル、オタマジャクシ、カエルといった水辺の環境に生息する生物を捕まえた経験については、第1期生に対して8割を割る体験率となった(第3-2-3図)。2つの調査を隔てた15年間に、水辺の生き物とふれあう機会が急速に失われたことが考えられる。
また、昆虫の雄雌による特徴についての設問では、15年前に比べて正答率がかなり低下している(第3-2-4図)。例えば、「ハチで刺すのは(雄雌の)どちらか」という設問では、第1期生では男女とも5割前後が正答したのに対し、第15期生は2割以下の正答率であった。同じく、「セミで鳴くのはどちらか」という設問に対しては、第15期生の正答率は5割を下回った。セミは都心部の公園においてもかなりその姿を見たり、鳴き声を聞くことが多いが、最近の子供達の昆虫に対する認識は曖昧なものになっている。実際の虫取り等を通じて体験的に昆虫の特徴を知る機会が減少していることが窺える。