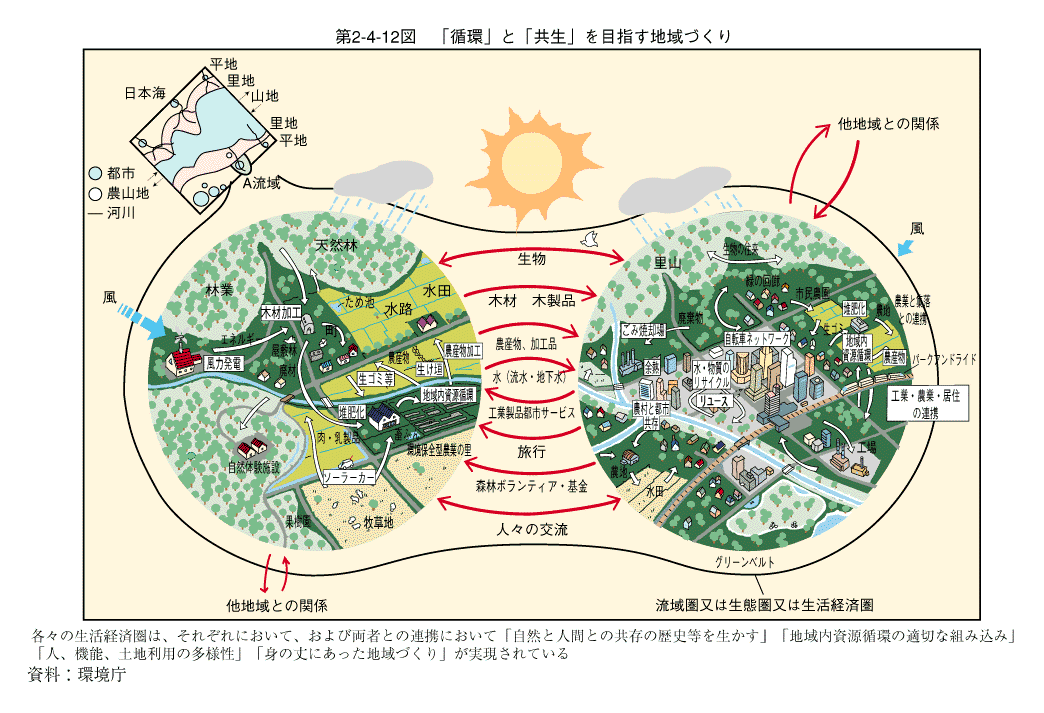
7 「循環」と「共生」を目指す地域づくり
本章の冒頭において、自然のメカニズムと人間の経済社会活動の乖離により、「全体の把握の欠如」と「配慮の欠如」が生じていることを指摘した。
それを解決するために、環境保全の観点から地域を捉えることが必要であること、その捉え方の例として、自然のメカニズムを基礎とした「生態圏」「流域圏」、人間活動を基礎とした「生活経済圏」の3つの圏域を紹介した。この圏域は、複数の自然のメカニズムをある程度完結して捉えることのできる「まとまり」であり、「循環」と「共生」を実現する人間の経済活動のあり方を模索するための枠組みとして論じてみた。
このように国土を「圏域」でとらえ、それをベースに人間活動を捉えることは、自然のメカニズムの尊重を基礎とした様々な主体の参加と連携により、健全で恵み豊かな環境を維持、保全し、恵み豊かな人間の生活の実現のため、有効な手法であるように思われる。
ここで最も重要なことは、自然のメカニズムを全体的に捉えるために、関わる様々な立場の人々、技術、仕組み、手法が連携することであろう。これをいいかえると、技術、社会資本等のハード、制度、文化、システム等のソフト、さらに我々人間の心と心のつながりであるハートの連携、ハードとソフトとハートの尊重といえよう。
最後に本章が目指す、循環と共生の地域づくりの一つのモデルを紹介したい。(第2-4-12図)