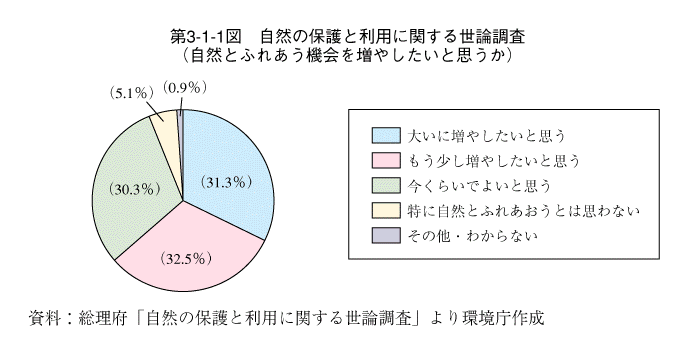
環境問題の中心課題が、産業公害から都市・生活型の環境問題や地球環境問題に移って久しい。産業公害は、加害者が事業者、被害者が周辺住民という構図が比較的明確であったのに対し、都市・生活型の環境問題や地球環境問題においては、我々一人ひとりが被害者であると同時に加害者でもある。生活に起因する環境負荷は、環境問題の様々な分野で大きなウエイトを占めるようになってきている。こうしたことから、「ライフスタイルを環境に配慮したものに変えていく必要がある」と繰り返し言われている。
しかしながら一人ひとりの活動からの環境負荷が、都市・生活型の環境問題や地球環境問題に結びついていくプロセスは、間接的・複雑であり、また、時間的・距離的・心理的に非常に離れており、実感できないことが多い。そのため、一人ひとりが何らかの活動を行う際に自分のその活動による環境への影響を正しく認識し、それを考慮した行動をするということは簡単ではない。
こうしたことから、「ライフスタイルを変えることが必要だ」といわれても、実際、どこをどう変えればよいのか、実行すべきであるとよく言われることを実行すれば本当に効果があるのか、また、本当に自分達の努力で変えうることばかりなのか、というような疑問が一人ひとりの中に残ったままになっているのではないか。
また、生活と環境との関係は、「発生させる環境負荷を極小化すればよい」というだけのものだろうか。平成8年11月に総理府が行った「自然の保護と利用に関する世論調査」によれば、「今よりもっと自然とふれあう機会を増やしたいと思うか」という質問に対し、「大いに増やしたいと思う」、「もう少し増やしたいと思う」と答えた人が6割を超えた(第3-1-1図)。また、「住まいの周辺にもっと自然があった方がよいと思うことがあるか」という問に対しては、8割の人が「もっと自然があった方がよいと思うことがある」と答えている(第3-1-2図)。自然と人間の豊かな交流を保つことは、環境基本計画の長期的目標「共生」の重要な内容であるが、生活と環境の関係はこうした側面からも同時に考えていく必要があるのではないか。
そこで本章では、上記のような疑問に答え、生活関連の環境負荷を実効性を持って低減していくために誰が何をすればよいのか、さらには、環境の観点から望ましい生活とはどのようなものであるかを明らかにすることを試みる。その際、ライフスタイルは、第1章、第2章で論じた産業活動や、土地・空間の利用のあり方等と不可分に結びついており、本来ライフスタイルのみ独立して議論できるものではないと考えられる。よって、常に社会全体を視野に入れて論じていく。
なお、生活を営んでいる主体の呼び方について、本章では便宜上「生活者」と呼ぶことにする。環境問題との関連で生活を取り上げる際には、個人の「消費者」としての側面ばかりが想起されがちであるが、生活とは消費生活のみから成っているものではない。自然を愛し、ふれあっていく側面、環境に関わる制度や事業について行政や事業者に働きかけていく側面、農業や森づくりなどに参画することにより直接環境の価値を高める側面等、生活の中で個人は様々な形で環境と関わっている。個人の持つこれらの側面全てを含めて「生活者」としたい。