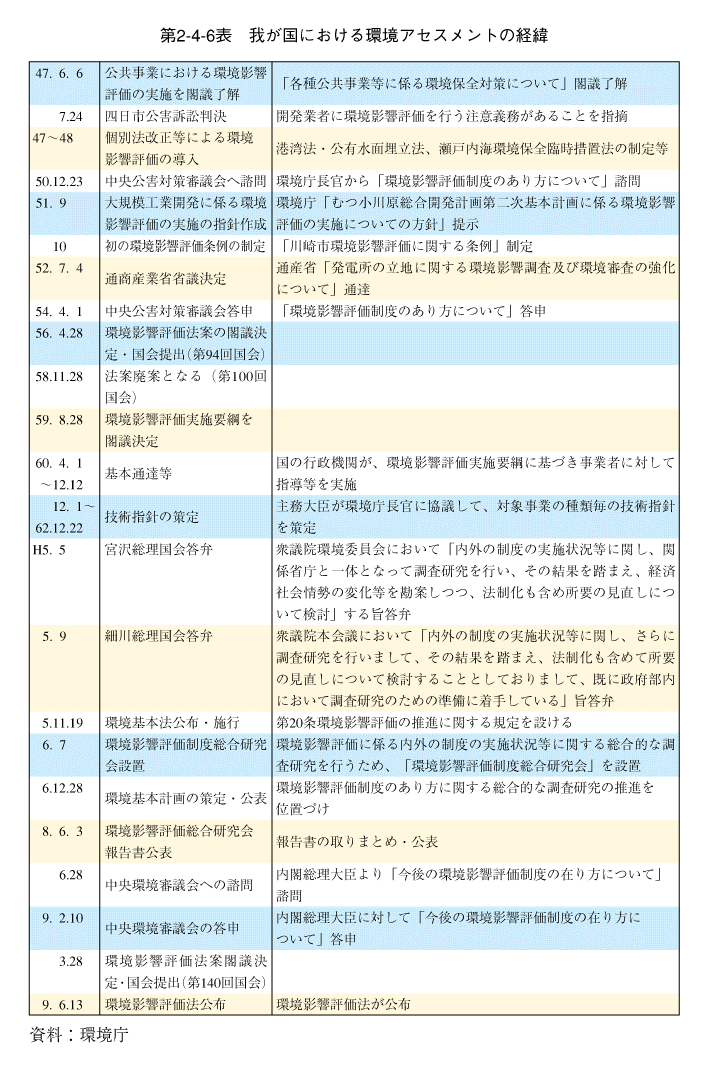
5 人間の活動と自然のメカニズムとの調整−環境影響評価(環境アセスメント)−
平成9年6月に、OECD諸国では最後発となる我が国の環境影響評価法(以下「環境アセスメント法」と呼ぶ)が成立した。環境影響評価実施要綱などに基づく従来の制度は、各事業の許認可における環境配慮の組み込みというものであったが、今回成立した環境アセスメント法は、それをさらに一歩進め、環境基本法の唱う「環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築」の理念を具体的に進めるための手段、あるいは考え方として、人間活動と自然のメカニズムを調整し、より環境に配慮した人間活動を行うことを念頭に置いたものとなっている。
ア 環境基本法時代の環境アセスメント制度へ
「環境アセスメント」という言葉が一般に周知されるようになってから久しい。環境アセスメントとは、土地の形状の変更、工作物の新設その他これらに類する事業を行う事業者が、その事業の実施に当たりあらかじめその事業に係る環境への影響について自ら調査、予測及び評価を行い、その結果に基づき、その事業に係る環境の保全について適正に配慮しようとするものである。
我が国の環境アセスメントは、昭和59年に閣議決定された環境影響評価実施要綱などに基づき行われ、一定の成果を上げてきたが、手続をより早期に実施すべきこと、住民等の関与の機会をより多くすべきこと、法律による制度とすべきこと等などについての指摘もなされてきた。
また、平成5年には環境基本法が制定され、また翌年には環境基本計画が策定された。これらの基本理念は、環境と経済の統合、持続的発展が可能な社会の構築といった、これまでの、公害行政にとどまらないものであった。
この環境基本法において環境アセスメントの推進がうたわれたことを契機に、関係省庁参加の下、制度見直しの検討が開始された。その後、平成8年6月の「環境影響評価総合研究会」報告書の取りまとめ、平成9年2月の中央環境審議会の法制化に向けた答申を受け、環境アセスメント法案を国会提出し、同年6月に法が成立するに至った。(第2-4-6表)。
イ 環境アセスメント法の概要
環境アセスメント法は、閣議決定要綱をベースとしつつ、問題として指摘された事項を踏まえ、拡充を行ったものとなっている。今回の法律による手続きの流れを従前の閣議決定要綱との比較で第2-4-10図に示す。この中にある新しく盛り込まれた点で特に重要なものは次の2点である。
? 早い段階から手続が開始されるよう、評価項目・調査等の方法について意見を求める仕組み(スコーピング)を導入したこと。
? 評価の項目を環境基本法で対象とする環境領域全般に拡大し、また、新しい評価の視点を導入したこと。
(ア) スコーピング
スコーピングとは、事業者が環境アセスメント(以下、単に「アセス」という)の実施前にその方法を公表し、それに対して専門家や地域住民、行政の意見を聞くという手続きである(第2-4-11図)。
従来の制度では、事業者による各種の調査等を経て関連情報が準備書にまとめられ、準備書の提出によってはじめて事業の関連情報が住民や地方公共団体に提供されることになっている。しかし、その時点では立地地点等の事業の概略が事業者として既にほぼ固まっており、アセスの結果を受けた柔軟な対応が難しい面があった。
一方、環境基本法においては、「環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な社会の構築」という理念を提示している。これは公害対策基本法のように環境を開発の制約要因として捉える考えから、環境を経済の基盤として捉え、環境保全を内部化していく考えへの転換を示していると言える。この理念を実際の人間の活動に取り入れていくためには、事業計画のできるだけ早い段階から環境配慮が組み込まれている必要がある。しかし、事業者は事業実施地域の環境などについて全てを知っているわけではない。
そこで早い段階で自らの事業内容とアセスの方法を公表し、外部の知恵や情報を収集することにより、より環境へ配慮した事業が実施可能となるであろう。また、地元の体験的な情報を含めた様々な有益な情報がもたらされ、その地域の環境特性に合致した効率的なアセスが可能になるものと期待される。
(イ) 新たな評価の視点
環境アセスメント法第11条では、環境基本法第14条に掲げる事項、すなわち、
・ 人の健康が保護され、及び生活環境が保全され、並びに自然環境が適切に保全されるよう、大気、水、土壌その他の環境の自然構成的要素が良好な状態に保持されること。
・ 生態系の多様性の確保、野生生物の種の保存その他の生物の多様性の確保が図られるとともに、森林、農地、水辺等における多様な自然環境が地域の自然的社会的条件に応じて体系的に保全されること。
・ 人と自然との豊かなふれあいが保たれること。
の確保を目的とすることとなった。
これにより、典型7公害と動物、植物など自然環境保全に係る要素に限定されていたアセスの評価対象が、廃棄物や温室効果ガスによる環境負荷の低減、生態系の保護、生物の多様性の確保や自然とのふれあいを保つことといったものを含む環境保全施策全般へ拡大されることとなった。
また、従来の制度による評価は、事業者が保全目標を設定し、それを満たすか否かで判断を行ういわば「保全目標クリア型」のみであったが、環境負荷をできる限り低減するような、実行可能な範囲での「ベスト追求型」とも言える視点を持つことが求められるようになった。
開発行為などの事業を行う場所の生態系はそれぞれ異なるであろうし、生物多様性や自然とのふれあいといったものは数値基準という考えになじみにくい。また、保全目標を設定することは、目標より以上に対策を進めようというインセンティヴを働きにくくする。
新しいアセスは、このような問題点を解消するとともに、実行可能な範囲でベストを追及するための検討の経過が明らかにされることを通じ、事業者と環境保全の意見を有する者との実質的な対話を促進させる。そういった意味で、「環境基本法時代のアセス」の根幹とも言うべき考え方であろう。
(ウ) 環境アセスメント法に加えられたその他の要素
その他、環境アセスメント法における新たな要素としては、主に以下のものが挙げられる。
○ 必ず環境影響評価を行う事業規模に満たない事業であっても一定規模以上のものについては、環境アセスメントの実施の必要性を個別に 判定する仕組み(スクリーニング)を導入する。
○ 意見提出者の地域限定を撤廃し、意見提出の機会を方法書段階と準備書段階の2回設けることにより、住民参加の機会を拡大する。
○ 不確実性に関連する記述、環境の保全のための措置の検討の状況の記述、委託先の名称の記述など、準備書の記載事項を充実する。
○ 閣議決定アセスメントでは環境庁長官は主務大臣から意見を求められたときしか意見を言えなかったが、本法では環境庁長官が必要に応じて意見を言えることとする。
○ 環境庁長官の意見や免許等を行う者等の意見を受けて、事業者が評価書を再検討することとする。
○ 準備書に事後調査に係る記述を記載することとし、環境アセスメント制度に事後の調査を位置づける。
○ 評価書が公告された事業や法律施行前に免許等を受けた事業でも、事業者が環境アセスメントを再実施することができることとする。
ウ 事業段階の環境配慮から計画段階での環境配慮へ
戦略的環境アセスメント(SEA:Strategic Environmental Assessment)の検討状況
行政における意思決定過程に環境配慮を組み込むための手法として、政策・計画・プログラムへの環境アセスメント(戦略的環境アセスメント:StrategicEnvironmental Assessment)の検討が近年、先進国を中心に始まっている。
(ア) EUの「一定の基本計画及び実施計画の環境への影響の評価に係る指令案」
EUでは、1996(平成8)年、「一定の基本計画及び実施計画の環境への影響の評価に係る指令案」を発表した。これは、開発許可の決定の枠組みとなる基本計画、実施計画の段階において環境への配慮を行うことにより、環境保護をこれまで以上に高いレベルで実施するというものである。
EU委員会に提出された同指令案の「解説のための覚書」では、計画段階で下される意思決定を対象とするには、環境アセスメントを事業実施段階で行ったのでは意思決定の段階として遅すぎるとし、開発許可の意思決定に至るプロセスにおいて、基本計画及び実施計画段階における環境アセスメントが位置付けられていなければ、開発が環境に及ぼす結果に対する総合的な考慮抜きで決定が下されることとなる、とした。
そして、EU加盟各国がSEAを導入することによって、?計画者や意思決定を行う者が環境への影響をより明確に理解し、効果的に考慮する結果につながり、?例えばある特定の種類の事業の実施場所の選択に関するなどの代替案がより適切に評価される、?計画作成のプロセスがより透明なものとなる、?事業段階での遅延や追加コストの発生が減少する、などの効果が期待されるとしている。
(イ) 我が国の地方公共団体の取組状況
我が国の地方公共団体においても、環境アセスメントをその対象事業の根拠となっている基本計画の段階で行うことを実施、検討する団体が出てきている。東京都では、平成5年以降「東京都計画段階環境アセスメント制度」の検討を行い、平成9年4月に報告を取りまとめた。
また、三重県では平成10年4月から「環境調整システム」の導入を決定し、県の策定する各種計画の意思決定過程における環境配慮を義務づけている。
囲み2-4-3 滋賀県の「環境自治委員会」の取組
滋賀県においては、平成8年に制定された滋賀県環境基本条例に基づき、県民参加の下に、県の施策を環境保全の観点から点検する「環境自治」が行われている。
健全で質の高い環境を確保するため、県の施策について、環境の保全の観点から調査審議を行う機関として滋賀の環境自治を推進する委員会(環境自治委員会)が設置されている。環境自治委員会へでの調査審議は、県民の申し立てに基づいて行われる。申し立ては、住民の意見が反映される仕組みを持たずに決定・実施されている施策について行うことができる。環境自治委員会は、当該施策の環境保全への影響の有無について知事等に対し説明、必要な資料の提出を求め、さらに実地調査を行うことにより調査審議を行う。自治委員会は、当該施策の環境保全への影響の有無について施策の是正その他の措置を講じる必要があると判断した場合、知事等にその旨を勧告することができる。
平成9年末現在まで計5件の申し立てがあり、4件につき審査結果が出ている。具体的な調査審査の例は以下の通り。
・ 琵琶湖文化館を取り囲む巻き堤の建設中止の申し立てに対し、自治委員会は水質汚濁のおそれがあり、また景観上も問題があると判断し、巻堤以外の方策を検討することを知事に勧告。
・ 水稲病害虫防除の空中散布について県の散布者への適正指導や事業中止を求める申し立てに対し、空中散布から環境に配慮した方法への転換へ指導するよう知事に勧告。
このような、県民参加の下に行政の施策を環境保全の観点から再検討する仕組みは、今後の「環境自治」のあり方の一つとして注目できよう。
エ 地方公共団体の環境アセスメント制度
(ア) 制度の条例化の状況
環境アセスメント法の制定後、多くの地方公共団体において制度の見直しが進められつつある。平成10年4月1日現在の各地方公共団体の制度の制定状況は第2-4-7表のとおりである。
要綱で制度を定めている地方公共団体が条例化を検討する例もあるが、これは、環境アセスメントを行政指導ではなく、住民代表による意思決定機関である議会を参画させることにより、開発行為に対する環境配慮を地域社会全体の意思とする意味においても重要である。
(イ) 情報公開
環境アセスメントを実施していく上では、国及び地方公共団体による情報の収集・提供が重要である。中央環境審議会の答申でも、「情報へのアクセスの向上等の観点から電子媒体の活用等も図られるべきである」とされた。また、国会審議においても「環境影響評価の適切かつ円滑な実施には、技術手法、過去の実例、地域環境の現状などの情報の活用が極めて重要であることにかんがみ、電子媒体の活用等、環境影響評価に関する情報の収集・整理・提供に努めること」が付帯決議された。
埼玉県では、平成9年11月に、まず県の行う2つの事業(県企業局の工業団地造成の環境影響評価書の概要版と土木部の道路建設事業の環境影響評価調査計画書)を対象として県のホームページに試行的に掲載した。今後は県条例を改正して全ての計画書、評価準備書及び評価書の掲載を行う方向で検討を行っている。