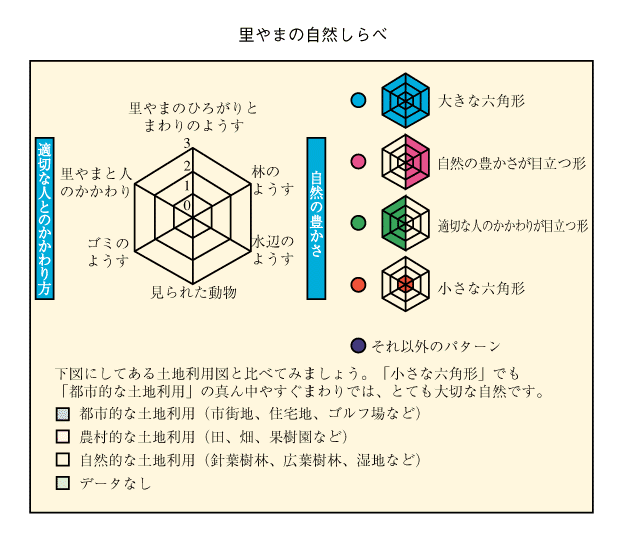
4 里地自然地域への期待 (※以下では「里地」という)
(1) 里地の再評価
環境基本計画では、国土空間を山地、里地、平地、沿岸地域の4つの自然地域に分けており、人口密度が低く、森林率がそれほど高くない地域を、里地自然地域として区分している。また計画は、里地においては、雑木林等の二次的自然が多く存在し、中大型獣の生息も多く確認され、農林水産業活動などの自然に対する人間の様々な働きかけを通じて環境が形成されてきたとしている。さらに、里地を野生生物と人間とが様々な関わりを持ってきた地域で、「ふるさと風景の原型」として捉えている。
いいかえれば、里地は、自然のメカニズムを人間が把握し、それに沿った形で人間活動が行われてきた場所であるといえよう。すなわち、里地には、元来の自然を活かしつつ、クリやコナラ林、耕作地、集落等の多様な機能が形成され、このようなモザイク状の土地利用の中に、多様な生物が生息している。また、農作業という生産活動や炭焼き等の雑木林を利用した生活等自然と人との関わりが濃密であり、自然と人との関わりに関する歴史・文化が多く残されている。さらに、山で刈った柴や畜産のふん尿、生活にともない発生した有機性の廃棄物を還元する等、林業、畜産業、農業、生活等の活動で発生するものを有効に活用し、外部での環境負荷を抑制する生活・経済様式が維持されているところも多い。このような里地における生活・経済様式は、そのもの自体が生活経済圏を構成するとともに、生態圏、流域圏の中における人間活動と自然のメカニズムとの調和の手法を構築する上での一つの模範となるものであろう。
また、里地を構成する主要な要素である農地と雑木林は、人間が自然のメカニズムに沿った形で人間活動を行うことにより形成されたものであるが、これは、適切な形で管理されることにより循環と共生を実現する資源として捉えることができよう。
しかしながら、このような里地は高度経済成長、都市化の進展により、里地の特性、公益機能を失い、活気も失いつつあるところが多い。道路、リゾート、宅地開発等により里地の多様な自然環境が破壊され、近代的農業の進展やライフスタイルの変化により、地域内循環のシステムが崩壊し、さらには人口の減少、高齢化等の過疎化が進行している。また、都市域において残された農地、里山林も失われつつある。
里地では、農地、里山林等の地域の資源を掘り起こし、その活用、管理を行うことにより、地域の活性化と環境保全につなげることができよう。つまり、里地においては、環境保全と地域活性化が表裏一体の関係にあるともいえる。すなわち、自然のメカニズムと人間活動の調和の接点ともっとも抵抗のない形で示すことの出来る地域であるのである。
囲み2-4-1 農村景観の価値
前述した仮想市場評価法により、農村景観の価値が周辺住民にもたらす便益を評価した事例を紹介しよう。
● 評価対象:大阪府能勢町(観光地化された景観ではなく一般的に存在する農村景観を有するまち)
● アンケート対象:能勢町までのアクセスが90分の圏内の住民
● 質問:「もし仮に近い将来に能勢町の美しい農村景観が消え、荒廃した農地だけが広がるようになるとします。そのような事態にならないように、景観保全のための組織を作り、農村景観の維持や保全のための活動を行うとします。そうした活動を支援するためにあなたのお宅ではどの程度なら負担してもよいと思いますか。年間の負担額が*円であれば、あなたのお宅では協力してもよいと思いますか。(回答:協力しても良い/協力したくない)」
(*の欄には、200〜50,000円までの8種類の金額からいずれか1つを入れる。アンケートの表紙には、茅葺き屋根の伝統的家屋と田植え直後の棚田の写真を各1枚ずつ掲載し、能勢町には水田を中心とした伝統的な農村景観が広がっているとの情報を回答者に対して掲示)
質問形式:2段階2項選択法:まずはじめに任意の提示額に対するYES/NO回答を尋ね、YESと回答した場合にはさらに高い金額を提示し、NOと回答した場合にはさらに低い金額を提示して、回答者の支払意志を尋ねる。(この方法により、質問の意図が提示された金額への賛否を明らかにすることにあり、提示された環境保全シナリオへの賛否ではないということを明確にすることができる。)
結果:1世帯当たりの支払意志額は、能勢町が19,891円、30分圏が17,138円、60分圏が11,053円、90分圏が8,248円となり、この金額に各圏内の総世帯数を掛けることにより求められる、能勢町の農村景観に対する90分圏内にすむ人々の総便益評価額は、355億1,467万円となった(能勢町の面積は98.68平方km、人口14,664人、世帯数4,209、平成8年版全国市町村要覧による)。
資料:「二段階二項選択CVMによる農村景観の経済的評価−大阪府能勢町を事例として−」吉田謙太郎・木下順子・江川章(農村計画学会誌 1997.12)
囲み2-4-2 里山の自然調べ……みんなでみればみえてくる
(財)日本自然保護協会では、1997年(平成9年)に全国の「里山の自然しらべ」を行った。これは、協会の会員を中心とした日本全国の人々(2469人)による933カ所の里山の状況に係る報告をもとに、里山の自然の状況についてマップ等にまとめたものである。里山は、自然そのものの働きと、人間からの働きかけがあって成り立ってきた場所である。したがって、自然の状態と人との関わりを知るための6つの調査項目を作り、総合的に評価を行っている
調査項目は、1.里山の成り立ち、2.林の様子、3.水辺の様子 4.里山の動物、5.ゴミの様子、6.里山と人との関わりを設定し、それぞれの項目及び項目間のバランスを評価するため、レーダーチャートを用いて評価した。それぞれの結果は以下のとおり
・ 大6角形(自然状態も人の関わり方も非常によい)221箇所
・ 小6角形(自然状態も人の関わり方もあまり良好でない)77箇所
・ 右側が大きい6角形(自然状態が良好)256箇所
・ 左側が大きい6角形(適切な人の関わりが良好)359箇所
・ 土地利用の関係と報告結果との関連を見ると、小6角形は都市部に集中していた。
これは様々な人間活動が里山の自然に悪影響を与えていることが想定される。また、里山に悪い影響を与えている原因もアンケートしたところ、宅地・工場開発の他、廃棄物処分や農地開発、レジャー施設開発等があげられる。さらに里山の過疎、高齢化も大きな原因を占めていることが分かった。割合が一番大きくなっていた。里山がどのように保護されているかを調べたところ、「自然公園・公園」「農家・寺家などの所有者」による保護の割合が高く、また、地域のボランティアや行政の働きが大きな割合を占めてきていることも特徴的であった。本調査より、急速に自然も人の関わりも減退している様子と同時に、自分たちの地域の里山に愛着を抱き、里山を守っていこくという方々の取組の様子がうかがえる。
(2) 持続可能な環境保全型の里地づくりと地域の連携の必要性 −里地ネットワーク−
ア 地域間の連携の必要性
前項では、里地の再評価を行うとともに、今日の里地が地域のコミュニティの崩壊、農地の放棄、適切な森林管理が行き届かないという懸念等により閉塞状況にあることを指摘した。その一方、大都市では、人口の集中に伴う環境の悪化、社会不安の高まりの中で、自然とのふれあいや心の安らぎが切実に求められており、里地の「ふるさと風景の原型」に対するニーズは高いと言える。こうしたことから、里地と都市の間をはじめとする地域の連携が重要となっている。様々な立場の人や地域の連携の重要性については、前節でも述べたが、ここでは、持続可能な里地づくりを目指す上でも、里地と都市がお互いを支え合い、新たな価値観や経済社会システムの仕組みを築いていくことが必要であることについて記述する。
イ 里地からのニーズ
本章でも既にいくつか紹介したように、持続可能な里地づくりのための活動は各地で動き始めており、多くの里地において、これまでの大量生産・大量消費・大量廃棄型の経済活動を見直し、新しい地域づくりを行っていこうという先駆的な取組が広がりつつある。里地ネットワーク(後述)が、平成9年8月、地方公共団体や企業、NGOに対して行ったアンケートでは、多くの団体が、既に有機農産物の販売や、エコツーリズム、自然保護・田園景観保全などをはじめとする里地の持続発展を目指す取組やこれをサポートする取組(これらの取組を「里地共生事業」と呼ぶ)に取り組んでいる、あるいは今後取り組む予定があると回答した。一方、このアンケートでは、情報の不足、資金・人材の不足、取組に対する地元での理解不足、里地商品のコスト高(関連して、企業としてのメリットがわからない)、縦割り行政の弊害等、取組を進める上で様々な壁があるとの指摘があった。現状では、既存の社会がもたらす様々な壁、技術・ノウハウの情報を得たり、情報を発信して幅広いネットワークを形成する機会の不足などが、里地共生事業のより大きな飛躍・発展を妨げているといえる。
ウ 都市からのニーズ
また、都市の側から見ても、里地に関わっていくことは、そのライフスタイルや行政、企業、大学・研究機関の役割に新たな可能性を提示するものである。すなわち、バブル期を経て、閉塞感のある今日の社会では、とりわけ将来世代の子供達に不安のない未来や心のうるおいを残せないのではないかとの焦燥感が高まっており、こうした中で里地の自然や文化、人々とのふれあいが、都市の住民に新しい命を吹き込み、ゆとりに満ちた豊かな暮らしを創り出していくことができるのではないかと考えられる。また、企業にとって、里地は自然環境を活用した新たな事業展開を可能とする地域ではないか。例えば、第3章第2節で紹介するが、都市に住む人々が里地に触れると同時に、里地を活性化させ得るものとしてエコツアーに対する需要が高まっている。さらに、大学・研究機関にとっては、エコテクノロジーの実践を図る新たなフィールドとなる可能性があるのではないか。
エ 里地ネットワークの設立
このような状況の中で、平成10年2月25日、里地の環境保全と経済的自立を両立させた地域づくりに寄与することを目指して、里地及び都市の、地方公共団体、事業者、大学・研究機関、市民団体等のネットワーク、「里地ネットワーク」が設立された。
里地ネットワークでは、里地共生事業に関する情報の収集・提供、里地共生事業のガイドラインの作成、モデル地域における調査研究などの実施を予定しており、具体的には、第2-4-9図のようなネットワークのイメージを描いている。例えば、前段で触れたエコツアーを例に取ると、現在は各地域が個別にエコツアーの企画を行っても宣伝力等の問題からなかなか集客が難しい状況にあるが、こうした各地域への旅を、ネットワークを活かして活性化するというようなことが期待される。また、里地ネットワーク事務局は、里地共生事業の成功の鍵として、以下の項目を挙げている。
? 構想のもつ質:地域の歴史風土文化に根差し、かつ新たな発想を取り組んだ都市と里地のNeedsとSeedsの双方を取り込んだ構想といえるか
? 構想のコンペ:コンペの発想とコンペを通じた高度な質の構想ができあがっているか
? 地域の各主体の参加の度合:計画当初から関係する各主体が参画していないと、かたよった構想になったり、足の引っ張り合いに陥らないか
? 地域環境基盤と地域環境の向上の度合:持続を前提とした構想になっているか
? 地域住民の参加:主体は、地域住民であってこそ地域の活性化につながる。参加のシナリオはあるか
? 地域住民への還元の度合:参加に応じた経済的文化的な還元がなされるか
? マスコミの評価とマスコミを通じた事業の浸透の度合
? 里地共生事業を担う人々の経験の広さと情報資源の度合
こうした考え方に基づいて、現在、里地ネットワークは、里地共生事業のガイドラインの作成を進めている。
里地ネットワークは、これらの活動によって、それぞれの取組の支援、社会へのアピールを行い、心のふるさとである里地の自立、ひいては持続可能な経済社会づくりに寄与できるのではないか。さらに、里地の現状、里地と都市の新しい関わりを求めるニーズは、国内にとどまらず、アジア全域に共通する課題であり、アジアをはじめとする他地域の様々な事例を学ぶとともに、我が国の事例を他の国々に紹介し、ともに手を携えて取り組んでいくことが必要であると考えており、今後の活動が期待される。