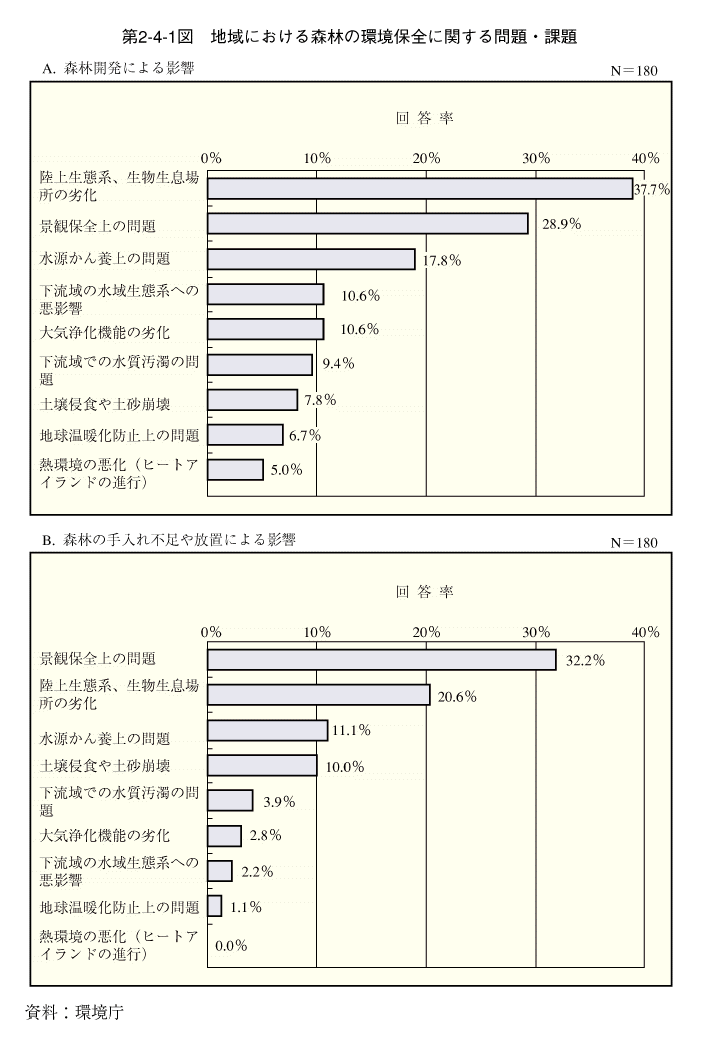
3 自然のメカニズムに合わせて人間が活動する仕組みづくり
自然のメカニズムを把握、明確にしたうえで、そのメカニズムに沿って人間の活動を行っていく仕組みを作ることが重要である。このような仕組みとして、行政による法制度的な仕組みや様々な主体の参画に基づくものとが考えられる。
行政による法制度的な仕組みとしては、前節までにおいていくつか紹介したものに加え、様々なものが考えられるが、ここでは、自然のメカニズムと人間活動を規定する国土利用、土地利用との調整の仕組みについて詳細に考察することとしたい。また、様々な主体の参画に基づく仕組みの重要性についても前節までの議論を踏まえ再度整理したい。
(1) 自然のメカニズムに合わせた形で実現する土地利用の仕組みについて
ア ニュージーランドの資源管理法
ニュージーランドでは、1991年(平成3年)に資源管理の合理化と環境管理の改善への要請を具体化し自然及び物的資源の持続的な利用を促進する「資源管理法」を制定した。この法律では、合理的に予測される次世代の要求に合致するように自然及び物的資源のポテンシャルを持続させること、大気、水、土壌及び生態系の生命維持能力を保護すること、さらに環境に及ぼすすべてのマイナスの影響を排除し、矯正し、緩和することに重点を置いている。さらに、海岸環境、湿地、湖沼及び河川の自然の保存、固有な植生や固有な動物群集の生息地の保護の優先的実施など特定地域における生物種と生息地の保護が重視されている。また、持続可能な資源管理をするために環境影響を制御する、法的拘束力を持った地区計画の策定により、資源と環境の総合管理が図られている。
ウェリントン市においては、本法律に基づき、ウェリントン南海岸土地利用管理計画が策定されているが、その中で生物種と生息地の総合的な保護、市を取り囲むグリーンベルト、保全すべき場所、生態学的回廊、及びその文化的な価値が尊重されている。この管理計画の策定に当たって、南海岸を多目的公園化する案が出されたが、土地所有者との対話により計画の趣旨を徹底する等の各種の協議を経ながら、環境資源の保護と利用の調整が行われた。このようにニュージーランドでは、自然のメカニズムに合わせて人間が活動する仕組みとして、「環境資源管理」の枠組みや土地利用管理計画と連動した総合的管理を担保する法制度が存在している。
イ 日本における国土利用、土地利用の制度について
(ア) 国土利用、土地利用による環境への影響の実態
環境庁では、平成10年に、環境保全の観点から見た国土利用、土地利用に関し、土地利用変化に伴う環境への影響、施策の取組状況等について自治体に対してアンケートによる実態調査を行った。(全都道府県、政令市、関東地方の市区)これは自治体としての又は環境担当部局としての認識を尋ねたものである。
森林、農地等の開発、転用及び管理の放置等により生じている環境への影響を尋ねたところ、第2-4-1図、第2-4-2図に掲げたような回答を得た。森林については、開発及び手入れ不足による陸上生態系の劣化や、景観上の問題、開発による水源涵養上及び大気浄化機能の劣化が多く回答された。農地については、耕作放棄及び転用による景観保全上の問題、生態系、生物生息場所への影響や劣化、下流域への水質汚濁、水源涵養上の問題が多く回答されている。
市街地については、回答中の約半数の自治体が、無秩序な拡大が進行していると回答し、約4分の1の自治体が森林や農地の減少により、生態系や水源涵養等の機能が損なわれてきていると回答している。さらに、多くの自治体において、市街地内の土地利用の変化により、交通量の増大、景観保全上の問題、下流域への水質汚濁やヒートアイランドの進行が生じていると回答している。(第2-4-3図)また農山漁村地域においては、宅地開発による新旧土地利用の不調和があげられている。
この調査から、土地利用の変化による様々な環境への悪影響が生じ、それが自治体において認識されていることが分かる。
(イ) 現行の国土利用、土地利用に係る法制度について
ここで日本の国土利用、土地利用に係る法制度についてレビューしてみたい。
日本の国土利用、土地利用は、国土利用計画法で、国土の利用に関する基本理念が示され、それに基づき国、都道府県、市町村の各段階において相互に調整のとれた国土利用計画を策定されることになっている。国が策定する全国計画については、国土の利用に関しては、国の他の諸計画の基本となるものとして、全国計画を頂点として国のすべての計画及び土地利用規制が体系化されている。国土利用計画は、国土の利用目的に応じた区分毎の規模の目標及びその地域別の概要及びこれらを達成するために必要な措置の概要が定められている。
平成8年には安全で安心できる国土利用、自然と共生する持続可能な国土利用、美しくゆとりのある国土利用といった観点を基本とした第3次国土利用計画が策定された。第3次計画の利用区分毎の目標は、第2-4-2表のようになっており、農用地が大幅に減少するのに対し、道路、宅地が増加するものになっている。この全国計画に基づき、各都道府県において土地利用基本計画が策定され、土地利用基本計画に沿って、都市計画法等の個別規制法に基づく措置がとられている。
第2-4-3表は、我が国における土地利用規制制度の一覧表である。人間活動を円滑に行う観点から、様々な目的を持った土地利用制度が制定され、その目的の達成のために様々な措置が講じられている。しかし、これらの法律の多くは、法目的の中に環境保全の観点を含めていない。また、規制区域の設定や区域内における行為の制限の基準、及びその運用に際しても環境保全の観点がとりいれられているものは少ない。
一方で、地方公共団体の独自の取組としては、土地利用調整会議などにおける部局間の調整や、環境配慮指針の策定により、環境配慮がなされるような仕組みがとられているところもある。熊本では、熊本地域地下水総合保全管理計画において水源涵養の観点から重要な地域を示し、当該地域における開発の際の留意事項を提示しており、これが開発行為を行うに当たっての指針としての役割を果たしている。しかし、これらの取組も法的拘束力がなく、必ずしも十分に機能している状況とはいえない。
このような状況下、多くの自然的土地利用が人工的土地利用に転換されているのが現状である。(第2-4-4図)その結果、自然のメカニズムが分断、破壊される等の悪影響が生じている。
さらに、先に言及した環境庁が行った自治体に対する実態調査において、環境保全の観点からの土地利用関連施策については、第2-4-5図、第2-4-6図のような回答が得られた。多くの自治体において、生態系保全のためのネットワーク、環境保全型の交通体系等各種の施策を将来的に実施したいと回答しているほか、検討を行っていない、無回答の自治体もあった。このように現在のところは全般的に見て取組はあまり進められていないが、今後この様な取組が自治体において地域の実情に応じて積極的に取り組まれることが期待される。さらに、地域における環境保全に配慮した土地利用に係る課題についてのアンケートでは、市民参加の仕組み、既存法制度等の観点からの課題を上げる自治体があった。(第2-4-7図)
先に紹介した、生態圏、流域圏、生活経済圏等における取組の多くは土地利用に関係するものである。しかし、今後、このような土地利用関連の法制度の連携等により、自然のメカニズムにあわせた国土利用、土地利用が図られ、環境影響の軽減がなされることが望ましい。
以下、今後の土地利用の仕組みを考えていく際に、参考となる手法をいくつか紹介しよう。
ウ 土地利用分級……自然のメカニズムを基礎とした土地利用計画の手法
国土を規定する自然的要素の観点から等質的な地域単位を区分し、さらに災害に対する危険度や土地利用の面からの適正等を評価した土地分級を行い、その結果に基づき、土地利用計画を行うといった手法がある。
これは、同じ類型毎に土地の区域に区分する「土地分類」を、地域の土地資源が持っている地形、地質、土壌、植生等の自然的な性質と文化財、法規制等の社会的性質をもとに行い、これをもとに、土地が持っている生産力、環境制御能力の差異と土地利用に伴う土地の改変の程度に着目して土地を区分し、現在の土地利用の適合状況を評価し、今後の土地利用のあり方を検討するものである。
昭和61年に富士宮市は、このような土地分級の手法によって土地利用構想図及び土地利用計画を策定している。
エ 掛川市の「生涯学習まちづくり土地条例」
−土地の利用のあり方を市民の生涯学習により決定していく手法−
掛川市では、「土地条例」を制定することにより、農地や森林そして自然の川などの復権を図るための取組が行われている。掛川市では、新幹線の掛川駅が開業した昭和63年前後から地価高騰の波が押し寄せ、土地の投棄と乱開発が始まった。この間特に、市街地周辺の農地や森林、原野が無差別に取得された。
そこで、掛川市では、土地利用をコントロールすることがまちづくりのベースであるとの考えの基、まちづくりの基本である土地利用のあり方を住民自身が考えていくことを生涯学習の一環として位置づけ、土地利用に対する規制を行っていく手法を定めた「生涯学習まちづくり土地条例」が制定された。この条例は、土地に関する所有や利用等について自然環境の保全を含む公共の福祉優先の立場を尊重することを明示している。そして地権者や住民は、土地が私有物であっても公共性を併せ持つことを生涯学習するとともに、地権者、地元集落、開発事業者、進入住民、進出企業及び市の5者が共に益し、良好な体制(5共益5良質体制)をつくることにより地域の土地利用の実効性を高めていくことを制度化したものである。(第2-4-8図)
条例では、市及び地元や地権者から申し出のあった、農林業の基盤となる保全すべき農地や森林、動植物の保護、水質保全上重要な区域について、地域の自治会、農業委員会及び利害関係者との調整を経て、「特別計画協定促進区域」に指定される。促進区域に指定された地域の住民は、検討委員会を設定し、まちづくりの目標や土地利用の方針を定めた「まちづくり計画案」を策定する。そしてこの計画について地権者の8割以上の同意が得られ、市の総合的な計画に適合していれば、市と地元自治会及び地権者の3者により、まちづくり協定を結び、市から「特別計画協定区域」に指定される。指定された協定区域内においては土地の売買、農地の転用、建物の新増築等の行為を行う場合、地元のまちづくり委員会の承認と市への届け出が必要となる。これにより地区内の土地利用は、まちづくり計画に沿った利用に誘導されていくことになる。そして平成10年3月末現在本条例に基づき、9地区が特別計画協定区域に指定されている。これらの地域におけるまちづくりの内容は、それぞれの地域の特性に応じたものとなっている。水質浄化を図るため全戸に合併浄化槽設置を義務付けた地域や、優良農地を確保し、農住共存型のまちづくりを進めている地区、さらに恵まれた自然環境や生態系を保全するため地形を生かす土地利用を目指し、住・商・工が共存するまちづくりを目指している地域などがある。このような掛川市においても?土地の経済的価値に重点をおいた「絶対的土地所有権」の考え方が強い状況にあって、土地条例により住民に土地の公益性を認識してもらえるかどうか、?まちづくり計画は市の基本計画と整合する必要があり、住民の要望と市の政策との調整及び各まちづくり計画の調和・調整・連携が十分図れるか等が課題となっている。
また、環境庁が行ったアンケートの結果、報告された様々な先進的な取組について、第2-4-4表、第2-4-5表のとおり紹介する。
(2) 様々な主体の参画に基づく仕組み
自然のメカニズムに合わせて人間が活動するためには、様々な主体の参画にもとづく取組が不可欠である。
生活経済圏のところでも見たように、様々な主体の連携により、人間の豊かな生活を保証しながら、自然のメカニズムに沿った人間活動を行うことが容易になる。このような様々な主体の連携のためには、流域圏で紹介した、兵庫県の流域水環境指針、アジェンダ21桂川・相模川のような自然のメカニズムと様々な人間活動の調和を図るための方向性を示す指針や、様々な主体が一堂に会して議論するための流域協議会等の「場」の設定、流域の人々が共同で活動を行うためのネットワーク組織等が非常に重要である。近年は、アジアシギ・チドリ湿地ネットワークのような地域のネットワークや、河川における流域連携、自然環境保全に係る市民のネットワーク組織が構築されるようになっている。
また、様々な主体の積極的な参画を促すためには、地域における資源と産業活動を有機的に組み合わせたプロジェクトを行うことが有効であろう。そのような取組事例をここで紹介したい。
日本第2の広さを持つ湖である霞ヶ浦の水辺を代表する水草がアサザである。霞ヶ浦はアサザの大群落が3カ所ほど残っている国内随一の生息地であるが、25年間にわたる霞ヶ浦開発事業で湖岸全域に護岸工事が施され、アサザが発芽できる砂浜が減少した。そこで、現在「湖と森と人を結ぶ霞ヶ浦再生事業」と銘打った「アサザプロジェクト」が市民グループの霞ヶ浦・北浦をよくする市民会議」により平成7年から実施されている。アサザの葉で覆われた水面は波が消えるため、群落の下には砂が堆積し、浅瀬が形成され、やがて時間がたつと砂浜が生まれる。このアサザ群落には波を消すことによりアシ原を波の浸食から守る働きを持っている。アサザプロジェクトは失われた砂浜やアシ原を再生しようという取組である。このプロジェクトは、まず砂浜が失われてしまった状態でアサザを増やすためには植木鉢やプランターで育ててから湖に移植する必要があるため、「里親制度」を設けることにより、平成9年までに計18000人以上の市民によって湖内の浅瀬にアサザの株の植え付けがなされている。移植に当たっては、湖岸における波消しが必要であるため、霞ヶ浦の水源地域の森林組合から間伐材を買い取り、木杭をつくり波消し用に打ち込みを行っている。材料は森林組合、工事は漁協の協力の下河川管理者が実施している。波消しに間伐材を利用することで魚礁としての役割が期待される。さらに漁協と生協との間でエビや小魚の産直を実施してもらう等一次産業の振興にも取り組んでいる。この農林水産業、学校、行政、市民の協同型事業プロジェクトは、湖をめぐる様々な分野の人々のネットワークの形成と共通の取組の場を作り、源流から湖まで住民によるトータルできめ細やかな流域管理を目指すプロジェクトとなっている。
このようなプロジェクトの実施により、様々な主体の自発的な参加が促され、自然のメカニズムにあわせた人間活動のあり方が模索されている。