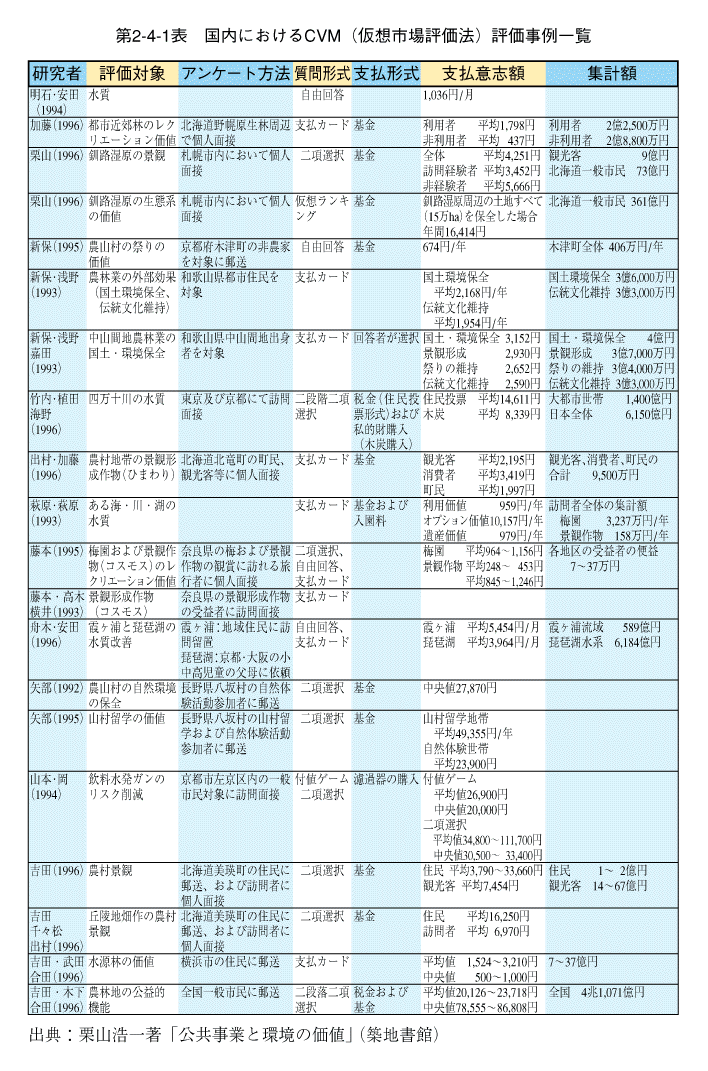
2 自然のメカニズムの持つ機能の適切な評価
さらに、自然のメカニズムへの配慮が適切になされるようにするためには、何らかの物差しを用いて、自然のメカニズムの持つ機能の価値を適切に評価し、分かりやすい形で示すことも重要である。
環境の持つ様々な機能は、我々人間に様々な便益をもたらしているにもかかわらず、現在は、その代価を支払われることなく利用されることが多く、このためどうしても過剰利用をされる傾向がある。環境を開発・利用することにより利益が生じる反面、環境の機能が失われる場合もあり、将来の世代を含む多くの人々が環境が存在していたことにより得ていた無形の恩恵を失うことになる。環境が適切に保全されるためには、まず、?こうした環境の持つ機能を適切に評価し、次に、?その評価を現実の我々の経済活動に組み込むことが必要である。以下、この2点について論じる。
(1) 環境の有する様々な機能の経済的評価事例について
取引が行われていない環境の持つ機能の経済評価を行う様々な研究が行われている。
例えば、1997年(平成9年)にメリーランド大学のロバート・コンスタンザ氏らが、この分野の様々な研究を総合して行った試算によると、世界全体の森林、海洋、湿地等生態系による、温室効果ガス・大気汚染物質の吸収、気候の安定化等様々な機能を経済的に評価すると、少なくとも年間16兆〜54兆ドルあり、世界全体の総生産の18兆ドルをも上回っているとされている。以下、いくつかの具体的な試算例を紹介する。
ア 代替法を用いた例
代替法とは、市場で直接計測できない外部効果を、同程度の機能を代替施設等により提供するとした場合に必要な建設コスト等により評価する方法である。直観的で理解されやすいことが利点であるが、適切な代替物が存在しない場合があること、代替物の選択が恣意的になされる可能性があることが欠点とされている。
林野庁が、この手法により、我が国の森林の有する公益的機能のうち、水資源かん養、土砂流出防止、土砂崩壊防止、保健休養、野生鳥獣保護、酸素供給・大気浄化の6つの機能について、その合計評価額を試算したところ、年間約39兆円(平成3年時点)となった。
イ 仮想市場評価法(CVM)を用いた例
CVMはある財に対して、いくらまでなら支払ってもよいか(支払意志額)を、財の需要者に対してアンケートすることにより、その財の便益評価を行う手法である(CVMの具体的な手続については、囲み2-4-1も参照)。質問の設定をうまく行えば、幅広い外部経済効果を評価できる上に、多数の市民の意見を反映した評価を得ることができるというメリットがあるが、設定によるバイアスやあくまで仮の問いかけであることによるフリーライダーが存在するという問題がある。
国内でも多数の評価事例があるが(第2-4-1表)、ここでは、仮想市場評価法により、アメリカ・エルワ川に設置されている2つのダムに関する評価を行った事例を紹介する。エルワ川の大部分は国立公園内を流れているが、今世紀の前半に建設された2つのダムによって、かつてこの川を遡上していたサケやマスが激減し、その絶滅が懸念されていた。米国では、第2節の流域圏の項で紹介したとおり、既存のダムの見直しが行われている。こうした見直しの際には、関係者の間で幅広い議論が行われるが、エルワ川の2つのダムのケースでは、様々な対策案を比較検討した結果、1994年(平成6年)、撤去することが決定された。
このエルワ川の2つのダムについて、これらを撤去することにより回復される生態系の価値を評価するため、全米の市民2500世帯を対象に以下のようなアンケートにより調査が行われた。
「エルワ川の2つのダムを撤去して河川や魚の生息数を元に回復させるためには、今後10年間、あなたの世帯の税金が*ドル上昇します。あなたはこのダム撤去に賛成しますか、反対しますか?」
賛成 反対
(*にはランダムに数値を記入しておく)
Loomis(Measureing the Economic Benefits of removing Dams andRestoring the Elwha River:Results of a Contingent Valuation Survey.WaterResources Research 1996)
この結果、支払意志額は1世帯当たり、年間平均68ドルとなり、これに全米の世帯数を掛けて、年間30〜60億ドルという総支払意志額が得られた。これはダム撤去に必要な3億ドルを大きく上回った。
(2) 環境の持つ外部経済効果をどのようにして内部化するか
上記のような環境の持つ機能の価値が、現実の経済の中でも適切に反映され、開発するよりも森林や農地等をそのままの形で保全した方が、大きな経済効果が得られるような制度を構築することが、社会全体の効用を最大化すると考えられる。すなわち、「自然として存在していることによる社会的便益」が、「自然を改変して得られる利益」を上回っている場合には、この評価が適切に経済活動に反映されるように、つまり転用されてしまわないように、土地の買い上げ、自然の所有者への助成、転用の規制等の施策を行う必要があるといえる。
例えば、相模原市では、市の拠出金や寄付金からなる相模原市緑地保全基金によって、市内の貴重な緑地や開発危機に直面している緑地などを取得し、将来にわたり保全することとしている。また、同市では、首都圏近郊緑地法により定められる首都圏近郊緑地特別保全地区等の緑地等の保全のための奨励金制度を設けており、区域内の土地所有者に奨励金を交付している。
また、住民自らが寄付金などを募り、土地の買い取り・保全契約などを通じて管理権を取得し、その土地の自然環境を保全するという「ナショナル・トラスト活動」もこうした役割を果たしうるものと考えられる。