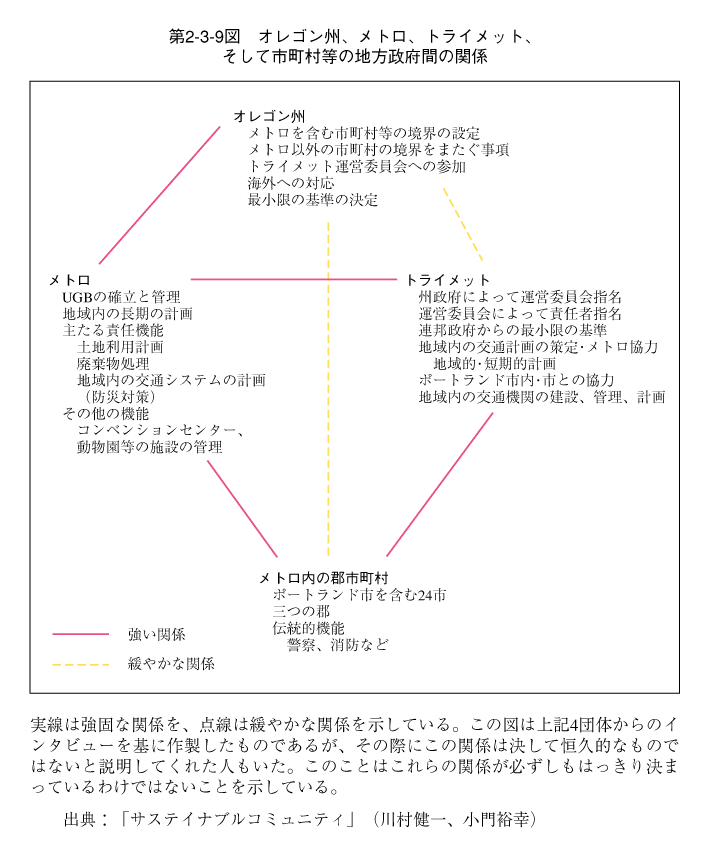
4 都市の成長管理と広域行政の試み
現代における我々の生活経済圏の一つである都市を、できる限り自然のメカニズムに沿った持続可能な形で発展させることは、都市部に約7割の国民が住んでいる我が国にとっては重要な課題である。
世界一自動車保有数が多く、自動車に依存した社会であると言われているアメリカ合衆国でも、近年、都市の成長管理と自動車交通への過剰依存からの脱却を図る取組が各地で進められている。
(1) 「アワニー原則」にみる、都市の成長管理とコミュニティの復活
1991年(平成3年)、アメリカの自動車に依存した都市形態とコミュニティの崩壊に危機感を抱いた地方自治体の幹部がヨセミテ国立公園のホテル「アワニー」に集まり、ここで「アワニー原則」という、持続可能なまちづくりを目指す原則を取りまとめた。
この原則では、アメリカ合衆国の諸都市のコミュニティ崩壊の理由を、自動車への過剰依存とそれに従った都市開発形態であるとし、「もっと住みよいまちへ」という目標のために、コミュニティ、及び複数のコミュニティを包含する地域リージョン(地域)のあり方が示され、実現のための戦略が記されている。この中には、我が国の環境政策や都市政策にとっても参考となるような示唆に富んだ記述が多く見られる。
右にアワニー原則の一部(川村健一・小門裕幸氏の訳による)を紹介する。
この原則で特徴的なのは、まず、コミュニティ及びそれらを含む地域のあるべき姿、目標をはっきり掲げ、個々の施策と全体計画とが整合性のあるものでなけらばならない、と指摘していることである。そのような取組の事例として、ポートランド市の例を見てみよう。
アワニー原則(抄)
? 序言(Preamble)
現在の都市及び郊外の開発パターンは、人々の生活の質に対して以下のような重大な障害をもたらしている。
・ 自動車への過度の依存によってもたらされる交通混雑と大気汚染
・ 誰もが利用できるような貴重なオープンスペースの喪失
・ 延びきった道路網に対する多額の補修費の投入
・ 経済資源の不平等な配分
・ コミュニティに対する一体感の喪失
? コミュニティの原則(Community Principles)(抜粋)
○ すべてのコミュニティは、住宅、商店、勤務先、学校、公園、公共施設など、住民の生活に不可欠な様々な施設・活動拠点をあわせ持つような、多機能で、統一感のあるものとして設計されなければならない。
○ できるだけ多くの施設や活動拠点が、公共交通機関の駅・停留所に簡単に歩いていける距離内に整備されるべきである。
○ 新たに作り出されるコミュニティの場所や性格は、そのコミュニティを包含する、より大きな交通ネットワークと調和をとれたものでなければならない。
○ コミュニティは、商業活動、市民サービス、文化活動、レクリエーション活動などが集中的になされる中心地を保持しなければならない。
○ それぞれのコミュニティや、いくつかのコミュニティがまとまったより大きな地域は、農業のグリーンベルト、野生生物の生息境界などによって明確な境界を保持しなければならない。またこの境界は、開発行為の対象とならないようにしなければならない。
○ 通り、歩行者用通路、自転車用道路などのコミュニティ内の様々な道路は、全体として、相互に緊密なネットワークを保持し、かつ、興味をそそられるようなルートを提供するような道路システムを形成するものでなければならない。それらの道は、建物、木々、街頭など周囲の環境に工夫を凝らし、また、自動車利用を減退させるような小さく細かいものであることによって、徒歩や、自転車の利用が促進されるようなものでなければならない。
○ コミュニティの建設前から敷地内に存在していた、天然の地形、排水、植生などは、コミュニティ内の公園やグリーンベルトの中をはじめとして、可能な限り元の自然のままの形でコミュニティ内に保存されるべきである。
○ すべてのコミュニティは、資源を節約し、廃棄物が最小になるように設計されるべきである。
○ エネルギー節約型のコミュニティを作り出すために、通りの方向性、建物の配置、日陰の活用などに充分な工夫を凝らすべきである。
? 複数のコミュニティを包含するリージョン(地域)の原則
(Regional Principles)
1. 地域の土地利用計画は、従来は、自動車専用の高速道路との整合性が第一に考えられてきたが、これからは、公共交通路線を中心とする大規模な交通輸送ネットワークとの整合性が先ず第一に考えられなければならない。
2. 地域は、自然条件によって決定されるグリーンベルトや野生生物の生息境界などの形で、他の地域との境界線を保持し、かつ、この境界線を常に維持していかなければならない。
3. 市庁舎やスタジアム、博物館のなどような、地域の中心的な施設は、都市の中心部に位置していなければならない。
4. その地域の歴史、文化、気候に対応し、その地域の独自性が表現され、またそれが強化されるような建物の方法及び資材を採用するべきである。
? 実現のための戦略
1. 全体計画は、前述の諸原則に従い、状況の変化に対応して常に柔軟に改訂されるものであるべきである。
2. 特定の開発業者が主導権を握ったり、地域のそれぞれの部分部分が地域全体との整合性もないままに乱開発されることを防ぐために、地元の地方公共団体は、開発の全体計画が策定される際の適正な計画プロセスの保持に責任を負うべきである。全体計画では、新規の開発、人口の流入、土地再開発などが許容される場所が明確に示されなければならない。
3. 開発事業が実施される前に、上記原則に基づいた詳細な計画が策定されていなければならない。詳細な計画を策定することによって、事業が順調に進捗していくことが可能になる。
4. 計画の策定プロセスには誰でも参加できるようにするとともに、計画策定への参加者に対しては、プロジェクトに対する様々な提案が視覚的に理解できるような資料が提供されるべきである。
(2) ポートランド都市圏の試み
前述のアワニー原則を重視した地域づくりを行っている事例として、アメリカ合衆国のポートランドが挙げられる。オレゴン州第一の都市圏(人口はポートランド市で約50万人、都市圏で約110万人)であるポートランド都市圏では、都市部の無秩序なスプロール化を抑えた土地政策と、それに見合った交通政策を統合させ、環境負荷も低減させる、「2040年地域発展構想」を作成している。
ア 自動車過剰依存への疑問
1970年代初め、同市では自動車専用道路建設の計画が市民の反対を受け、大幅に縮小された。その代わり道路交通渋滞問題の解決のために路面電車を建設することを決定した。この決定の背景として、ロサンゼルス市のような自動車過剰依存型の都市に対する疑問や、当時の市長が進めていた公共交通機関中心のまちづくりによる中心市街地活性化策が住民のある程度の理解を得るようになった、等の要因があったと考えられている。
イ 広域行政機関「メトロ」の設立とその役割
この計画の中心的役割を果たしたのは、ポートランド市を中心に3つのカウンティ(郡)により設立された「メトロ(Metro)」という行政機関である。都市の無秩序な成長の抑制はポートランド一市で解決しうる問題ではなかった。そこで1977年(昭和52年)6月にオレゴン州議会は「メトロポリタン・サービス・ディストリクト(MSD、メトロの前身)」の設立を決定し、翌1978年にはMSDに関わる3つのカウンティの住民たちによる投票が行われ、MSDが正式に発足した。これによりアメリカ唯一の住民の投票によって選ばれた議員と首長を持つ地域政府が誕生した。そして、1992年(平成4年)11月、地域政府の任務を記したメトロ憲章が施行され、この地域政府の名称が「メトロ(Metro)と定められた(第2-3-9図)。
メトロの主な役割は、地域全体の土地利用計画、都市計画と整合性のとれた交通計画の策定である。既存の自治体では対応が難しかった広域的地域での整合性のとれた計画策定を担うことになった。
1979年(昭和54年)には「都市開発境界(The Urban Growth Boundary)」を設定して都市地域のスプロール化を抑制し、高密度でコンパクトなまちづくりを目指している(第2-3-10図)。この目的は、?都市開発境界内の土地の効率的な利用を推進する、?公的施設やサービスの効率性促進、?境界外の重要な農地や森林を守る、といったものであった。しかし、設定当初は開発の方法についての枠組みがはっきりしていなかったため、効果はそれほどにはあがらなかった。
その後、地球温暖化が問題として大きく取り上げられ始めた1993年(平成5年)には地域行動計画を策定し、CO2の排出量を1988年(昭和63年)よりも20%削減する目標を立てた。また、1995年(平成7年)には「2040年地域発展構想」が示された。この構想では、?土地浪費を抑制し、近距離交通の発達とコンパクトな都市発展、?現在の地域の土地利用を保つ、?都市開発区域に加えない農業地域を示す、などの考え方が示され、都市開発境界の重要性が明示された。
ウ 土地政策と整合性のとれた交通計画の策定
また同じく策定された「地域交通プラン」では、「合衆国地上交通網効率法」や「合衆国大気保全法」、「オレゴン州交通計画規制」の要請もあり、両者を統合することで目標を達成していく方針を決めた。メトロの目指すものは非常に明確である。すなわち、今後の都市成長を管理するために、開発を拡大させず、既存市街地の高密度化を進めるとともに、自動車交通に依存しない交通体系を整備し、環境負荷を低減し、住みやすい都市を作ることである。
この地域交通プランでは、交通政策と土地利用の統合を唱ったうえで、5つの移動手段(徒歩、自転車、公共交通機関、貨物輸送、道路)を適切に組み合わせ、各地域ごとの土地利用に沿ったプログラムを作成し、実際に様々な施策が講じられている。以下では、特にポートランド市中心部を対象とした対策を取り上げる。
(ア) 歩行環境改良プログラム (Pedestrian Transportation Program)
このプログラムは、ポートランドをもっと歩きやすい町にする目的で、1992年(平成4年)に始められた。市の中心部を、安全に楽しく歩くことができるような歩道を整備し、学校やバス停、公的施設、事業所などを結びつけるとともに、オフィス街や商店等の位置やデザインを歩行者の利便に沿ったものに変えるよう奨励している。
(イ) 自転車移動マスタープラン
1973年(昭和48年)には最初の自転車計画がされており、これは米国でも最も古いもののひとつであった。これを、前述の2040年構想に合わせる形で、自転車のより積極的な活用を目指し、1995年(平成7年)に現在の計画が策定された。現在では約240キロにも及ぶ自転車道路ネットワークが整備されている。また、都市圏の公共交通機関との協力で、自転車を路面電車やバスに持ち込むことを可能にすることで自転車利用を促進している。市の調査によれば1994年(平成6年)から1995年(平成7年)の1年間で延べ約8万台の自転車が運ばれた。さらにシャワー設備や更衣室などを備えた自転車通勤者用の施設を建設した。この計画には、市の様々な事業所や団体や自転車店などが協力し、市内での自転車移動を支援している。また、市民、特に子供に対して自転車安全教育を行っている。ちなみに同市は1995年(平成7年)に米国自転車雑誌「サイクリングマガジン」紙により、「全米一自転車にやさしいまち」に選ばれている。
(ウ) 公共交通機関
市内には現在、通称「MAX」と呼ばれる低床型の路面電車(LRT)とバス路線が、「トライ・メット」(Tri-MET)と呼ばれる交通公団により整備・運営されている。MAXは1986年(昭和61年)に運行が始まり、運賃制度はゾーン制を採用し、都心部の約2キロ四方の区域は無料である。現在では1日平均約2万人を運び、市内中心業務地区への通勤の約43%を分担している。また、市中心部には「トランジット・モール」(「モール」(遊歩道、歩行者天国)の形態のひとつで、一般車の走行を規制し、歩行者空間の確保と公共交通機関の共存を図ったもの)が配置されており、歩行環境の改善とバスの定時性確保に貢献している。現在、MAXの西方への延伸工事が進められており、1998年(平成10年)には開通予定である。
以上の対策の他にも、中心部における駐車場政策(総数を抑制したうえで、通勤用の長時間駐車場を削減し、業務や買い物等の短時間駐車場を増加させる)や、地域計画への市民の参加機会を保証する、また、あらゆる機会での住民への広報活動など、市域全体が「住み良いまち」をめざしてハード、ソフト様々な施策が結びついた施策が行われている。
ポートランド都市圏における、各種計画の統合的推進の取組はまだ始められたばかりであり、一定の評価を与えるには尚早であろう。しかし、これまで自然のメカニズムが十分配慮されてこなかった都市において、成長管理及び土地利用と整合性の取れた交通計画、さらにそれをサポートするソフト、ハードの各種計画により、住み良く環境への配慮もされた持続可能な地域社会を構築していく試みが、人口50万人のポートランド市を中心とした地域で考えられ計画が実行されている。このことは我が国の地方中核都市にとっても参考となるのではないか。
囲み2-3-1 シュツットガルト市の「風の道計画」
南ドイツにある人口約60万人の都市シュツットガルトは、自動車産業が立地する工業都市である。周辺を山地に囲まれたすり鉢上の盆地の中に市街地が広がっており、大気が滞留しやすく、都心と郊外の温度差が6度にも達していた。
そこで市では気候を緩和しヒートアイランド現象を解消させるために、気温、湿度をコントロールする風に着目して「風の道計画」を策定した。この計画に従い、土地利用計画と地区詳細計画という二段階の計画によって、実際の土地利用と建築行為に対し詳細な規則が定められている。例えば、郊外から都心への風の流れを誘導するように、公園、緑地等を連続的に配置するとともに、建物のセットバック、高さ制限、緑の保全・導入・立て替え以外の新規の建築行為の禁止等の規制が行われ、そのうえで屋上庭園や水を張ったウェットルーフの設置や、道路には街路樹の植栽を施す等、様々な手段を講じて都市部の気温上昇を抑える対策を行っている。