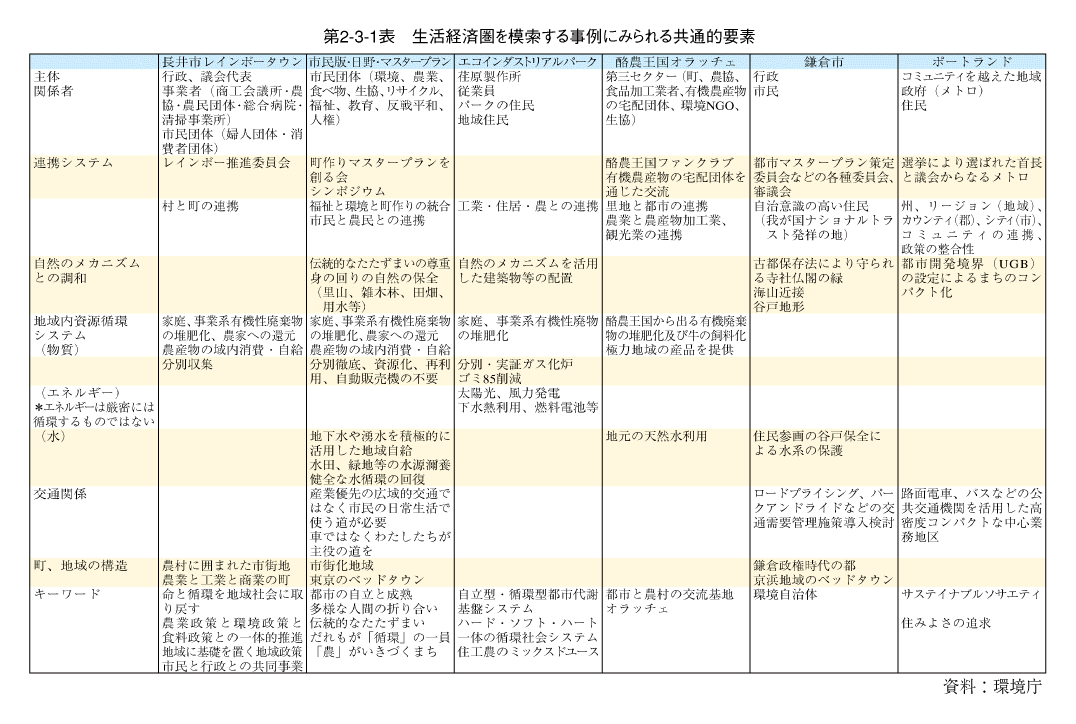
5 生活経済圏を構成する要素
以上生活経済圏を考えるに当たって、参考となる取組事例を紹介した。ここでは、これらの生活経済圏を模索する事例にみられる共通的な要素を整理し、(第2-3-1表)生活経済圏の構成要素及び捉え方を抽出してみることとする。
(1) 自然と人間との共生の歴史等を生かす
地域づくりを支える地域の人間と自然のメカニズムとの調和の歴史を尊重しているということが、いくつかの事例から共通的に見いだされる。
人間は、自然から数々の影響を受け、影響を与えながら自然の恵みの中で暮らしてきた。そして、里山林や水田、畑及び居住空間を作り上げるに当たっては、自然のメカニズムと調和する形で自然に働きかけることが必要条件であった。
鎌倉市においては、市街化が進められているにも関わらず、自然の地形を残した谷戸地域を残し、開発の際にもその地形を残しつつ行うという動きが出てきている。市民版・日野のマスタープランは、武蔵野台地という自然のメカニズムに沿って歴史的に形成されてきた、畑地、段丘崖の緑地、沖積地の水田とを三位一体として保全することの必要性を指摘している。ドイツにおける風の町づくりもまさに、自然の営みを保全、活用した地域づくりの事例である。
それぞれの地域は独自の気候風土や土地条件、文化や歴史を持っている。「生活経済圏」を構成する要素の一つとして、このような自然のメカニズムに調和した自然と人間との共生の歴史等を生かすことが指摘できよう。
(2) 地域内資源循環の適切な組込み
次に、地域内における資源の動きに注目して、「生活経済圏」における循環と共生を実現する方策を考えてみたい。
最初に健全な物質循環を実現する取組をいくつか紹介したが、取りあげた事例が、ほとんど共通して自然のメカニズムを活用した物質循環を、目指していることが分かる。さらに、地域に存在する資源を発掘し、利用し、地域内で循環させるといった地域内資源循環ともいうべき手法が試みられているのが特徴的である。
近年、日常生活から出る一般廃棄物の増大が問題となっているが、その中でも生ごみ、ふん尿等の有機性廃棄物は依然一定の割合を占めている。最近は、これらの有機性廃棄物を、廃棄物ではなく貴重な資源として堆肥化することが見直され始めた。長井市や日野市の取組では、消費者を一方的な消費者ではなく農産物の母体である土の再生産者として位置づけたうえで、このようなシステムを確立している。一方、農業が衰退している都市域でも、堆肥化の取組に加え、残された農地を保全し、市民農園、さらには援農、農業ボランティアという形で活用、保全していこうという動きがでてきている。
また、食料品についても、近年の環境、安全志向から、有機農産物及び特別栽培農産物(無農薬、無化学肥料、減農薬、減化学肥料)への指向が高まり、急激に需要が増えており、最近は、有機栽培や無農薬・無化学肥料栽培による野菜の利用を始めるレストランも増えてきた。このような農産物の需要の増加は、環境保全型農業の振興を促し、その結果有機質肥料の需要の増加をもたらすであろう。
身近な生活により生じる有機性廃棄物を「循環」させるためには、分別、堆肥化という再資源化が重要であり、そのサイクルを確保するには有機物から再資源化された肥料を受け入れる「農」の存在が求められている。この「農」は、農業に加え市民農園、自家菜園等現代の生活様式に合わせた様々なスタイルが考えられよう。
さらに、幾つかの事例においては、地域内でできるだけ自給することにより地場の新鮮な農産物を求める動きもみられる。長井市では、地産地消をめざし、市街地が大部分を占める日野市においても市民は、地場の新鮮な農産物を求めている。この動きもまた健全な「循環」の観点からも評価することができる。
農業の大規模化及び都市と農村の分化は、効率的な食料生産、分業体制による効率的な経済の発展を可能にした。また、農業経営の安定化のため、また日本どこでも豊富な食材を季節を問わず楽しむ日本人のライフスタイルに対応するために付加価値の高い食物の生産、広域流通は必要な選択であったのだろう。また、世界全体として経済のグローバリゼーション化、自由化している事実も認識する必要がある。しかし、今全国各地で芽生えつつあるこのような地域内資源循環も経済社会の中に組み込んでいくことも、21世紀の地域づくりの要素として注目に値する。
その理由を循環と共生の観点からみてみることとする。まず、窒素のフローの観点から考察してみよう。日本の窒素のフローは第2-3-11図のように移り変わっている。そのうち農産物輸入による窒素の投入量が大きな割合を占めているとともに、窒素全体の投入量が非常に増え、日本内に蓄積されていることが分かる。窒素は、人間の生活を支える上で重要な元素であるが、過剰な窒素は、硝酸性窒素による健康被害、水の富栄養化等環境悪化等につながりかねない。地域内資源循環は、循環システムの運用に係る流通、保存等のエネルギーが削減され、炭素循環からも効率的といえる。農畜水産物の輸送機関別輸送量をみると約70%が自動車(トラック)で輸送、新鮮さを保つという観点からより負荷の少ない鉄道、船舶等への代替は困難という。または予冷施設、保冷車の使用も通常的である。(夏期……30%程度)
さらに、日野のマスタープランは、「広域流通がすっかり確立した現在では、国内はもとより遠い海外からくる多くの農産物によりわたしたちの食べ物への認識はすっかり変わってしまった。食べ物を作るには土や太陽や水などの自然と一定の時間が必要だが、加工を施されすぐ食べるばかりで売られる食べ物からそのことを想像することは難しい。食べ物から自然の恵みを作る人の汗を実感することができればそれを粗末にすることなどが出来ないであろう。人が身の回りから食べ物を得ようとすれば、人は身の回りの環境をこの上がないものとして大切にするだろう。自分が食べる米を育む水ならば人はその水を決して汚そうとはしないはずだ」と訴えている。
この「地域内資源循環の適切な組込み」は、自然のメカニズムと調和しながら健全な「循環」型社会を形成する一つの要素であると同時に、「食」という日常生活の中から自然とふれあい、自然の恵みを体ごと享受する「共生」のために重要な要素であるといえよう。そして、それを確保するために不可欠な地域に残された「農」を再評価することが出来よう。
その他の物質に関しても、地域における小規模なシステムにより供給するシステムが提案されている事例が見受けられる。荏原製作所のエコインダストリアルパークにおいては、都市代謝基盤システムを自立型にしていくとの観点から、「水」については循環利用や雨水利用により、「エネルギー」においては、太陽光、風力等の自然エネルギーの活用により、水については30%、エネルギーについては30%地域内でまかなうことを検討している。
このような地域内資源循環型のシステムを、今後の「生活経済圏」の社会経済構造を構築していくための一つの要素として注目したい。
(3) 人、機能、土地利用等の多様性
第3に、「生活経済圏」における地域づくりを推進する主体とその実行体制に注目してみたい。
まず、共通していえることは、これらの地域づくりの推進主体が様々な立場、分野、年齢の人々にわたっていることである。どの事例も、例えば、行政・事業者・市民という立場の違い、工業・農業という業の相違、環境・農業・福祉・教育等の分野の違い、都市住民・農村住民という地域の違い、老年・婦人・青年等年齢や性別の違い等、様々な観点からみた多様な人々が関わっている。
今日の経済社会では、これらの人々が、それぞれに異なる立場で環境保全に関わっている。ときには、立場の違いからや利害が対立することもあるだろう。しかし「生活経済圏」においてはこれらの人々が相互に働きかけ、共通の認識を作り、連携・協力体制を組んでいくことにより、自然のメカニズムが認識され、配慮の手法が見いだされるのであろう。
この連携体制のあり方を考える上で考慮すべき観点が幾つか抽出できよう。
まずは、行政、事業者、市民とのパートナーシップである。
次に、都市住民と農山村住民との連携があげられる。長井市のレインボータウン計画の「レインボー」という言葉には、「町と農村との間に希望の橋を架けよう。生産と消費の関係の中に希望の橋を架けよう」という願いが込められている。すなわち農村住民は生産活動において、町の住民は消費活動において、町の全員が「土づくり」に参加し、持続可能な生産や生活のあり方を見い出していくプランなのである。日野市においても、農が息づくまちを作るために市民が耕す農支援や援農の仕組みづくりの提案がなされ、ファーマーズセンターが建設予定されている。 都市の住民が森林づくりを手伝うネットワーク団体の森づくりフォーラムや横浜市民の森づくりのように、里山林の維持管理に都市住民が森林づくりを手伝う動きもでてきている。
このような地域内における連携体制に加え、酪農王国では、都市住民の当該地域への訪問、滞在を推進している。この交流により、都市住民に自然とのふれあいの機会や休養の場を提供するとともに、酪農王国の住民に対しても、精神的、経済的な元気づけを与えられるのである。このように都市住民と農山村住民は、消費者と生産者、生産支援者と生産者、地域資源評価者と地域資源保全者として、様々な形で密接に関わり合っている。
環境庁が全都道府県・政令市、関東圏の市区において実施した「環境保全の観点からの国土利用・土地利用の調査」において、都市部と農山村部との連携についての取組は、あまり実施されていないものの、多くの自治体において関心が高いことが明らかになった。(第2-3-12図)
さらに、地域を構成する産業構成、機能の観点からみてみよう。興味深いのは、農業・工業・住居・商業等異なる業種・立場の連携が図られていることである。すなわち、農林水産業(第1次産業)と工業(第2次産業)と都市(第3次産業・居住生活地域)が資源利用と空間利用において、連携・調和して存在することによってはじめて、完結した有効な資源の循環と自然との共生が実現されていることである。酪農王国では、農を主体に工業、商業の連携が図られ、エコインダストリアルパークでは、住居と工業と農業が連携した新たな生活と経済の場が提案されている。長井市のレインボー計画は、農業と住居の連携であるが、今後工業、商業版のレインボー計画が検討されるようである。またこれらの要素の一つが欠ければ、効率的な循環は達成されないであろうし、豊かで多様な人間生活も実現しにくいであろう。
これらは、いいかえれば、農林水産品の生産主体である第1次産業、その加工、再利用を確保する第2次産業、消費者のもとに生産物を流通させ、廃棄物を消費者から生産者の元へと循環させる第3次産業のバランスが求められているともいえよう。最近の生産と加工、流通のすべてを担うという農業の6次産業化もこの動きに沿ったものと言える。
囲み2-3-2 農業の6次産業化の動き
近年の我が国全体の飲食費に占める帰属割合の動向を見ると、農水産業のシェアが低下する反面、食料消費の外部化・サービス化等に伴い外食産業を中心に食品産業のシェアの高まりがみられる。
農業の6次産業化とはこのような食に関してのサービス・付加価値を高めることを農業自らが行う、すなわち農業に「1次産業+2次産業+3次産業=6次産業」の機能を持たせ、農業・農村を豊かに活力のあるものにしようという提案である。近年、農業の6次産業化を目指す動きが活発化しているが、山口県の船方グループの取組は先進的な取組である。
船方グループは、農業生産を担当する有限会社船方総合農場と加工流通を分担する株式会社みるくたうん、都市交流を分担する株式会社グリーンヒルATO及びこれらを総合調整する緑の風協同組合3から成り立っている。農場で生産された牛乳をみるくたうんでチーズ等に加工し、グリーンヒルによりレストランや宅配により消費者への販売を行う。農場には農業を営む景観を求めて年間12万人の人々が訪れる。ここでは、1次、2次、3次産業の部分が密接な相互補完関係にある。総合農場の内部においても酪農、肉牛、稲作のなかで循環型のシステムが構築されている。第6次産業は、地域内資源循環が、効率的にまた農業の活性化をもたらす形で実現されるシステムとして今後の発展が期待される。
人、業、機能の連携は、人間の経済活動を保証しつつ、資源の効率的な循環、人間の効率的な活動を確保するとともに、人間と自然との共生を確保するために不可欠な要素なのである。このような形の連携は、各機能が共存関係、相互補完関係にあることにより、相乗効果を生み、全体としての地域経済の活性化をもたらすことができよう。そして、これらの経済活動が環境保全をより進めることにもなるのである。
上記のような様々な立場の人、業が連携の地域レベルで確保するためには、それらの空間的な近接性、連携が必要となってこよう。そこで、土地利用においても例えば、農地と市街地の近接化、共存といった空間的な配置を考慮することによる、生活と産業、消費と生産が最適な関係にある地域社会の形成が重要である。
その一つの方向性として、地域における都市型土地利用と農山村型土地利用の共存があげられよう。多くの都市で市街化の拡大が進められてきたが、一方で地域によっては共存のあり方も、模索されてきたところもある。例えば、横浜市の港北区では都市化と農業との調和のある発展を促すために、農業専用区域という永続的農地保全を目指す農地確保手法を行ったり、帯広では、市街地を緑でつつむことにより市街化の無秩序な拡大を防いでいる。さらにこの森は、「帯広の森」として、市民と自然及び町の住民と農山村の住民同士のふれあいの場ともなってきた。さらに土地区画整理事業における運用上の配慮等により市街地と農村との共存を図る取組が試みられている地域もある。環境庁が行った自治体へのアンケート結果においても、住宅、緑地、農地等との共存を促す施策を実施している自治体は多くはなかったが、検討中、将来的に検討したいと回答した自治体はかなりの数にのぼった。このことから、多くの自治体において「共存」指向が高まっていることがうかがえる。(第2-3-13図)
さらに、人と人、業と業、人と業をつなげるためには、道、交通のあり方も重要になってこよう。市民版・日野・まち作りマスタープランでは、市街地を通過する道路は十分に整備されているものの、人と人を結ぶ生活の道が不十分であることを指摘している。交通体系についても、これらの様々な立場の人、業を有機的に連携させるという観点から必要な道、運輸手法が設定されていくことが望まれる。
(4) 身の丈にあった地域づくり
近年の、人間活動の領域の拡大、経済活動の分業化等により、人間活動全体が非常に見えにくくなってきている。ここで取りあげた事例は、人間が直接的に触れることができる範囲で捉えた「身の丈にあった地域づくり」が目指されているといえよう。
「アワニー原則」においては、コミュニティの原則を最初に位置づけ、人間活動におけるコミュニティの重要性を強調している。さらにコミュニティとそれを含む地域の開発について、全体計画と各種計画との整合性の必要性を訴え、生物たる人間の活動に合わせたものを奨励している。
ポートランド市では、都市の無秩序な成長の抑制を目指すことにより、既存市街地の高密度化の土地利用を進め、自動車交通に依存しない交通体系を整備する等土地政策と交通政策を統合することにより、低負荷型の生活を営むことができるまちづくりをめざしている。そしてそれが住民への我慢の強要ではなく、何よりも住民の住みやすさのためであるということに注目をすべきである。
エコ・インダストリアルパークにおいては、地域内に小規模なシステムを導入することにより、物質、水、エネルギー等の都市代謝基盤システムを自立型、循環型にすることを目指している。
また、市民版・日野・まちづくりマスタープランでは、自分が必要なものは、自分の力で作り上げ、自分が必要でなくなったものは自分の力で処理する「自立した成熟したまち」を目標としている。
これらは、自分の生活において、自然のメカニズムをなるべく完結した形で捉え、身の丈にあった社会を構築することを目指したものであるといえよう。
(5) 生活経済圏の捉え方
以上、生活経済圏を構成する要素について、紹介した事例を基に抽出してみた。すなわち、
自然のメカニズムと人間活動との調和を図るため、
? 自然のメカニズムに調和した「自然と人間との共生の歴史等を生かす」こと
? 「地域内資源循環の適切な組み込み」を考慮すること
? 「人、機能、土地利用等の多様性」
? 「身の丈にあったまちづくり」
が重要であることを述べた。
生活経済圏は、生態圏や流域圏を構成する地域をミクロにとらえたものであると同時に、生態圏や流域圏と一致することも想定されよう。前者の生活経済圏は、一定の自立性を確保しつつ、生態圏、流域圏における他の同等の規模の生活経済圏と連携、相互補完関係を結ぶことによりより豊かな「循環」と「共生」を実現させ、このような連携体制が全体として生態圏、流域圏を構成することが望ましいであろう。例えば、生態圏における渡り鳥の湿地ネットワーク、また流域圏における上流域と沿岸域の連携は、まさにこういった関係にあるといえる。
また、生態圏、流域圏が一つの生活経済圏として捉えられることもあろう。例えば、山地から平地、沿岸域までにわたる全域的なビオトープの保全を、そこに関わる人間活動との調整を行いながら進める場合にはそれを一つの生活経済圏として一体的に捉え、人間活動と自然のメカニズムとの調整を図っていくことが望ましい。流域圏においても、例えば桂川・相模川の事例のように上流域の森林で製造された製品の流域内での利用、また近年注目がむけられつつある舟運による人流、物流の復活等、生活経済圏と流域圏の一致が指向されてきていることがわかる。(第2-3-14図)
このような、生活経済圏において、そこに暮らす人々は、自分の生活の中で自然のメカニズムをできるだけ完結した形で捉えることができ、「循環」と「共生」を実現する生活が容易になるのではないかと考えている。
『生活経済圏における連携のあり方』
?自然のメカニズムの連携・相互補完関係
↓ 水、緑、大気、土等
?物質循環の連携 物質、水、エネルギー
↓
?人々の連携 市民と農民、市民と林業者や土地所有者
市民と事業者等 市民と行政と事業者
↓
?業(系)としての連携
農・工・住居・商業の連携
第1次産業、第2次産業、第3次産業の連携
↓
?機能の連携 都市機能と農村機能の共存、
道、場(市民農園、交流センター)、
↓
?ネットワークによる連携 ネットワーク組織