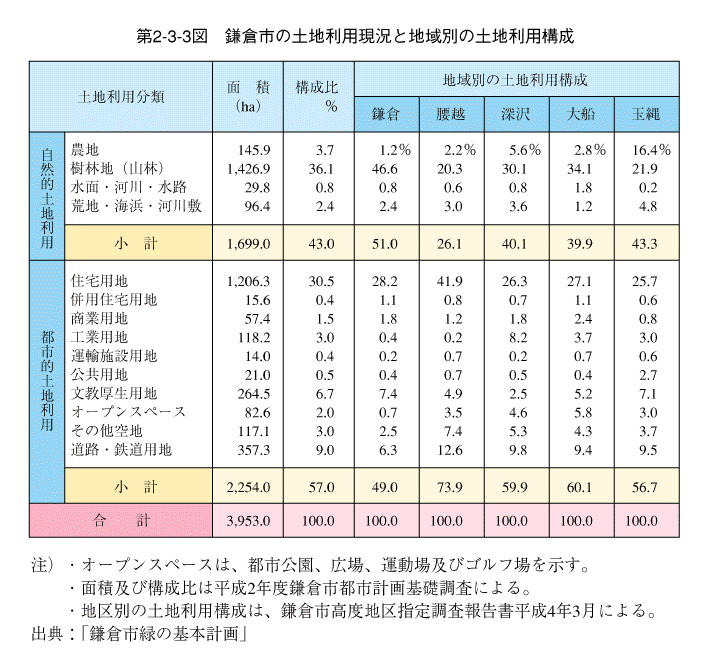
3 「循環」と「共生」を目指す様々な地域づくり
自然のメカニズムと人間活動との調和を図り、「循環」と「共生」を実現する様々な取組をさらに広く紹介することにより、生活経済圏を構成する要素を抽出したい。
(1) 鎌倉市における環境配慮を軸とした各種計画の策定と市民参画型地域づくり
神奈川県鎌倉市は、我が国のナショナルトラスト運動発祥の地であり、その運動が古都保存法(古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法)の制定へと結びついたことは広く知られている。海山が近接した自然環境は古くから文化人に愛され、住民の環境保全意識も高いと言われている。同市では「環境自治体」の創造を掲げ、市民参画のまちづくりを進めている。
ア 鎌倉市緑の基本計画
鎌倉市は東京から50km南西に位置しており、身近に海・山がある起伏に富んだ地形に制約されたコンパクトな都市構造を持っている。平成7年10月現在、人口は約17万人。土地利用は第2-3-3図のとおりである。首都圏にある都市の中では比較的緑に恵まれているが、樹林地は年々減少しており、平成2年時点では市面積の約36%となっている。緑被面積を見ると、その約94%は民有地の緑によって占められており、約42%が都市計画法の市街化区域に分布している(第2-3-4図)。平成6年に都市緑地保全法が改正され、新たに都市計画区域内における緑地の保全及び緑地の推進に関する基本計画(緑の基本計画)を市町村が策定できることとなった。そこで鎌倉市は、一般公募から選ばれた市民委員も積極的に参画し、平成8年4月に「鎌倉市緑の基本計画」を策定した。
この計画は、鎌倉市が市民参加のもとに主体的に策定する計画として、?自然共生型・低負荷型の都市環境の形成、?古都の歴史的風土の保全・継承、?自然・歴史とまち並みが融和した都市景観の形成、?緑を基盤とした安全性の高い都市空間の形成、?多様なレクリエーション活動の場を備えた都市空間の形成、の5つを計画のテーマとした。これらのテーマごとに緑地の役割・機能をA〜Cランクまで評価し、総合的に市内の緑地について3段階評価を行い、それぞれの緑地に合った保全施策を行うものである。
計画の第一のテーマである、自然共生型・低負荷型の都市環境の形成については、自然との共生、健全な水循環の確保、ヒートアイランドの防止のため、市内の丘陵部にある緑地を骨格軸として確保しビオトープネットワークを形成させるとともに、谷戸、海岸線の自然的環境を保全し、河川や道路沿いなどにも緑地を整備することとしている。
また、計画では、鎌倉市が2015年に確保すべき緑の量を市全体の5割をめざすこととしており、市民、行政、事業者による積極的な取組が期待されている。
イ 鎌倉地域交通計画の策定と交通需要管理の検討
鎌倉市は全国有数の観光地であり、年間約2,000万人の観光客が訪れ、休日には市内の主要道路は大渋滞となる。中でも市中心部にある鎌倉地域は、古都としての歴史的環境の保全という課題と道路建設の推進というジレンマを抱えていた。しかし、平成7年7月に市民を中心とした38名の委員で構成される「鎌倉地域地区交通計画研究会」が設置され、平成8年5月には会の提言がまとめられた。その中では、まず鎌倉地域の交通混雑の解消には「自動車利用の抑制」を基盤とし、「公共交通機関への転換」や「歩行・居住環境の向上」を図るため、パークアンドライドやロードプライシングなどの施策を活用するよう提言している。
この提言を受け、市は研究会と協同で平成8年11月23日から24日にかけ、国道134号線沿いの駐車場と江ノ島電鉄を利用したパークアンドライドの交通実験を実施した。この実験では、観光客の自動車から公共交通機関への乗り換えの可能性と、取組み自体を広く周知させることを目的とし、実験参加者のアンケートを行った。今後は、この鎌倉地区交通計画を含めた市全体の交通のあり方を、都市マスタープランの掲げる基本目標の一つとして位置付けた。しかし、鎌倉市周辺は通過交通も多く、鎌倉市一市だけでは解決が困難な問題でもあり、周辺市町との連携が今後の課題であると言える。
ウ 都市マスタープランの策定
鎌倉市の第3次総合計画基本構想では、「人と人間が共生し、災害に強いまちづくりをめざす環境自治体の創造」をまちづくりの基本理念の一つとして掲げており、平成6年には市の環境基本計画を策定した。さらに平成10年3月には、都市計画法に基づく都市マスタープランを策定した。この策定作業では、まず「たたき台」を作る段階で、市域を11の地域に区分してその地域住民による「ワークショップ」を開催(4回で延べ290人参加)し、地域ごとのまちづくりに関する課題や方針について検討を行った。その後平成8年12月には、「鎌倉都市マスタープラン策定員会」(公募市民15人、団体推薦市民5人、学識経験者6人の構成)が設立され、議論を重ねた。委員会の検討状況についても市のインターネットホームページに掲載、ネット上の談話室へ誰でも自由に意見を送信することができるようにするなど、市民参加型の都市マスタープラン策定に取り組んだ。
(2) 市民版・日野のまちづくりマスタープランと農の息づく地域づくり−都市型の循環と共生の地域づくりの提案−
ア 市民版・日野まちづくりマスタープラン
東京の多摩地域に位置する日野市は、市のほとんどが市街化区域に指定されているにも関わらず、多くの農地が残されている町である。日野市は、多摩川中流域の典型的な米作地帯で、1950年代から60年代の初めは、市の面積の30%は農地で、市内で働く人の30%は農業に従事していた。ところが60年代に入り、高度経済成長を支える都市型労働者のベッドタウンとしての変身を余儀なくされていった。その過程で、市内の丘陵地、台地上に大規模な団地が造成され、また川沿い、水田地帯にも宅地造成が増加し、人口が飛躍的に増加していった。(第2-3-5図、第2-3-6図)
このような都市化が進められてきた日野市において、平成7年4月に日野市の市民が中心となって市民版・日野・まちづくりマスタープラン(以下、マスタープランという。)が策定された。これは、平成5年に日野市の市長選がきっかけとなって、それまで個別分野毎に活動していた環境・農業・食べ物・生協・福祉・教育・人権等の市民グループが、共同してマスタープランを作成したものである。マスタープランの作成にあたっての当初の課題は、それぞれ蓄積したノウハウをお互いに分かり合える言葉で表現できるか、個別の取組が「まちづくり」をキーワードとして一つの体系に融合できるかということであった。
マスタープランの作成に当たっては、「みどり」「くらし」「いのち」の3つの部会を設置し、これらの部会に共通するテーマについては「まちづくり会議」を開き、各部会のメンバーが合流して検討する場を設けるなど、議論を進めていくうちに、それぞれの分野を複合的に組み合わせて始めて、望ましいまちづくりが実現できることが認識されていった。(第2-3-7図)
マスタープランは、日野のまちを、若者、障害を持つ人、高齢者等さまざまな市民の単なる「ねぐら」ではなく、「多様な人間の暮らし」を支え、多様な人間の折り合いを図る場として位置づけ、そのためには農の営みによって維持されてきた日野市の「伝統的なたたずまい」を構成している水とみどりの保全を図っていく必要性があることを指摘している。その上で、「多様な人間の暮らし」を可能にする手法と「伝統的なたたずまい」を保全・再生させる手法との結びつきが必要であることを強調している。そこで「都市の自立と成熟」をキーワードに、この2つの折り合いをつける手法を「命をつなぐ水」「ゴミとのつきあい方」「農のいきづくまち」「暮らしを形づくる仕組み」等の観点から記述している。例えば、「命をつなぐ水」としては、浅川を出発点とした多摩川流域を視野に入れた水循環の保全の必要性を論じ、周辺市町村を含めた「水とみどりの市民会議」の構想を提示している。またマスタープランでは、人間の暮らしとしてどのようなものが望ましいかということを、単なる快適性にとどまらない人間主体の本来あるべき姿があるか、つまりアメニティがあるかということを判断基準として用いて分析を行っている。
マスタープランでは、30年ほど前には日野の経済を支える中心的な存在であった「農」をとりあげ、「循環」と「共生」の暮らしを実現するための一つのあり方として「農」の息づくまちを提案している。ここでは、「農」を単に農地を耕し食料を生産する行為としてではなく、自然の循環を損なわずに暮らすための知恵と営みの総体としてとらえている。「農は、人間が自然の一部として、自然に生かされているという倫理のある暮らし方と言ってもいいだろうか。そのような『農』を暮らしの場に取り戻し、土や水や大気と直接交われば、都市的暮らしで萎えた肉体と精神はよみがえり、身の丈にあった小規模な生産の仕組みを手に入れることができるようになるであろう」と論じている。
具体的な提案としては、市民たちを都市農業における耕作主体として位置づけ、利用者相互の自主運営を主体とした市民農園、各小中学校での学校農園の設置、さらには、兼業化、高齢化が進む農家を市民が応援する手法として、市民の援農を組織化して定期的に労力を提供する「援農ワーカーズ」の結成等、市民と農家との交流をベースにした斬新な提案がなされている。さらに、人と自然とが食べ物を通じてつながっていること、人間は自然と生き生きと交流して始めて健康さを身につけることが出来るとの認識から、地域で多様な食べ物を生産し、それを地域の人々が消費する「地産地消」を実現するため、例えば学校給食における地場の農産物の利用、市内農産物の加工と流通の仕組みを提案するとともに、これらを支える兼業農家の重要性、水田の保全の重要性を強調している。これらの提案の根拠は、地域にある人材と素材、つまり多様な人間と地域の自然的、伝統的要素を最大限生かすことにより、「循環・共生」の地域づくりを目指すことにある。
イ 日野市の行政における取組
日野市では、都市において農のあるまちづくりを実現するためには、農家と市民との相互理解や交流が不可欠であるのと認識に立ち、農業団体、市民、研究者、行政関係者による「農のあるまちづくり委員会」を設置して、土地区画整理事業を前提としながら、「農のあるまちづくり」の実現手法について検討を行い、その結果を平成6年にとりまとめている。そこでは、農家、市民、行政、農協等団体との協働により、土地区画整理事業を通して、環境、景観、文化等の総合的視点に立って、農のあるまちづくりを目指すこととされている。区画整理を通したまちづくりとしては、農業専用街区、散在地の農地の保全、水田の保全、さらには、宅地部分を含め農のあるまちづくりにふさわしい土地利用、市民との交流拠点の確保、有機農業の推進等の提案がなされている。さらには、農業への市民の援農の仕組みや、市民農園、学校給食での市内農産物の活用等マスタープランにおいて提案されていた事項も含まれている。
日野市では、本報告書に基づき、農家と地域住民との交流の場としてのファーマーズセンターの計画や生態系豊かな農業用水路整備が始まった。
現在、日野市では環境基本計画、緑の基本計画の策定が検討されているほか、平成10年3月には農業を市の基本産業として位置づけた農業基本条例が制定された。この条例は、農業の生産機能だけでなく、環境保全機能を明確に位置づけたものとして注目される。日野市におけるこれらの取組が、さらに具体的に進められていくことを期待したい。
(3) 緑と清流・活力のあるゆとりの里づくりをめざす木頭村のまちづくり
徳島県最南西端、清流那賀川の最上部に位置する水源の村の木頭村において、緑と清流・活力のあるゆとりの里づくりが進められている。
木頭村は、全国屈指の清流である那賀川の川の幸と村面積の98%を占める森林から得られる山の幸に恵まれた山村である。村の主産業は木頭杉の銘柄を持つ林業と、高品質の木頭ゆずを中心とした農業及びあめご・うなぎを中心とした内水面漁業の第1次産業及び建設業が中心となっている。このような木頭村において、村民は、川と森林がもたらす恩恵を存分に受けながら、森林と川に深く関わりのある生活様式を形成してきた。
一方、木頭村では、主産業である林業の経営難、人口の減少に伴う農林業等の産業の担い手不足等の多くの日本の中山間地と同様の問題を抱えている。また、木頭村内に予定されていた細川内ダムは現在のところ事業が一時休止されている状況にある。
このような状況下、木頭村では、住民と事業者、行政とが一体となった環境保全型の地域づくりの取組を始めている。
平成8年度に策定された第3次総合振興計画においては、村の防災と環境保全を枠組みとし、住民参加と住民自治を原則とした、安全な那賀川流域づくりと流域との共同を目指した町作りを行っていくことを基本としている。木頭村では、住民参加による村づくり事業検討委員会を開催し、そこで森林の公益的機能の維持と林業の活性化が村の最重要課題として取り上げられた。そこで、木頭村の森林管理のために必要な間伐を進めるため、林業者間の共同施業、それに必要な林道、作業道の整備を計画的に実施し、建設業と提携した木頭杉による住宅一貫生産を検討している。ここでは、このように村民の多くが従事している村の公共事業も産業の振興、環境保全と調和する形で実施している。
さらに、木頭村の新たな特産品づくりを目指した第3セクター方式で「きとうむら」という会社が設立された。これは、地域資源を活用し、応援する新たな村づくりである。木頭村で生産された大豆、ゆず、さらに那賀川流域の町村で生産されているすぎな等を用いて、豆乳をベースにしたムース、しぼりかすのおからを用いたおからケーキを製造している。また、きとうむらの工場は、村で加工された間伐材の集成材を利用して建設されている。さらに今後は、村で廃棄・回収されたペットボトルに那賀川の水を入れて、ミネラルウオーターとして提供したり、人手不足に悩む農業に人手を派遣する等、木頭村及び流域の資源を活用した環境保全型のまちづくり拠点たるべく、事業展開をすすめている。このように木頭村は、村民自治を基本に、農林業等の地域産業の活性化を図っている。
また、木頭村の教育も木頭村ならではの自然教育が実施されている。ブナの植林や、田植え等木頭村の自然や伝統・文化を、目で見て、足で確かめ、手で触れることにより、心と体で体験するふるさと教育を推進している。さらに木頭村の良さを引き出しつつ、都市市民の自然環境指向のニーズを満たすための交流・観光事業も構想されている。
木頭村は、村民と村の行政が力を合わせて、自然のメカニズムを尊重し、最大限生かしつつ、大規模な公共事業に依存しないで地域の産業の活性化を行うまちづくりを模索している山村といえよう。
(4) 新たな地域づくりの構想・荏原製作所のゼロエミッション・エコインダストリアルパーク構想
環境総合エンジニアリング会社である荏原製作所では、平成7年度から、環境共生型の住宅、工業、農業連携型タウンとして「エコインダストリアルパーク」構想が検討され、2010年の完成を目指して事業を開始された。(第2-3-8図)
本構想は、大量生産、大量消費、大量廃棄のライフスタイルを背景とした現在を見直し、環境共生型産業、循環型都市構造を実現し、都市代謝基盤システムを自立型、循環型に作り替えることを目指した新しいまちづくりの構想である。さらにそのシステムによりパーク全体の環境負荷を少なく押さえると同時に、居住者のライフスタイルを環境調和型に変換していくこと、周辺地域、他の産業との連携や情報発信を通じて地域社会との連携を実現することを模索しているものである。
本構想は「ハードの技術の実施」のみならずゼロエミッションを実施するためのタウンマネジメント、人間の価値観の問題にも関係する「ハード・ソフト・ハート」一体型の「循環社会システム実験事業」といえよう。エコインダストリアルパークは、6haの敷地に約1500人分の寿命100年の環境共生型住宅を建設し、街の代謝基盤を自立させるためのコンポスト、メタン発酵、廃棄物の固形燃料化等の物質循環システム、中水道、雨水利用、ビオトープ等の水環境保全型システム、蓄熱層、風力発電、太陽光電池、燃料電池等の再生可能エネルギーシステムを組み込んだゼロエミッションセンターを配置する。さらにパークの中に農園を設置することにより、住宅から排出される廃棄物の循環を確保する等、工業系と住居系と農業系を有機的に連結させることをねらっている。
本構想の実現後の環境負荷のシミュレーションを行っているが、その結果、ゼロエミッションを試みなかった場合と比較して、電気、水道等の公共サービスの利用量がエネルギーでは38%、水では28%、廃棄物では96%削減し、二酸化炭素排出量も30%削減するという試算も行っている。また、ビオトープ等の公園、農園等を緑、水、生態系、そして土に親しむ「循環」と「共生」を実現するライフスタイルを選択し享受できる場として位置づけている。
さらに、パーク全体を荏原製作所の従業員だけでなく、地域に開放し、または地域で生産された産品をパーク内の「エコストア」に流通させる等地域との密接な連携の確保も検討している。
このエコインダストリアルパークが構想する、街全体における住工農の混在型システムは、自然のメカニズムを活用し、循環と共生を実現する生活経済圏の一つの重要な要素といえよう。