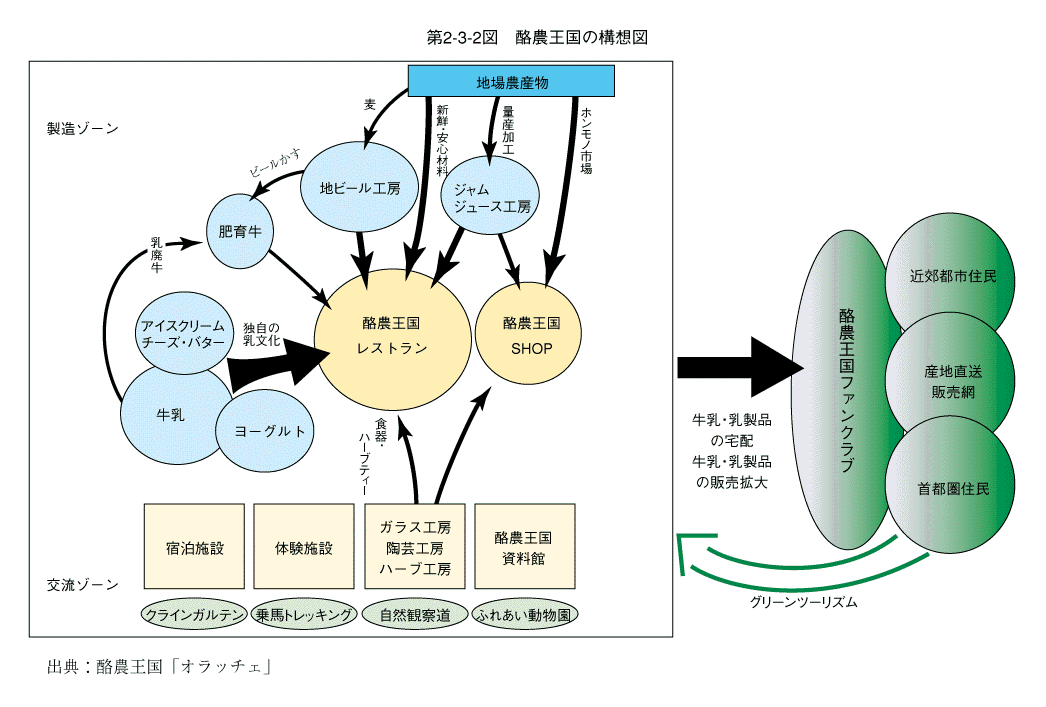
2 自然のメカニズムを活用した物質循環を実現させる試み
環境の保全と利用に当たって要をなしているのは、環境を形成する生態系の物質循環であり、この物質循環は、自然のメカニズムの主要な要素である。人間活動はこの物質循環に非常に大きな影響を与えている。 この物質循環は、自然のメカニズムによって行われる部分と人間が介入する部分があるが、ここでは、自然のメカニズムと人間活動が調和して実現される物質循環を模索する取組を紹介したい。
(1) 自然循環農業(米沢郷牧場における20年の取組)
山形県の東南部に位置する高畠町を中心に1市2町にまたがる地域に広がっている米沢郷牧場は、米、野菜等の栽培と畜産を組み合わせ、「自然循環農業」に取り組んでいる。米沢郷牧場は、伊藤幸吉氏が代表を務める農事組合法人であり、昭和53年に4人で始めてから除々に組合員が増加し、現在は、組合員、準組合員を併せて約270戸の農家で構成されている。米沢郷牧場の取組は、畜産農家がオイルショックを契機に多角経営の必要性を認識したことに始まる。それから、20年間試行錯誤しながら「自然循環農業」のしくみ、技術を構築してきた。
米沢郷牧場では、日光、温度、雨、土、水、大気の相互関係の下、人間、作物、動物が生かされているという認識のもとに、米、野菜等の栽培と畜産を組み合わせることにより「自然循環農業」の実現を図っている。具体的には、米を生産する過程で生じる米ヌカや豆腐の製造過程で生じるおから等の副産物を有効な資源ととらえ、これにポストハーベストフリー(収穫後の農薬処理をおこなっていない)のトウモロコシを混合して飼料として家畜に給与する一方、家畜から出されるふん尿については自然に存在する微生物の作用により浄化処理を行ったり、発酵処理を行うことにより良質な堆肥を製造し、牛舎や鶏舎の敷料として利用したり、米や野菜、果樹の肥料として利用している。さらに、稲ワラは家畜の飼料に、モミ殻は畜舎の敷料に利用し、循環させるなど、無駄のない農業をめざしている。牛、鶏の畜舎の中にもみわら、堆肥を敷き詰め、敷料として用いその中にふんをさせることで、畜舎のにおいが少なくなり、かつ、ふん出しという手間のかかる作業を省くことができるという。
また、生産された堆肥は、必要最低限度の窒素成分を含めた(1%)肥料へと調整して用いられている。その結果、作物には虫がほとんどよりつかなくなり、無農薬栽培を容易にするとともに、水質汚濁を引き起こすこともなくなったという。
本牧場では、畜産、堆肥化の部分を法人化することにより効率化し、農業の中にも機械化、合理化を取り入れることで、農家の週休2日制を可能にしている。その結果、農業法人の組合数は増え、後継者不足、高齢化とは無縁の農業を継続しているとのことである。また、米の収量は有機栽培で10アールあたり600kgを越える高い生産性を上げている。代表を務める伊藤氏は「農業は芸術である。自然循環農業は楽しくて、多くの収穫をあげる。伝統的な農業を基とし、新しい技術を利用して、よりよい農業へと発展させることが重要」という。
こうした米沢郷牧場の取り組みは長年にわたる取り組みを通して構築されてきたものであり、また、地域的な条件もあるため、すぐに、模倣できるものではないが、「有機物の物質循環」の実現を図っている取り組みとして注目に値するといえよう。
(2) 台所と農業をつなぐながい計画(レインボープラン)
山形県長井市では、「台所と農業をつなぐながい計画」(略称レインボープラン)という、家庭や事業所から分別収集した生ごみで堆肥を作り、その堆肥を農家に供給し、農家が生産した農産物を市民や事業所が購入するという地域循環システムを作ることを目標とする事業を、平成9年冬から本格的に開始した。
山形県長井市は、人口約3万3千人で9千世帯、そのうち市街地に5千世帯、周辺の農村部に4千世帯が住んでいるまちである。このまちで、1988年に「自分たちが住みたくなるようなまちを構想しよう」と市民百人が集まったのがきっかけで、レインボープランと名付けられた計画の調査委員会が設けられた。以来、7年あまり200回を越える会議が開催され、様々なモデル事業を重ねてきた。その結果、以下のようなプランの本格実施に移ろうとしている。まず、市民が家庭の生ごみ類を台所から分別し、さらに農家のモミ殻など、これまで地域社会の中で廃棄されていた物をすべて集めて堆肥センターに投入する。堆肥センターで出来た堆肥は農協を通して農家に販売されるが、その価格は堆肥センターでの製造費に関係なく、農家が買いやすい価格に設定する。差額は、土を健康に保ち、やがて安全な食べ物として還元される経費つまり公共の福祉に資する経費として、行政が負担する。畑では、この堆肥を利用し、なるべく農薬や化学肥料を使用せずに作物を作るというものである。
従来は、農作物は付加価値商品として大都会に運ばれていたが、このプランでは、まず市の学校給食に活用され、さらにスーパーを通して一般家庭に運ぶことによる地域の自給を目指している。この背景には、長井の農地の土が衰えていること、つまり土は水をかん養し、食べ物を作る基盤であり、わずか1gの土の中に億を越える微生物の住む場所であり、このような土がやせ衰えることはすべての生命力が衰えることにつながるとの認識がある。そこで地域内の資源である市内の有機物の活用により土を再生していくことが必要だったのである。さらに、市域の自給率は5%程度で、よいものはすべて大都会に出荷され、都会で並ばなかったUターン野菜や地域以外の産地の食品に頼っていた。このような中、長井市民の93%は地元の安全で新鮮な野菜を食べることを望んでいたのである。
市街地を農村地域で取り囲むという市の構造、そしてコンセンサスが得られやすい3万3千人という人口規模が有機物の循環システムの構築に当たって適当な規模、構成であったといえよう。
(3) 丹那酪農王国「オラッチェ」
ア 酪農王国の誕生
平成9年9月、伊豆半島の付け根、静岡県函南町の丹那盆地に、農業振興と、都市と農村の人々の交流の拠点として、酪農王国「オラッチェ」(以下「酪農王国」と呼ぶ)がオープンした。丹那盆地は、周りを山で囲まれたふちのある小さなお盆のような地形で、その中には、緑豊かで牧歌的な風景が広がっており、古くから酪農が行われている地域として知られている。
酪農王国は、こうした丹那の自然と牛乳をはじめとする産物を活かした酪農テーマパークであり、10年、20年先をも見通せる地域づくりの核となることを目指して開設された。運営は、町、農協、食品加工業者、有機農産物の宅配団体、環境NGO、生協により構成される第3セクターが行っており、現在、チーズ、アイスクリーム、バター工房、ジャム、ジュース、ケーキ工房、地ビール工房、レストラン、花の温室などの施設が完成している。
オラッチェ王国憲章
Organic………有機農業のすばらしさに触れて下さい
Refresh………心身の疲れを癒し、元気になって下さい
Agriculture…農業の大切さを知って下さい
Tanna…………酪農の里「丹那」を第2の故郷にして下さい
Comfortable…澄んだ森の空気と緑を楽しんで下さい
Healthy………自分、家族、みんなの健康について考えて下さい
Ecology………地球環境の未来について考えて下さい
イ 酪農王国への期待
丹那盆地で飼われている乳牛の頭数は、10年前よりやや増えている一方、酪農家の戸数は、6割程度に減少しており、酪農家の規模拡大は進んでいる。しかしながら、その他の飲料との競合等による価格低下などの影響を受け、生産額は横這いとなっているのが現状である。酪農王国は、こうした厳しい情勢、乳製品の国際化の中で、優れた牛乳、古くからの酪農の歴史により育まれた乳文化、首都圏から比較的近距離にあることなどを活かして、消費者と直結した安定した流通や地域内の雇用増加を実現させる場となってほしいという、地元の期待を担っている。
こうしたことから酪農王国には、都市などに住む外の消費者との交流が欠かせない。また、逆に、運営に消費者団体が関わっていることからもわかるとおり、酪農王国は、豊かな自然とふれあい、安全でおいしい物を食べたいという都市に住む人々の願いに応えうるものとしても期待されている。
酪農王国は、このように「生産者と消費者の交流基地」となることを目指すとともに、極力、地域における資源の循環を実現させることも考慮に入れている。例えば、丹那の酪農家や有機栽培農家は、酪農王国のレストランや工房、ショップに、牛乳や野菜、果物、麦等を持ち込む。これらは、そのままの形で、あるいは加工されて、料理や乳製品、ビール等になり、地域や都市の住民に丹那の味を提供する。ビールは麦だけでなく、水についても地元の天然水を利用する。また、酪農王国から出る生ごみは堆肥として農家に戻し、ビールかすは乳廃牛を肥育するための良質のえさとして利用し、これにより生産された牛肉は酪農王国のレストランで地元の食材として食べてもらう、といった構想である。さらに酪農王国は、食のみならず、牧場体験、農業体験の機会提供や様々な自然とふれあうイベント等の開催を計画している(第2-3-2図)。また、ビールは、宅配団体によって都市の住民にも配達され、会員の間ではビールびんの回収システムも構築されている。
この酪農王国によって、地元の酪農をはじめとする産業が持続的に発展することより、地域の自然も保全され、またその過程で、都市にすむ人々も自然の恩恵を受けるという、都市と農村の交流の理想的な形が具現化されることが期待される。
酪農王国は、このように、畜産を含む農業とそれを加工する工業、さらには流通業が相互に連携することにより実現される循環システムを構築するものといえよう。