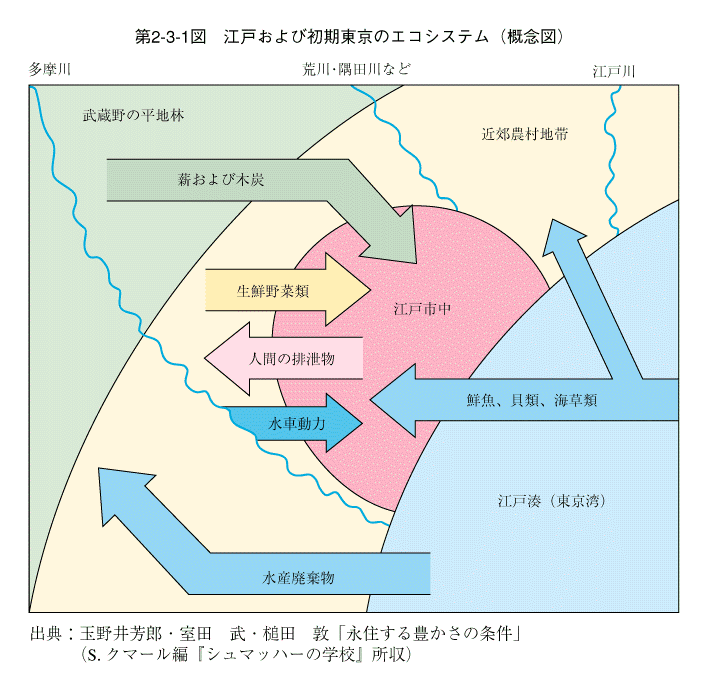
1 人間の活動領域の拡大
(1) 人間の「生活経済圏」
人間が積極的に自然環境への働きかけを行い、人間的要素が自然的要素に優越する活動を行う際には、両者のバランスを取り、より自然のメカニズムに配慮することが望まれる。
国土を規定する人間的要素は、前項で概観したように人間の活動全般である。これらの様々な人間活動を基礎として、自然のメカニズムとの調和を図る上である程度完結した人間活動のまとまりを、国土を規定する自然的要素を基礎として捉えた生態圏、流域圏に対して、「生活経済圏」として捉えてみることにする。以下、「生活経済圏」とは具体的にどのようなものか、そして生活経済圏の中における自然のメカニズムへの配慮の手法について具体的な事例をもとに考察してみよう。
(2) 我が国における経済社会の変遷
我が国における人間の経済社会は、大陸と切り離された島国という地理的条件、気候特性とそれに対応して発達した第一次産業、あるいは江戸時代の鎖国政策など、様々な自然的、社会的条件により形成されてきたと考えられる。
明治の近代化以前における人間の経済社会の領域は、多くの場合、流域圏や生態圏に包含され、形成されていたといえる。近代交通技術の未発達な段階では地形的、距離的制約により人の移動は限定され、交流手段も流域に沿った舟運や街道が主なものであった。また生態圏を構成する要である里山林や田畑等が生活のための主たる場であり、農業、林業、漁業、畜産、生活の間で物質循環が形成されていた。また、江戸のような大都市でも、市内の農地や周辺の農村との間での物質循環が形成されていた(第2-3-1図)。明治時代以降、特に戦後の高度成長期においては、急速な工業化とその太平洋沿岸への集中立地、都市化、あるいは交通技術の発達といった過程で、人間活動の領域は自然要素で規定されていた制限を超越していった。その結果人間や物質の行動・移動範囲は拡大し、物質的豊かさについては全国的にほぼ等しく享受しうる状況を作り出した。しかし同時に全国的な人口の偏在をもたらし、様々な環境問題も生じた。過密となった都市部においては、人間活動の過度の集中等による大気汚染、ヒートアイランド、水質汚濁など、地域の環境容量を超えた負荷や、自然循環の不可能な廃棄物の問題等が生じた。一方、過疎となった農村部では管理されるべき二次的自然の荒廃と共同体の存続困難、あるいは各種の開発圧力による自然破壊の懸念という問題を抱えている。
しかし、近年、自然のメカニズムと人間活動との調和を目指し、環境基本計画の長期目標である循環と共生の実現を模索するような、地域づくりの試みが各地で始まっている。
ここでは、地域内での物質循環を取り戻そうという試み、地域間、地域内での経済社会の構成要素の連携をはかろうとする試み、都市の成長管理と広域的な視野に立った取組等の事例を挙げて、今後の人間活動と自然のメカニズムとの調和のあり方を考察してみることとする。