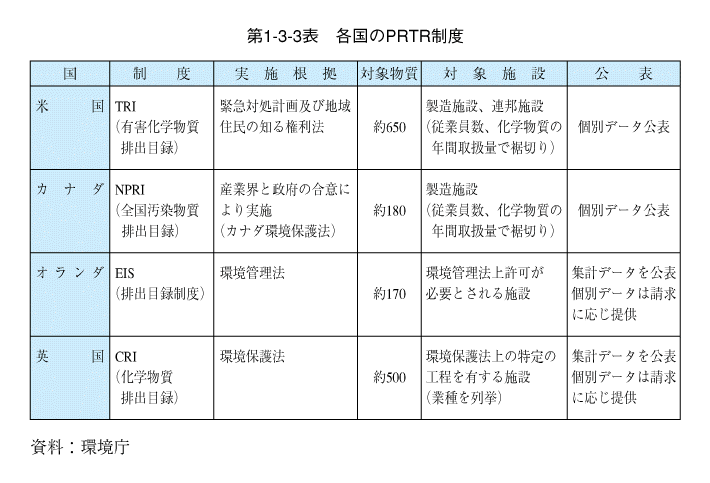
4 環境リスクの認識と企業行動 −PRTR制度−
ア PRTR制度とは
事業者が、自らの事業活動に伴う環境リスクを認識し、これを適切に管理することを促進するため、環境汚染物質排出・移動登録(PollutantRelease and Transfer Resister:PRTR)の活用が考えられる。
PRTRとはOECDのガイダンスマニュアルによれば「様々な排出源から排出又は移動される潜在的に有害な汚染物質の目録若しくは登録簿」とされる。これは、事業者が、規制・未規制を含む潜在的に有害な幅広い物質について環境媒体(大気、水、土壌)別の排出量と廃棄物としての移動量を自ら把握し、これを透明かつ客観的なシステムの下、何らかの形で集計し、公表するものである。
このようなPRTRには、利害関係者たる政府、事業者、国民にとり、それぞれにメリットがあり、例えば、次のようなものが考えられる。
? 政府:排出・移動に関する情報把握と化学物質管理の向上
・ 排出主体、排出物質の種類と量、排出媒体、発生源の地理的分布を把握
・ 規制物質等の監視、対策効果の追跡
・ 排出削減、環境保全型技術への転換の促進
・ 地域レベルでの環境リスクの把握
? 企業:排出・移動量の把握と適切な自主管理
・ 自らの排出・移動量の把握と業種全体の排出、移動情報の入手
・ どれだけの物質資源が環境中へ汚染物質として無駄に排出されているかを知ることにより排出量の削減と経費の削減が促進
? 国民:政策決定への国民参加の基礎
・ 国民の意識向上と参加の促進
・ 国民が、行政、企業と同じ土俵で議論
企業は、このPRTRを活用することにより、自社が環境中に放出している環境汚染物質の種類と量を把握してその環境リスクを認識し、より効率的、効果的な方法でその排出量、ひいては環境リスクの低減を促進することができる。また、排出量等を継続して把握することにより、削減努力の効果を判断することができる。
イ 各国におけるPRTR制度の導入状況
PRTRに関する国際的な取組としては、1992年(平成4年)の地球サミットで採択された「アジェンダ21:持続可能な発展のための人類の行動計画」において言及され、その導入が推奨された。
これを受け、OECDがPRTRを世界的に普及させるためのガイドラインの検討に着手し、その結果、1996年(平成8年)2月に「OECD域内の環境汚染物質排出・移動登録(PRTR)の実施にかかる理事会勧告」及び「環境汚染物質排出・移動登録(PRTR)のための政府手引きマニュアル」がとりまとめられた。前者の勧告の中で「加盟国政府はOECD作成の環境汚染物質排出・移動登録(PRTR)のための政府手引きマニュアルに記された原則、情報を利用しつつ、PRTRシステムを適切に構築し、実施し、公衆に利用可能なものとするよう取り組むこと」とされており、加盟各国に対し、PRTR制度の導入に取り組むよう勧告している。
PRTRは、OECD諸国を中心として、各国で既に導入されている。主な導入国は米国、カナダ、オランダ、英国等である。制度の内容は、それぞれに異なり、対象とする化学物質の数も米国約650、カナダ約180、オランダ約170など様々である。また、いずれの制度でも情報の公表が行われているが、その公表方法については、米国のように原則としてすべて公表するところと、英国のようにPRTRの制度の中では、物質別排出量のような形で集計した数値のみ公表するところとに大別できる(第1-3-3表)。
ウ 我が国における取組
我が国でも、環境庁が、試験的にPRTRを実施し、PRTRシステムを導入するに当たっての問題点等を検証し、また、PRTRに関する関係各主体の共通の認識の形成を図るため、平成9年度よりPRTRパイロット事業を行っている。
このパイロット事業は神奈川県及び愛知県の一部地域(第1-3-13図)において、毒性及び暴露可能性の両者の観点から選定した178物質(第1-3-4表)について、製造業等約1800の事業所を対象に、事業所から年間排出・移動量の報告を受けるとともに、行政が家庭からの排出量等「非点源」からの排出・移動量を推計し、これらを集計して情報提供を行うものである。
なお、パイロット事業の対象となる排出・移動は第1-3-14図のとおりである。
産業界では、まず、(社)日本化学工業協会が、平成4年よりレスポンシブル・ケア活動の一環として、対象物質を順次拡大しながら、PRTRに関する取組で化学物質排出量調査を実施し、平成7年度分の調査から、その結果を化学品審議会で報告している。また、(社)経済団体連合会においても、平成9年度より、174物質を対象に、全国45業種の団体の参加を得て、化学物質排出量等の調査を開始している。
今後、パイロット事業の評価とその結果及び産業界の自主的取組の状況を踏まえつつ、我が国へのPRTRシステムの導入について本格的に検討を行うこととしている。