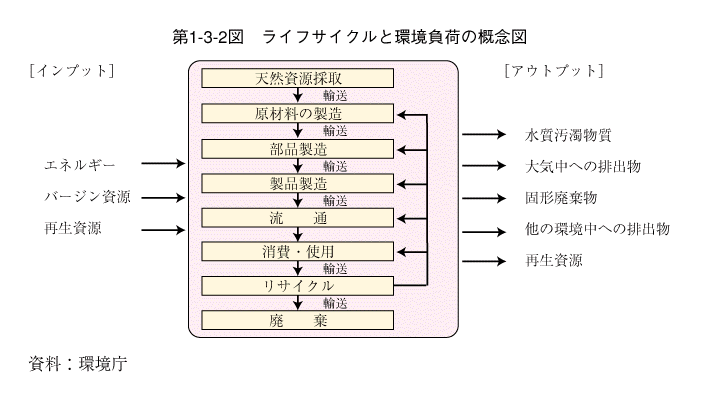
2 環境効率性の実現に向けて−ライフサイクルアセスメント−
ア ライフサイクルアセスメントの意義
前節まででとらえてきたように、事業者は製造から廃棄・リサイクルまで一連のライフサイクルの過程を通じて、より環境負荷の少ない製品やサービスを提供することが求められている。また、消費者も、より環境への負荷の少ない製品を選択しようとする意識が定着してきている。こうした動きを支援していくのに有効なツールとなるものにライフサイクルアセスメント(LCA)といわれるものがある。LCAとは、その製品に関わる資源の採取から製造、使用、廃棄、輸送などすべての段階を通して、投入資源あるいは排出環境負荷及びそれらによる地球や生態系への環境影響を定量的、客観的に評価する手法である(第1-3-2図)。
LCAを用いることにより、事業者は、例えば
? 製品の製造から廃棄・リサイクルに至る製品寿命全体をとらえつつ商品設計を行うことが可能となり、
? どの段階で環境負荷が発生しているかを客観的に認識できるようになるので、効果的に環境負荷を削減できる。また、
? 製品のライフサイクル全体を考慮した最適化設計が可能となる。
? 次世代製品の企画、開発の意思決定を行う際の指針を得られる。
? 消費者に科学的な情報を提供し、コミュニケーションの促進が図られる。
といったメリットが得られることが期待される。一方、消費者にとっては、例えば
? 客観的な評価に基づく環境負荷情報を入手することにより、より環境負荷の少ない製品を選択することで環境負荷の低減に貢献することが可能となる。
? 選択的な購買を行うことで、生産者の環境配慮を促すことが可能となる。
等のメリットが期待される。
イ LCAの手法
LCAの手法はまだ確立には至っていないが、国際標準化機構(ISO)の規格ISO14040(ライフサイクルアセスメント−原則及び枠組み)においては、6つの段階から構成されている。すなわち、
? 目的及び調査範囲の設定
? ライフサイクルインベントリ分析
? ライフサイクル影響評価
? ライフサイクル解釈
? 報告
? クリティカルレビュー
の6段階である(第1-3-3図)。以下では、それぞれの段階について概説する。
? 目的及び調査範囲の設定
第1段階は、LCAを実施する目的及び調査範囲を明確にする段階である。LCAの結果はこれらの設定により多様な形となり、これらの結果はその設定された目的及び調査範囲の中で有効なものとなる。
? ライフサイクルインベントリ分析
この段階は、LCAの対象となる製品やサービスに関して、投入される資源やエネルギー(インプット)と生産あるいは排出される製品・排出物(アウトプット)のデータを収集し、環境負荷項目に関する出入力明細表を作成する段階である。収集されるデータは、?の目的及び調査範囲に合致したものであることが要求される。また、複数の製品が同じ工程を経る場合、その工程からの環境負荷をどのようにLCA対象の製品又はサービスに振り分けるかという問題等がある。
? ライフサイクル影響評価
この段階では、?で得られたデータをもとに各環境負荷項目に対するインベントリ結果を各環境影響カテゴリーに分類し、環境影響の大きさと重要度を分析評価する。LCAの利用目的にあわせて、適切な情報提供を行うために、利害関係者の意思決定に即した操作性の高い定量的なLCA情報を作成・報告する重要なプロセスである。したがって、影響評価はできるだけ客観性を保ち、透明で、科学的に妥当性のある方法で実施されるべきである。
? ライフサイクル解釈
この段階は、設定された目的及び調査範囲と整合性をもって、?及び?の結果を評価、解釈する段階である。
? 報告
?〜?までの手順により得られた結果を報告書として報告対象者に示す段階。LCAの結果はもちろん、使用したデータ及び収集方法、LCAの結果の解釈に関わる前提条件等が明示される必要がある。
? クリティカルレビュー
この段階は、採用された方法やデータが目的に対して適切であり、合理的であることを確認する段階である。すなわち、実施方法がISO14040の規格に合致しているか、科学的及び技術的に妥当なものであるか等を保証するための手順である。
ウ LCAの用途
こうしたLCAは様々な用途で適用することができる。例えば、
? 商品や製品あるいはサービスなどを利用あるいは使用することによって提供される便益について、環境負荷という観点から、その代替製品、代替サービスを評価すること
? 企業の環境マネジメントシステム等の関連から、環境目標値や基準値の達成度を評価すること
? 新規製品開発等における環境負荷を評価すること
といったことが考えられる。
自社の製品等をLCAにより評価を実施したり、実施への研究・検討を行っている企業が増えてきており、企業が作成している環境報告書などの中で、こうした取組について記述する例も出始めている。例えば、ある大手家電メーカーでは、平成3年から製品のLCAに取り組み、平成9年からは評価項目に従来の省エネルギー、環境負荷化学物質といったものから新たに総合定量評価等を加え、35区分50項目にわたってアセスメントを実施している。評価は次世代製品の設計にフィードバックされ、環境に配慮した製品作りが進められている。
さらに、環境ラベルの認定基準や環境家計簿の評価基準等として、LCAの考え方を適用する方向で検討が進められている。
現在の都市・生活型の環境問題は、人間の通常の活動そのものに起因している問題である。現代の複雑に入り組んだ経済社会システムの中で、このような都市・生活型の環境問題に対して有効な対策を施していくためには、あらゆる角度からの取組が必要となる。こうした中にあって、環境保全のための取組の中に、LCA的な考え方を織り込み、トータルの環境負荷を削減させるようにしていく必要がある(第1-3-4図)。
囲み1-3-1 LCAの積み上げ法と産業連関法
インベントリ分析の手法には大きく分けて2つの手法がある。積み上げ法と産業連関法である。
積み上げ法は、製品を生産するプロセスの各段階において使用した資源・エネルギー(インプット)と排出物(アウトプット)を詳細に計算し集計することで環境負荷を求めるもので、環境負荷の原因と実態を明確にするものである。欧米等を中心に検討が進んでおり、現在ISOでは、この積み上げ法を念頭において国際規格化作業が進められている。
産業連関法は、約500項目にわたる産業連関表を用いて、部門間の金額ベースのやりとりから特定製品に関わる環境負荷を算定するもので、マクロなレベルで分析できる。
また、この両者をミックスさせた方法も検討されている。
エ LCAの今後の課題
我が国においても、近年、LCAを適用した研究事例が急速に増加してきている。しかしながら、データの入手困難性を主たる原因として、ほとんどが環境負荷項目としてエネルギー消費量やこれをもとにしたCO2排出量のみを取り上げたものにとどまっている。LCAを実施する上での最大の課題の一つは、インベントリ分析に必要なデータの収集であり、今後、データベースの整備やデータ収集が容易なLCA技法の開発を進めることが、LCAの普及促進に非常に重要と考えられる。
また、我が国のLCAに関する研究においては、影響評価段階まで踏み込んだ研究事例はほとんどない。これは技法の未確立が主たる原因と考えられるが、様々な環境負荷項目を総合的に評価するためには、影響評価技法の成熟が不可欠であり、技法開発を積極的に推進する必要がある。
ISOで検討されているLCAでは、調査項目として定量的な加算が可能なものを想定している。しかしながら、より総合的な評価とするためには、定量評価の要件をある程度緩和し、定量的な測定が不可能な項目をも加えることも検討する必要がある。このような項目の追加は、ライフサイクル全体にわたって総合的に評価することを厳密な客観性の確保に優先させており、測定可能なデータに加えて、測定可能な形となっていない調査項目を定性的な情報に基づいて評価の対象とする。このような方法論はまだ確立していないが、今後検討すべき事項の一つであると考えられる。
囲み1-3-2 ISOにおけるLCAの検討状況
ISO(国際標準化機構)においても、1993年(平成5年)から環境マネジメント専門委員会(TC207)の第5分科会においてLCAの標準化作業が進められている。1997年(平成9年)6月に「原則及び枠組み」がISO14040として発行している。その他「目的及び調査範囲の設定並びにライフサイクルインベントリ分析」がISO14041として1998年(平成10年)前半に発行することが見込まれるなど検討が進んできている。